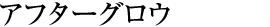 | 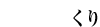 |
第5話
誰もいない廊下を走る。顔にあたる空気が熱い。
太田くんは爆弾があるはずの体育館へと向かった。その一方であたしと澪と真知子は、学校にいるすべての人たちの注意をそらそうっていう作戦だ。
とにかく、3時。3時、爆発が起こった時点で体育館に誰もいなければいいんだ。なんとか3時までは、先生と生徒の注意を体育館からそらさなければならない。
足音を殺して、職員室の横を通る。細く開いた引き戸から中をのぞくと、先生たち、おそらく全職員が席についてお茶を飲みながら何か話しあっている。隣の事務室をのぞくと、用務員のおじさんはテレビをつけたままソファーで寝てる。まったく、無用心な学校だなぁ……。
そのまま、向かいの空き教室に入った。
『この学校はお前らのもんだと思って、好き放題やればいいんだぜ』
さっきの太田くんの言葉が、あの笑顔とともによみがえる。
未来を変えられるのは、あたしたちしかいない。
――できる。
覚悟は決めた。
そばにあった椅子を持って、窓を勢いよく叩いた。ガシャンと大きな音をたてて、ガラスの破片が飛ぶ。まだだ、もっともっと。横の窓も、その横の窓も、椅子で叩き割る。ガシャン、ガシャン。やばい、けっこう楽しいかも。ガシャン、ガシャン。腕はすぐに疲れて痛くなったけど、やめられない。
最後に、黒板に椅子を投げつけた。ドォンという音を背に、めちゃくちゃにした教室を飛び出した。これでバッチリ、先生たちの耳には届いただろう。
『校内を引っ掻き回す』――これが今あたしにできることだ。
(先生、みんな、こっち見て! 全校集会なんて中止にしようよ!)
顔をあげると、廊下の突き当たりで真知子が手を振っている。
「こずえー! 派手な音させて何してんの!」
「騒ぎをおこすにはあのくらいがちょうどいいでしょ。そっちはどう?」
「とりあえず今、学校の公衆電話使って『小沢野高校に爆弾があるそうです』って、3時に爆発すること警察に通報してきたわよ。匿名で」
警察も計画に加担しているのだろうか。真知子の通報に対してどのように動くか。通報記録は残るはずだから、まさか放っておくことはないだろう。
その時。
『全校の職員および生徒のみなさんに連絡します!』
天井のスピーカーから、何の前触れもなく震えたすっとんきょうな声で放送が流れた。これは澪だ。
『えーと、6時間目の全校集会は中止となりました。あー、えーっと、生徒のみなさんは教室で静かに自習をしていてください!』
「うっわぁ、ヘタクソ……」
真知子がスピーカーを睨んで悪態をついた。
「澪に任せたのがマズかったかしら」
「まぁ、機械オンチの澪にしてはがんばったほうだと、あたしは思うよ」
「そうね。……さて、職員室はどう動くかしら」
今の澪の放送で、校内にいる人間全員が少しずつ異常を感じはじめるだろう。524人を巻き込んだ「計画」が大きく別の方向に転がりはじめる。
「あたし、太田くん見てくる。なんかちょっと心配でさ」
「わかった。じゃあ教室棟のほうはあたしと澪に任せなさい」
「みんなのこと守れるの? 勝算は?」
「あたしのこと甘く見てんじゃないわよ」
真知子がこれだけ言ってるんだ。不安はない。
「太田に言っときなさい、アンタも早めに体育館から離れろ、って」
「うん」
じゃあね、と真知子と別れて体育館へ向かう。さっきのことを思い返す。あーあ、あたし結局窓ガラス何枚割ったんだろ……先生たちに怒られるに決まってる。だけどそんなことどうでもいい。説教されようが、校内でこんな騒ぎを起こしたことであたしの評価が下がろうが、どうでもいい。今は、みんなが生きていられればそれだけでいい。
渡り廊下を抜けて体育館に入ると、用具庫のまわりにいろんなものが散らかっていた。ペンチ、ドライバー、針金、ロープ、金槌、その他いろんな工具。その奥に、太田くんはいた。座り込んで、背中を丸めて何かをカチャカチャといじっている。
「太田くん?」呼びかけると、彼は振り向いた。
「お、城岡」
「すごい、いろんな道具持ってるんだね」
あたしが馬鹿みたいに素直に言うと、太田くんは、すげえだろー、と笑った。
「この工具たちさ、親父がいつも使ってたんだ」
親父、ものづくりとかロボットとかにすげえ詳しい人だったんだぜ。
笑顔で、だけど過去形で、お父さんのことを話す太田くんを見て、心が痛んだ。あたしは太田くんみたいには、できないな。
「あ、さっきの野崎の放送、聞こえたよ」
彼は思い出したように言った。
「うん。職員室からいちばん近い空き教室で暴れてきたし、一応警察にも通報したよ。今もまだ2人がいろいろやらかしてるはず」
「よし。騒ぎが大きくなってきてるな」
教室棟のほうからざわめきが聞こえる。
「で、太田くんは、うまくいってる?」
「ああ、おれのほうは大丈夫だよ。ほら」
太田くんは黒っぽい何かをこっちへ投げた。
ゴロゴロと足下に転がってきたそれは、体育のリレーで使うバトンのようなものが何本も束になった、これは……
「ダーイナマイートっ」
「ぎゃっ」
「大丈夫だよ、時限装置はぶっ壊したし火薬も水で濡らしてダメにしたから」
「なぁんだ……」
「びびってやーんの。あははは」
太田くんは得意気な顔で笑う。すごいなぁ、あたしにはこんなこと到底できないや。
「おれはもう少し体育館に残って調べてるよ。まだ何かあるかもしれないからな」
外から警察のサイレンが耳に届いた。おそらくさっきの真知子の通報を受けて来たんだろう。
「あとは警察に任せてさ、早く逃げようよ、もうあと10分で3時だよ」
「いや、任せられるかはわからない」
「え?」
「警察も、クロかもしれないってこと」
確かにそうだ。警察が計画に加担しているとしたら、あたしたちはどうなってしまうんだろう。
「まぁ、その時はその時だ、な」
よっこらせ、と好青年がおやじくさい台詞を吐いて立ち上がった。
「城岡、体育館を出ろ」
「え、太田くんは」
「おれはもう少しここにいる。もし生徒が来たら、追い返さなきゃなんねーだろ」
「だけど、」
「だーいじょうぶだって。3時前にはちゃんと体育館から離れるから」
友達のところ行ってやれよ。そう言って、太田くんはあたしの背中をポンと押した。
「……早く、なるべく早く体育館から出てね!」
「おう」
「あぶないと思ったら逃げるんだよ!」
「大丈夫だよ」
「絶対、ぜーったい、死んじゃだめだからね!」
「あたりまえだろ」
にっこり笑った太田くんに少し安心して、あたしは走りだした。
渡り廊下から体育館を出ると、いきなり、下ろされたシャッターの前に真知子がいた。
「渡り廊下は防火扉で塞いだから。これでもう教室棟から体育館には入れないでしょ」
仁王立ちする彼女を見て、改めて、あたしには敵わないなぁと思った。
「……真知子、やっぱアンタ賢いんだね」
「今さら何言ってんの。それより、体育館の昇降口を塞がれる前にあたしたちも逃げなきゃ。澪はもうみんなに紛れて校庭に出たわよ」
「生徒はみんな校庭?」
「さっき教室に先生たちが来て、みんな避難させたわ。……3時まであと8分ね」
真知子は廊下の時計を仰いだ。
「真知子、あたしたちも校庭に出よう」
「いいけど、こずえ……太田は? いいの?」
「太田くんなら、きっと大丈夫だよ。信じよう」
あれだけ死ぬなと言ったんだ。彼なら、自分の身を犠牲にしてまで爆発阻止に関わろうとはしないだろう。そうであってほしい。
体育館の中を通って、昇降口へ走る。探したが、どこにも太田くんの姿はなく、散らかった工具だけが残されていた。よかった、もう逃げたのか。
校庭に出ると、生徒はみんな体育館から離れるようにして集まっていた。マイクを通して「そこの女子2人、早く来なさい!」という先生の声が聞こえた。パトカーがたくさん止まっている。消防車も数台きている。
「城岡、広瀬! 大丈夫か!」
担任があたしたちのほうへ駆け寄ってきた。
「ったく、お前らどこにいたんだ」
「あー、いや、あの、トイレにいたら、なんか、出られなくなっちゃって」
「でもっ、でもほら、ケガもないし大丈夫ですよ」
「そうか。ならよかった」
よかった。悪行の数々については問われない。
「あとは……太田だけか」
ぽつりとこぼれた担任の言葉に、耳を疑った。
「先生! 太田くんは?」
「お前らも知らないのか。うちのクラスは、あとあいつだけ姿が見えてなくてな……」
校庭に避難してきていない? じゃあ太田くんはいったいどこに――
担任に問いつめようとしたとき。
体育館から、ドン、と花火のはじけるような音が聞こえた。
生徒から悲鳴があがった。ざわめきがおこった。
とっさに時計を見ると、3時だ。爆発だ。予定通りに爆発がおこったんだ。駅舎のときのような、派手な爆発ではないのだろうか。煙も炎も見えない。
だけど太田くんは、爆弾は処理したって、それに、ちゃんと3時になる前に校庭に避難するって、そう言って。なのに、どうして、ここにいないの?
「こずえ、まさか太田は――」
真知子の声を聞く余裕もなく、あたしの頭は最悪の展開で染まっていた。
無意識のうちに生徒の集団から少しずつ離れ、一気に体育館までダッシュした。警察の目を盗んで、裏まで回りこむ。そして下のほうにある小さな引き戸をくぐりぬけて、体育館の中に入った。
校庭、つまり避難所ではどこにも姿が見えなかった。だけどまさか、太田くんがこの中にいるなんて、そんなことはないだろう。そうであってほしいと願った。それでも、なんだか胸騒ぎがしたから、あたしは体育館に吸い寄せられた。
「おーおーたくーん?」
体育館に入った瞬間に熱いと感じた。気温が高い。暑さもあるが、そんなやさしいものではないような、熱さだ。なんとなく、昨日爆発した駅の前で感じたような、熱さ。そして、埃なのか煙なのか、白い気体が薄く充満している。前方がハッキリ見えない。
「太田くーん……って、やっぱりここにはいないよね」
足に何か当たった。
人間の、手?
(まさか、)
「太田くん?」
恐る恐る足元を見た。あたしが蹴った手の主は、横たわる太田くんだった。しゃがみこんで肩を揺さぶると彼は、あたしの方へ視線はやらずに薄く目を開け、また閉じた。
――やだ、まさか。
また名前を呼んで、肩を揺さぶった。彼は目を開けない。
「太田くん! ねぇ太田くん!」
死なないって約束したじゃん。大丈夫だよって言ってたじゃん。うそだ。やだ、やだやだやだやだ。
『おれ、まだ死にたくねえんだよな』
『この工具たちさ、親父がいつも使ってたんだ』
意識はないのに、工具の巾着袋を強くつかんで離さない太田くん。視界が涙でにじんだ。あたしは、死なない、死なない、と口に出して言い聞かす。自分にも、応じない彼にも。あたしは、重たくなった太田くんをずるずると引きずって、いつもよりも遠く感じる昇降口の光へ向かう。
ひたすら向かう。
もう誰も死なせるわけにはいかないんだ。
|
【第4話に戻る】 【第6話に続く】
| 第5話 |  |
 Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved.
Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved. |