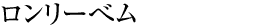 |  |
第2話
ベムは怖くなりました。
手が震えだし、目の前は真っ暗になりました。
ベムは床にあった鉛筆を持ち、震えた手を動かして『怖い』と床に書きました。
ギザギザの一本線がひとつ。
『怖い』
ベムはもう一度新聞紙に目を向けました。
が、どこからどう見ても新聞紙に書かれた文字はただの『落書き』。
理解できたのは、無残な姿のたくさんの人間だけでした。
ベムは考えました。
頭を全部使って、できるだけ昔のことを思い出そうとしました。
が、なにも思い出せませんでした。
覚えているのは、1人っきりで暮らした日々のことだけ。
ベムは、また怖くなって手を動かしました。
ギザギザの線は2つに。
そう、彼はずっとずっと1人ぼっち。
だから、
なぜ、自分が1人ぼっちになったのか。
ナゼ、自分の周りに他の人がいないのか。
何故、自分がここに住んでいるのか。
考えたこともありませんでした。
1人ぼっちで暮らすのが当たり前だったのですから、考えようとも思わなかったのです。
ただ漠然と生きてきたベムにとって、その新聞はあまりにも唐突なものでした。
体の中で悪い何かが弾けたような気分。
ベムは新聞を床に置きました。
何か食べよう。
気を紛らわそうと物置の掃除をやめ、彼はキッチンへと向かいました。
1人には大きすぎる家、その真ん中にある廊下を通ってキッチンへ。
木でできた流し台にたくさんのお皿、コップ。
ベム1人のキッチン。
キッチンにあったのは、ベムがとってきたたくさんの果物。
犬に噛まれたようなかたちをした毒のありそうなものから、ほんとうにどこから見ても美しい、おいしそうな果物まで、たくさんありました。
ベムはその中の赤い丸い林檎のような果実をひとつ、とって口にしました。
いつもより苦い気がした赤、でもやっぱり甘い。
ベムはたった1人で暮らしていましたが、食べものに困ることはありませんでした。
彼の家を一歩出ると、日々変化して季節を知らせる草や木々達の紫がかった茶色。
いつ見ても透き通っている川の底の緑。
それら全てを照らすために朝と昼にだけ、毎日違うところから上ってくる、オレンジよりオレンジな球。
そして、冬のひまわりが咲く庭。
尽きることのない自然がベムの家を、まるで大事に守るかのように囲んでいました。
月は夜空の下でピンク色に輝き、
火が燃えると大きな熊よりも高く火柱がたちのぼりました。
ベムは毎晩、水面に映った星に願いを。
木々の葉からは、ほのかな優しい香り。
ベムの家の周りには、この世の全ての色をとりそろえたような、多彩な野菜や果物がたくさんありました。
だから、食べものに困ることはありませんでした。
食べものだけじゃありません。
服だってたくさん家にありました。
布団だってベッドだって、机だって。
ベムは物に困るなんてことはありませんでした。
どれもありあまるくらい、ベムには多すぎるくらいあったのです。
少々の果物を食べ終わったベムは気が落ち着きました。
川からくんできた透明な水をコップに入れて飲み、ソファーにこしかけました。
しばしの安らかな時間。
音のない、静かな空間。
この家ではベムが動いていないと外からも内からも、スズノネ一つ聞こえません。
ベムの家に時計はなく、部屋に響くのはドクン、ドクンと波打つ彼の鼓動だけでした。
古いうす黄色のソファー。
このソファーに座ると真上に見える、傾いた四角形の窓。
そこに映る「月」を眺めるのがベムは大好きでした。
深い夜に満天の空の中、ひときわ目立つピンク色を眺めるのが大好きでした。
眠れない夜は、窓から差し込む月の明かりをじっと眺めていたりもしました。
ベムはこのソファーに座って「月」を見ていると、なぜだか気持ちが落ち着いて、何かに守られているような気がして、いつだって心地良くなれたのです。
そんなソファーで、ベムはいつもと変わらない時間を過ごそうとしました。
なにもなかったかのように流れる時間。
しかし、彼は気になってしかたがありませんでした。
あの箱、新聞紙以外にも何か入っていること。
見えたのに怖くて見なかったフリをしたあの茶色い紙。
ベムは鉛筆でソファーにもうひとつ、ギザギザの一本線を書いてから物置へと向かいました。
物置につくと、さっき開けた箱。
その中には茶色い古い紙。
ベムはそれを開けました。
________________
ベムへ。
あなたがこれを読んでいるということは、私はもうこの世にはいないのですね。
とても悲しい。
私はもう永くないから、最初で最後のこの手紙をあなたに送ります。
ごめんね、ベム。1人にしちゃって。
何も言ってあげられなくて、ごめん。
あなたは私の大事な息子です。
私はあなたのお母さんです。
私たちは3人家族で暮らしていました。
この小さな家で、十分とはいえないけど、幸せに3人で暮らしていました。
ベムは覚えていないと思うけれど、とても大切な思い出は今でも私の中にたくさんあります。
あなたが生まれたあの日。
生まれてすぐ、あなたが風邪をひいてしまって必死に看病をしたあの夜。
あなたが机を掴みながら、よろけながらも初めて立ったあの朝。
あなたが初めて「お母さん」って言ってくれたその言葉。
雷の日に、絵を描くのが好きだったあなたがどうしてもって、私の鉛筆を使って描いて見せてくれたあの絵。
線だけでかかれたあの絵。
お父さんにむけていつも歌っていたあの歌。
おんなじメロディーをただただ繰り返すだけのあの歌。
ベムが大好きだった、お父さん手作りのピンクのあのボール。
そのボールで無邪気に遊ぶあなた。
何も考えないでただ川で遊んでいるあなた。
ご飯を作るのを手伝うといって火傷をしてしまったあなた。
私がすこしでも離れるとすぐに泣いてしまうあなた。
私がずっとそばにいるだけで嬉しそうな顔をするあなた。
その全てが私の生きる希望となりました。
決して多くの時間を家族3人一緒に過ごせた訳ではありません。
でも、ただただ3人でいることだけが楽しかったのです。
とても幸せでした。
そのうちお父さんは戦争に行き、帰って来なくなってしまいました。
あの、全てを焼き尽くした戦争。
世界を変えた戦争。
東も西も南も北も、全てを燃やしつくした、あの忌まわしく醜い戦争。
やがて戦争は終わりました。
がしかし、それと同時に『人』が終わったのです。
ベム、私はお母さんとして何もしてあげることができませんでした。
ほんとうにごめんなさい。
ごめんなさい、ごめんなさい、
ごめんなさい、ごめんなさい、
ごめんなさいがいくつあっても足りません。
ごめんなさい。
でも、
1人で寂しいと思っても、
1人で生きていて苦しくなっても、
1人が嫌で嫌でしかたなくなっても、
自ら死ぬようなことだけはしないでください。
何のために生きているかわからなくなっても。
お願いです。
ベム、生きてください。
生きていれば必ず幸せは訪れます。
必ずです、あきらめなければ世界はいつでも始まります。
だから生きて。
それが私の最後の願いです。
私は今でもあなたが大好きです。
私は今でもあなたを想っています。
世界はあなたを想っています。
生きてください。
人のために、生きて、
生きてください
生きて
______________
手紙はそこで終わっていました。
ベムはこの手紙を読んでも、なにひとつ理解することはできませんでした。
文字を失った彼にとってこの手紙は、ただの茶色い紙。
そう、ただの『落書き』。 |
【第1話に戻る】 【第3話に続く】
| 第2話 |  |
 Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved.
Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved. |