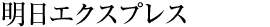 |  |
最終話
2009年12月25日 金曜日 21時50分。
電車を降りた莉菜(りな)は、ふうっと吐いた息が白くなって消えていくのを、ぼんやりと見ていた。迎えに来るように悠希(ゆうき)にメールを送ったのは2分前。駅から自宅までは近いとはいえ、走っても5分はかかるだろう。それに、雪がこんなに積もっているのだ。おそらく、今家を出たばかりだろうから、もう少しかかるかもしれない。やっぱり悪かったかな、と一瞬思ったが、悠希は最近家に籠もってばかりいるから、たまには外に出たほうがいいだろうと済ました。
ひゅうっと冷たい風が吹き抜ける。寒さに身震いをして、腕をさする。
「あの……」
突然の声に莉菜は飛び上がった。振り向くとおずおずとこちらを見ている少女がいた。黒いスーツ姿の割には顔が幼く、莉菜が少し目線を下げないと顔全体が見えない。おそらく、10センチくらい少女の方が背は低い。いつからここにいたのだろう。駅には、1時間に1本程度しか電車は停まらず、先程の電車で降りたのは莉菜ひとりだけ。それに、この辺りでは見ない顔だ。どうしたの? と笑みを作っても、相手は口ごもったままだった。
「どうしたの?」
声をかけて近寄ると少女は思い切ったように顔を上げた。
「はじめまして。三橋莉菜さんですよね。ちょっとお時間よろしいでしょうか」
突然、矢継ぎ早に話し始める少女に莉菜は退いたが、この少女は莉菜を知っている。もしかしたら、後輩かもしれない。
莉菜は駅の中の椅子に腰掛けるように促し、2人は並んで座った。
「一応、名前を訊いてもいいかな?」
「……タイラミクです」
タイラミク、覚えのない名前だ。ミクという知り合いは数人いるが、タイラといったら悠希しかいない。どこかで会っていただろうか? 会ったことすら忘れている、ということも有り得る。とっても失礼なことだが。
「ちなみに、あなたは初対面ですよ。私は違いますけど」
莉菜が、少女をなんとか思い出そうとしているのを見透かしたのだろう。莉菜は照れて笑って見せた。しかし、ミクはつられて笑うことなく、無表情のままだった。
ふと、莉菜の耳にその言葉が引っかかった。あたしは初対面で、この子は違う――?
「……今からお話しすることは、信じてもらえないかもしれないけれど事実です。聞いてください」
真剣な眼差しを向けるミクに、莉菜はすかさず聞き返した。
「……もしかして、あたしを消しにきたの?」
ミクはぎょっとして莉菜を見た。その顔はもう笑ってなんかいない。
「あたし、わかるよ。自分が何をしてここにいるのか。そして君が、何をしに来たのか」
平然と言い出す莉菜は、ミクが何も言えなくなるくらい実に落ち着き払っていた。
「どうしてですか?」
どうしてだろう? 自分でも分からない。今まで生きてきた中で、一番古い記憶として残っている、あの日のこと。なぜ、自分はそんなことが出来たのかわからない。世間でよく言う『サイキック』だろうと、それで片付けていた。しかし、本来ならばあたしはここにはいない。あたしがここにいるのは間違っている。だから、それはいけないことであり、いつかはもとに戻さなければならない。そんな意識があった。今がその時だ。
莉菜は驚くほどに淡々と、全てを悟っているかのように穏やかな顔だった。
「私は、あなたを消しに来たのではありません。あなたを助けに来ました」
「助けに……? 君は何者なの?」
ミクは大きく冷たい空気を吸い、そしてゆっくりと吐いた。
「私は……私は、あなたの娘です」
しばしの間、莉菜は何の反応も示さなかった。今、何て言った? と、聞き返したそうにしていたが、結局は黙ってミクを見つめていた。
すると、莉菜は突然はっとして、目を大きく開いた。
「ひょっとしたら、君のお父さんって……」
ここまで言うと、両手で顔を覆った。ミクは静かに頷いた。
悠希が夫だということには、ただ驚いている。だが、それ以上に莉菜は申し訳ない気持ちでいっぱいだった。この子は、どんな思いでここまで来たのだろう。あたしが消えると知ってから、助けようと決心するまで、相当辛い思いをしただろうに。あたしを助けることが、間違っているのに。この子に責任はないのに、あたしの所為なのに。
「そっかぁ……。あー……何だろうこの変な感じ。ごめん、話続けていいよ」
莉菜をこんなに思い煩わせるのなら言わなければよかった。と思ったが、話を進めるためには仕方がないことだ。
「私は、あなたを助けに来ました。今日中に別の人物があなたを消しに来ます。でも、私が絶対助け出してみせますから。ただ、今と同じような生活が出来るとは限らないですけど、大丈夫。安心してください」
すると、莉菜はミクの顔をまじまじと見つめ始めた。
「なんか、悠希に似ちゃったんだね。雰囲気が」
真面目な話をしているのに、本人はこちらを気にせず、相変わらず自由に振舞っている。ミクの母であった莉菜も、本当に自由奔放な人だった。それを思い出すと、溜め息が出る。
「ねぇ、いちごとか好きでしょ」
はい、と返事をすると、莉菜は迷いから抜けたように嬉しそうに笑い、いつのまにか自動販売機の前にいて、いちごオレを買っていた。それをミクに渡すと、莉菜は駅の外壁へと向かった。ミクも後についていく。
「何か書くもの持ってない? ペンとか」
ミクは胸ポケットに引っ掛けてある黒ペンを取り出し、莉菜に手渡した。すると、壁に向かって何かを書き始めた。
『たとえ間違いだったとしても、あなたに会えて幸せだった』
よし、と小さく呟くと、それを目をぱちぱちさせながら眺めるミクにペンを返した。
あたしは間違いでここにいる。でも、その間違いでたくさんの人と出会えた。お父さん、お母さん、友達、先輩、後輩、悠希や、ミク。特にお父さんとお母さんには、言い足りないほどの感謝でいっぱいだ。あたしを拾ってくれて、ここまで育ててくれて、本当の親子のような生活をさせてもらって。本当に感謝している。
悠希のことは……。おもちゃにして遊んでいたけれど、一緒にいて楽しかった。本当は、これから先の未来も一緒に歩んでいくはずだったのかもしれない。でも、そんな未来がなくなっても、今まで一緒に過ごせてきて幸せだったと思う。
この落書きを悠希が見るかどうかわからないけれど、出会えて本当に良かった。
「ミクにも会えて、良かった。ここまで来てくれてありがとう」
心配そうな眼差しを向けるミクに、莉菜はにっこりと微笑みかけた。
ミクは知っていた。時間調律師が関わったもの全てが、時空間に影響してしまうことを。だから、ミクのペンで書かれたそれは、消えることはない。莉奈が消えたとしても、この落書きは残るのだ。同時に、仕事としてはこれを消さなければいけないことも知っていた。
だが、そんな莉奈――母親の姿を見て、ミクはどうすることも出来なかった。
「そんな仏頂面なところは、あっちに似たんだろうけど」
ミクの顔をぺちんっと音が鳴るように両手で挟む。目をぱちぱちとさせて驚くのを見て、莉奈は吹き出す。それにつられて、ミクもぎこちない笑顔を見せる。
「やっぱりあたしの娘だね」
変わらない母親の微笑みに、ミクは目を潤ませていた。
そっとしておくべきなんだろうが、弱ったなぁ。
宵闇が迫り、街灯が灯り始める。この駅にもそろそろ灯りを点けてもいい頃だ。無人駅のため、駅舎の電灯は部屋のようなスイッチで、利用する人が勝手に点けられるようになっている。この季節だと暗くなるに連れて、寒さが昼間と比べ物にならないほど増している。
ミクはあの時を思い出し、椅子の上にうずくまっていた。悠希がもともといた時空に戻ってからというもの、10分以上はこの調子だ。ミクが何を思っているかは大体予想できていたので、悠希とワタルは壁に寄り掛かり、時折ミクの様子を伺っていた。
「あの体勢って、ツラくないんやろか」
ミクは小さな椅子の上に体育座りをして、膝に顔を埋めている。
「どうにかしてあげたいなら、話しかければいいじゃないですか」
ワタルは「どうすればええのかわからへんから、わしらこうなってんねん」と小さく文句を言い、溜め息と同時にネクタイを緩めた。この男も疲れているだろうに、何だかんだと先ほどからミクのことを気にかけているのだ。
「ミクはこっちから何かしなくても、きっと全部わかってます。自分で」
「お前、見かけによらずええ奴やな」
見かけによらず、って。
ワタルはポケットに手を突っ込んだ。どうやら煙草を吸いたいらしい。
「最初会ったときは、消極的っちゅうか何を考えとるかわからん感じで、どうしようもない奴や思っとった」
「いや、普通ですよ。初めて会ってすぐには喋れないですって」
「そうかもしれへんけれど、今はそう思っとらんよ。ぼけっとしとるように見えて、実際は色々考えとる。ミクのことも、会って間もないはずなのに、ちゃんとわかっとるトコとか、エライと思うで」
ワタルは空笑いをすると、何の断りもなく煙草に火を点けた。悠希が嫌そうな顔をしたのに気が付き、ばつが悪そうに会釈した。
「ミクもそないな感じやったなぁ。割と一緒に仕事しとるのに、今でもよそよそしいし。反抗期やろか?」
「でも、ワタルさんを避けたくなる理由はわかる気がする」
「何でや?」
「べらべらとまくしたてるからじゃないですか」
さらっと言ってのけた悠希に、ワタルは痛いところを突かれたようで、固まった笑顔のまま何も言わなかった。そのかわり、悠希に向かって煙草の煙を吐き出した。煙くてむせていると、意地悪そうな顔でこちらを見ていた。
「われもわれやけど、ミクももうちょっと可愛げがあったらええのに」
そうぼやくワタルに、悠希は苦笑いだけで返しておいたが、それが正解であった。なぜなら、ワタルのすぐ横でミクが聞いていたからだった。
ミクは静かに立ち上がり、俯きながらこちらへ寄って来る。
「お、最後の仕事やな」
近くに来てわかったが、その目が赤くわずかに潤んでいた。
「ここに私たちがいた痕跡と、私たちに関わるお前の記憶の全てを消す」
ミクが言い放つと同時に、悠希の顔の前に手をかざす。
これで、全てなかったことになるのか……。
「未来では、もうちょっと可愛げのある娘に育てるからな」
からかうように笑う悠希に、ミクは目を丸くさせ、ワタルは半笑いを浮かべている。
莉菜の時空間を調律した今、これから悠希が莉菜に出会うことはないかもしれない。しかし、偶然の一言では済まされないくらい奇跡的に、悠希と莉菜は出会えた。それで出会えたなら、お互いの記憶がなくても、未来で必ず出会える、そういう気がしてならないのだ。
「それは間に合ってますから」
ミクはふっと頬を緩ませて、真っ直ぐと悠希を見ていた。その顔はやっぱり莉菜に似ていた。
「じゃあ、未来でな」
そう呟き、悠希は静かにまぶたを閉じた。
俺は言葉足らずだったのかもしれない。
だから、これから先の未来で健仁(たけひと)を困らせて、あんなことになってしまった。今までにも、この消極的な性格の所為でトラブルはいくつか起こしてきた。俺は、いつも、他人との間に一線を引いてしまっていたのだ。
じゃあ、具体的にどうすればいいのか。それは正直よくわからない。いきなり人との接し方を変えろ、と言われても無理だ。
でも、もし、これからの積み重ねで未来が変わっていくというのなら……。
俺に出来ることは一体何だろう。
誰が書いたかわからないあの落書きの通りだ。俺もミクやワタルさんに会えて、これからの未来に新しい風が吹いた。……莉菜に会えて、本当に良かった。
莉菜。
間違いだったかもしれないけど、毎日が楽しくて幸せだった。振り回されてばかりだったな。これからはお前のいない、お前を知らない生活が始まる。それでも俺は、この先の未来で莉菜に会えることを信じる。
2012年 3月末。
まだ防寒着が手放せない肌寒い日が続くが、雪に覆われていた道端には、たんぽぽやふきのとうが芽吹き始め、春の訪れを感じさせる。この辺りの桜の開花は、卒業式や入学式には間に合わない。だから、桜よりもふきのとうの方が、春が来たという実感が湧く。
悠希は三橋家を離れて、一人暮らしをすることになった。これからは、大学生として新しい生活が始まるのだ。
あと、3分で電車が来る。悠希は手荷物をコンクリートの上に下ろし、壁にもたれかかった。実家に寄って両親に顔を出し、健仁と合流しアパートへと向かう予定だ。健仁も同じ大学に行くのだが、一人暮らしはせずに親戚の家に下宿するらしい。お金がかかるからという理由で、一人暮らしはやめてほしいと説得されたと聞いた。「アパートに一緒に行く」、「入り浸ってやる」など言い出したのは、自由な悠希が羨ましいからだろう。対する悠希は「うるさい」「来るな」の一言でスパッと切り捨てていたが、次第に「仕方ないなぁ」「いちごっぽい菓子は必ずな」と折れてしまった。まだまだ二人の腐れ縁は続きそうだ。
不安はないが、少しの緊張はある。自由な一人暮らしに憧れていたため、今はとても心が弾んでいる。
向こうから電車がやって来るのが見える。悠希は手荷物を持ち上げ、駅のホームへと足を踏み入れる。停車し、電車に乗り込むとそのまま出入り口付近を陣取る。車内には5人程度しかいないが、悠希は座らなかった。昔、座席に財布を置き忘れていったことがあったからだ。
ふと、向かいに座っている20歳くらいの女性と目が合う。見覚えはないが、目が合い会釈をしてくれたのでこちらも返す。ボブヘアが似合う可愛らしい女性だった。
電車が発車する。少しよろめいたので、吊革に手を伸ばす。
「すみません」
凛とした声に振り返る。
「落としましたよ」
にこやかに真っ直ぐと見つめる女性に思わず見惚れてしまい、しばらくは固まっていた。
差し出したのは、紛れもなく悠希の財布。落とさないように気を付けていたのに。
「あ、ありがとうございます」
目を見られずに礼を言ったのにもかかわらず、相手は「いいえ」と自然な笑みを浮かべて、身に付けている赤チェックのマフラーを緩めながら座席に戻っていった。
悠希は目を伏せてゆっくりと大きく深呼吸し、肩の力を抜いた。
人は明日に向かって進むしかない。
俺達は、毎日ものすごいスピードで前に進んでいる。戻れはしないし、やり直したりも出来ない。
だから、俺は決めた。
今まで俺は、周りに一線を引いていた。初めて会う人は当然、伯父さんにも伯母さんにも友達にも。別にそこまで自分をわかって貰おうなんて思ってないし、相手に無理をさせたくもない。でも、それでは何も始まらないし、知らないうちに周りが離れていく。
大切な人には自分の言いたいことや気持ちをちゃんと伝えること、表現すること。俺はそうしようと決めたんだ。
特急列車のように時間は進む。それについていけなくても、明日は必ずやって来る。不確かな明日を向かえるために、今の自分の気持ちをはっきりとさせて生きて行きたい。
――今の俺に出来ることは、今の一瞬を大切に生きることだ。
電車が停まってドアが開き、悠希は1歩を踏み出した。 |
【第4話に戻る】
| 最終話 |  |
 Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved.
Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved. |