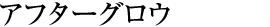 | 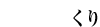 |
第6話
もう誰も死んじゃいけない、死なせない、死なせない
――ハッと目が覚めた。あれ、あたし何してたんだっけ?
目だけを動かして周囲の状況を確認すると、どうやらあたしは、大きめの車か何かに乗っているようだ。エンジンの振動が響く。
隣で太田くんが横になっていた。学ランの黒いズボンは白く汚れている。肩を揺さぶってみるが、やはり反応はない。
「彼なら大丈夫だよ。体に大きな損傷はなさそうだから」
ビクッとした。声のする方を見ると、バックミラーごしに運転席の人間と目があった。中年の男だ。熊みたいな体型。頭にタオルを巻いている。顔を見ると、どこかで会ったことがあるような気がした。
「あの、ここって――」
どこなんですか。言おうとしたが、視界の端に見慣れないものをとらえて、言葉は止まった。
運転席の横に転がっている白い軍手が、赤褐色で汚れている。
血だ。乾いた血の色だ。
恐怖とショックで叫びだしたくなる衝動を、やっとのことで抑えた。
できるだけ平静を装って、聞いた。
「……警察の、かたですか」
「うーん、警察ではないねぇ」
「あたしたちのこと、どこに連れていくんですか」
「さぁーて、どうしようかねぇ」
まさか、この人も政府の人間――
あたしの頭は再び最悪の展開で染まった。
「降ろしてください!」
「だーめ」
「やだ! 降ろして! こんなところにいる場合じゃないんです! 学校が、みんなが、」
「オジサンはね、目の前の命を見殺しにするような冷たい人間じゃないから。安心しなさい」
車は、病院の前で止まった。
ロビーは、人がまばらだった。どこからか、涼しい風が入ってくる。空いていた椅子に座った。
澪は、真知子は、学校のみんなは、どうしただろうか。そういえば携帯は教室に置いたままだ。
お父さんはどこにいるのだろう。体育館の爆発を、知っているだろうか。それともあらかじめ知っていたのだろうか。だとしたら、どうして助けてくれなかったんだろう。お父さんは何考えてるの? あたしのことをどう思ってるの? わからない、わからない、わからないよ。
「はい」
突然目の前に缶コーヒーが置かれた。顔をあげると、あたしたちをここに連れてきた男だった。男はそのままあたしの向かいに座って、自分の缶コーヒーをぐいっと飲んだ。
「体育館の昇降口の近くに、君たち二人が倒れていたんだよ。彼、足首が折れてる。しばらくは歩けないだろうね」
「えっ」
「あと火傷と擦り傷が何か所か。そのほかは大丈夫らしい」
「あ、よかった……」
ずっしりとした彼を引きずったことを思い出す。正直、ほんの一瞬だけど、太田くん死んだんじゃないかと思った。
「コーヒー、飲まないのかい」
「いりません。苦手なんです」
本当は苦手なわけではない。缶コーヒーなんて、いつも飲んでる。ただ、見知らぬ男に出された缶コーヒーをやすやすと飲むほど、あたしは軽率ではない。
この人が意図していることはなんだ? それとも、本物の善意から太田くんとあたしを助けた?
一般市民か、それとも計画に加担している側の人間か。
シロかクロか。
「どうしてあたしたちを病院なんかにつれてきたんですか」
「え? そりゃあ、」
「だって、ほっといたら死んだかもしれないのに」
「何言ってるんだ、君は。だからこそ病院に連れてきたんじゃないか。そんな死にそうな人、目の前にしたら、そのままにしておけないって思うのが普通だよ」
普通、か。普通ってなんだろう。倒れてる人を目の前にしたら、そりゃあ放っておけないかもしれない。それが人間にとって普通の感情かもしれない。だけど、人殺しが目的の政府にとっては、逆だ。死にそうな人がいたって、そのまま放っておくのが普通だろう。
「あたしたちのこと、また一人殺せたかもしれないのに?」
「……『殺せた』、か」
――しまった。
「さては君、計画のこと知ってるんだねぇ」
心臓がものすごい速さで動く。全身が緊張して、動けない。
だめだ、この人もクロだったんだ。計画に加担している人間だ。どうしよう。
「さっき、車の中で血のついた軍手を見ただろう」
内心、ひどく動揺しているあたしとは反対に、男は意外に穏やかな様子で話し続けた。
「あれは、駅舎の爆発の犠牲になった人たちの血だよ。オジサンの仕事はね、ああいう人たちの片付けなんだ」
また心臓がドクンと鳴った。
どうしよう、どうしよう。頭が真っ白になった。計画を知っていてはならないはずのあたしたちは、口封じに殺される。そして『片付け』られる。
どうする。逃げるか。でも太田くんひとりを残して行けない。だけど、だけど、
「――この国は狂ってるよ」
あたしの沈黙は、相手の思わぬ言葉で破られた。
「こんなふざけた計画、やりたくてやってる人間なんか、数えるほどしかいないさ。だけど上には逆らえない。逆らったら殺されるからね。殺される側か、殺す側か。だったらみんな殺す側になるしかないんだ」
次々と、あたしが予期せぬ言葉が発せられる。この人は一体何を考えているんだろう。
「絶やさない限り、人の数だけ未来があるんだ。できることなら誰も死なないのがいちばんいい」
ちょっと待って。なんか、そういう話、どこかで聞いたような……
「ま、一種の職業病ってやつかもしれんね」
職業病?
「……おじさん、名前は」
「ノザキだよ」
――ノザキ。
「山のほうに、霊園があるだろ。あそこ、うちなんだよ」
その屈託のない表情は、あたしのだいすきな友だちにピッタリ重なった。
信じられる「加担者」は、まだまだいるのかもしれない。
「結局、学校での死者はゼロだったんだよ。つまり一人も殺せなかったってことだから、」
澪のお父さんは、空っぽになった缶を静かに置いた。
「……政府は、次はもっと派手なことをしでかすつもりらしい」
心のどこかでホッとして、だけど闘わなければならない問題は解決してなくて。何から考えたらいいかわからなくなって、とりあえずあたしは缶コーヒーを開けた。
太田くんの病室に入ると、彼はベッドの上で起き上がったまま目をぱちくりさせていた。
「おはよ」
あたしが声をかけると、なんだかまだ状況がわかっていないようで、彼らしくないぼさぼさの頭を掻いている。そのまま、包帯でぐるぐる巻きになった自分の足を神妙な顔で見つめている。
「あー……」
「思い出した?」
「うん。あーあ、弱っちいなぁ、おれの骨」
はー、と盛大なため息とともに、太田くんは再び仰向けに倒れた。困ったような笑顔。その顔には、見慣れない擦り傷がいくつもあった。
あたしは傍にあった椅子を引っ張ってきて腰を下ろした。
「太田くん、どうして逃げなかったの」
「……忘れものしたから、体育館まで取りに戻ってた」
「忘れもの?」
「親父の形見だよ」
体育館で爆発物を相手にしながら、いろんな工具を広げて、いきいきとしていた彼の様子が脳裏に浮かんだ。きっと太田くんは、あたしの言うとおりに3時前には1度体育館を出た。あたしが3時前に体育館から逃げたとき、使ってた工具たちが残されているのを見たから。だけど、自分だけが体育館から逃げて安全な場所に行くということに、やっぱり彼は耐えられなかったんだろう。大切な大切な、お父さんの形見。爆発の後あたしが見つけた太田くんは、それを離すまいと掴んでいた。
「いろいろ必死になってて、気づいたら3時だったんだよ。ヤバイって思った瞬間にもう、ボンって。爆弾、まさか床下にデカイのがあるなんて誰もわかんねーよな。足ぶっ飛んだかと思った。そう思ったら、上からバスケのゴール落ちてくるし。逃げられるかっての。あははは。……だけど、こんな中途半端なことになるくらいならさ、親父にも会えるし、おれも、いっそひと思いに」
「ばか!」
無意識に彼の言葉を遮っていた。大きい声が出たことに自分でも驚いた。太田くんの言葉の、その先を聞きたくなかった。
「太田くん、今日、おれまだ死にたくないって、言った」
「うん」
「あたし、太田くん、死なせない、って、言った」
「うん、おれ生きてるよ」
「ごめん、ごめん、ね」
「なんで城岡が謝んだよ」
みんな守れると思っていた。誰も傷つかずにすむと思っていた。だけどそんなに甘いものじゃなかったんだ。なんとかなるだろうと甘く見ていた、あたしたち、たった17歳の力はちっぽけなんだ。計画は、動いている。とても大きな力で。あたしの大切な人たちを巻き込んで。計画は、動いている。止まらない。ああ。
体の奥から悔しさがこみあげてきた。涙がぼろぼろ落ちた。
無力。
あたしは、無力だ。
「いたかったよね、いたいよね、ごめんね、ごめん」
太田くんは何も言わずに、大きな右手であたしの頭をわしゃわしゃと撫でた。
乱暴だけど、彼の手から確かな体温を感じた。
生きてるって、あったかい。
うつむいたら、手の甲へまた涙がぼろぼろ落ちた。いつのまにか沈みかけていた太陽でキラッと光った。
あたしは
あとどれくらい、こうやって生きていられるだろう。
浮かんで消えた問い、答えはない。
|
【第5話に戻る】 【第7話に続く】
| 第6話 |  |
 Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved.
Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved. |