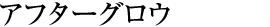 | 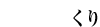 |
第8話
「こずえにとって、家族って何?」
いつだったか、真知子はあたしにそんなことを言っていた。
「え?」
「だから、家族の定義。どういうのが『家族』で、どういうのが『家族じゃない』の?」
「そんな難しいこと……あたしに聞かないでよ。辞書ひいたら? あ、国語の先生に聞くとか!」
「それじゃ意味ないわよ。あたしは、こずえの意見が聞きたいの」
「あたしの?」
「そう。こずえの思う『家族の定義』」
「うーん……ええと……」
その後あたしがどう答えたかは憶えていない。
だけど、どうして彼女がそんな突拍子もないことをあたしに聞いたのかは、今やっとわかった。真知子の生い立ちを聞いて、納得がいった。いわゆる『ワケありな家庭の子ども』である真知子は、自分とよく似た境遇の『父子家庭の子ども』であるあたしの意見が聞きたかったんだ。
泣き疲れておとなしくなった真知子を連れて家に帰ってきた。澪もずいぶん疲れていたらしく、ソファーに倒れこんですぐに寝息を立て始めた。
ふと目に留まったお母さんの写真を手にとってみる。窓から差し込んだ月の光が、それをぼんやりと照らす。
「お母さん、友達に聞かれたんだけどね、あのね」
問いかけても、もちろん返事はない。
「家族って、何だと思う?」
写真の中で、ずっと同じ表情のままのお母さん。それでも、あたしの大切な家族だ。
今日は本当に長い1日だった。体はくたくたに疲れているのに、真夜中の今だって頭は覚醒しっぱなしだ。たぶん、考えることが多すぎるからあたしの脳は眠りたくないんだろう。
だけど、疲労で動けなくなるのは嫌だ。そう判断し、頭は無視し体に従うことにして、あたしも真知子の隣で横になった。
病院の焼け跡に行きたい。
迎えた翌朝、窓から差す光に包まれて寝起きの澪がそんなことを言った。反対する理由もないから、3人でフラリと家を出た。
昨日の惨事を忘れてしまうような、いい天気だった。家の前の道沿いに、背の高いヒマワリがたくさん咲いている。昨日の出来事すべての輪郭がほやけて、まるで夢のように思えた。
だけど、病院の近くまで来るとそんな浮遊感は消えた。
見慣れていた景色がそこにはない。代わりに、ぐるりと張られた立入禁止のテープ。嫌なにおいが鼻をつく。
原型をとどめていない、かつて病院だった建物を見て、あたしはぼんやりと思い出していた――確か、今から50年くらい前のことになるんだっけ。あたしが生まれる前の昔のこと。アメリカの大きなビルがテロに巻き込まれて、飛行機に突っ込まれてぐちゃぐちゃになった。さらにその50年くらい前の夏、日本の南のほうではめちゃくちゃデカい爆弾が2発も落とされて、街2つが一瞬で吹っ飛んだ。いずれも、たくさんの、本当にたくさんの人が死んだ。最近、日本史と世界史の授業で得た知識。授業中に教科書で見た、それら惨事の写真が頭の隅っこでよみがえった。
あの事故みたいなことがまた起こる、しかもその首謀者は自国の政府。こんな悲しい現実を、あの時代に生きていた人は想像できただろうか。
目の前の瓦礫の山は、あたしに無言で残酷な事実を叩きつけてくる。
真知子がおもむろに口を開いた。
「こずえさぁ」
「うん」
「ずっと前にあたしが聞いたでしょ、『家族の定義って何』って」
「憶えてるよ」
「こずえ、どう答えたか憶えてる?」
「ええと、……ごめん忘れた」
昨日の一件から、なんとなく気まずくて真知子と話してなかった。というか、真知子が無口になっていたんだ。だから、いつもの調子で話しかけてくれて正直ほっとした。
「澪は? 家族ってどういう人のことを言うんだと思う?」
座り込んで砂いじりをしていた澪は、少しの間動きを止めて沈黙した。それから、まだ何か考えこむみたいに、こちらに顔を向けないまま答えた。
「家に帰ったら待っててくれる人……かなぁ」
――あ。
「そうだ、思い出した。真知子、あたしあの時、『帰る場所』って言ったよ。澪と同じだ」
「そうよ。アンタたち二人、思考回路が似てるわ」
真知子が言うと、澪は思い出したように喋りだした。
「あとね、あとね。家族って、いっしょにいる人。安心できる人。あったかい人。学校の授業じゃわかんないような大切なことたくさん教えてくれる人。あと、」
澪はパッと明るい顔をしている。
「あたしのことをすきでいてくれる人! そんで、あたしもすきな人」
真知子は微笑んでいた。澪の言葉を理解してるのかしてないのかよくわからないけど。
「だからさ、マッチ。大丈夫だよ」
「え?」
「あたしはね、マッチもコズも家族だって思ってるから! 二人ともさ、あたしはずっと味方でいるから、安心しなさーい」
澪は歯を見せて、にひひひ、と笑った。
確かに、真知子の言うとおり、あたしと澪は思考回路が似てるのかも、だってあたしも澪の言うことには大いに同感だから。
「ね、血のつながりとかさ、どうでもいいんだよね」
「そうだよ、マッチ」
焼け跡をぼんやりとした目で見つめていた真知子が口を開いた。
「じゃあ、あたしは、今からでも、叔父さんたちのことを、」
「うん」
「……家族だって、思っても、いいの?」
「あったりまえじゃん」
いつも澪の保護者みたいになってる真知子が、澪に救われてる。なんだかおかしな図。
ねぇ真知子、あんた、澪がいてよかったね。絶対に言わないけど、心の中でそう思った。澪に限ったことじゃない、友達がいてよかったね。よかった。あたしだってそうだ。二人がいてよかった。いなかったら、今のあたしはいないだろう。恥ずかしいから、澪みたいに素直に言えないけど。
少しだけ幸せな空気に包まれていると、後ろから複数の足音が近づいてきた。
「真知子」
振り向くと、中年の男女が立っていた。真知子が目を丸くしている。ああ、きっとこの人たちが――
「叔父さん、叔母さん……」
やっぱり。この人たちが、真知子の叔父さんと叔母さん。育ての親。
「恭平おじさんから聞いたぞ。学校も大変だったんだって」
「昨日から連絡もとれないし……心配したのよ」
あたしは、少し真知子から後ずさった。
澪を見ると、じっと立って真知子たちを見つめている。あたしを見ると、無言でうなずく。
がんばれ、がんばれ。ちゃんと向き合って、一歩踏み出せよ、真知子。
「――ごめんなさい」
彼女の第一声は意外なものだった。
「あたし、自分の生みの親じゃないって知ってから、叔父さんと叔母さんのことどうしても、お父さんお母さんって呼べなかった。ただ自分のことを養ってくれてるだけの大人だって思ってた。どうしても、家族だって思えなかったの、」
声が震えている。
「今までごめんなさい、そっけない態度で、ろくに話もしなくて、接しづらい嫌な子どもで、めんどくさい子どもで、本当にごめんなさい」
それだけ一気に言うと、頭を垂れた。真知子の表情は見えない。
たったこれだけのことを伝えるのに一体どれだけの時間がかかったんだろう。何日、何か月、何年かかったんだろう。この瞬間を、どれだけ待っていたんだろう。
「謝ることなんてないんだぞ」
「そうよ。むしろ謝るのは私たちのほう」
「え?」
二人から思いがけない言葉が発せられた。
「とにかく不自由なくさせてあげたいと思って、仕事で成功することにばかり気が行ってたわ。何度もさみしい思いをさせたわよね。私たちの勝手な考えで。本当に、ごめんなさい」
「それに、面倒な子どもなんて思うわけないだろう」
「ほんとに……?」
「当たり前だろ。だってな、真知子。お前は、」
叔父さんはにっこりと笑った。
「お前のお父さんとお母さんが残した大切な宝物なんだから」
真知子が嗚咽を漏らした。手で顔を覆って、静かに泣いた。
叔父さんと叔母さんは真知子にとって、昨日みたいに泣き叫ぶことができるような相手ではないのかもしれない。だけど今はいい。真知子が二人の前でほんの少しでも弱さを見せたから。見せることができると思えたのだから。これまでに作ってしまった隙間も、少しずつ少しずつ埋めていけばいい。
真知子、叔父さん、叔母さん。3人はきっと、『家族』。これまでそう呼べなかったなら、これからそう呼べればいい。
だけど、澪がさっき言ったように、あたしと澪と真知子も『家族』なんだろうと思う。だって、今のあたしは、まるで母親みたいな気持ちなのだから。
そうだよね、澪。
「あれ?」
真知子たちの邪魔をしないように、話しかけようとした、澪の姿が見当たらない。辺りをぐるぐると見渡して視界の端にとらえた彼女は、あろうことか黄と黒の縞模様のテープをくぐって、人のいない場所から焼け跡の中へふらふらと歩いていた。
「澪?」
あわてて追いかける。澪は、何かに呼ばれるかのように迷うことなく足を進める。どこへ行くのかまったく見当がつかず、なんとなく、呼び止めることはためらわれた。
そのまま焼け跡から逸れて、パトカーや救急車など救助車両がたくさん止まっている場所へたどり着いた。そういえば今朝「焼け跡に行きたい」と言いだしたのも澪だった。もしかして何か目的があったのかもしれない。昨日ここでなくし物でもしたのかな?
大きな消防車の向こう側で、ついに澪の足音は止まった。澪、何かあったの。そう言ってのぞきこんだあたしは、思わず声をあげそうになって口を押さえた。
そこにあったのは、学校の爆発の時に倒れたあたしと太田くんが乗ったワゴン。傍に並べられているのは、火傷と黒焦げで悲惨な状態になった――人。何人もの人。それをワゴンに積む、一人の男性。その手には、血のついた軍手。
そして、それらにまっすぐに対峙する澪は、抑揚のない声で言った。
「おとうさん」
澪の『おとうさん』――ノザキさんはギョッとした顔で振り向いた。澪の顔には表情がなかった。
「澪……こんな危ないところで、何してるんだ」
「おとうさんこそ何してるの」
ノザキさんは何も答えずにうつむいた。
「その人たち、うちのワゴンに乗せてどうするの」
「……うちに、連れていくんだよ」
澪の目がカッと開いた。
「ねぇ、昨日の火事の時だって来てたでしょ。あたし自分の目を疑ったけど、確かにうちのワゴンだった。もしかしてと思った。そしたらやっぱり今日も来てたんだね」
やっぱり。澪は昨日から確信を持っていたんだ。それで今日もおとうさんが来ているかと思って、焼け跡に行きたいって言い出したんだ。
「おとうさん、タヌキ殺したときのあたしにどう言ったかおぼえてないの?」
「澪、あのな、」
「誰にでも、どの命にも平等に未来があるんだって。あたしはおとうさんのその言葉を信じて、今までずっと命を大切にしてきたよ。ねぇ、あのときに教えてくれたのって、全部いい加減に言ったことだったの? 嘘だったの?」
「……嘘じゃないさ」
「意味わかんないよ。政府の人殺しの手伝いみたいなことしてさ、」
そこまで言って澪は声を詰まらせた。
「……情けない父さんを許してくれ」
|
【第7話に戻る】 【第9話に続く】
| 第8話 |  |
 Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved.
Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved. |