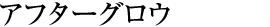 | 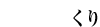 |
第10話
「あたしは、目の前で小沢野駅の駅舎が爆発するのを見ました」
まずは澪だ。緊張のせいか少しだけ震える声で、あの日のことを話す。
「駅から、いつもどおり電車に乗って帰るつもりだった。だけど、少し用事があったから駅から離れた道を歩いていました。そしたら、何の前触れもなく、駅舎が爆発したんです。耳が壊れるような、大きな音でした。近くにいた人たちはみんな慌てて逃げ惑うし、パニック状態で、」
ひと息おいて、澪は続ける。
「本当に、こわかった」
切実な声だった。それは作り話でも伝聞でもなくて、澪自身が体験したことだからだ。
「そのあとニュースで駅の様子がうつされました。あたしも見ました。そのとき政府は、爆発時に駅舎の中にいた人たちについてはっきりした情報を出してなかったはずです」
そう、『現在調査中』とかいう曖昧な言葉でごまかして。
「クラスメートのお父さんがその時駅舎にいたんです。それで……お父さんは帰ってこないそうです」
太田くん、ごめん、許してね。あたしは心の中で謝った。
「そんなあたしたちが通っているのは、小沢野高校です」
さぁ、今度は真知子の番だ。
「駅舎の爆発があった次の日、うちの学校の体育館で、小規模ではあったけど爆発がおこりました。幸いにも、全員無事でした」
あたしたち3人と太田くんが協力して、なんとか全校生徒を体育館に行かせないようにした、あの日のことだ。
「駅や学校……どちらも、人がたくさん集まる場所です」
「そして最後はここ、病院」
「あたしたちは友人のお見舞いに来ていました。昨夜発生したのが、出火元不明の火災」
「おかしいと思いませんか? どうしてこんなに連続して、人がたくさん集まるような場所で爆発や火事が起こるんですか」
「昨日の火事では、人間以外も、たくさん傷つきました。あたしは、焼けた花や虫をたくさん見ました」
澪が、ぽつりと言う。
「まるで、……一度にたくさんの命を巻き込もうとしているみたいでしょ」
「これら一連の出来事、裏につながりが何かあるんじゃないか? って思ったのは、さっきのことで、」
真知子に目で合図を送る。真知子は、頷いて計画書を広げた。
「はいはいはい。実はこれは、さっきここで拾ったものなんです。カメラさーん、ちょっと寄ってもらえますかー?」
兄ちゃんが真知子の手元にぐっとカメラを近づける。
「見えますでしょうか、『小沢野市に於ける人口削減計画』の文字」
「これがどういうことは、初めはあたしたちもわかんなかったよね」
「うん」
「でもここまで話せば、この計画の名前の意味するところは伝わると思います」
落ち着け、あたし。落ち着け。
「政府は、小沢野市の人口を無差別殺人によって減らそうとしているってことが」
――ああ、言っちゃった。今テレビを通してあたしたちの言葉を聞いてる人たち、ショック受けて泡吹いて倒れちゃったりしてないかな。そんなことを、頭のすみっこでぼんやり考えた。
「じゃあどうして人口を減らす必要があるのか? っていうことについては、この計画書に詳しく書いてありました。あたしが簡単に説明させていただきます」
真知子がカメラの前に出る。
「この計画書によると。地球温暖化が進んだことについて、その原因は日本にあると諸外国は主張しているみたいなんです。日本の人口増加によるものだ、って。このまま日本のせいで温暖化を進められちゃたまらないから、その人口の多さをどうにかしろと」
「殺せばいい、殺せば人口を減らせるだろ、……みたいなことを言われて」
「それで……実行しちゃったんだね」
「そういうこと。そして、たまたま第一の実験台として選ばれたのが、この小沢野市だったというわけ、だそうです」
これでおおまかなことは伝えられただろう。あたしたち3人、顔を見合わせて頷いた。
「小沢野市のみなさん、」
誰でもいい、あたしたちのちっぽけな叫び、誰かに伝わればいい。ひとりでもいい、誰か、誰か。
「政府はとんでもないことをしているんです」
「あたしたちは、死にたくないし、殺されたくもない!」
「命あるものは、すべて未来があります。こんなわけのわからない計画で、あたしたちの自由な未来、奪われていいのでしょうか?」
澪も真知子も、驚くほど冷静だった。二人とも、確かに、伝えようとしているんだ。
あたしは、カメラをじっと見据える。
「これ以上、犠牲者が増える前に」
「全力を尽くして、『人口削減計画』を止めましょう!」
++++++++++
「うわぁ……」
広げたお弁当に手もつけず、あたしと澪は真知子の成績表の紙っぺらに見入る。昼休み前、春休み明けの実力テストの成績表が配られたのだ。
「ま、特に力入れて勉強した科目もないしね。こんなもんよ」
叔母さんのお手製だという杏仁豆腐を口に運びながら、真知子はこれといって喜んだ様子もなく答える。各科目の順位の欄にずらりと並ぶ数字は、すべて1桁だ。
「数学だけは、どーしても太田に適わないのよね。次は絶対勝つわよ」
「いやいや真知子、力入れて勉強してないのにどうして英語で1番が取れるの。ていうかどんな頭の構造してんの」
「マッチ、あたしに脳みそ分けてよ……」
「馬鹿ね澪。脳は重量じゃなくてシワの数よ、シワの数」
真知子は、あたしと澪の成績表を手にとって眺めた。
「こずえは、前よりは成績あがってるわね。がんばったじゃない」
「うん、春休みに兄ちゃんに勉強少し教えてもらったんだよね」
「澪は……数学をがんばりましょうか」
「157人中154位って、アンタ……」
「大丈夫、あたしより数学ができない子が学年に3人もいるんだよ? それよりさ、あたしね生物がんばったんだよぉ」
「生物は、えーと……98点、で、1番!?」
澪は誇らしげにあたしたちを見る。
「えへへ、すごいでしょ! 生物、1等賞だけは譲れないんだよね〜」
「98点、やるじゃん。あと2点、何を間違えたの?」
確かに気になる。
「……えーとね、うんとね、あれだよ」
「いや、あれって何のこと?」
「ほら、あれだって」
「あれじゃわかんないわよ」
「……あーっもう! 思い出せない!」
「えっ、あたしたちまで気になっちゃうじゃない!」
「ほら、あれだってば……ああもう、思い出せない! ここまで出かかってんのに!」
そう言って、はがゆそうな澪は人差し指で自分のこめかみをトントンと叩いた。
「あっはははは! 澪、それをやるならこめかみじゃなくて喉でしょうが!」
「こめかみって、喉のところ過ぎちゃってんじゃん! あははは!」
「あっ、ほんとだ。あたし今まで気づかないでずっとこうやってたかも」
「えー、澪、恥ずかしっ! 恥ずかしいよアンタ!」
「あっはっはっは」
ひとしきり爆笑して、ようやくお弁当に手をつけた。
「あ」
開いたあたしのカバンの中で、マナーモードになった携帯が黙って光っている。すっかり忘れてた。時計を見ると、そろそろだ。あたしは携帯には応えずに、カバンを持って立ち上がった。
「じゃね、帰るわ」
澪と真知子が手を止めて、あたしのほうを見た。
「あ、そういえばコズ、今日だっけか」
「行ってらっしゃい。あたしたちのこともよろしく言っといてね」
「わかったよ。んじゃ、ばいばい」
教室を出ると、焼きそばパンをくわえた太田くんとすれ違った。
「ふぉう、ふぃおーふぁ、」
「とりあえず太田くん、食べるかしゃべるかどっちかにしようか」
「……はーっ」
ひとしきり飲み込んで、太田くんは息を吐き出した。
「城岡、帰んの? なんかあった?」
「うん。……ほら、あれ。今日なんだよね」
太田くんは一瞬きょとんとしたが、すぐに理解したようで、にっこり笑った。
「いい天気で良かったな」
「うん!」
廊下の窓を通して見た空は、雲ひとつない晴天。そうだね、今日、晴れてよかった。
「じゃあ、行くね」
「親父さんによろしく言っといてくれよ、太田の息子ですって」
再び焼きそばパンに食らいついた彼を見て、あたしは玄関へと向かった。
丘の坂道を歩く。春の風があたしの髪の毛に絡む。傷んだ毛先が太陽を通して茶色く光っている。
そういえばずいぶんと髪の毛が伸びた。高校生最後の1年が始まろうとしているんだ、次の日曜日にでも、美容院に行こう。おすすめの美容院、真知子に教えてもらおうかな。
数メートル後ろを歩いているお兄ちゃんは、くしゃみばっかりしてる。花粉症にとって春ってのはつらいだけの季節らしい。花粉とは無縁のあたしにはわかんないけど。
「親父ぃ、ティッシュくれ〜」
「さっきあげたアレで最後」
「えぇ! まじかよ……じゃ、こずえ〜」
「あたしティッシュなんて持ってないよ」
「お前なぁ、女子たるものハンカチちり紙はヒチュジュヒンだろ、ヒチュジュヒン」
「何その男女差別。ていうか『必需品』でしょ、ひ・つ・じゅ・ひ・ん。兄ちゃん言えてないよ」
「シツジュヒン?」
「……もういいよ」
たわいのない話をしながら丘をのぼりきると、眼前に小沢野市が広がった。
あたしたちの生きる、ちっぽけな地方都市。
「あの白いきれいな建物が小沢野駅舎で、あれが学校の校庭で、あれが病院跡か」
「うちの屋根は見えるかなぁ」
「んー、どこらへんだろうなー」
目をこらして見ると、道路沿いなど、街の随所に見える淡い桃色のかたまり。
「兄ちゃん、桜」
「本当だ。あの白っぽいやつって全部桜の花だよな」
「うん、たぶん桜だよ。きれいだねえ」
「こういう花見も、オツなもんですなぁ」
そう言って、兄ちゃんは「ぶぇっくしゅ」とくしゃみをした。オツだかなんだか知らないが、その下品なくしゃみには風情もくそもない。
「あぁぁもう、おれ限界。車にティッシュ取りに戻るわ」
「あーはいはい、いってらっしゃいな」
とりあえずあたしは携帯を取り出して、見下ろした街にカメラを向けた。ピロリンと音がして、小さな液晶の中に小沢野市が閉じ込められた。
もうそろそろ授業も終わった頃だろうから、澪と真知子と太田くんに写真を送った。本文は考えるのが面倒だったからナシ。だけどいいや、今見えてるこの景色を3人にも見てもらえればそれでいいや。
「おーい、線香つけたぞー」
お父さんの声がした。あたしは、返事をして、二人――お父さんとお母さんのもとへ向かう。
そう、今日はお母さんの命日だ。
お母さんが死んでから今までは、お父さんが忙しかったり兄ちゃんがいなかったりで、命日にお墓参りに来たことなんてなかった。だけど、お父さんが、「今度の命日は墓参り行くか」なんて言い出した。だから、家から少し離れたこの丘の上の墓地、お母さんのお墓があるここに来た。
「やっと、落ち着いて話ができるなあ」
「……あたしはいつだって落ち着いてたけどさ」
「こずえには迷惑かけたな。……本当に、すまなかった」
お父さんが少し頭を下げる。
「だけど、これでやっと母さんに顔向けできるよ」
あの日、あたしたちがブラウン管を通して告発した結果、それは見事に市民に広まった。
最終的に、「人口削減計画」は、白紙に戻った。
持ってた計画書は、ハサミで細かく細かく切り刻んで再現不可能にしてから、学校の焼却炉で灰にした。もう必要のないものだったから。
澪は今までどおり元気いっぱい飛び回っている。真知子は前よりも少し性格がまるくなった気がするけどやっぱり金持ちだ。太田くんは、相変わらずの人のよさで人気者だ。
あの夏の数日間のことは、今でも夢だったんじゃないだろうかと思う。だけど、つるりと新しく建てられた小沢野駅の駅舎が確かな証拠となって、出来事の数々があたしの脳裏によみがえる。
「お父さん、あたしお父さんに聞かなきゃいけないことがある」
「ああ。俺も、こずえに話さないといけないことがある」
だいたい、考えてることは同じだろうけど。お父さんが重々しく口を開いた。
「―――母さんのことだよ」
お父さんと兄ちゃんの言動で、あたしの中でいろんなことが引っかかっていた。
「まるで、お母さんが計画に関わってたみたいな感じで話してるでしょ。お母さんはもう6年も前に亡くなってるのに」
「こずえ、あのな」
お父さんが、あたしの言葉を遮った。
「計画自体は、お前が生まれる前からあったんだよ」
「あたしが生まれる前……って、17年以上も前?」
「そう、温暖化が深刻になってきた頃から」
知らなかった。人口削減計画なんていう恐ろしい話は、そんなに昔からあったんだ。
「母さんは、国の専門機関に勤めてる研究員だっただろう」
「うん、そうでしょ」
「何の研究してたのか、憶えてるか」
「えーっと……」
確か、お母さんは、地質の研究のために向かった山で土砂崩れに巻き込まれて亡くなったはずだ。そう聞いていた。
「土、とかの研究かな?」
「んー、それもだけどな。母さんは、生態系とか、大気とか……おおまかに言えば、環境について研究してたんだよ」
「そうだったんだ……」
「今だから言える話、お前たちの名前だって、母さんが『これがいい』って言って聞かなかったんだよ」
『大地』と『こずえ』。お父さんは笑った。
兄ちゃんの名前は大地という。あたしの名前はこずえ。なるほど、環境のことについて研究してたんなら、納得のいく話かもしれない。あたしは、どうして自分の名前が「梢」なのか、なんて、考えたことなかった。
「俺があそこまでして計画を阻止したかったのは、母さんのためなんだよ」
「お母さんの、ため?」
風が吹いた。線香の匂いが流れてくる。
「温暖化が進む中で、当然、母さんの耳にも計画のことが入った。正義感の強いあいつのことだったからなぁ……まわりの人間も止めたんだが……告発しようとしたんだよ」
「うん」
「それが本部に知られて……こずえ、嘘ついてて本当にごめんな、母さんは本当の事故で死んだわけじゃないんだ。……計画のことを公にする前に、……政府の手によって、母さんは、」
「お父さん、いいよ、何も言わないで」
その先は、言わなくてもわかる。わかって、あげなくちゃ。
お父さんの話を聞いても別段驚かないのは、きっとあたしはどこかで気づいていたからだろう。お母さんも計画の犠牲者のひとりだということ。
あたしは手をのばして、つやつやとした光沢をのある墓石に触れてみる。冷たい。
「おかあさん、」
あなたの願いは、今ようやくお父さんが叶えてくれたんだよ。もしかして、この世界を去ってからの6年、ずっと不安であたしたちのこと見てたのかな。だったら、お母さん。もう心配することなんか何もないんだよ。
だから、ね、
「おやすみなさい」
人口削減計画が白紙に戻って、今、お母さんは安心できただろうか。そうだといいな。
街を見下ろしたお父さんが、ずずっと鼻をすする音が聞こえた。表情は見えないけど、たぶん、花粉症ではないだろうと思う。
どこから現れたんだろう、兄ちゃんが箱ティッシュをお父さんに差し出した。お父さんは無言で取って鼻をかんだ。あーあ、せっかく今一瞬だけ兄ちゃんかっこいいと思ったのに、差し出したのが箱ティッシュじゃあ、なんかキマらないんだよなあ。お父さんも、鼻かんでるの見てると、ただの中年のオヤジなんだよなあ。兄ちゃん、また「ぶぇっくしゅ!」ってくしゃみしてるよ。あーあ、よくわかんない親子だ。……だけどあたしもあの男どもと同じ血が流れてるのか。うーん、複雑な気分だ。なんだか笑えてきた。
「こんな家族で、いいのかなぁ」
ぶわっと強い風が吹いた。傍に立っている大きな樹がざわめいて、それがなんとなく、お母さんが「いいんだよ」って言ってくれてるみたいだった。そう思った途端、いろんな気持ちといっしょに涙がこみあげてきて、すぐに目から溢れた。
愛情とか、感謝とか、そんな簡単な言葉では表すことができないような、なんだかすごく尊くてきれいな涙。
あたしは、もう一度、目の前に広がる小沢野市を見渡した。
これが、あたしの住む、小さくて大きな世界。
澪、真知子、太田くん。
みんながいるから、あたしは家族と向き合えたよ。だから3人のことも、『家族』って呼ばせて。
お父さん、兄ちゃん。
離れてたって、あたしのことを考えてくれてる二人がいるから、あたしは生きていける。
ねぇ、お母さん。
この街を、あたしを、生かしてくれて。
本当にありがとう。
夕方5時のサイレンが鳴り始めた。『遠き山に日は落ちて』。
ここから見える世界は、こんなにもやさしい色をしている。
あたしは、ぐっとひとつ伸びをした。
「お父さん、兄ちゃん、家に帰ろう!」
どうか、明日も明後日も。
あたしの大切な人と、その人たちの世界が、
穏やかでありますように。
|
【第9話に戻る】
| 第10話 |  |
 Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved.
Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved. |