アーカイブ
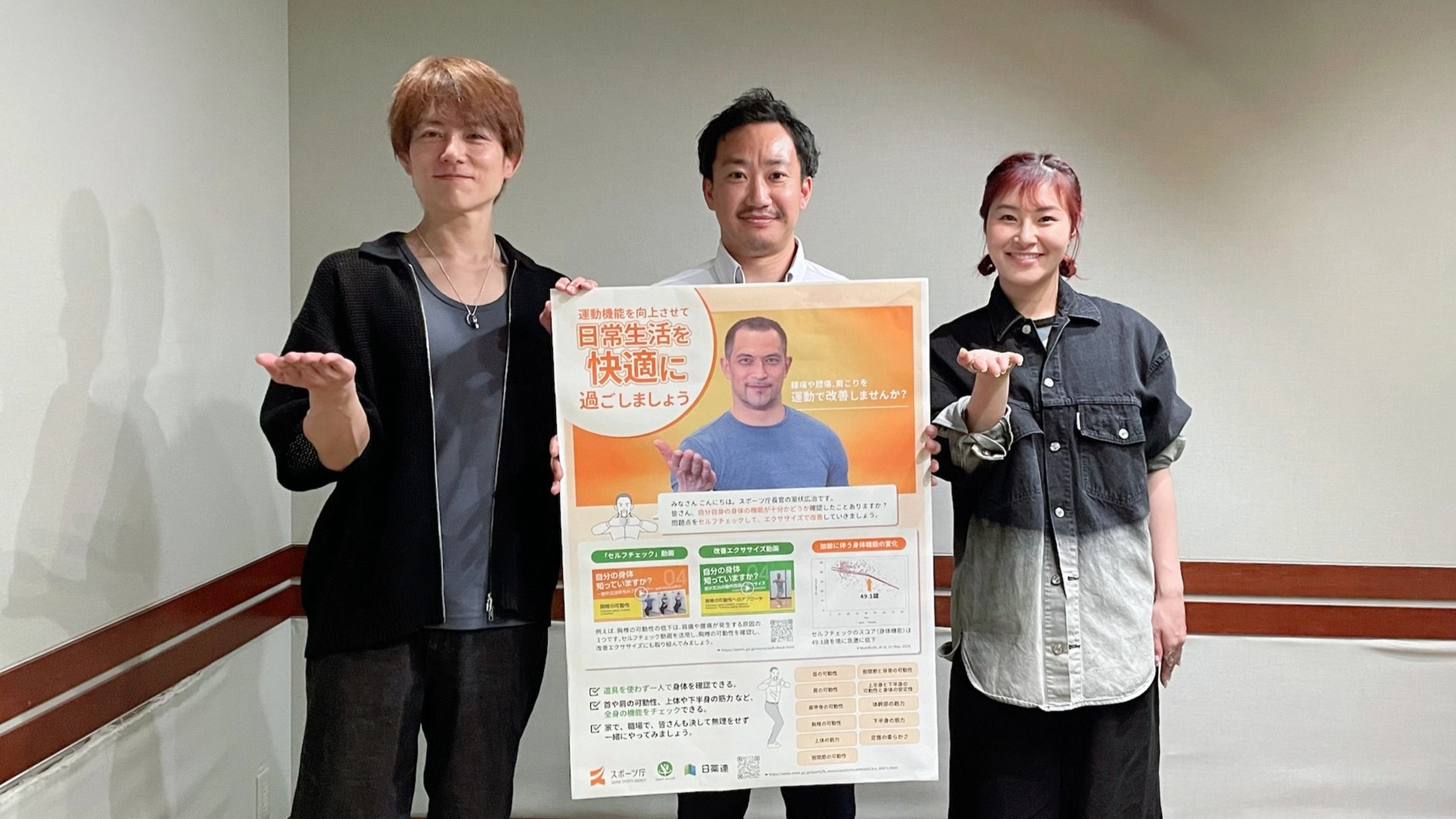
2025.05.25
ライフパフォーマンスを上げていこう!
皆さんは日々、運動していますか?
運動やスポーツを行う際、自分の心や体の状態に合わせ、目的を持って行うことで、より効果が期待できることがあります。
そのためにも、まずはあなた自身の身体状態を知ることが大切です。
今回は「ライフパフォーマンスを上げていこう!」というテーマで学びました。
続きを読む
運動やスポーツを行う際、自分の心や体の状態に合わせ、目的を持って行うことで、より効果が期待できることがあります。
そのためにも、まずはあなた自身の身体状態を知ることが大切です。
今回は「ライフパフォーマンスを上げていこう!」というテーマで学びました。
(杉浦)
まずは佳菜子ちゃん、そしてリスナーの皆さん! これ、できますか? 今日は、まず、これから僕が言うことをやってみてほしいんだよね。いきますよ。背筋を伸ばし、手を両腰に当てて、まっすぐ立ちます。口を閉じたまま、首をゆっくりと右側へ回してみましょう。顔の中心が肩の前のラインまで向いていますか? 顔を反らすなど左右に傾けてはいけません。頭の軸はずらさずに、肩の前のラインまで回せますか?
(村上)
私、できてますか?
(杉浦)
佳菜子ちゃんは…、できてると思います! 皆さんもできてますかー? これができないかた、首の可動域が十分ではない可能性があります。リスナーの皆さん、どうですか? できましたか? 実はですね、これ、アテネオリンピックのハンマー投げ金メダリスト、現在スポーツ庁長官の、あの室伏 広治さんが、身体運動に関わる骨、筋肉、関節などの状態を把握して「ライフパフォーマンス」を上げるために考案した、「セルフチェック」のうちの一つなんだよね。
(村上)
やっぱり、スポーツ イコール 室伏さんのイメージありますから。「室伏さんが考案した」と聞くと信頼もありますし、興味も沸きますね。でも、その「ライフパフォーマンス」って何ですか?
(杉浦)
それね。きっと初めて聞くかたも多い言葉だと思いますので、早速、今日の講師に教えていただきましょうか。スポーツ庁健康スポーツ課の見供 翔(みとも しょう)さんです。見供さんは理学療法士で、これまで多くのアスリートに運動指導をされてきたかたなんです。
(村上)
見供さん、早速「ライフパフォーマンス」についてなんですけど、これ、どういったものなんでしょうか?
(見供)
はい。簡単に説明しますと、ライフパフォーマンスとは、年を取ったり、就職、結婚、出産、子育てなどで環境が変わったとしても、自分の心や体をうまくなじませて、自分のやりたいことや目標に向かって前向きに行動できる能力のことです。
(杉浦)
「たとえつらいことがあっても乗り越えられる力」でもあるんですよね。
(村上)
なるほどねー。
(見供)
そうですね。ライフパフォーマンスのイメージを例えるなら、高齢者の場合、寝たきりにならずに、家事や外出、地域活動をし続けることができる能力のことです。また働く世代や子育て世代の場合は、仕事と家事をキビキビと両立し、周りと良好な人間関係を築きながら活躍し続ける能力という感じでしょうか。
(村上)
やっぱり「どんな状況であっても、自分が望むように活動できる能力」っていうことですよね。それは、誰しも身に付けたいと思っているものではありますよねー。
(見供)
そのためスポーツ庁では、性別、年齢、障害の有無に関わらず、運動・スポーツを通じて多くの人の「ライフパフォーマンスの向上」を目指しているんです。
(村上)
そもそもスポーツ庁は、スポーツを通じてさまざまな取組を行うところですもんね。
(見供)
はい。スポーツ庁は、みんながスポーツを楽しめるようにしたり、学校や地域での運動をサポートしたり、日本の選手が世界で活躍できるように応援する国の機関です。現在は、「どうすればもっと多くの人が日常的に楽しく運動できる機会を増やせるか」「スポーツを通じて健康増進が図れるか」「スポーツで地方を盛り上げられるか」「まちづくりをできるか」「共生社会をつくれるか」こうした課題と向き合い、様々な取組を進めています。
(杉浦)
最近だと、JAXAとスポーツ庁がタッグを組んだことが話題になりましたよね。
(見供)
はい。トップアスリートと宇宙飛行士に求められる能力は違うと思いますが、共に厳しいトレーニングを経て、高いパフォーマンスを発揮する点では同じです。そのため、アスリートと宇宙飛行士の知見やノウハウを共有し、人類の可能性を広げていこうと連携する協定を結びました。今後この協定に基づいて、様々な取組を進めていく予定です。
(村上)
すごいですね! 人の肉体の進化が見られそうで楽しみですね。めちゃくちゃ興味ありますよ! スポーツ庁が取り組んでいることって、国民の健康増進から、地方創生、共生社会の実現、さらには人類の可能性の拡大への挑戦まで、ものすごく幅が広いんですね。
(見供)
はい。こうした様々な取組の中の一つが、先ほどご紹介した「ライフパフォーマンスの向上」なんです。
(村上)
ライフパフォーマンスは「どんな状況であっても、自分の心や体をうまく適応させて自分のやりたいことや目標に向かって前向きに行動できる能力のこと」ということでしたけど、その能力はどのように上げていけばいいんでしょうか?
(杉浦)
そう、そこがポイントでございます! ライフパフォーマンス向上に向けて実践してもらいたいこと、それは「目的を持った運動・スポーツ」です!
(村上)
目的って、例えばダイエットとか、マラソン大会で上位入賞とか、そういうことですか?
(杉浦)
いや、そう思いがちなんですが、ここで言う「目的を持った運動・スポーツ」は、また別の考え方なんだよね。
(村上)
見供さん、ライフパフォーマンスの向上に向けた「目的を持った運動・スポーツ」というのは、どういうことでしょうか?
(見供)
簡単に説明すると、ただなんとなく体を動かすのではなくて、自分の心や体の状態に合わせて「どんな運動をしたらいいのか」考えて、それに適した方法で運動をすることです。
(杉浦)
例えば「ウォーキング」って、なんとなく健康に良さそうじゃない?
(村上)
確かに。家でじっとしているよりは、ワンちゃんのお散歩でウォーキングしたりとか。やっぱりいい運動になりそうですよね。
(見供)
そうですね。ウォーキングは、ただなんとなく歩くのもいいのですが、目的を設定して、それに応じた歩き方を工夫すると、ウォーキングの効果を更に高めることができます。例えば、「いくつになっても元気に歩きたいから下半身の筋力を向上させたい」という目的がある場合は「大股で歩いてみる」。「最近、すぐ疲れてしまうから、もっと動けるようになりたい」という目的がある場合は、心肺機能を向上させるよう「長時間歩く」。同じ歩くでもこういう工夫をすると、より効果を期待することができます。
(村上)
確かに! じゃあ、例えば「よく足を捻ってよろけちゃう」という悩みがあったとしても、歩き方の工夫で改善できちゃったりするんですか?
(見供)
はい。よく足を捻ってしまうのは、バランス感覚とも関係しているかもしれません。バランスや姿勢を向上したり柔軟性や機敏性を強化するために、デコボコした道を歩くといいかもしれません。
(杉浦)
デコボコした道だと、ハイキングとか登山とか良さそうですよね。
(見供)
はい。また「勉強や仕事でイライラすることが多いから、楽しく運動してストレス発散したいな」という目的があったとしたら、自律神経などを安定させるために、自然の中を歩くのもいいですね。
(村上)
私も、だからすぐ宮古島に行って…。宮古島でランニングをしたとき、めちゃくちゃ爽快だったんですよ。坂があるのでめちゃくちゃしんどいんですけど。でも、スッキリするから。そういうことですよね? やっぱり、ウォーキングも目的によっていろんな工夫ができるものなんですね。
(見供)
目的を持った運動・スポーツを実施して、ライフパフォーマンスの向上を目指せば、健康の維持や増進はもちろん、クオリティ オブ ライフ、いわゆる生活の質も高めることができ、充実した生活を送ることが期待できるんです。
(村上)
なるほど。でも、その目的を設定するのが難しい、っていうかたもいそうじゃないですか? 今、特に心や体のことで気になることや悩みがない人もいますもんね?
(杉浦)
そう。そこで、皆さんにやってみてもらいたいのが、番組冒頭で行った、室伏長官が考案した「ライフパフォーマンス」を上げるための身体診断「セルフチェック」なんです。
(見供)
どんな運動・スポーツをするにも、まず自分自身の身体機能が十分かどうか知ることが大切です。その知るためのツールとして、セルフチェックを皆さんにやっていただきたいと思っています。
(杉浦)
室伏長官考案のセルフチェックの特徴は二つありまして、一つは「道具を使わず一人で身体の機能を確認できること」。もう一つは、「首や肩の可動性、全身の筋力などの機能をチェックできること」なんですね。
(見供)
このセルフチェックは、室伏長官自らが動画で分かりやすく紹介していて、問題点が見つかった場合、改善するためのエクササイズも動画で紹介しています。
(村上)
それはありがたいですね、セルフチェックだけじゃなくて、その先までサポートがあるのは。「やってみよう!」と思いますよね。
(杉浦)
エクササイズもね。家でできちゃう。
(見供)
では、今日はお二人に、肩甲骨の可動性をセルフチェックしてもらいたいと思います。
(杉浦)
リスナーの皆さんは、鏡を見ながら、無理せず一緒にやってみましょう。
(見供)
では、まず最初に、右手の親指と人差し指で左側の耳たぶをつまんでみましょう。その時、親指が顔の方、前を向くようにしてください。これがスタートポジションになります。そして、耳たぶをつまんだまま、肘を顔の前から頭の後ろに回し、回せたら、今度は顔の前まで戻します。この時に頭を前後左右に動かさないよう、頭の軸はずらさずに行ってみましょう。できますか? 左右やってみて、左右の違いも確認するといいかもしれません。
(杉浦)
肩甲骨、動きますね!
(村上)
肩甲骨、めっちゃ気持ちいいです!
(見供)
これ自体が運動にもなるんですが、この動きが難しい場合は、改善エクササイズをやってもらえるといいかと思います。実はこのテスト、トップアスリートでもできない場合があります。
(杉浦)
筋肉が邪魔になってでしょ? 室伏さん、筋肉パンパンですけど。
(見供)
筋肉が邪魔の場合もあるんですけど。室伏長官は、しっかり、きれいにできます。できない人は、顔が横を向いてしまったり、くぐれないっていうかたが多いです。ちょっと杉浦さん、怪しいなと思ってたんですけど。杉浦さんは、右に比べると左の肩甲骨の可動域が固い可能性があります。先ほど言ったトップアスリートでできないかたは、よくあるのが、腕を酷使する野球ですとか、バレーボール、水泳といった競技の選手が多いです。
(村上)
水泳の選手とかできそうなのに。
(見供)
そうですね。同じ動作を繰り返すことによって、特定の筋肉が固くなって、肩甲骨の動きが悪くなってしまう。そういう状態が起こり得るんです。
(杉浦)
逆にねー。これをできないかたは、改善エクササイズの動画を観て、肩甲骨の可動域を改善できるように日々取り組めばいいんですよね。
(見供)
はい。ライフパフォーマンスを向上させるためには「目的を持った運動・スポーツ」をすることが重要です。まずは、自分自身の身体の機能がどうなっているか確認して、問題があるようであれば改善できるよう、エクササイズを実施するなど、生活の中でできる運動から取り入れてみましょう。
(村上)
今日の話の中で特に注目したのは、「室伏長官のセルフチェックをやってみよう!」です。セルフチェックをやってみて、できなかったときの改善トレーニング方法までありますから。実際にやってみて楽しかったので、皆さんにもやってほしいなと思いました。
(杉浦)
僕は、「セルフチェック」「改善トレーニング」をやって、「ライフパフォーマンスをみんなで向上させましょう!」です。
「 関連リンク 」
・スポーツ庁「室伏長官が考案・実演する身体診断「セルフチェック」動画」
・スポーツ庁「Sport in Life~目的を持った運動・スポーツでライフパフォーマンスの向上を!」
まずは佳菜子ちゃん、そしてリスナーの皆さん! これ、できますか? 今日は、まず、これから僕が言うことをやってみてほしいんだよね。いきますよ。背筋を伸ばし、手を両腰に当てて、まっすぐ立ちます。口を閉じたまま、首をゆっくりと右側へ回してみましょう。顔の中心が肩の前のラインまで向いていますか? 顔を反らすなど左右に傾けてはいけません。頭の軸はずらさずに、肩の前のラインまで回せますか?
(村上)
私、できてますか?
(杉浦)
佳菜子ちゃんは…、できてると思います! 皆さんもできてますかー? これができないかた、首の可動域が十分ではない可能性があります。リスナーの皆さん、どうですか? できましたか? 実はですね、これ、アテネオリンピックのハンマー投げ金メダリスト、現在スポーツ庁長官の、あの室伏 広治さんが、身体運動に関わる骨、筋肉、関節などの状態を把握して「ライフパフォーマンス」を上げるために考案した、「セルフチェック」のうちの一つなんだよね。
(村上)
やっぱり、スポーツ イコール 室伏さんのイメージありますから。「室伏さんが考案した」と聞くと信頼もありますし、興味も沸きますね。でも、その「ライフパフォーマンス」って何ですか?
(杉浦)
それね。きっと初めて聞くかたも多い言葉だと思いますので、早速、今日の講師に教えていただきましょうか。スポーツ庁健康スポーツ課の見供 翔(みとも しょう)さんです。見供さんは理学療法士で、これまで多くのアスリートに運動指導をされてきたかたなんです。
(村上)
見供さん、早速「ライフパフォーマンス」についてなんですけど、これ、どういったものなんでしょうか?
(見供)
はい。簡単に説明しますと、ライフパフォーマンスとは、年を取ったり、就職、結婚、出産、子育てなどで環境が変わったとしても、自分の心や体をうまくなじませて、自分のやりたいことや目標に向かって前向きに行動できる能力のことです。
(杉浦)
「たとえつらいことがあっても乗り越えられる力」でもあるんですよね。
(村上)
なるほどねー。
(見供)
そうですね。ライフパフォーマンスのイメージを例えるなら、高齢者の場合、寝たきりにならずに、家事や外出、地域活動をし続けることができる能力のことです。また働く世代や子育て世代の場合は、仕事と家事をキビキビと両立し、周りと良好な人間関係を築きながら活躍し続ける能力という感じでしょうか。
(村上)
やっぱり「どんな状況であっても、自分が望むように活動できる能力」っていうことですよね。それは、誰しも身に付けたいと思っているものではありますよねー。
(見供)
そのためスポーツ庁では、性別、年齢、障害の有無に関わらず、運動・スポーツを通じて多くの人の「ライフパフォーマンスの向上」を目指しているんです。
(村上)
そもそもスポーツ庁は、スポーツを通じてさまざまな取組を行うところですもんね。
(見供)
はい。スポーツ庁は、みんながスポーツを楽しめるようにしたり、学校や地域での運動をサポートしたり、日本の選手が世界で活躍できるように応援する国の機関です。現在は、「どうすればもっと多くの人が日常的に楽しく運動できる機会を増やせるか」「スポーツを通じて健康増進が図れるか」「スポーツで地方を盛り上げられるか」「まちづくりをできるか」「共生社会をつくれるか」こうした課題と向き合い、様々な取組を進めています。
(杉浦)
最近だと、JAXAとスポーツ庁がタッグを組んだことが話題になりましたよね。
(見供)
はい。トップアスリートと宇宙飛行士に求められる能力は違うと思いますが、共に厳しいトレーニングを経て、高いパフォーマンスを発揮する点では同じです。そのため、アスリートと宇宙飛行士の知見やノウハウを共有し、人類の可能性を広げていこうと連携する協定を結びました。今後この協定に基づいて、様々な取組を進めていく予定です。
(村上)
すごいですね! 人の肉体の進化が見られそうで楽しみですね。めちゃくちゃ興味ありますよ! スポーツ庁が取り組んでいることって、国民の健康増進から、地方創生、共生社会の実現、さらには人類の可能性の拡大への挑戦まで、ものすごく幅が広いんですね。
(見供)
はい。こうした様々な取組の中の一つが、先ほどご紹介した「ライフパフォーマンスの向上」なんです。
(村上)
ライフパフォーマンスは「どんな状況であっても、自分の心や体をうまく適応させて自分のやりたいことや目標に向かって前向きに行動できる能力のこと」ということでしたけど、その能力はどのように上げていけばいいんでしょうか?
(杉浦)
そう、そこがポイントでございます! ライフパフォーマンス向上に向けて実践してもらいたいこと、それは「目的を持った運動・スポーツ」です!
(村上)
目的って、例えばダイエットとか、マラソン大会で上位入賞とか、そういうことですか?
(杉浦)
いや、そう思いがちなんですが、ここで言う「目的を持った運動・スポーツ」は、また別の考え方なんだよね。
(村上)
見供さん、ライフパフォーマンスの向上に向けた「目的を持った運動・スポーツ」というのは、どういうことでしょうか?
(見供)
簡単に説明すると、ただなんとなく体を動かすのではなくて、自分の心や体の状態に合わせて「どんな運動をしたらいいのか」考えて、それに適した方法で運動をすることです。
(杉浦)
例えば「ウォーキング」って、なんとなく健康に良さそうじゃない?
(村上)
確かに。家でじっとしているよりは、ワンちゃんのお散歩でウォーキングしたりとか。やっぱりいい運動になりそうですよね。
(見供)
そうですね。ウォーキングは、ただなんとなく歩くのもいいのですが、目的を設定して、それに応じた歩き方を工夫すると、ウォーキングの効果を更に高めることができます。例えば、「いくつになっても元気に歩きたいから下半身の筋力を向上させたい」という目的がある場合は「大股で歩いてみる」。「最近、すぐ疲れてしまうから、もっと動けるようになりたい」という目的がある場合は、心肺機能を向上させるよう「長時間歩く」。同じ歩くでもこういう工夫をすると、より効果を期待することができます。
(村上)
確かに! じゃあ、例えば「よく足を捻ってよろけちゃう」という悩みがあったとしても、歩き方の工夫で改善できちゃったりするんですか?
(見供)
はい。よく足を捻ってしまうのは、バランス感覚とも関係しているかもしれません。バランスや姿勢を向上したり柔軟性や機敏性を強化するために、デコボコした道を歩くといいかもしれません。
(杉浦)
デコボコした道だと、ハイキングとか登山とか良さそうですよね。
(見供)
はい。また「勉強や仕事でイライラすることが多いから、楽しく運動してストレス発散したいな」という目的があったとしたら、自律神経などを安定させるために、自然の中を歩くのもいいですね。
(村上)
私も、だからすぐ宮古島に行って…。宮古島でランニングをしたとき、めちゃくちゃ爽快だったんですよ。坂があるのでめちゃくちゃしんどいんですけど。でも、スッキリするから。そういうことですよね? やっぱり、ウォーキングも目的によっていろんな工夫ができるものなんですね。
(見供)
目的を持った運動・スポーツを実施して、ライフパフォーマンスの向上を目指せば、健康の維持や増進はもちろん、クオリティ オブ ライフ、いわゆる生活の質も高めることができ、充実した生活を送ることが期待できるんです。
(村上)
なるほど。でも、その目的を設定するのが難しい、っていうかたもいそうじゃないですか? 今、特に心や体のことで気になることや悩みがない人もいますもんね?
(杉浦)
そう。そこで、皆さんにやってみてもらいたいのが、番組冒頭で行った、室伏長官が考案した「ライフパフォーマンス」を上げるための身体診断「セルフチェック」なんです。
(見供)
どんな運動・スポーツをするにも、まず自分自身の身体機能が十分かどうか知ることが大切です。その知るためのツールとして、セルフチェックを皆さんにやっていただきたいと思っています。
(杉浦)
室伏長官考案のセルフチェックの特徴は二つありまして、一つは「道具を使わず一人で身体の機能を確認できること」。もう一つは、「首や肩の可動性、全身の筋力などの機能をチェックできること」なんですね。
(見供)
このセルフチェックは、室伏長官自らが動画で分かりやすく紹介していて、問題点が見つかった場合、改善するためのエクササイズも動画で紹介しています。
(村上)
それはありがたいですね、セルフチェックだけじゃなくて、その先までサポートがあるのは。「やってみよう!」と思いますよね。
(杉浦)
エクササイズもね。家でできちゃう。
(見供)
では、今日はお二人に、肩甲骨の可動性をセルフチェックしてもらいたいと思います。
(杉浦)
リスナーの皆さんは、鏡を見ながら、無理せず一緒にやってみましょう。
(見供)
では、まず最初に、右手の親指と人差し指で左側の耳たぶをつまんでみましょう。その時、親指が顔の方、前を向くようにしてください。これがスタートポジションになります。そして、耳たぶをつまんだまま、肘を顔の前から頭の後ろに回し、回せたら、今度は顔の前まで戻します。この時に頭を前後左右に動かさないよう、頭の軸はずらさずに行ってみましょう。できますか? 左右やってみて、左右の違いも確認するといいかもしれません。
(杉浦)
肩甲骨、動きますね!
(村上)
肩甲骨、めっちゃ気持ちいいです!
(見供)
これ自体が運動にもなるんですが、この動きが難しい場合は、改善エクササイズをやってもらえるといいかと思います。実はこのテスト、トップアスリートでもできない場合があります。
(杉浦)
筋肉が邪魔になってでしょ? 室伏さん、筋肉パンパンですけど。
(見供)
筋肉が邪魔の場合もあるんですけど。室伏長官は、しっかり、きれいにできます。できない人は、顔が横を向いてしまったり、くぐれないっていうかたが多いです。ちょっと杉浦さん、怪しいなと思ってたんですけど。杉浦さんは、右に比べると左の肩甲骨の可動域が固い可能性があります。先ほど言ったトップアスリートでできないかたは、よくあるのが、腕を酷使する野球ですとか、バレーボール、水泳といった競技の選手が多いです。
(村上)
水泳の選手とかできそうなのに。
(見供)
そうですね。同じ動作を繰り返すことによって、特定の筋肉が固くなって、肩甲骨の動きが悪くなってしまう。そういう状態が起こり得るんです。
(杉浦)
逆にねー。これをできないかたは、改善エクササイズの動画を観て、肩甲骨の可動域を改善できるように日々取り組めばいいんですよね。
(見供)
はい。ライフパフォーマンスを向上させるためには「目的を持った運動・スポーツ」をすることが重要です。まずは、自分自身の身体の機能がどうなっているか確認して、問題があるようであれば改善できるよう、エクササイズを実施するなど、生活の中でできる運動から取り入れてみましょう。
(村上)
今日の話の中で特に注目したのは、「室伏長官のセルフチェックをやってみよう!」です。セルフチェックをやってみて、できなかったときの改善トレーニング方法までありますから。実際にやってみて楽しかったので、皆さんにもやってほしいなと思いました。
(杉浦)
僕は、「セルフチェック」「改善トレーニング」をやって、「ライフパフォーマンスをみんなで向上させましょう!」です。
「 関連リンク 」
・スポーツ庁「室伏長官が考案・実演する身体診断「セルフチェック」動画」
・スポーツ庁「Sport in Life~目的を持った運動・スポーツでライフパフォーマンスの向上を!」

