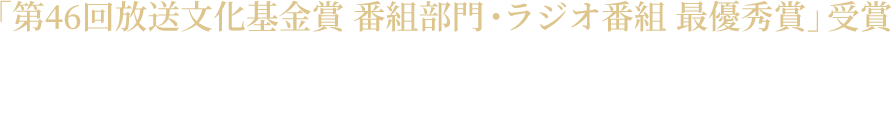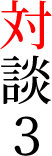
「教え子が振り返る
加藤典洋先生」
加藤典洋さんの元ゼミ生ライター・書評家 長瀬海 /
エフエム東京 藤岡泰弘
加藤典洋氏は明治学院大学、早稲田大学で教鞭を執ってきた。学生を愛し、学生から愛される「先生」だったと、加藤氏の教え子である書評家の長瀬海氏、エフエム東京社員の藤岡泰弘氏は語り合う。加藤典洋氏は自分の思想を学生に押し付けるようなことはしてこなかった。学生の肩の位置まで降りて、一緒にものごとを考える。加藤氏の作る、そういったゼミの空間は知的好奇心をくすぐるものだったと二人は言う。ゼミを離れて10年が経った今、加藤氏の教えは、異なる分野で活躍する二人にどのように身についているのだろうか。

学生を愛し、
学生に愛された加藤典洋さん

- 小川:加藤典洋さんの元ゼミ生でライター/書評家の長瀬海さんとエフエム東京の社員で今回の加藤典洋さん追悼番組の企画者である藤岡泰弘さんにお越しいただいています。お二人が加藤さんのゼミ生になったきっかけを教えてください。

- 長瀬:僕は大学1年生のときから加藤先生のゼミに入りました。ちょうど、僕が早稲田大学の国際教養学部に入学したのと加藤先生が早稲田に移られたのが同時だったんです。だから、お互い1年生でした。そもそも、なぜ、加藤先生のゼミに入ったかというと、高校生のときの国語の教科書に「オフサイドの感覚」という加藤先生のエッセイが収録されていたんです。それを読んで、この人の書くものはとても面白いと思っていたので、早稲田に入学した際、シラバスで加藤典洋の名前を見て、「あっ、あの人だ!」って思ったんですね。シラバスを読むと、1年生のゼミで、夏目漱石、村上春樹、鶴見俊輔、見田宗介を読んでいくとあって、早稲田に入ったし、村上春樹をちゃんと読んでみたいしなって動機で入ゼミしました。

- 小川:「オフサイドの感覚」というエッセイには何が書かれてたんですか?

- 長瀬:「批評のずるさ」とは何かを、オフサイドというサッカーのルールに照らし合わせて考えてみるという文章だったんです。サッカーのルールには二つあって、ひとつが見ている人に納得してもらうためのもの、もうひとつがプレイヤーのなかで不満が出ないためのもの。オフサイドというのは後者によって作られたルールなんです。つまり、ボールを基準にサイドを右・左に分けて、ボールの向こう側である「オフ」サイドにボールを蹴り込むことを、プレイヤーは「ずるい!」と感じるわけです。この「ずるい!」という感覚こそ、批評にとっては重要だと書かれていました。ある時点から、批評は観客本位の面白さのなかでものを書くようになってしまった。理論を持ち出して、外部の人間がいかに面白がるかということを目的に書かれるようになってしまった。それは、ずるい。批評家はもっとオフサイドの感覚に鋭敏になるべきだ、と加藤先生は書いていました。批評とは何かについて、初めて、僕が触れた文章でした。

- 小川:加藤典洋という批評家の軸がうかがい知れる文章ですね。藤岡さんはどういう経緯でゼミに入られたんですか?

- 藤岡:僕は四国の田舎から東京の大学に入ったんですが、入った学部が国際教養という学生の半分が帰国子女で構成されているところでした。授業も全部英語で、二年次には留学が必須で、英語漬けの日々に疲れたんですね。留学から帰ってきた頃には、もう、英語はいいやって、諦めまして(笑)。それで、どうしようかなと、「日本語で、考える」ことをもっとやりたいなって思ったときにシラバスを見ていたら、加藤先生のゼミでは映画、小説、音楽、全部やる、しかも日本語で、とあったので、なんとなく入りたいなぁぐらいの感覚で入りました。ゼミに入るには「私の偏愛する表現者」という文章を書いて送らなければならないんですが、僕は当時から今にかけて心酔しているヒップホップについて書いたんです。そうしたら、受かった。入ってみたらすごく楽しい。ハズレじゃなくて、良かったです(笑)。後日、加藤先生に、お前をとるか迷ったよ、でもとって良かったという言葉をかけていただいて、なんだか救われた気がしました。
加藤ゼミという空間

- 小川:長瀬さんは藤岡さんと同期で、ゼミ長を務められていたとか。加藤先生とはある程度の信頼関係があったのでしょうか?またゼミのスタイルってどのようなものだったんでスカ?

- 長瀬:加藤先生は学生ととても仲良くする人でした。決して教師だからって偉そうにしないで、授業外でも一緒に遊んでくれました。ご飯とかよく連れっていってくれましたし。加藤先生のお話は、大学に入りたての人間の知的好奇心をくすぐるものばかりだったんです。それがとても面白くて。飽きなかったんですね。僕は大学を卒業してから加藤先生が退官されるまで、都合10年間ずっとゼミに出ていました。10年間ゼミのスタイルは変わらず、毎週、1作品、小説なり評論なり映画なりを読んだり見たりして、それについて学生がすごく重厚なレジュメを作って発表するという形でした。レジュメは30ページくらいになることも多々ありました。文字数でいえば40000万字前後のレジュメを作るわけで、新書が一冊書けちゃいますね(笑)。そこで相当鍛えられました。

- 小川:扱うテーマは学生が選ぶんですか?

- 長瀬:一緒に選ぶっていう感じですね。学生が興味あるもの、加藤先生が興味あるのもをすり合わせた結果っていう形で。だから、加藤先生が「お前らこれを読め」っていうことは絶対にしなかったです。学生が興味あるものを知りたいという加藤先生の想いもあったと思います。こういう形式でゼミを行うと、普通、先生としては、ある意味、やりにくいわけです。というのも、学生の方が取り上げる作品について詳しいので、先生ヅラをして、「これっていうのはこういう読み方が正しいんだよ」と言えないんですよね。加藤先生は自らそれを禁じられた。なるべく学生と同じ目線でものを見て、ものを考えて、ものを喋るということを心掛けられていました。

- 小川:藤岡さんはゼミで扱った作品で印象に残っているものって何かありますか?

- 藤岡:ドイツの小説家、カフカの『変身』ですね。僕は、ゼミに入ったばかりの頃から、自分の好きな表現者について語るのに「あれ? うまく喋れないぞ」って感じを持っていたんです。だから、もぞもぞ、と喋る。でも、それをなんとか言葉にできた瞬間が幸せだって感じるようになって。言い当てる感覚っていうんですかね。それをゼミで少しずつ学んで、カフカの『変身』のときにちゃんと自分の言葉で語ることができたと思いました。

- 小川:長瀬さんが印象に残っている作品をひとつ挙げるとすれば?

- 長瀬:村上春樹の『ノルウェイの森』ですね。あの作品は細かく調べれば調べるほど、面白い。例えば、何が、いつ起きたのか、当時のカレンダーと照らし合わせてみると、物の見事にぴったり合致するんです。僕の持論では、あの作品は村上春樹が自分の学生時代の日記を参照しながら書いた作品なのではないかと思っています。70年代の早稲田の学事歴と照らし合わせるといろいろと面白いことがわかるわけです。そういう作業を加藤先生と一緒にしているのがとても楽しくて。文芸評論ってこうやるんだって教えてもらいました。加藤先生は村上春樹についていろいろ書かれていますが、ひとつの集大成が幻冬舎から文庫が出ている『村上春樹のイエローページ』ですね。あの本のなかで、加藤先生は村上春樹の作品を初期の頃から詳しく見ていって、分析している。『村上春樹のイエローページ』という本の面白いところは、加藤典洋編となっていて、加藤先生が一人で書いたことになっていないところです。あの本は加藤先生が明治学院大学のときに学生と一緒に村上春樹の作品をつぶさに読んでいった軌跡になっているわけです。だから、加藤先生はこの批評は加藤典洋一人の手柄じゃないんだぞ、という具合にクレジットを明記している。そこが加藤先生らしいというか。学生と一緒に考える共同の場がどんなものだったかよくわかる本になっています。アンチ村上春樹の人も、ハルキストの人も、絶対に読んだ方が良い本です。
借り物の言葉で喋らない
ということの大切さ、
あるいは指針を持つということ

- 小川:加藤典洋さんが文学を読解する上で重要視していたものってありましたか?

- 藤岡:僕が感じた限りでは、これは文学作品の読解に限らずだと思うんですが、加藤先生はある事柄と向き合ったときに、どこから自分の考えをスタートさせるかその起点を大事にしている人でした。借り物の言葉では喋るなよ、ということを自身に言い聞かせていらっしゃった。だから、ゼミでは僕たちもひとつの作品を前にして、気になったところから語り始める。その重要性について教えられました。

- 長瀬:批評家って誰にでも引き受けられることなんだと思います。小説を読んで、面白いか、面白くないか、それを言葉にすることから始めれば良いわけですから。面白いと思ったことをどういう風に自分のなかで咀嚼し、文章にするかというのが文芸批評の本来の姿だと思うんです。その出発点を誤魔化してはならない。加藤先生は徒手空拳で、理論に頼らずに、なるべく誰にでもわかる発想の地点に立って物事を考えるということをしてきました。だから、学生に対しても、これがなんで面白いか考えてごらん。君は本当にこの作品を面白いと思ったの?って具合に何度も問い詰めていく。そうすると、学生の側も、なんで私・僕はこの作品を面白いと思ったんだろうって素朴に考えさせられるんです。それが批評の始まりなんですよね。

- 藤岡:僕はそれまでほとんど本を読んでこなかったんです。小説なんて、野坂昭如の「火垂るの墓」を小さい頃に読んだくらいで止まっていました。そんな人間が、加藤ゼミに入ると、みんなの読書量に圧倒されるわけです。でも、加藤先生は、本を100冊読んでいる人間と1冊しか読んでいない人間が対等にぶつかることができることこそ、批評の空間なんだと考えていました。だから、ゼミでも、僕のような人間の発言が、それなりに本を読んできた人たちの発言と、同じ重さを持って扱われる。加藤先生もかつては柄谷行人といった先行する批評家に噛み付いたときに、知識量で勝負しようとする姿勢を愚劣だと考えて、相手が100冊読んでいようが関係ない、批評とは学問とは違い徒手空拳で戦えるものなんだ、と考えたと書いていますね。

- 小川:長瀬さんは文芸誌『すばる』2019年8月号に加藤典洋さんの追悼文を寄せています。そこに、加藤先生がゼミの初回に必ず梶井基次郎の「闇の絵巻」という短編について話をするというくだりがありますね。この短編には、闇夜でも走れる泥棒の話が出てくる。この泥棒は闇夜の中を、「30cmの棒切れ」を突き出してどんどん走る。加藤ゼミでは、自分のなかのこの棒切れを見つけなさい、と最初に教わったと。

- 長瀬:棒切れを持つというのは、自分の指針を持てということなんですよね。人間、寄る辺がない状態だと、すぐに不安になってしまう。不安にならないためにも、生きるための指針を持ちなさい、ということですね。この指針が、社会に出るときに自分を支えてくれる、と。確かに、ゼミでやったことは文学作品を読むということで、社会に出て、会社員になるとほとんど何も関係がなくなるわけです。けれど、文学作品を読んでいく上で、自分の拠り所となるものを見つけておくと、文学とは関係のない場所に行ったときも必ず役にたつ。そういうことを先生はおっしゃったんだと思います。

- 藤岡:同じような話を最後のゼミでも加藤先生が言ったのを覚えています。このゼミで何を教えられたかなみたいなことを振り返りつつ、「ものの考え方」みたいなことを受け取ってくれていたらいいな、と先生が仰っていたのがすごく記憶にあります。その「ものの考え方」というのが、「30cmの棒切れ」のことなのかなと。
愛せなければ通過せよ

- 小川:加藤典洋さんがよく口にしていた言葉ってありますか?

- 長瀬:ドイツの哲学者ニーチェの言葉で「愛せなければ通過せよ」というものがあります。加藤先生はこの言葉が好きでした。要するに、無意味は批判はやめなさいってことですね。批判とは愛を持ってこそ成就するのだ、ということを加藤先生はご自身の主軸となる部分に持っていらした。加藤典洋という人は、一見するとあまのじゃくだし、頑固っぽいし、いつも批判めいたことを言っているイメージがあるかもしれません。しかし、加藤先生がしている批判というのは、自分の身を犠牲にしてでも、ここは言っておかなければならないというときに繰り出されるものでした。批判のための批判なんてもってのほかだと考えていらっしゃいました。例えば、先日、芥川賞を受賞した今村夏子さんという小説家がいます。今村夏子さんは、加藤先生が選考委員をされている太宰治賞を受賞して小説家デビューしたのですが、その選評で加藤先生はすごく厳しい言葉を書きました。もしかしたら、その選評を読んで、今村さんは小説を書く気力を失くしてしまったかもしれない。実際、今村さんはしばらく小説が書けませんでした。だけど、あのとき加藤先生は、どうしたらこの若い小説家が次に進むことができるのか、一生懸命考えた上で、言葉にしたんだと思います。この小説家を世に送り出すためには、唇を噛んで、血を流してでも、言っておかなければならない、そう考えたんでしょう。

- 小川:逆に言えば、加藤さんにそこまで言わせる力が今村夏子さんの作品にはあったわけですね。

- 長瀬:はい。愛が無ければ通過しているはずですから。文学をやっている、特に若い人間は自分の価値観に閉じこもって、頭でっかちになってしまうんですよね。だから、自分の既存の価値観と相容れない何かと遭遇すると、すぐに批判してしまう。でもそれは違うんだよ、意味のない批判ならやっても仕方ないでしょうってことを加藤先生はすごく考えていたと思います。
加藤典洋さんと村上春樹さん、
二人の同時代を生きた文学者

- 小川:加藤典洋さんにとって村上春樹はどういう小説家だったんでしょうか。

- 長瀬:同時代を生きた小説家だったんです。最初、村上春樹が『風の歌を聴け』で小説家としてデビューしたとき、加藤先生は日本にいませんでした。だから、全く日本の現代文学の状況がわからないまま帰ってきて、友人に聞くんですね。今、日本の小説家で面白い人誰かいる?って。すると、一人は村上春樹で、もう一人は高橋源一郎だって言われるわけです。そこから村上春樹を読んでみようと思った、と言っていました。僕の知っている限りでは、加藤先生は初め、村上春樹に批判的だったと思います。でも、おそらくは竹田青嗣さんや笠井潔さんといった同年代の書き手と村上春樹を徹底的に読んだ共著『村上春樹をめぐる冒険』という本を1991年に出したあたりから、村上春樹についての評価を改めるようになったのではないでしょうか。村上春樹は、面白い。そう考えるようになったんだと思います。この小説家は、普通、言われているような都会のなかで孤立した人間の姿をただ記号的に描いている小説家ではなくて、もっと芯のある部分で物事を考えている小説家なんだ、ということを理解するようになったわけですね。同時代の社会状況だったり、現代の文学が考えるべきことを、露骨にではなく、その表層の下に潜り込ませる。薄皮を一枚めくると、そういった問題意識がドロッと溶け出してくる。そのことに気づいてから、もっと綿密に村上春樹を読まなければならない、そう思うようになったんだと思います。
加藤典洋さんが学生と
師弟関係を結ばなかったわけ

- 小川:ゼミでは加藤先生のキー概念である「ねじれ」というのは教わったりしませんでしたか?

- 藤岡:一回だけ、「ねじれ」という言葉が出てきたのを覚えています。ある作品を取り上げたなかで、「ねじれ」というのは面白い言葉でね、という具合に。でもそれくらいでしょうか。先生はご自身の思考のスタイルを押し付けることはしませんでしたから。

- 長瀬:ゼミでも加藤先生の本を扱うということはほとんどありませんでした。というのも、先ほどの話に通じますが、加藤先生の本に関しては、加藤先生が答えを持っている。それを学生に教える、ということは、やりたくない、そう考える人でしたから。

- 小川:長瀬さんの先の『すばる』に寄せた追悼文では、加藤先生は生涯弟子をとらなかったと書いています。自分の考えを誰かに押し付けることはしない、という教師のスタンスと、それは通じるのでしょうか。

- 長瀬:そうですね。加藤先生は弟子をとるということは絶対にしなかった。自分の思想を若い人に押し付けることは嫌いました。それは自分の流儀ではない、そう思ったんだと思います。やはり、師弟制度というのは、どうしてもパターナリスティックなものになるわけで、自ずとそこには上下関係ができてしまう。加藤先生は学生と話すときは、学生の肩の位置まで降りてきて対話をするのが好きな人でした。フラットな関係を結びたかったんだと思います。だから、理論や知識を振りかざして、学生を従わせることは絶対にしなかったわけです。僕は加藤先生のそばに15年間居続けました。はたから見たら加藤の弟子だって思われたでしょう。そういう風に言われることも多々ありました。でも、その度に、加藤先生は「いや、長瀬くんは僕の若い友人だから」って言うんです。友人。加藤先生らしいですよね。対等にものを言える関係性作りを心がけていたんです。
グレーゾーンの価値観を
大切にするということ

- 小川:今、長瀬さんは文芸批評のお仕事をされていて、藤岡さんはラジオ局で働いています。全く異なる領野で活動されているお二人ですが、加藤先生から教わって、今の自分に活きていることって何かありますか?

- 長瀬:僕は割とそばで加藤典洋という批評家を見てきて、だからこそわかるんですが、加藤先生は孤立している人だったんです。意図的になのか、自然とそうなってしまったのかわからないけれど、自分の周りに信者を置いて身を固めるということはしてこなかった。そういう加藤先生の姿を見てきたからか、僕は批評家とは一人の個であるべきで、集団として群れることは恥ずかしいことなんじゃないかと思うようになりました。

- 小川:藤岡さんは今のお仕事に活かせていることって何かありますか。

- 藤岡:卒業する直前くらいに加藤先生に、物事って白か黒かで分けられないことが多くて、その中間のグレーゾーンに、大事なことってあるんだよ、そこをいかに捉えるかが、大事なんだよって言われたのを覚えていて、自分にとって大事な言葉になっています。グレーゾーンというのは、今思えばまさに「ねじれが発生する場所」ですよね。ただ、サラリーマンとして働き始めると、真っ白か真っ黒な言葉しか交わされない瞬間が結構多くて(笑)。白黒はっきりしないとビジネスとして成立しないし、きっぱりどっちかはっきり言わないと人にも伝わらない。ビジネス上の言葉としては、「グレーゾーンにとどまる」というのは、弱弱しい。でも、僕としてはそこには大事なものが詰まっているというか、もっとグレーゾーンな価値観を大切にしたいと、思っているんです。

- 小川:グレーゾーンにとどまるというのは僕も腑に落ちる言葉ですね。今の時代、政治家たちも白と黒のどっちかの争いになってしまう。すごく極端なんです。でも、憲法改正とかを考える時に、白と黒だけでは考えられないグレーゾーンな部分がある。加藤さんの概念で言うと「ねじれ」ですよね。政治家の言葉ではそのグレーゾーンにとどまることができないんです。本当に必要なのはもうちょっと迂回する言葉だったり、立ち止まったり、掘り下げたりするための文学の言葉だったりするんですね。加藤さんの『9条入門』や『敗戦後論』が僕に教えてくれるのは、そういった文学の言葉で立ち止まるということでした。

- 藤岡:小川さんの仰る「立ち止まる」ということはまさにその通りだと思います。グレーゾーンの状態で立ち止まる、わからないことをわからないままにしておく、そこから始める。そういう思考回路を持った大人に、大学生のときに出会えて、救われた思いがしたのを覚えています。
加藤典洋さんと交わした
最後の言葉

- 小川:長瀬さんは最後に加藤さんと会ったのはいつなんですか?

- 長瀬:最後に会ったのは加藤先生が入院されているときでした。具体的に言うと、2018年12月。悲しいお話になるんですが、そのとき加藤先生は自分の死というのを悟っていた時期だったんです。僕は加藤先生とちょっとお話がしたいなと思って、会いに行きました。僕としても何を喋ったらいいんだろうって不安だったんです。でも、一対一でお話をしたときに加藤先生がすごく楽しそうに江藤淳や秋山駿の話をするんですよ。その笑顔が今でも忘れられない。本当にこの人は根っからの文芸批評家なんだなって思いました。

- 小川:具体的にどのようなお話をされたんでしょうか。

- 長瀬:ちょうど僕の文芸時評の連載が決まったので、その報告をしました。すると、加藤先生は自分のもとから優秀な編集者は何人も輩出することはできたけど、書き手はほとんど育てることができなかった、そのことを悔いていると言って、すごく喜んでくれました。僕は、まだまだ、物書きとしては未熟なので、これからもっともっと成長しなければいけないな、と思うことしきりなのですが。とりあえず、スタート地点に立つことができたということで、「じゃあこれからどうするか考えなきゃいけないね」と仰り、加藤先生がスタート地点に立った若い頃のお話をしてくれました。加藤先生は若い頃、江藤淳に、「最近の批評家はバッター・ボックスに立とうとしない」と苦言を呈されたらしいんですね。加藤先生はへそ曲がりだから、そう言われて、人様の用意したバッター・ボックスなどに立つ気はないと言って軽く受け流したらしいんです。でも、その言葉がしこりとなっていた。それで、後に文芸時評の話が来たときに、バッター・ボックスに立とうと思った、と。だから、お前もバッター・ボックスに立つ以上、全力でバットを振り回していけ、と加藤先生に言われました。他人のことなんて気にするな、どうせお前のことなんて誰も見てないんだからって。それが加藤先生から授かった最後の言葉だったんですが、自分の原点ともなるものでした。ここから、始めよう、そう思わされました。