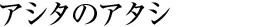 |  |
第9話
一歩、たった一歩踏み出して外に出れば、こことは全く違う世界。
楽しそうにはしゃいで、笑いあって、輝いてる。
あたしも、笑えるかな?
あんな風に笑えたらいいのにと思ってしまう。
青空にマッチして「青春オーラ」を放てたらどんなにいいだろう。
しかし、今現在、あたしは間違いなく独り浮いていて。
ほんの少しだけ、羨ましくなる。
ほんの少しだけ。
そんな自分を馬鹿みたいと鼻で笑う。
「あんたは、もう戻れないのよ」
ガラスに映ったあたしが言った。
学校から抜け出してウチへ帰ろうとすると、
さっきの華やかムードとは違った罵声が聞こえてきた。
「うぜぇんだよっ!」
ダンッとベンチを殴る音。
「物に八つ当たりするな」
相手の声に対して、とても穏やかな佐藤の声。
金髪にピアスというホストファッションの男子と佐藤が向き合っている。
「んじゃ、てめえ殴るわ」
チッと舌打ちをして、男子が言うと、
佐藤はなだめる様に「殴った手が痛いだろ。心も」と肩を叩いた。
はぁ?
あたしは、その男子と同時に疑問符を並べる。
「心も」だって。
くっさ。
……どこまで、調子外れなんだ。
あたしは、あんなヤツに連れて来られたのか。
あたしは、とてつもなくやるせなくなる。
「何で、タバコなんて吸うんだ?」
佐藤の手には、赤く火の着いたタバコ。
どうやら、ホストくんから取り上げたものらしい。
「きもちーから」
そう言って、彼はまだ火の着いたタバコを佐藤の手から奪い、吸いこんだ。
……。
真っ白い煙が、佐藤とホストくんの間に揺れる。
煙を口に含むだけの真っ白い吹かしの格好つけた煙が。
あたしは、思わず笑ってしまう。
「馬鹿じゃねーの!!」って叫びたくなる。
でも我慢。
佐藤に見つかりたくない。
ってか、吹かしなのに気付かない佐藤もどうかと思う。
佐藤ってきっとタバコ吸わないんだろうな。
佐藤さん、彼、煙草吸ってる自分が格好いいと勘違いしてらっしゃいますよ。
加えて、彼、ほんとはタバコ吸えないみたいですよ。
そう言ってあげたいくらい、ホント佐藤って健気だなぁと思った。
わざわざ、人から見えない所で注意するのとか、
なんか「自分強い」って誇示しないところとか。
あぁ、佐藤って生徒好きなんだなって思った。
なんか、最後に良いもの見たって気がした。
あたしは、校舎と文化祭と、それから佐藤に背を向けて歩き出す。
ふと、空を見上げるともう空の端っこは、仄かに淡いオレンジになっていた。
どんどん夜が増えてくる。
……あたしの、心はいつでも夜だけだけど。
少し歩くと川岸の道に差し掛かる。
涼しい秋風が傍を駆けて、枯れた草をさらさらと鳴らしていく。
そのうち焼き芋屋さんなんかも通ったり、木々の葉も色づいたりして、
どんどん秋は深まっていくだろう。
あたしを置いて。
川岸を暫く行くと、あの橋が見える。
「始まりの場所」。
昨日まで、何もかもが平穏で静かだったのに。
世界は、母の吐息と静寂の中に佇んでいたのに。
もう、あの肌の温もりも、柔らかな声も、暖かな笑顔も、
何もかもが、失われてしまった。
土手に腰を下ろして、ため息をつく。
あの中指立てる父も、馬鹿笑いする母も、もう居ない。
あたしには、家族も友達も、誰も居ない。
レベッカの曲の通り、ひとりぼっち。
橋を親子連れが渡っていく。
リコーダーの曖昧な音色が流れてくる。
小学二年生くらいの女の子と、母親らしき女性が楽しそうに歩いている。
時々、女性が立ち止まってかがむのが見える。
きっと、これは「ド」これは「ソ」などと話しているに違いない。
ほんのり染まった夕空に彼女らのシルエットが、あたしの網膜に焼きついた。
あー、目が痛いよ、お母さん。
涙を拭ってくれる人も、抱きしめてくれる人も、心配してくれる人も居ない。
……いや、たった一人だけ。
佐藤。
あいつは、あたしを連れ出してくれた。
あいつのおかげで「光」を知る。
光って、やっぱあったかい。
そんでもって優しいし、嬉しくなる。
闇に同化したあたしを照らし出す。
それは、良い事。
それは、良い事?
光は、あたしを傷つける。
母は、母は、絶対あたしを傷つけなかった。
傷つけなかった?
あたしは、母に死んで欲しくなかった。
母が死んで、あたしは傷ついた。
あたしは、傷ついたのだ。
傷ツカナイ世界ハ在ルノ?
「光」暖かく優しいもの。
けれど、闇を消し去るもの。
「母」あたしを護るもの。
けれど、あたしを傷つけたもの。
「自分」偽るもの。
けれど。
けれど、あたしを「護る」もの。
あたしは、自分自身でさえも傷つけなければならないのでしょうか。
自分を護ることのできる唯一の存在をも殺してしまっていいのでしょうか。
何も残っていないあたしは、自分さえも失ってしまっていいのでしょうか。
あたしは、死にたいのでしょうか?
あたしは、死ななくてはいけないのでしょうか?
「明日、一緒に死のう?」
「生まれなきゃ良かったのに!」
母の為に、母が死のうと言ったから、「死ななければならない」。
せ、せやな。
あたし、死ななあかん。
むっちゃ母が、大好きや。
あたしは、母しかおらへんもん。
母の世界の住人やもん。
泣いたらあかん。
母の苦しみは、こんなもんやなかったはずや。
母は、あたしと一緒に死にたかったから、そないな風にゆーたんや。
おう!
だったら、死のうやないの!
目を拭って、立ち上がる。
母よ、待ってなさい!
アンタの為に死んだるわ!!
落ちてた小石を、大きく腕を振って川に投げる。
ポチャンと音がして、あたしはちょっぴり悲しくなった。
ほんとは、ほんとはね。
気付いちゃったんだ。
あのね、おかあさん――。
ふいに焼き鳥の匂いが鼻を掠める。
買い物帰りのおばさんのスーパーのビニール袋の音が耳に入る。
結局のところ、世界は何も変わっちゃいないんだな。
変わったのは、あたしの心と母が居なくなった、そのことだけ。
この夕焼けも焼き鳥の香りも、何一つ変わってなくて、可笑しくなる。
「死」は凄く大きくて暗くて、こんなにも人に多大な影響を与えるのに。
あたしが死んだとしても明日は来るだろう。
あたしの明日は無くなっても。
命って平等だけど、不公平だ。
なんで個性なんて創ったの。
なんで感情なんて持ったのだろう。
あたしが神様だったら、こんな世界は創らなかった。
後ろから誰かが駆ける音が近づいてくる。
息遣い、コンクリートを叩く足音、段々近づく。
たんたんたんたん、機械的に。
はぁっ、は、はぁっ、規則的に。
と、止まる。
息遣いだけが耳に届く。
はぁーっと強く息を吐いた音が聞こえて、
「森……口」
あたしの名前を呼ぶ。
あたしが振り向くと、そこには輝が居た。
息を切らして、両手を両膝に当てて肩で息をしてる。
「どしたの?」
あたしは、そう言ってしゃがむ。
顔を覗きこむと大粒の汗が、おでこと頬にへばりついてる。
「どしたの?」
あたしは、もう一回訊く。
「……ご、めん」
「ごめん?」
予想外の言葉に聞き返す。
「知ってたん、だ」
輝は言う。
何を?と思ったけど、言わない。
「森口の……母さん亡くなったって……知ってたんだ」
え?
どーゆーこと?!
ってか、何で?
よく解らなすぎて言葉が出ない。
「森口の母さんさぁ。亡くなる前にうちに電話してきた」
彼は、そう言って長く息をつくと顔を上げる。
あたしは、彼の足元を見つめたまま動けない。
「知らないかもしれないけど、森口の母さんと僕の母さん職場同じ」
思い当たる節があって。
「輝、苗字何?」
「若山。若山輝」
あぁ、やっぱり。
全部繋がった。
だからか。
だから「似てる」んだ。
だから、あの時、保健の先生の「お父さん居なくて大変ね」に反応したんだ。
なーるほどね。
でも、なんで、若山さんに?
……知っている?
母が独り死んだ理由を知っている?
「じゃあ、お母さんが死んだ理由も知ってる訳?」
「いいや。でも、母さんのせいなんだ」
「どーゆーこと?」
あたしは、立ち上がって訊く。
「母さん、森口の母さんが死ぬの止めなかったみたいなんだ」
あの人なら、止めないだろう。
人は人、自分は自分、そーゆー人だ。
「森口には話すなって」
嫌いだったのかな、母のこと。
「でも僕、違うと思った」
なんで奪ったのかな。
「森口は死んじゃ駄目だって、そう思ったんだ」
一呼吸おいて、輝は言った。
あたしの中を、窓を開けた時のような、爽やかな風が通り抜ける。
そんな気がした。
「母さんなら、きっと死にたいならそうしなさいって言うだろうけど」
けど?
「僕は、母さんじゃない」
「そっか」
あたしは歩きはじめる。
「人の意見は尊重しなさい。そう教えられてきたけど、必ずそれが正しいって訳じゃない」
「そっか」
コンクリートに二人の足音が響く。
「全員の意見が合致しないことだってあるし、僕の思うことだってあるし」
「そっか」
「無責任な発言だし……僕は皆に合わせる弱い人間、流される人間はもう嫌なんだ」
あたしは俯いた。
「間違ったことを間違えたままに、違うって思ったことをそのままにしたくない」
輝は静かに淡々と、けれどはっきりとそう言った。
「僕、変わりたいんだ。変わらなきゃいけないんだ」
頭を殴られたような衝撃が、頭の先からつま先まで走り抜ける。
あたし、君みたいにはなれないよ。
でも、なれたら強いだろうな。
でも、それは大変だよ?
自分の意見を主張することは好まれないのだから。
学校だって、個性個性と喚き散らしてるけど、結局生徒に求めているのは、
騒ぎを起こさない「協調性」。
煙たがられるだけだよ?
それでもいいの?
「そっか」
あたしは、そう言って空を見上げる。
茜色の太陽に照らされて、二人の影が長く伸びる。
「だから、言わなきゃと思って」
一呼吸おいて、あたしは言う。
「ん。ありがと。でもね、今でもうちには、おかあさんの死体があんのよ。しかもね、おかあさん、昨日あたしに一緒に死のうって言ったんだよ」
輝は一瞬、何かを探すように沈黙する。
そして、あたしに向き合い言った。
「それでも、生きて欲しい」
生きて欲しい……か。
あたしは、自然と眉間に皴を寄せる。
なんで、あたしに生きてなんてゆうんだろ。
「だって世界は一つじゃないから」
そう言った輝の瞳の中に、あたしが映る。
学校、家庭、母、本、携帯、友達。
確かに世界は一つじゃない。
「こんな風に軽々しく言っちゃいけないかもしれないけど、森口の気持ちも解るよ。
でも、森口は縛られてちゃいけない気がするんだ、生きた方が良いと思うんだ」
「死ぬなんて言ってないじゃん」
「腕切ったでしょ」
リストバンドを外してみせる。
「ね?あたしに死ぬ度胸なんてないわよ」
「なら、なら、明日の文化祭、来るよね?」
……。
「さぁね」
あたしは、そう言って足早に歩き出す。
もう、あたしを混乱させないでよ。
きっと、今あたし、必死な顔してる。
「死ぬなよ!」
輝はあたしの気持ちを察してか、歩くのを止める。
輝は、今どんな顔をしてるのだろう。
「さぁーね」
僕は、母さんじゃない。
僕、変わりたいんだ。
世界は一つじゃないから。
森口は死んじゃ駄目だって、そう思ったんだ。
あたしの影は、ゆらりゆらりと揺れていた。
家の扉を開けると、冷たく、重々しい空気が立ち込めている。
部屋に入ると、母は死んでいた。
血の水溜りはてらてらと部屋を映し出している。
裾をクシャッと握り締めて、俯いたあたしが写る。
電話の子機と親機が並んでいるのも見える。
橋の上の女の子と母親のよう。
視線を上げると、机の上が片付いているのに気がつく。
千切れた写真とピンクの封筒と手紙とリモコンと水玉の箱しかない。
惣菜や酒のゴミは、片付けられたようだ。
死ぬ前に片付けするとか、あたしたち似てるなぁ。
暗くなった部屋に、蛍光灯を点ける。
一瞬、ガス爆発しないかなと思ったけれどしなかった。
手癖でテレビもつけると、
丁度、NHKのみんなのうたが始まる。
「PoPo Loouise」という曲が流れ始める。
リコーダーの懐かしい感じのメロディーとUAの歌声。
急激に寂しさが、あたしの身体を侵食していく。
「ただいま」
そう呟いた声に返答はない。
もう一度言ってみるけど、やっぱり返ってこない。
母は、死んでしまったんだなぁ。
おかあさん。
真っ白なおかあさん。
どうして死んだのよ。
なんで若山さんに電話したのよ。
リコーダーの静かなメロディーが部屋を包む。
椅子に座ってうつ伏せになると、オンブルローズの香りが手首からする。
甘い甘い香り。
でも……何か違う。
答えは、見つからない。
香りの違いも、死の理由も。
何かを探すように、水玉の蓋を開ける。
冷たい鉄が、あたしの掌に当たって熱を奪う。
中には、さっきは無かった物が入っていた。
白い封筒。
中には便箋が入っている。
母の字が、垣間見える。
あたしは、おもむろに便箋を開いた。
「瑠璃へ」
その言葉で始まる手紙を、母があたしに宛てた手紙を、母の隣で読む。
あたしは知る。
死の理由を。
あたしは知る。
母の想いを。
あたしは、便箋を再び封筒にしまって机に置く。
そして……。
あたしは、母の血で染まった血溜まりの中の包丁を手に取り……。
突き刺す。
トスッと鈍い音がする。
その身が、紅く紅く染まっていく――。
|
【第8話に戻る】 【第10話に続く】
| 第9話 |  |
 Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved.
Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved. |