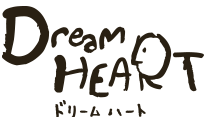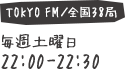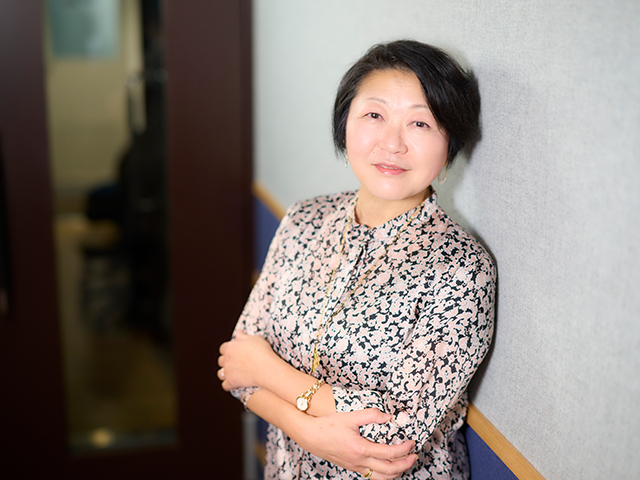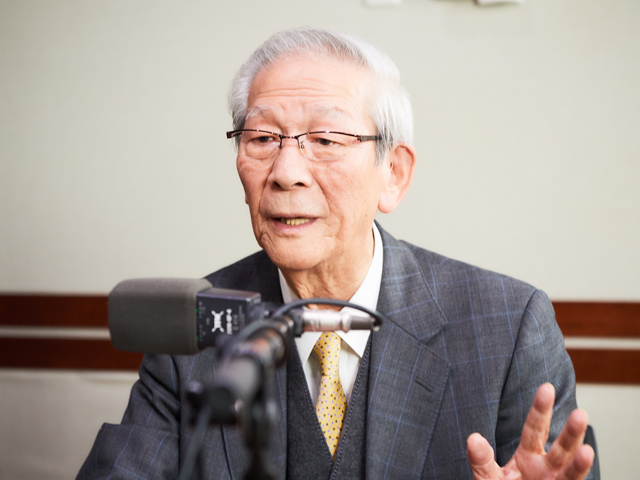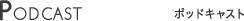2025年05月17日
「Dream Heart」は、日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、その方の「挑戦」に、そして、「夢」に迫っていきますが、今週はスペシャルバージョン!
皆さんからお送りいただいたメッセージを、番組パーソナリティの茂木健一郎が、脳科学者として答えていきます!

──想像力を働かせる時間帯を作る
茂木:では、まず、こちらのメッセージから…。大阪府 ラジオネーム<ラジオlistener>さん。
茂木さん、先日のお悩み相談室の回を聞かせてもらいました。
そこで、相談なのですが、勉強法を教えてもらいたいです。
今、本を読んでいますが、進まないのと、頭にイメージが浮かぶ事がなく、困っています。
一行一行、読むしかないと思っていますが、なにか頭に描きやすいポイントなどあれば、教えてもらえるとありがたいです。
茂木:ラジオlistenerさん、これはとてもとてもいいご質問だと思うんですよ。
というのは、今ネット上で動画コンテンツがたくさんありますよね。そういう時代だからこそ、かえって「ちゃんと本を読みたい」と考えている方が多いんです。
これの一番大事なポイントは何かと言うと、現代人はどうしてもインプットが多すぎるんですよ。僕もそうですけど、朝から晩までスクリーンタイムが多くて、色々なテキスト、映像、音をインプットしていますよね。
その結果に何が起こるかと言うと、実は想像力が鍛えられなくなるんですよね。読書をする上で一番大事なことは、まさにラジオlistenerさんが書いてる「本を読んで、頭にイメージを浮かばせる」。本というのは「言葉」ですから。言葉というのは情報が凝縮されています。それを頭の中でイメージする能力というのが大事なんですけど、現代人はともすれば、これが衰えがちなんですね。情報が過多なので。
どうしたら、イメージを浮かばせられるか・想像力を育めるかと言うと、脳がオフになる時間が大事なんですね。
これは私自身も心掛けているんですけど、「時には情報をオフにして、頭の中でイメージを想像する時間を作る」と。例えば「昔のことを思い出す」でもいいですし、一つの言葉…『木漏れ日』と言ったら「ああ、木漏れ日ってこんな感じだよな」とか、『楽しい』と言ったら「楽しいってこんな感じだよな」というように、まるで白昼夢のように…脳科学的に言うと「マインドワンダリング」と言われることもありますけども、想像力を働かせる時間帯を作って頂くと、まずは想像力の回路が鍛えられるんですね。
時々お話しますけども、「デフォルトモードネットワーク」、情報をオフにした時に活動する神経細胞などが発達するんです。この想像力を鍛えておくと、本も読みやすくなるんですね。
この番組にも来て頂いた、小説家の村田沙耶香さん。『コンビニ人間』という作品が世界中で高く評価されているんですけど、村田さんは何か時間があると、「色々ストーリーを頭の中で組み立てる、その想像力を羽ばたかせる時間を持つ」と仰っていました。
なので、是非ラジオlistenerさんも、本を読むことも大事なんですけども、その前にイメージを…例えば、映画やドラマを思い出して、「このキャラクターはこんな俳優がいいんじゃないかな?」とか、「この人は友達の〇〇さんに似てるな」のような形で想像力を活性化させる。それでエクササイズしておくと、今度本を読む時にも、すーっと想像力を鍛えることができるようになります。
また、「本を読む」というのは習慣なんですよね。よく小学校とかでも「1日10分の読書体験」ということをやっていたりしますけど、大人であっても、本当に1日5分〜10分でいいんですよ。「1日5分〜10分、本を読む」という習慣をつけて、一方で、今申し上げた「想像力を鍛える」。これをやって頂くと、ラジオlistenerさんもきっと本がスラスラ読めるようになるのではないかなと思います。

──食事を楽しめる、味わえる環境で食べる
茂木:続きまして…、千葉県 ラジオネーム<ぺこ>さんからのメッセージです。
茂木さん、こんばんは!
私は、ストレスを感じた時、食事を味わうことなく、ひたすら食べ、結局、食べ過ぎてしまうことがあります。
脳科学的に、過食を防ぐ対策を教えていただきたいです。
茂木:ぺこさん、実はですね、「ストレスを感じた時に味わうことなくひたすら食べる」というのは、我々人類の祖先にとっては、正しい道だったんですよね。だって、考えてみてくださいよ。我々の祖先は、いつ野獣が追いかけてくるか分からない、敵が攻めてくるか分からない、そういうところで暮らしていたわけでしょう。だからストレスが起こるような状況になったら、とりあえず「食べられる時に食べておく」というのは正しくないですか?
「腹が減っては戦ができない」というように、「いつ食べられなくなってしまうか分からないから、とにかく食べておかないと」ということで、当然そういう反応はあるんですけど。
ただね、今、我々は文明社会に生きているじゃないですか。かつて、我々の祖先としては正しかった行動が、文明の中だと、食べ物はいつでも手に入るわけでしょう? ストレスがあってもなくても。だから昔のやり方でやっていると、つい食べ過ぎになったり太ってしまったりするわけですよね。
なので、まずはぺこさんのその反応は正しいから、一概に自分を否定する必要はない、ということを認識してください。
脳科学では、ストレスに関連する「コルチゾール」という物質があるんですけど、ある種、このコルチゾールが臨戦態勢にしてくれて、食欲も出てきちゃうんですよね。食べると、脳の報酬系である「ドーパミン」が出てきて満足する、というサイクルで。これは昔の祖先にとっては良かったんですけど、今は現代なので、ちょっとそこを変えないといけないんですね。
私のオススメは、実はぺこさんも答えは分かっていて、まさに「食事を味わうことなく」と書いてあるじゃないですか。そうなんですよ。「食事を味わえばいい」んです。
と言うのは、何かを食べると脳の中で「嬉しい」という報酬が出るこのドーパミンというのは、実はいろんな出方があって、「食事が美味しいな」とか、あとね、「誰かと食べる」ということも重要ですね。1人で食べるのではなくて、お友達と食べる、家族と食べる。そのように「誰かと食べる」というような、ちょっと複雑な楽しみや喜びでも、ドーパミンは出るんですね。
ですので、「とりあえずこの状況は危険だから、食べておこうか」というような反応をするより、「他の人と楽しく会話しながら、食事を味わいながら食べることで、ドーパミンを出す」ということが、現代では特に重要だと思います。
これにもうちょっと話を広げると、「本能よりも、自分の置かれた状況を細かく見ることで行動していく」ということに繋がっていくんですね。
我々の脳の中には、「爬虫類の脳」と言われる「扁桃体」などがあります。そこは「ストレスを感じたら、とりあえず食べとけ」という命令を出すんですが、大脳新皮質…特に前頭葉を中心とする回路というのは、本能は本能として、「今、自分の置かれている状況をもっと広く、細かく、深く把握する」という働きを持っているわけです。
ですから、「食べちゃおう」という本能は置いておいて、今自分が置かれている状況を見ると、「お友達と食べればいいかな」とか、「そんなに量を食べなくても、この食べ物だったら味わって食べられるな」というような判断ができるはずだと思うんですよね。
ですから、ぺこさん、この「食べる」ということから始まりましたが、実はぺこさんの人生を、本能に従うだけでなく、広く色々判断してより良い生き方をする、ということにも繋がっていくと思うので、「たかが食べる。されと、食べる」で、是非、人と楽しんで味わいながら食べるという行動を身に付けて頂けたらなと思います。

──今まで使っていない回路を使うことで脳のバランスを回復させる
茂木:では、続きまして…。群馬県 ラジオネーム<きょんちゃん>さんからのメッセージです。
茂木さん、今晩は。
私は、今更ですが、仕事をがむしゃらに頑張っていたのですが、最近スランプが続き、やる気が起きません。
このスランプを、どう乗り切れるのか…考えてしまいます。
何か良い方法ありますか?
茂木:とにかく「休むこと」というのはすごく大事で。脳は、休むことで自然にバランスを回復していくんですね。
よく「癒される〜」とか、「ヒーリング」とか言うじゃないですか。いわゆる「癒し」というのは、普段偏った使い方をしている脳の回路の使い方を、もっと脳全体でバランスよく使うこと、それが「癒される」ということなんですね。
ですので、きょんちゃんさんはがむしゃらに頑張ってきたんですけど、その中で、ひょっとしたら脳の使い方がちょっと偏っていたのかもしれないんですよ。それはそれで素敵なことだったんですけど、ちょっとここで、極端なこと言えば1時間でもいいので、「仕事を忘れて、1時間何か違うことをする」、あるいは「今までと違った人と会ってみる」とか、「違った場所に行ってみる」とか、いわゆる気分転換をすることで、脳のバランスが回復します。そして脳のバランスが回復すると、いわゆるこの「スランプ」というものから出ることができるかも知れません。
実は仕事を頑張っている人ほど、全く違ったことをやった方がいいことが多いんですね。脳の回路は色んな活動のパターンがあって、普段我々はそのごく一部分しか使わないで生きているんですよ。
だから例えば、ボランティアやってみるとかね。子供達相手のボランティアをやってみたりすると、全然違う回路を使うでしょうし。
あるいは、都会で働いていらっしゃるんでしたら、自然の中に行ってゆっくり歩いてみるとか、写真を撮ってみるとか、バードウォッティングをしてみるとか、とにかく今まで使っていない回路を使って頂くと、脳がマッサージを受けるような状況になるんですよね。それでバランスを回復することができます。
「スランプ」というのは、簡単に言うと、「ちょっとバランスが崩れている」ということなんですよ。なので、アスリートとかでもスランプに陥った時はちょっと休養して、違う体の動かし方をしたりしますよね。そういう手法を参考にして頂けたらなと思うんですけども。
一番大事なのは、「やる気が出ないのは、自分が駄目なんだ」というように自分を責めないで欲しいんですよね。だってもう今まで十分頑張ってきているわけですから、それはそれで褒めてあげて、「ちょっと違う自分の活動を試してみる時期なんだ」と頭を切り替えることが大事です。脳で言うと、「尾状核(Caudate nucleus)」というところがその切り替えをしている回路の一部なんですけども、その切り替えのスイッチを入れる、そういう時期に来ているのかもしれませんね。
ちょうど(ゴールデンウィークの)連休も終わって、これから夏になるという、色々と野外で活動するのがとても気持ち良い時期になっていると思うので、きょんちゃんさんも是非、尾状核を使って脳の中で切り替えスイッチをオンにして頂いて、今までとは違う活動をすることで脳の活動のバランスを回復する、ということを試して頂けたらなと思います。

●今夜ご紹介したような茂木さんへのご質問メールは、すべて、メッセージフォームへお送りください。お待ちしております!
●音声配信アプリ「AuDee」では、「茂木健一郎のポジティブ脳教室」を配信中です。こちらでも皆さんからのご質問にお答えしています。
(毎週・土曜日、夜10:30に更新)
●茂木健一郎(@kenichiromogi) / X(旧Twitter)公式アカウント
皆さんからお送りいただいたメッセージを、番組パーソナリティの茂木健一郎が、脳科学者として答えていきます!

──想像力を働かせる時間帯を作る
茂木:では、まず、こちらのメッセージから…。大阪府 ラジオネーム<ラジオlistener>さん。
茂木さん、先日のお悩み相談室の回を聞かせてもらいました。
そこで、相談なのですが、勉強法を教えてもらいたいです。
今、本を読んでいますが、進まないのと、頭にイメージが浮かぶ事がなく、困っています。
一行一行、読むしかないと思っていますが、なにか頭に描きやすいポイントなどあれば、教えてもらえるとありがたいです。
茂木:ラジオlistenerさん、これはとてもとてもいいご質問だと思うんですよ。
というのは、今ネット上で動画コンテンツがたくさんありますよね。そういう時代だからこそ、かえって「ちゃんと本を読みたい」と考えている方が多いんです。
これの一番大事なポイントは何かと言うと、現代人はどうしてもインプットが多すぎるんですよ。僕もそうですけど、朝から晩までスクリーンタイムが多くて、色々なテキスト、映像、音をインプットしていますよね。
その結果に何が起こるかと言うと、実は想像力が鍛えられなくなるんですよね。読書をする上で一番大事なことは、まさにラジオlistenerさんが書いてる「本を読んで、頭にイメージを浮かばせる」。本というのは「言葉」ですから。言葉というのは情報が凝縮されています。それを頭の中でイメージする能力というのが大事なんですけど、現代人はともすれば、これが衰えがちなんですね。情報が過多なので。
どうしたら、イメージを浮かばせられるか・想像力を育めるかと言うと、脳がオフになる時間が大事なんですね。
これは私自身も心掛けているんですけど、「時には情報をオフにして、頭の中でイメージを想像する時間を作る」と。例えば「昔のことを思い出す」でもいいですし、一つの言葉…『木漏れ日』と言ったら「ああ、木漏れ日ってこんな感じだよな」とか、『楽しい』と言ったら「楽しいってこんな感じだよな」というように、まるで白昼夢のように…脳科学的に言うと「マインドワンダリング」と言われることもありますけども、想像力を働かせる時間帯を作って頂くと、まずは想像力の回路が鍛えられるんですね。
時々お話しますけども、「デフォルトモードネットワーク」、情報をオフにした時に活動する神経細胞などが発達するんです。この想像力を鍛えておくと、本も読みやすくなるんですね。
この番組にも来て頂いた、小説家の村田沙耶香さん。『コンビニ人間』という作品が世界中で高く評価されているんですけど、村田さんは何か時間があると、「色々ストーリーを頭の中で組み立てる、その想像力を羽ばたかせる時間を持つ」と仰っていました。
なので、是非ラジオlistenerさんも、本を読むことも大事なんですけども、その前にイメージを…例えば、映画やドラマを思い出して、「このキャラクターはこんな俳優がいいんじゃないかな?」とか、「この人は友達の〇〇さんに似てるな」のような形で想像力を活性化させる。それでエクササイズしておくと、今度本を読む時にも、すーっと想像力を鍛えることができるようになります。
また、「本を読む」というのは習慣なんですよね。よく小学校とかでも「1日10分の読書体験」ということをやっていたりしますけど、大人であっても、本当に1日5分〜10分でいいんですよ。「1日5分〜10分、本を読む」という習慣をつけて、一方で、今申し上げた「想像力を鍛える」。これをやって頂くと、ラジオlistenerさんもきっと本がスラスラ読めるようになるのではないかなと思います。

──食事を楽しめる、味わえる環境で食べる
茂木:続きまして…、千葉県 ラジオネーム<ぺこ>さんからのメッセージです。
茂木さん、こんばんは!
私は、ストレスを感じた時、食事を味わうことなく、ひたすら食べ、結局、食べ過ぎてしまうことがあります。
脳科学的に、過食を防ぐ対策を教えていただきたいです。
茂木:ぺこさん、実はですね、「ストレスを感じた時に味わうことなくひたすら食べる」というのは、我々人類の祖先にとっては、正しい道だったんですよね。だって、考えてみてくださいよ。我々の祖先は、いつ野獣が追いかけてくるか分からない、敵が攻めてくるか分からない、そういうところで暮らしていたわけでしょう。だからストレスが起こるような状況になったら、とりあえず「食べられる時に食べておく」というのは正しくないですか?
「腹が減っては戦ができない」というように、「いつ食べられなくなってしまうか分からないから、とにかく食べておかないと」ということで、当然そういう反応はあるんですけど。
ただね、今、我々は文明社会に生きているじゃないですか。かつて、我々の祖先としては正しかった行動が、文明の中だと、食べ物はいつでも手に入るわけでしょう? ストレスがあってもなくても。だから昔のやり方でやっていると、つい食べ過ぎになったり太ってしまったりするわけですよね。
なので、まずはぺこさんのその反応は正しいから、一概に自分を否定する必要はない、ということを認識してください。
脳科学では、ストレスに関連する「コルチゾール」という物質があるんですけど、ある種、このコルチゾールが臨戦態勢にしてくれて、食欲も出てきちゃうんですよね。食べると、脳の報酬系である「ドーパミン」が出てきて満足する、というサイクルで。これは昔の祖先にとっては良かったんですけど、今は現代なので、ちょっとそこを変えないといけないんですね。
私のオススメは、実はぺこさんも答えは分かっていて、まさに「食事を味わうことなく」と書いてあるじゃないですか。そうなんですよ。「食事を味わえばいい」んです。
と言うのは、何かを食べると脳の中で「嬉しい」という報酬が出るこのドーパミンというのは、実はいろんな出方があって、「食事が美味しいな」とか、あとね、「誰かと食べる」ということも重要ですね。1人で食べるのではなくて、お友達と食べる、家族と食べる。そのように「誰かと食べる」というような、ちょっと複雑な楽しみや喜びでも、ドーパミンは出るんですね。
ですので、「とりあえずこの状況は危険だから、食べておこうか」というような反応をするより、「他の人と楽しく会話しながら、食事を味わいながら食べることで、ドーパミンを出す」ということが、現代では特に重要だと思います。
これにもうちょっと話を広げると、「本能よりも、自分の置かれた状況を細かく見ることで行動していく」ということに繋がっていくんですね。
我々の脳の中には、「爬虫類の脳」と言われる「扁桃体」などがあります。そこは「ストレスを感じたら、とりあえず食べとけ」という命令を出すんですが、大脳新皮質…特に前頭葉を中心とする回路というのは、本能は本能として、「今、自分の置かれている状況をもっと広く、細かく、深く把握する」という働きを持っているわけです。
ですから、「食べちゃおう」という本能は置いておいて、今自分が置かれている状況を見ると、「お友達と食べればいいかな」とか、「そんなに量を食べなくても、この食べ物だったら味わって食べられるな」というような判断ができるはずだと思うんですよね。
ですから、ぺこさん、この「食べる」ということから始まりましたが、実はぺこさんの人生を、本能に従うだけでなく、広く色々判断してより良い生き方をする、ということにも繋がっていくと思うので、「たかが食べる。されと、食べる」で、是非、人と楽しんで味わいながら食べるという行動を身に付けて頂けたらなと思います。

──今まで使っていない回路を使うことで脳のバランスを回復させる
茂木:では、続きまして…。群馬県 ラジオネーム<きょんちゃん>さんからのメッセージです。
茂木さん、今晩は。
私は、今更ですが、仕事をがむしゃらに頑張っていたのですが、最近スランプが続き、やる気が起きません。
このスランプを、どう乗り切れるのか…考えてしまいます。
何か良い方法ありますか?
茂木:とにかく「休むこと」というのはすごく大事で。脳は、休むことで自然にバランスを回復していくんですね。
よく「癒される〜」とか、「ヒーリング」とか言うじゃないですか。いわゆる「癒し」というのは、普段偏った使い方をしている脳の回路の使い方を、もっと脳全体でバランスよく使うこと、それが「癒される」ということなんですね。
ですので、きょんちゃんさんはがむしゃらに頑張ってきたんですけど、その中で、ひょっとしたら脳の使い方がちょっと偏っていたのかもしれないんですよ。それはそれで素敵なことだったんですけど、ちょっとここで、極端なこと言えば1時間でもいいので、「仕事を忘れて、1時間何か違うことをする」、あるいは「今までと違った人と会ってみる」とか、「違った場所に行ってみる」とか、いわゆる気分転換をすることで、脳のバランスが回復します。そして脳のバランスが回復すると、いわゆるこの「スランプ」というものから出ることができるかも知れません。
実は仕事を頑張っている人ほど、全く違ったことをやった方がいいことが多いんですね。脳の回路は色んな活動のパターンがあって、普段我々はそのごく一部分しか使わないで生きているんですよ。
だから例えば、ボランティアやってみるとかね。子供達相手のボランティアをやってみたりすると、全然違う回路を使うでしょうし。
あるいは、都会で働いていらっしゃるんでしたら、自然の中に行ってゆっくり歩いてみるとか、写真を撮ってみるとか、バードウォッティングをしてみるとか、とにかく今まで使っていない回路を使って頂くと、脳がマッサージを受けるような状況になるんですよね。それでバランスを回復することができます。
「スランプ」というのは、簡単に言うと、「ちょっとバランスが崩れている」ということなんですよ。なので、アスリートとかでもスランプに陥った時はちょっと休養して、違う体の動かし方をしたりしますよね。そういう手法を参考にして頂けたらなと思うんですけども。
一番大事なのは、「やる気が出ないのは、自分が駄目なんだ」というように自分を責めないで欲しいんですよね。だってもう今まで十分頑張ってきているわけですから、それはそれで褒めてあげて、「ちょっと違う自分の活動を試してみる時期なんだ」と頭を切り替えることが大事です。脳で言うと、「尾状核(Caudate nucleus)」というところがその切り替えをしている回路の一部なんですけども、その切り替えのスイッチを入れる、そういう時期に来ているのかもしれませんね。
ちょうど(ゴールデンウィークの)連休も終わって、これから夏になるという、色々と野外で活動するのがとても気持ち良い時期になっていると思うので、きょんちゃんさんも是非、尾状核を使って脳の中で切り替えスイッチをオンにして頂いて、今までとは違う活動をすることで脳の活動のバランスを回復する、ということを試して頂けたらなと思います。

●今夜ご紹介したような茂木さんへのご質問メールは、すべて、メッセージフォームへお送りください。お待ちしております!
●音声配信アプリ「AuDee」では、「茂木健一郎のポジティブ脳教室」を配信中です。こちらでも皆さんからのご質問にお答えしています。
(毎週・土曜日、夜10:30に更新)
●茂木健一郎(@kenichiromogi) / X(旧Twitter)公式アカウント