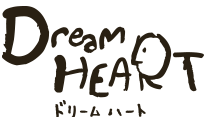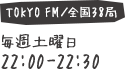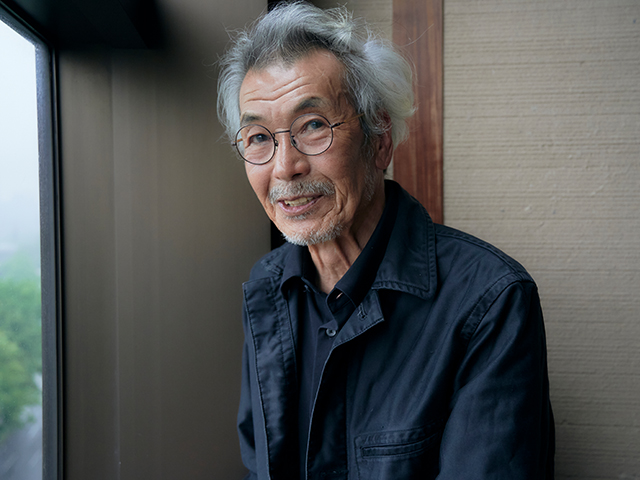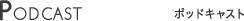2025年06月07日
今夜ゲストにお迎えしたのは、『サラダ記念日』で知られる、歌人の俵万智さんです。
俵さんは、1962年、大阪府のお生まれです。
早稲田大学第一文学部をご卒業されていらっしゃいます。
学生時代に、佐佐木幸綱さんの影響を受け、短歌を始められます。
そして、1987年に上梓された第1歌集『サラダ記念日』は、280万部のベストセラーとなり、翌年、現代歌人協会賞を受賞されました。
歌集、『チョコレート革命』『未来のサイズ』『アボカドの種』『愛する源氏物語』の他、評伝、エッセイなど、多くの著書がございます。
そして、2023年、「秋の褒賞」で「紫綬褒章」を受章されていらっしゃいます。

──生きているからこそ紡げる言葉
茂木:俵万智さんは今回『生きる言葉』という新刊を出されましたが、どうですか? 現代、ある意味では人工知能なども出てきて「言葉が危機に瀕している」という見方もあると思うんですが、どのようにご覧になっていますか?
俵:人工知能…AIの話もちょっと(本に)書きましたけれども、短歌を作るAIや俳句を作るAIも出てきて、本当に嫌になっちゃうんですよ。奴らは、5・7・5・7・7の「5」を入れたら、もう数秒で100首ぐらいババババッと作るんです(笑)。
茂木:100首!? これは少し変な話ですけど、俵さんは「NHK短歌」などで選者をされていらっしゃると思うんですが、応募されている作品が、人が作ったのか、AIが作ったのか、分からなくなってきていませんか?
俵:それは多分、これからもっともっと悩みの種になっていくとは思うんですけれども。でも、「じゃあ何で私達は短歌を作るの?」と言ったら、「NHK短歌」で入選するために作っているわけではなくて、それを1つの目標にして自分で歌を紡ぐことに意味があると思うので、そこはAIには真似できない部分ではあると思うんですね。
茂木:それがまさに『生きる言葉』ということですかね。
俵:そうです。私達が生きているからこそ紡げる言葉、それがAIと差別化されていくべきじゃないかな、と思います。
茂木:僕、このご著書から色んなことを学ばせて頂いたんですが、すごいなと思ったのが、例えば「光る君へ」に出てきてた藤原道長のあの有名な一首。あの分析なんか、もう痺れました。こうやって見るんだ、と思って。
俵:そうですね。歌というのは本当に短いものですけれども、だからこそ色んなふうに、100年経っても1000年経っても色んな読み方ができる。あの時は「道長の歌を俵万智がディスった」とか言われて(笑)。

茂木:ディスっていませんよね。
俵:ディスったわけではないんですけど。
有名な「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」という歌が、今の社会の教科書なんかではすごく俺様感が強い感じで「この世を俺のものにしたぜ。ワハハ」みたいな歌として紹介されているんだけど、そうでもないんじゃないか、というかね。でも、どうしてそんなふうに俺様な歌に取られているかと言うと、やっぱり「思ふ」という言葉が2回出てきてしまっている、というようなことで(笑)。
茂木:それはでも、道長のその時の気持ちが自然に出た「生きた言葉」だから、そこに何かがあるということですよね。
俵:そうです。史実を見ても、あの歌はその場で口ずさまれた歌だ、ということが分かっているので、「口ずさまれた」ということは頭から作っていったんだな、と。まず「この世をば 我が世とぞ思ふ」と言って、「望月の 欠けたることもなし」、彼の気持ちはそこで終わったんだと思うんですね。でもまだ字数が残っている(笑)。そこで、「と思へば」と入れてしまったんじゃないかな、という、そういう推理ですね。
茂木:今回この『生きる言葉』を拝読していて僕がすごく感動したのは、技巧じゃないんだ、と。知識でもないんだ、と。まさに、「心から言葉が出てくる」ということが大事なんだ、と。
素晴らしい歌人の方の作品が『生きる言葉』に出ているんですけど、「最後とは知らぬ最後が過ぎてゆく その連続と思う子育て」。この素晴らしい歌、これは俵万智さんが読まれた歌ですが、素晴らしいじゃないですか。
俵:ありがとうございます。
茂木:これも、技巧を凝らしたとかそういうことではないんですよね。
俵:はい。これはむしろ、「技巧」という点から見ると結構ツッコミどころの多い歌なんですけれども、やっぱりすごく多くの人…子育て中の人はもちろん、あるいは介護している人とか、何か知らないうちに最後が過ぎたな、という、人生での様々な場面がありますよね。そこに当てはめて皆さんが読んでくださっていて。この歌は、本当に多くの人と心を共有できたな、という実感の持てる歌ですね。
茂木:どうしても、特に短歌作られる方は構えちゃうと思うんですよね。やっぱり色々知識とか技術とかなくちゃいけないんじゃないか、とか。でも、必ずしもそうではない、ということなんですかね。

俵:そうですね。歌は誰にでも詠める。最後に短歌のすすめを書いていますけれども、音楽とか、絵を描くとか、手芸とか、とりあえず道具がいったり、何かしらの技術が要ると思うんだけれども、短歌の場合は言葉が道具で、皆さんはもう既に音が出る状態ですから、是非楽しみましょう、ということは常に言っていますね。
茂木:この『生きる言葉』の中にも痺れるようなことが色々書かれているんですが、僕はやっぱり谷川俊太郎さんとのやり取りがすごいな、と思いましたね。「君は現代詩の敵なんだ」みたいなことを仰った、と。これはどういう意味なんでしょうか?
俵:初めてお目に掛かった時に、すごい笑顔で仰ったんです(笑)。その頃、私も初めての歌集の『サラダ記念日』がワーッと評判になって、ですから、谷川さんにお目にかかるようなチャンスも生まれたんですけれども。
5・7・5・7・7、この5音7音のリズムというのは、本当に日本語を心地よくしてくれる魔法の杖みたいなものなんですけれども、谷川さんの書いていらっしゃる現代詩というのは、そこから自由になる、と言うか、むしろそれを封じて禁じ手として使わずに、頑張って自分たちのリズムや形を模索する、と。「地平を切り開くんだ」ということを頑張っているのに、「あんたたちは、やすやすとその便利な魔法の杖を使ってずるい!」みたいな、砕いて言うと、そういうことだと思うんです。
それでその頃、なかなか現代詩の詩集が売れないと言われていた時に、「歌集でこんなに…?」という感じで仰っていました。
でも、そこがかっこいいな、と思って。私なんか、その頃は結構ちやほやされがちだったので(笑)。
茂木:しかも、本質を貫いていますよね。
俵:そうなんです。
茂木:確かに、短歌の5・7・5・7・7は心地良いし、恐らく、定型にその魔法の杖を使うということのありがたさ、と言うか。
一方で、谷川さんみたいに「いや、俺はそういうことしないんだ」という、そこの芸術家と芸術家のバチバチがすごいな、と思って、僕は拝読しました。
俵:でも、そこにも書きましたけれども、「私の敵です」とは仰らなかったなと思って、もう、あっという間に懐きました(笑)。
茂木:それで、もうすごく仲良くされていて。
俵さん、この新潮新書『生きる言葉』をこれから読まれるという方も多いと思うので、メッセージを頂いてよろしいでしょうか?
俵:言葉と無縁に生きている人は多分いないと思うので、もしこの本を読んで何かしら自分の日頃の言葉について考える時間を持ってもらえたら、そのことが「言葉の足腰を鍛える」ということに繋がっていくかな、と思います。
今、言葉を紡ぐのにはすごく忙しいですよね。でも、ちょっと立ち止まって言葉について考える時間を持つ、ということは、すごく大事なような気がするので、この本がそのきっかけの1つになってくれたら嬉しいな、と思います。

●俵万智 さん (@tawara_machi)公式X(旧Twitter)
※↑茂木さんが番組の中でお話ししていた俵さんの固定ポストは、こちらからご覧いただけます!
●新潮社 公式サイト
●生きる言葉 (新潮新書) / 俵 万智 (著)
 (Amazon)
(Amazon)
俵さんは、1962年、大阪府のお生まれです。
早稲田大学第一文学部をご卒業されていらっしゃいます。
学生時代に、佐佐木幸綱さんの影響を受け、短歌を始められます。
そして、1987年に上梓された第1歌集『サラダ記念日』は、280万部のベストセラーとなり、翌年、現代歌人協会賞を受賞されました。
歌集、『チョコレート革命』『未来のサイズ』『アボカドの種』『愛する源氏物語』の他、評伝、エッセイなど、多くの著書がございます。
そして、2023年、「秋の褒賞」で「紫綬褒章」を受章されていらっしゃいます。

──生きているからこそ紡げる言葉
茂木:俵万智さんは今回『生きる言葉』という新刊を出されましたが、どうですか? 現代、ある意味では人工知能なども出てきて「言葉が危機に瀕している」という見方もあると思うんですが、どのようにご覧になっていますか?
俵:人工知能…AIの話もちょっと(本に)書きましたけれども、短歌を作るAIや俳句を作るAIも出てきて、本当に嫌になっちゃうんですよ。奴らは、5・7・5・7・7の「5」を入れたら、もう数秒で100首ぐらいババババッと作るんです(笑)。
茂木:100首!? これは少し変な話ですけど、俵さんは「NHK短歌」などで選者をされていらっしゃると思うんですが、応募されている作品が、人が作ったのか、AIが作ったのか、分からなくなってきていませんか?
俵:それは多分、これからもっともっと悩みの種になっていくとは思うんですけれども。でも、「じゃあ何で私達は短歌を作るの?」と言ったら、「NHK短歌」で入選するために作っているわけではなくて、それを1つの目標にして自分で歌を紡ぐことに意味があると思うので、そこはAIには真似できない部分ではあると思うんですね。
茂木:それがまさに『生きる言葉』ということですかね。
俵:そうです。私達が生きているからこそ紡げる言葉、それがAIと差別化されていくべきじゃないかな、と思います。
茂木:僕、このご著書から色んなことを学ばせて頂いたんですが、すごいなと思ったのが、例えば「光る君へ」に出てきてた藤原道長のあの有名な一首。あの分析なんか、もう痺れました。こうやって見るんだ、と思って。
俵:そうですね。歌というのは本当に短いものですけれども、だからこそ色んなふうに、100年経っても1000年経っても色んな読み方ができる。あの時は「道長の歌を俵万智がディスった」とか言われて(笑)。

茂木:ディスっていませんよね。
俵:ディスったわけではないんですけど。
有名な「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」という歌が、今の社会の教科書なんかではすごく俺様感が強い感じで「この世を俺のものにしたぜ。ワハハ」みたいな歌として紹介されているんだけど、そうでもないんじゃないか、というかね。でも、どうしてそんなふうに俺様な歌に取られているかと言うと、やっぱり「思ふ」という言葉が2回出てきてしまっている、というようなことで(笑)。
茂木:それはでも、道長のその時の気持ちが自然に出た「生きた言葉」だから、そこに何かがあるということですよね。
俵:そうです。史実を見ても、あの歌はその場で口ずさまれた歌だ、ということが分かっているので、「口ずさまれた」ということは頭から作っていったんだな、と。まず「この世をば 我が世とぞ思ふ」と言って、「望月の 欠けたることもなし」、彼の気持ちはそこで終わったんだと思うんですね。でもまだ字数が残っている(笑)。そこで、「と思へば」と入れてしまったんじゃないかな、という、そういう推理ですね。
茂木:今回この『生きる言葉』を拝読していて僕がすごく感動したのは、技巧じゃないんだ、と。知識でもないんだ、と。まさに、「心から言葉が出てくる」ということが大事なんだ、と。
素晴らしい歌人の方の作品が『生きる言葉』に出ているんですけど、「最後とは知らぬ最後が過ぎてゆく その連続と思う子育て」。この素晴らしい歌、これは俵万智さんが読まれた歌ですが、素晴らしいじゃないですか。
俵:ありがとうございます。
茂木:これも、技巧を凝らしたとかそういうことではないんですよね。
俵:はい。これはむしろ、「技巧」という点から見ると結構ツッコミどころの多い歌なんですけれども、やっぱりすごく多くの人…子育て中の人はもちろん、あるいは介護している人とか、何か知らないうちに最後が過ぎたな、という、人生での様々な場面がありますよね。そこに当てはめて皆さんが読んでくださっていて。この歌は、本当に多くの人と心を共有できたな、という実感の持てる歌ですね。
茂木:どうしても、特に短歌作られる方は構えちゃうと思うんですよね。やっぱり色々知識とか技術とかなくちゃいけないんじゃないか、とか。でも、必ずしもそうではない、ということなんですかね。

俵:そうですね。歌は誰にでも詠める。最後に短歌のすすめを書いていますけれども、音楽とか、絵を描くとか、手芸とか、とりあえず道具がいったり、何かしらの技術が要ると思うんだけれども、短歌の場合は言葉が道具で、皆さんはもう既に音が出る状態ですから、是非楽しみましょう、ということは常に言っていますね。
茂木:この『生きる言葉』の中にも痺れるようなことが色々書かれているんですが、僕はやっぱり谷川俊太郎さんとのやり取りがすごいな、と思いましたね。「君は現代詩の敵なんだ」みたいなことを仰った、と。これはどういう意味なんでしょうか?
俵:初めてお目に掛かった時に、すごい笑顔で仰ったんです(笑)。その頃、私も初めての歌集の『サラダ記念日』がワーッと評判になって、ですから、谷川さんにお目にかかるようなチャンスも生まれたんですけれども。
5・7・5・7・7、この5音7音のリズムというのは、本当に日本語を心地よくしてくれる魔法の杖みたいなものなんですけれども、谷川さんの書いていらっしゃる現代詩というのは、そこから自由になる、と言うか、むしろそれを封じて禁じ手として使わずに、頑張って自分たちのリズムや形を模索する、と。「地平を切り開くんだ」ということを頑張っているのに、「あんたたちは、やすやすとその便利な魔法の杖を使ってずるい!」みたいな、砕いて言うと、そういうことだと思うんです。
それでその頃、なかなか現代詩の詩集が売れないと言われていた時に、「歌集でこんなに…?」という感じで仰っていました。
でも、そこがかっこいいな、と思って。私なんか、その頃は結構ちやほやされがちだったので(笑)。
茂木:しかも、本質を貫いていますよね。
俵:そうなんです。
茂木:確かに、短歌の5・7・5・7・7は心地良いし、恐らく、定型にその魔法の杖を使うということのありがたさ、と言うか。
一方で、谷川さんみたいに「いや、俺はそういうことしないんだ」という、そこの芸術家と芸術家のバチバチがすごいな、と思って、僕は拝読しました。
俵:でも、そこにも書きましたけれども、「私の敵です」とは仰らなかったなと思って、もう、あっという間に懐きました(笑)。
茂木:それで、もうすごく仲良くされていて。
俵さん、この新潮新書『生きる言葉』をこれから読まれるという方も多いと思うので、メッセージを頂いてよろしいでしょうか?
俵:言葉と無縁に生きている人は多分いないと思うので、もしこの本を読んで何かしら自分の日頃の言葉について考える時間を持ってもらえたら、そのことが「言葉の足腰を鍛える」ということに繋がっていくかな、と思います。
今、言葉を紡ぐのにはすごく忙しいですよね。でも、ちょっと立ち止まって言葉について考える時間を持つ、ということは、すごく大事なような気がするので、この本がそのきっかけの1つになってくれたら嬉しいな、と思います。

●俵万智 さん (@tawara_machi)公式X(旧Twitter)
※↑茂木さんが番組の中でお話ししていた俵さんの固定ポストは、こちらからご覧いただけます!
●新潮社 公式サイト
●生きる言葉 (新潮新書) / 俵 万智 (著)
 (Amazon)
(Amazon)