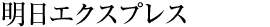 |  |
第1話
『たとえ間違いだったとしても、あなたに会えて幸せだった』
随分と酔狂な真似をする人がいるものだ。こんな田舎の無人駅の壁に。黒ペンで小さく書かれたこの落書きは、おそらく若い女性が書いたものだろう。可愛げのある丸い文字である。元からある赤と青のスプレーをぶちまけたような落書きの上に書かれたそれは、見る人を物悲しくさせる。目立ちたくないけれど気付いて欲しい、そんな思いでここを選んだのだろう。
2009年、12月25日金曜日。
平悠希(たいらゆうき)は、落書きの書かれた壁の横にもたれて、足元のさらさらとした雪を軽く蹴った。すると、ふわっと優しく雪の上に被さる。そこを踏むと、ぎゅっと音を立てながら足跡を形作る。先程降り止んだばかりの雪は、雪合戦に向いた軟らかい粉雪だ。
こんな雪遊びをするために、わざわざ駅まで来たわけではない。20センチも積もる中を急いで来たのだ。コートだけを羽織ってきたので、指や耳が赤くなる。
21時54分。さすがに夜は冷え込みが激しい。
「……わっ!」
「ぅわぁ!」
突然背中を押されて、飛び上がって驚いた悠希。それを見てボブヘアを揺らして笑うのは、田舎風景に似合わない年相応のおしゃれをした女子高生、三橋莉菜(みつはしりな)だ。
「ちょっと、驚き過ぎだよ。何してるの?」
「……迎えに来いっていうから」
莉菜は悠希の下宿先の一人娘で、いとこにあたる。大学受験生でもあり、3つ先の駅前の塾で行われている冬期講習に出ていた。最終日の今日は、寄り道して帰ってきたのだ。
「本当に来るとは思ってなかったんだもん」
「伯父さんも伯母さんも心配してたし」
すでに辺りは真っ暗。だから、莉菜も年下とはいえ男である悠希にメールを送ったのだろう。
『21時50分に着くから迎えに来て♥』
「頼むのはいいけどさぁ……」
莉菜は首に巻いていた赤いチェックのマフラーを解き、悠希の首に巻き始めた。背丈があまり変わらないので、簡単に巻き終えてしまう。悠希はいくら自分が2つ年下だからといって、莉菜の方が背が高い事が気に入らなかった。170センチと168センチ。たった2センチの差でも。
「何でマフラーしてないの。寒いでしょ」
「……じゃあ48分にメール送んなよ。到着2分前でビビッたし」
「マフラー汚さないでよ、お気に入りなんだから」
「……莉菜さん、会話して下さい」
莉菜の傍若無人な振る舞いに、見事に悠希は振り回される。悠希は遊ばれているのである。しかし、彼女は明るく気配りも出来るしっかりした面もあり、幼い時から姉のような存在だった。今巻いてくれたマフラーも、そんな気質からだろう。
莉菜の体温で温まったマフラーに、冷えた顔を埋めながら、二人は帰路についた。
雪の上にできた車の轍の上を歩く。これは、雪国ならではの歩き方であるが、田舎だからできる技でもある。なぜなら、歩道がない一車線で、車が滅多に通らないからである。
「最後の講習はどうだった?」
「んー、まあまあかな。鯛焼きも美味しかったし」
「……寄り道の事じゃなくて」
「だからまあまあだっていったでしょ。合格ラインは既に超えてるんだもん、大丈夫」
莉菜の志望校は都内の有名私立大学で、並大抵の努力じゃ合格は難しい。しかし、後ろから聞こえる声は、絶対的な自信を含んでいた。
「今度はお土産に買って来るよ」
どこまでも気楽な様子の本人に、ふっと笑みがこぼれた。
「鯛焼きを?」
「うん。あんこ以外にもいろいろあって。カスタードとか、いちごクリームとか、ごまクリームとか……」
静かに聞いていると、一人でどんどん喋り出す。この人が『女子高生』というカテゴリーから、綺麗なお姉さんイメージの『女子大生』に変わっていくのか。父親みたいな事をしみじみ思う。
「でも、今日でもうあっちの駅には行かないじゃん」
「今年はね。クリスマスが最終日っていうのもちょっとアレだけどね。だから、遊んで来たんだけど」
「……大学では彼氏できるといいね」
「うるさいな。いない者同士で遊んできたからいいじゃない」
莉菜がむくれているのが、声音で手に取るようにわかる。
「鯛焼きは食べたいでしょ?」
「いちごクリーム」
その即答に莉菜は甲高い笑い声をあげた。悠希の好物を知っていたから、答えは予想外ではなかった。
「じゃあ買って来て」
「……買って来るって言わなかったっけ?」
この手は莉菜の得意技だった。前にも、「悠希、チョコレート食べる?」の問いに「食べる」と答えると「じゃあ取って来て」と返されるという始末だった。
きっと、鯛焼きも俺が買いに行く破目になるんだろうなぁ。
そんな事を考えていると、突然の強風に襲われる。つい今まで凪いでいたとは思えないほどの強い風が、びゅうびゅうと吹き荒む。立っていられないと思い、とうとう屈んで風が弱まるのを待つ。
「莉菜、大丈夫!?」
あまりの強さに叫んだが、莉菜からの返事はない。顔を上げると粉雪が風に乗って、悠希の顔に突き刺さる。
しばらくすると、ピタッと風が止んだ。あまりにも不自然だったので、辺りを見回す。後ろを見たときに気が付いた。
莉菜がいないのだ。どこにもいない。この辺は見通しが良いので、どこかに隠れても、道を引き返しても、姿が見えるはずだ。足跡を探すにしても、街灯さえもない農道だ。見えたとしても、轍の上を歩いていたので、探すのは難しい。
「り、莉菜?」
まさか風に……とまでは思えなかったが、家はすぐそこだ。もしかしたら、さっさと先に帰ったのかもしれない。いや、そうに違いない。
はぁ、と思わず呆れの溜め息を吐いてしまう。
今の俺の焦りと心配を返してくれ。短時間だったけど。
「ただいま」
「お帰り。寒いのにわざわざごめんね」
伯母の良子(よしこ)がリビングから顔を出す。その瞬間、リビングの中の暖かい空気が悠希を包んだ。その所為もあってか、良子の血色はとても良い。
「いや、大丈夫です。伯父さんは?」
「帰ってきて、今お風呂に入ったところ」
コートを脱いで叩くように雪を落とす。マフラーは、コートと一緒にハンガーに吊るしておいた。
「寝るんだったら暖かくしてね」
「はい。でも、まだ起きてますよ」
そう言うと悠希は二階の自室へ向かった。
この時、莉菜が履いていたブーツが玄関に無い事に、悠希は気付かなかった。
翌日、12月26日土曜日。
悠希は自室に入るなり、赤チェックのマフラーを力いっぱい床に叩き付けた。そして、そのままベッドに倒れ込んでピクリとも動かない。
あぁ、頭がおかしくなりそうだ。それとも既におかしくなってしまったのか。だとしたら、今までの人生が空虚な妄想だったって事か。
莉菜が消えた。
「伯母さんも出掛けるんですか?」
悠希は遅めの朝食を食べながら良子に尋ねる。
「神社の手伝いにね。あの人は雪掻きしに行くんだけど、私は初詣の準備を手伝いに行くんだよ」
「毎年?」
「そう、奥さんとは仲良くさせてもらってるからね」
「莉菜もですか?」
先程起こしに行ったのだが、莉奈の低血圧には敵わなかった。ノックをしても、応答が無かったのだ。
「リナ……ってどこの子? あ、もしかしてカノジョさん?」
口に含んでいたホットミルクを、思わず吹き出すところだった。この人は何て事を言うんだ、と伯母ながらに思った。
見送るために玄関まで歩くと、伯母が何かを手渡した。
「これの持ち主でしょ? 昨日やけに可愛いマフラーしてるなと思ったのよ」
悠希君もお年頃ね、とニコニコして呟いているが、これは紛れも無く昨夜借りた莉奈のマフラーだった。
「でも、若い子は来ないと思うよ」
寝起きの所為か状況が上手く掴めない。
「……いや、大丈夫です。気を付けて行ってらっしゃい」
行ってきます、と外で声が聞こえる。そこで、下駄箱の上の写真立てを見た。
なんか違和感が、と凝視していると、なんとその写真に写っていたはずの莉奈がいなくなっている。その隣も、そのまた隣もだ。
莉奈が消えた。
スイッチが入ったように突然走り出した悠希は、自室の隣の部屋、莉菜の部屋へ向う。
彼女はまだベッドの中のはずだ。
壊す勢いで扉を開けると、足の裏から全ての力が抜け落ちた。
そこはただの物置と化していた。
莉菜が消えた。何も残さず、綺麗に。
何故だ。彼女は何処へ行ったのか。本当に悠希の頭の中の住人なのか。夢であって欲しいと願った。最後に会ったのは自分だ。異様な責任感と不安が襲う。
むくっと顔を上げると携帯電話を手に取って、着信履歴から『関川健仁(せきかわたけひと)』を探すと電話をかけた。
「もしもし?」
「もしもし、健? 今から質問するけど真面目に答えて」
息を吐いて笑ったのが、電話ごしでもわかる。
「はぁ? 何言って……」
「いいから。答えてくれ」
しばらく沈黙が続く。
「……わかった」
「いくよ。俺の下宿先は誰の家?」
「え、何それ。三橋さんでしょ、伯父さんだっけか」
笑みを含んだ答えだったが、今はこれほど安心できるものは他に無かった。
「じゃあその娘に会ったことある? 一応高校の先輩なんだけど」
「何て名前?」
「み、三橋莉菜っていう人。音楽部の」
健仁は絶対莉菜の事を知っている。廊下で見かける度に「莉菜さん可愛い」と呟いていたのを聞いた事があるし、何度か莉菜の話もした事がある。
「ちょっとわかんねぇな。後で水野とか葉山に訊いてみるわ。っていうか、どしたの?」
悠希は深呼吸をして、一方的に
「そっか。ありがと」
と言い残して電話を切った。
ふーっと長い溜め息を吐いて、再び横になった。そして、静かに目を伏せた。
先程と比べて、悠希はとても落ち着いていた。これは諦めに近かった。何を信じて何を疑えばいいか、考える気にもなれない。
俺は依存性の強い夢を見たのだ。その夢は毒となり、現実と交錯して悠希を混乱させたのだ。ただそれだけの事。
自分に言い聞かせるようにそんなことを思っていると、悠希に莉菜を連れ去ったあの時と同じ突風が吹き付けた。窓の鍵は閉めたはず、と慌てて顔を上げて見ると窓も扉もしっかり閉まっている。それにもかかわらず、目の前では風の強さに、机の上のプリント類が舞い上がり、棚の上のザックも床の上に落ちていた。
あまりの事に、俺も一緒に吹き飛ばされてしまえばいいのに、と自暴自棄になっていると風はピタッと吹き止んでしまった。不思議な風の所為で部屋は台風の過ぎ去った後のように物が散乱し、足の踏み場も無くなっている。
すると、ガラッと窓が開いた。呆けていた悠希は驚いて思い切り振り向く。驚く事はこれだけでは無かった。今度は、桟に足をかけて同い年くらいの少女が部屋に押し掛けて来たのだ。真っ黒なスーツに身を包み、首には淡い赤のリボン。その無表情で、土足で散乱している物を踏みつけるような歩き方に、悠希は恐怖に近いものを覚えた。
そして、いまだ茫然としている悠希をじっと見つめ、白い細腕を悠希に差しのべた。
「三橋莉菜を取り戻しに行かないか?」
この少女との出会いが、悠希の未来、現在、そして過去までもを大きく変える事になる出来事のはじまりとなるのであった。 |
【第2話に続く】
| 第1話 |  |
 Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved.
Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved. |