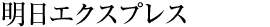 |  |
第4話
日が暮れる。まだ夕方の4時を過ぎたばかりだというのに。静かに沈みゆく太陽を、悠希(ゆうき)は電車の窓を通して見つめていた。夕日は山々の縁を朱色に染め、そこから色をぼかすように白色、藍色と天に向かって彩られている。逆光を受けた雲は、それらと馴れ合いを嫌うように黒々と孤立している。
ぼーっとしていると、突然隣から大きないびきが聞こえ、思わず飛び上がって驚いた。口を開けて寝ている健仁(たけひと)だった。年の瀬も迫る12月27日の今日、6つ先の駅周辺に遊びに行った2人は、まずドラマの続編映画を見た後、年末セールで混み合っている郊外の総合スーパーの中を約4時間歩き回ったのだ。疲れないわけがない。だが、映画のパンフレットやら購入したCDなどを、全て悠希に持たせていたくせに健仁は寝ている。少し気に食わない。
「……タケ」
声をかけても反応はなく、変わらずいびきをかき続けている。
仕方がない、デコピンで起こすとしよう。悠希はにやりと口の端をつり上げると手が震えるほどの力を込めて、親指のはらの上に中指を勢いよく滑らせる。ベチッという痛そうな鈍い音が電車内に響く。
「いたっ」
「もう着くから起きろよ」
すました顔で言う悠希に、健仁は渋い顔をして額をさする。揺れと共に電車が停車し、2人の身体も右へ左へと揺れる。悠希は自分の荷物のみを持って先に降りた。
「絶対赤くなってる」
後から健仁が追ってくる。
「だって、起きなかったじゃん」
「あー、すげぇ痛い」
文句を言いながら健仁はひとりでさっさと改札を抜けると、自動販売機が2つ並ぶ無人駅の外へと向かうと、お金を投入し、缶のコーラを買う。
「俺、いちごオレね。紙パックのやつ」
そう言いながら健仁のコーラを拾い上げる悠希を見るなり、舌打ちをして健仁は仕方なくもう一方の自販機でいちごオレを購入する。その短い間に悠希は健仁に見えないように、コーラを思い切り振った。顔がニヤつく。
「ほらよ、いちごオレだ」
そう言って自販機からいちごオレを取り上げた健仁に、悠希は何もなかったかのようにコーラを渡す。
「まさか、振ったんじゃねぇだろうな」
しまった、開ける前に勘付かれた。思わず噴き出すと、健仁はいちごオレを握り締め、にたりと笑った。そして、なんと健仁は力いっぱい道路側にいちごオレを投げてしまったのだ。ピンク色の紙パックが美しい弧を描く。
あぁ、俺のいちごオレが。悠希はふと、中学時代の給食時間を思い出した。紙パックの牛乳を投げ合って遊んでいたのだが、その内のひとりが受け損ねて床で破裂したことを。その場は大爆笑に包まれたが、今だと笑うのは健仁だけだろう。このままだと、悠希のいちごオレがあの時と同じ結末に……そう思っていると、紙パックはコンクリートの道路を越えて、田んぼに積もった雪の上に落ちた。幸いにも、耳にした音は液体が床にぶちまける音ではなく、ザクッという凍った雪に刺さる音だった。しかし、わざわざ田んぼの中まで取りに行く元気など、悠希には微塵も残っていなかった。
「いちごオレが……」
「俺のコーラだって同じだっつの。つーか、俺の金を返せ。俺のはもう飲めないんだぞ」
「明日になれば飲めるんじゃない?」
「お前、それ適当に言ってるだろ」
呆然としながら思わず壁に手をつくと、悠希の手が何か文字のようなもの覆っていることに気付く。手をよけるとそこには2行にまたがって何かが書かれていた。それは黒ペンでくっきりと書かれていて、ごく最近のもののようだ。小さく書かれた可愛げのある文字だ。いまどき、こんな所に落書きだなんて珍しい。この辺りはカラースプレーが主流なのに。
『たとえ間違いだったとしても、
あなたに会えて幸せだった』
悠希は無意識にそれを呟いていた。すると、突然、悠希の頭の中にいつかの情景が浮かび上がる。この落書きを見たのは初めてじゃない。これは2回目だ。なぜかそんな確信があった。しかし、その思いは浮かんでは静かに消え、消えたものを思い出そうとするとまた新たなものが浮かんでくる。ごく最近に見たことは間違いない気がするのだが、いつ、どうして見たのかが思い出せない。
いつだ? これを見たのは。最後にここに来たのは4、5日も前だが、そんなに前のことではない。
昨日は? 午前は健仁に電話して、夜は早めに寝た。
一昨日は? クリスマスだったが、特別何をするわけでもなく終わった気がする。ケーキはクリスマスイヴに伯父夫婦と3人で食べた。3人で? 果たして本当にそうだっただろうか。誰かと苺の奪い合いをした覚えがある。伯父でもなく伯母でもない人物と……。
「悠希?」
急に黙りこんだ悠希に対し、健仁は怪訝そうにこちらを見ている。しかし、悠希はそれどころではない。
そういえば、昨日こいつに電話したのはどうしてだったか。電話する理由はなかったはずだ。
一昨日の夜、俺は一体何をしてた?
「おい、顔色悪いぞ」
悠希の身体がふらふらし始めて、ついにはその場に座り込んだ。
その瞬間、悠希の目に赤いチェックのマフラーが映った気がした。俺はここで、温かいあのマフラーをあの人から受け取った。
思い出した……。
莉菜(りな)だ。
莉菜を迎えにここまできたのが、一昨日の夜。莉菜が消えて慌てて健仁に電話したのが、昨日の午前。そこから、ミクに出会い時空間を移動して、ワタルに未来を見せ付けられて……。
「悠希、調子悪いのか? 動けるか?」
健仁を見上げると、心配そうな顔でしゃがみこむ。その時、悠希が赤いマフラーだと思ったのは、健仁が手に持っていた赤いコーラの缶だったことに気が付いた。
心配? 本当に? 何のために?
だって、このときから既に上辺だけで話をしている感覚だったんだろ。そんな俺を信じるのか。お前は、未来で俺をナイフで刺して、殺すんだぞ。
「今、誰か呼んでくるからな。待ってろ」
健仁は荷物を全てその場に置き、持ち前の俊足で一目散に走り去っていった。その背中は真剣そのものであるが、悠希はどうしても信じられずにいた。
ふわっと、嫌に生温い風が悠希の頬を撫でる。そっと何かが降り立ち、忍ぶようにして悠希に近づいてくる。
「時空間の歪みを失くすことって、そんなに大事なことなのか?」
悠希の後ろには、静かに佇むミクがいた。
「どうして?」
ミクの気配を背後に感じながら、顔を見ることもなく話し続けた。
「時間調律師として未来を生きるお前らからすれば、生きるってことは、決められた時空間を正しく進むってことだろ。でも、今を生きてる俺らからすれば毎日が偶然だ。偶然で生きてるんだ。やり直しのきかない偶然がいくつも重なって、今の俺がいる。時空間の歪みが出来たのも、誰かが意図的につくったわけじゃない。それも偶然だ。だからこそ今が成り立ってたのに、わざわざそんなことする必要なんてない気がする」
ゆっくりと、ミクに聞かせるような語り口だ。
時間調律師なんて、最初聞いたときは便利で過去の過ちを直せるいいものだとばかり思っていた。しかし、歪みながらも崩れずにしっかりと建っていた積み木の塔を、歪んでいるところから順に直していく。そうすると、その上の積み木もそれに合うように直さなければいけなくなる。倒れるほどの歪みでもないのに、その歪みがあってもその塔は成り立っていたのに、時間を調律する意味があるのか。
ミクは少し目を閉じてから答えた。
「私たちの間でそういう論争が起こっているのは事実だ。自然や時間は人間が手を加えるものではない、と」
一呼吸置いて、ミクは続けた。
「でも、それが仕事だから。そのために、私たちがいる」
冷たい風の所為かひどい頭痛が襲うが、悠希は平静を装う。
「ひとつ、訊いていいか」
ミクは黙っている。
「あの時、お前は謝ったよな。俺が未来に飛んだ時。何で謝ったんだ?」
ミクはひとつ空気を吸って、少し躊躇ってから話し始めた。
「……繋がりがないとはいえ、やっぱり私は私が居た証が欲しかった。きっと、お前は後悔していると思う。未来を知ってしまったこと、過去を知ってしまったこと、私と出会って巻き込まれてしまったこと。こうなってしまう位なら、最初から私はいない方が良かったのかもしれない」
この時、悠希ははじめて振り向いてミクの顔を見た。少しやつれて大きな目が伏し目がちだったが、落ち着いた面持ちだった。
「でも、これで最後だ。これから私は三橋莉菜の時間を調律しに行く」
打って変わってミクは決然たる態度で宣言した。が、悠希はぽかんとして聞いていた。
「お前の言う通りだ。無闇に時空間は変えるものじゃない」
ミクは悠希に静かに近寄り、今までにないくらい優しい声音で話し始めた。
以前、別の時間調律師がある男の時間を調律した。その男は1989年の冬に飲酒運転の車にはねられて亡くなるはずだったが、時空の歪みによってその男は生き延びていた。その時空間を調律し、その男は正しい時空間の流れに沿って亡くなった。
「その男は、三橋莉菜の父親だ」
悠希は目を見張った。それと同時に、なぜ莉菜の母親が莉菜を置き去りにしたのかを悟った。
事故当時、妊婦だった莉菜の母親は、突然の夫の死に戸惑っただろう。子どもと自分を残され、2人だけで生きていかなければいけない。経済的にも苦しかっただろうが、それ以上に精神にダメージが大きかったのだろう。だからあの時、森の中であんな泣き方をしたのだ。頼る人はもういない、全て自分に責任があるのだと。
「その時間調律がなければ、三橋莉菜は何事もなく生きていただろう。莉奈がお前に出会うことはなかったろうけれど」
「莉菜の時間を調律しても大丈夫なのか?」
「上からの指示だ。ただし、1989年の時空間に生まれて、母親が置き去りをしないような選択をという条件付きで」
ミクは悠希に手を差し伸べた。出会った頃とは違う、何も隠し事をしていない所為もあってか、ミクは清清しい表情を浮かべていた。
「一緒に来てください」
移動した先は、莉菜が置き去りにされた日で、加えて悠希が知らない街の駅だった。
「あと5分でここに来るはず」
ミクはいそいそと働く悠希を見ながら、緊張した面持ちで鋭く言い放った。
「よし、これで大丈夫なはずだ」
「本当に上手くいくのかな」
心配そうな顔で母親を待つミクの肩を、安心させるようにポンと2回叩いた。
悠希は、この時空間に来るなり、駅員に頼んでこの辺の地図を借りて、一番近くの養護施設へ向かい、そこで行われている行事やボランティアの様子が載った広報紙を大量に貰って来ていた。施設の人に怪しまれるかと思ったが、ボランティアに興味のある若者と思ってくれたのか、終始にこやかに接してくれた。そこから駅に戻り許可を得て、掲示板に張ったりツアー広告の横にさり気なく置いたりと、どこでも目につくように準備した。
これを見た莉菜の母親が、別の選択をしてくれるように必死だった。
「来た! あの人だ」
2人は売店に居座って、来る女性の様子を伺った。女性の腕の中には赤ん坊の莉菜が、しっかりと抱かれていた。森にいた時は顔を見ることは出来ずにいたのでわからなかったが、母親は莉菜にそっくりだ。莉菜よりも髪が長くて小柄だが、歳は20歳前後とあまり変わらないように見える。
赤ん坊を抱いて辺りを気にして歩く母親は誰から見ても挙動不審で、これから何か起こしそうな匂いがぷんぷんしている。この人の素直なところは、莉菜とは対照的だ。
俯いて早足で歩く母親に、ふと、このまま通り過ぎてしまうのではないかという不安を感じた。それはミクも同じらしく、一瞬目が合った。
すると、女性は掲示板の前で立ち止まった。しばらく釘付けになって、辺りを見回し置いてある広報紙を手に取り、そのまま早足で走り去った。その顔つきは決して良いものではなかったが、先程よりは幾分晴れたように見えた。
2人は顔を見合わせて、安堵の胸を撫で下ろした。
「そんで、残業は終わったんか?」
後ろからひょっこり顔を出したワタルに、2人そろって飛び上がって驚いた。その反応に更に驚かされたワタルは、1歩後退っていた。
「と、とりあえず終わりました」
「おぉ、ごくろーさん。じゃあ、戻るとしますか」
「ちょっと、いいですか?」
そう言いながら、悠希はワタルの服の裾を引っ張って、ミクを残しその場を離れた。ミクは不思議そうな顔で見つめているが、ついては来なかった。
「ちょ、何なん?」
「頼みがあるんです。私的なことだけど、かなり」
「そないなことを言われても、話を聞かん限りは何も言えへんしなぁ」
悠希はミクが遠くにいることを確認し、呟くように手短に話した。ワタルは考える素振りを見せた後、何かに思い当たったようだった。
「なんか……さすがというか。わしよりガキのくせに物分かりがええな」
ワタルは笑みを浮かべて快く引き受けた。悠希がお礼を言う前に、早速彼は行動に移していた。手招きをして、ミクをこちらに呼ぶ。
「ちぃとばかし、出掛けるで」
消毒液独特の匂いが広がる病院で、またひとつ新たな命が誕生した。それは、もうすぐ9月に入るという、まだまだ夏を感じさせる日のこと。
2018年 8月 27日 午後4時24分。
「名前は結局どうするんだ」
悠希は病室の丸椅子をこちらに引き寄せて座った。
「あれ、前から言ってなかった?」
ベッドに横たわる莉菜の顔色は、最初はよくなかったものの徐々に回復に向かっているようだった。
「みく、が良いなぁって」
「どうして?」
莉菜はそっと微笑んで、ゆっくりと言い聞かせるように話し始める。
「未来って書いてみくにしようと思ってるんだけど、あたしには本当の親がいないじゃない? だから、この子にはこの先の未来ではあたしからも、誰からも愛を注がれて生きて欲しいことがまずひとつ」
「ほかは?」
「あたしは、拾われなかったらここにいないわけでしょ? でも、ここにいることが出来てるのは、お父さんとお母さんがここまで育ててくれたから。だから、未来に向かって生きれるし、そのお陰でたくさんの人に出会えた」
悠希にもね、と彼女は付け足した。その目は少し悲しげに見えた。
「何が起きても、未来に向かって進んで欲しいから」
「すごく……いいと思うよ」
「本当に?」
先程から莉菜の意見を聞くばかりだが、悠希にも考えがないわけではない。
「未来って未だ来ないって書くから、自分で未来を掴めるような子に、なって欲しいと思う。でも、こんなに意味が多いならひらがなでもいいと思う」
「なんだ、まともに考えてるじゃん」
「当たり前ですが」
悠希は新生児用ベッドに眠っている子ども――みくを覗き込んだ。何故だか微かに笑っているように見えて、こちらまでほころんでくる。
「きっと、美人になるね」
「なんで?」
「あたしの子だから」
莉菜は自分で言いながら笑っていた。
「うちにわがまま姫がこれ以上増えるのはキツイなぁ」
「それって、誰のことかな?」
ここの病室からは幸せそうな笑い声が、絶えず響いていた。
病室の外で二人の会話を聞いていたミクは、途中から俯き始めて最後には顔を手で覆っていた。
「これでも、最初からいなかった方が良かったなんて言うか?」
ミクは鼻をすすりながら、静かに首を横に振った。
「ごめんなさい」
目の前に年が変わらない自分の娘がいる。今になってその不思議さに気付き、ミクを見守るように見ていた。
「お前がここにいるのは奇跡に近いんだ。だって、俺と莉菜は出会わないはずだったんだから。証が欲しいって言ったけど、お前が俺と莉菜が出会えた証だと思うけどな」
ミクは涙を拭い、悠希に小さく笑って見せた。笑い慣れていないのであろう。その引きつった笑顔に、悠希も顔をほころばせていた。 |
【第3話に戻る】 【最終話に続く】
| 第4話 |  |
 Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved.
Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved. |