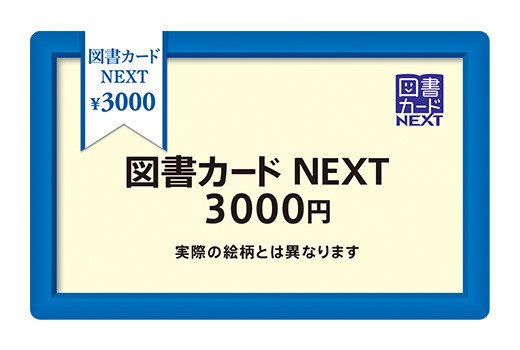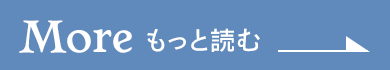2026.02.03
ヴィーガンの気持ちに寄り添いたい
ONE MORNING「 The Starters 」
火曜日のこの時間は社会に風穴を開けようと取り組む若き起業家をお迎えして
そのアイデアの根っこにあるものや未来へ向けたビジョンを伺います。
今週と来週のゲストは、株式会社ブイクック 代表取締役CEOの工藤 柊さんです。
工藤 柊さんは、1999年生まれ、大阪のご出身。高校3年生からヴィーガン生活を始め、進学した大学の食堂にヴィーガン対応メニューを導入。その後、ヴィーガンカフェの店長を経て、2020年にブイクックを創業されています。
そもそもこの“ヴィーガン”について知っているようで知らないんですが、ベジタリアンとの違いなど、ヴィーガンについて詳しく教えてください。
「最初にそれをお話ししておくと、“ベジタリアン”というのがお肉とか魚食べない、ライフスタイルとか考え方。 その中でさらに卵とか牛乳だったり、はちみつだったり、動物性のものを一切食べない・買わないというのがヴィーガンですね。」
ベジタリアンの中でもさらに厳密に動物性のものを採らないというのがヴィーガンということなんですね。
今週は主な事業内容をうかがいます。まず会社のミッションはなんでしょうか?
「僕たちは「Hello Vegan!な社会をつくる」というのをミッションにしています。今ヴィーガン生活をするのってかなり大変で、スーパーや外食に行っても食べられるもの・選べるものが少ないので、それをもっと簡単に、始めやすくて続けやすい、そういった環境を作るというのをミッションにしてやっています。例えば、家族からもあまり理解されないといった問題ですね。僕も高3からヴィーガン生活をしているんですが、学校の友達に言っても「何それ?」みたいな反応で理解されない、もっと言うと批判されてしまうという感じなのでもう少し、普通に窮屈なく生きられるようにしたいです。」
ヴィーガンの方は海外で多いイメージがあるのですが、日本でも増えているんでしょうか?
「そうですね!日本でもお店だったり商品だったりはどんどん増えて、特に2020年のオリンピックの時期から各メーカーさんや飲食店さんがヴィーガン商品を出すところは増えてきてはいますが、日本人・日本在住でヴィーガン・ベジタリアンの方は少しずつ増えているぐらいで、まだ大幅に増えているわけではないとふうに見ています。」
確かにインバウンドで需要があるからお店も増えたのかもしれないですね。
ヴィーガンの方って世界的に見ると結構いらっしゃるんですよね。
「欧米は特になんですが、国にもよりますが5%から10%くらいがヴィーガンやベジタリアンの方というデータもあります。」
人口を考えたらかなり多いですね!
そんな中、工藤さんが創業されたブイクック、今力を入れている事業を教えてください。
「今は「Vegan Sushi Tokyo」というヴィーガン寿司の専門店をやっております。」
お寿司はどうしても魚のイメージがあり、ヴィーガン寿司というのは想像がつかないんですが、かっぱ巻きはヴィーガン寿司に入るんですか?
「かっぱ巻きは入りますね笑。」
せっかく寿司屋にいってカッパ巻きだけじゃ嫌ですよね。
「まさにそうで、僕もそうですが、お寿司を食べに行っても、みんないろいろ食べている中、自分だけかっぱ巻きを食べ続けるみたいな感じなんです。そういった経験がヴィーガン寿司を作ろうと思ったきっかけです。元々僕も高3まではヴィーガンじゃなかったので、もちろんお寿司をいろいろ食べられるのは楽しかったし、好きだったので、自分でもいろいろ食べたいという気持ちがありました。他にもベジタリアン、ヴィーガンの方とお話ししていると、日本人でも観光客の方でも寿司を食べたいけど結局キュウリのカッパ巻きしかないといった状況、かなり残念な思いをされている方が多かったということで、じゃあ自分たちでお寿司をやろうと思い、始めました。」
ヴィーガン寿司にはどういったネタがあるんでしょうか?
「僕たちいろんな種類を出しているんですが、もちろんかっぱ巻きだけではなく、ミョウガやキノコなど、そういったシンプルなものや、ヴィーガンらしいものとして大豆ミートでできた焼肉寿司や、ツナではないツナマヨ、卵をしようしない玉子などを用意してご提供しています。」
写真を見ているとかなり色とりどりで、美味しそうですね!一個気になったのがいくらのようなものがあるのですがこれは一体なんなんですか?
「これ驚かれる方多いんですが、いくらじゃないんですよね。海藻のワカメや昆布、海苔などからうまみを取って、見た目をいくら風に加工しているんですけど、全然いくらじゃないんです。」
玉子っぽいものもありますが、こちらはなんですか?
「こちらも豆腐や豆乳を使い、色はかぼちゃのペーストを使って再現したものです。」
お肉っぽいものありますね。
「そちらは大豆ミートですね。かなり人気でしっかり焼き目もつけて、お店オリジナルの焼肉のタレも付けてご用意しています。」
こう見るとお魚を使っていなくても色とりどりで美味しそうです!
「使用する砂糖も気にされている方も多く、白砂糖を作る過程で、牛の骨の成分を使って精製するものもあるので、僕らはてんさい糖を使用して酢飯を作っています。」
徹底してますね。
逆に、お寿司である必要もないんじゃないかと思ったんですがいかがでしょうか? 海外のお客様のヴィーガンの方たちの中では、やはりお寿司で食べたいみたいな意見もあるんですか?
「ヴィーガンの選択肢がまず少ないので、ヴィーガンのお店がまず求められていますね。その中でも自分でもまず食べたかったし、他の方にとってもお寿司って自分でやっていてもかなり大変というか、めんどくさいことが多いんですよ。 仕込みも一つの料理じゃないので。というのもあって、他の人もやってないならやってみようかなっていうので始めました。」
よくその未知の世界に飛び込みましたね。そもそも飲食の経験自体はあったんですか?
「ほぼほぼないですね。 本当にアルバイトで一か月やったぐらいで、家でも料理を少しやるぐらいだったので、何もわからないところから始めました。寿司についても野菜切るところから酢飯、シャリを作るところまで何もわかりませんでした。ということもあって、知り合いの野菜寿司職人の谷水晃さんという方に、お店を始める前に教えていただいて、スタッフ全員で野菜の切り方から焼き方まで一から教えていただいて、スタートしました。」
どの業種でも難しいとは思うんですが、特に飲食って浮き沈みが激しいと聞くんですけれども、ヴィーガン専門のお寿司屋さんってレアな存在ではありますが、お店を出した当初の皆さんの反応はいかがでしたか?
「やっぱり最初はもちろん、お店を始めてすぐお客様がいらっしゃるわけじゃないので、本当に地道に毎日用意していましたが、結局全部使えずに残り物をスタッフで頑張って食べるといった状況から始まり、少しずつお客様も増えてきてくださって、「寿司はヴィーガンだと食べられなかったから嬉しいよ」といった声があったり、メニュー表に僕自身の今までのストーリーも載せていて、ヴィーガンを始めてこういう事業をやってきてこのお店出したんですというのを書いているんですが、それを読んで涙ぐみながら「このお店を作ってくれてありがとう」と言ってくれるお客様がいらっしゃったりしました。」
ヴィーガンの方にとっては選択肢が増えたわけですから嬉しいでしょうね。
ネタの試作の段階で上手くいかなかったりボツになったりしたものはあるんですか?
「オペレーション面や味の面などいろいろあるんですが、味でいうと、大豆ミートの商品がクオリティがまちまちというか、合う合わないがあるんですよね。なので大豆ミートの中でも大豆臭さがまだ残っている商品使うと、ちょっと美味しくなかったみたいなことがありました。それを何種類も大豆ミートを試しながら作りましたね。」
何度も試作しながらね、美味しい形を見つけてくれたわけですね。
ということで今週はそろそろお時間となってしまいましたが、最後にこれまで乗り越えてきたハードルを教えてください。
「お寿司を始める前にハードルがあって、今までヴィーガンレシピの投稿サイトやECをやってきていたんですがそれがあんまりうまいこといかずで、本当にあと数ヶ月で倒産するかもという状況になったのが大変でしたね。そこから最後の数ヶ月あるなら挑戦しようとできたのが今の「Vegan Sushi Tokyo」の事業です。」


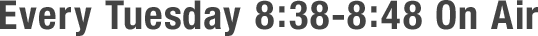




 20代~30代の若手起業家をゲストに迎え、
20代~30代の若手起業家をゲストに迎え、