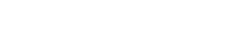第495話 逆境に負けない
-【福岡県にゆかりのあるレジェンド篇】作曲家 古賀政男-
[2025.02.22]
Podcast

福岡県に生まれた、昭和を代表する作曲家・ギタリストがいます。
古賀政男(こが・まさお)。
作曲した楽曲は、5000曲とも言われ、『酒は涙か溜息か』『丘を越えて』『影を慕いて』や『東京ラプソディ』など、独特の曲調、旋律はリスペクトを込めて、『古賀メロディ』と呼ばれています。
古賀は、昭和13年から東京、代々木上原に移り住み、その地を音楽村にしようという構想を持っていました。
現在、その遺志は「古賀政男音楽博物館」として結実。
大衆音楽の伝統を守り続けています。
この博物館にはホールもあり、古賀の自宅から一部移築した書斎や日本間が展示されている他、1000曲にも及ぶ彼の楽曲を視聴できるコーナーもあります。
作曲家として大成功を収めた古賀ですが、実は、その人生は苦難の連続でした。
幼い頃、父を亡くし、故郷を追われて朝鮮に渡ったこと。
貧しさや強い喪失感は、後に発表した楽曲に影響を与えています。
さらに、有名になってからも苦労は絶えませんでした。
特に古賀を苦しめたのは、誹謗中傷。
日本図書センター刊『古賀政男 歌はわが友わが心』には、そのときの思いが綴られています。
・・・心ない批評にたいして、血の気の多い頃の私は、ほんとうに腹がたった。
作品がヒットしても、「なに、あれはマスコミの力さ」と、こともなげに言い放つ人々もいた。
しかし、私は一言も反論や弁解をせずにじっと耐えてきた。・・・
古賀がイチバンに信じたのは、彼が作曲した曲を口ずさんでくれる一般大衆でした。
毎日、汗水たらして働き、嫌な思い、辛い思いをかみしめ、ささやかな幸せを大切にして生きているひとたちに、届く歌。
彼は、歌の力を信じていたのです。
常に聴くひとの心に寄り添い続けたレジェンド・古賀政男が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

戦前戦後、数多くの流行歌を世に送り出した作曲家、古賀政男は、1904年11月18日、福岡県三潴郡田口村、現在の大川市に生まれた。八人兄弟の六番目。
父は、瀬戸物を天秤棒にかついで売り歩く行商人。
幼い古賀は、父の帰りを待つ夕暮れ時が大好きだった。
山間の向こうに、陽が落ちていく。
カラスが鳴きながら空を横切る。
村に続く一本道を父が、えっちらおっちら帰ってくる。
古賀が、天秤棒の片方の畚にのせてもらう。
風景が、揺れる。
父の動きに合わせて、揺れる。
家に戻ると、母に叱られた。
「お父さんは疲れてヘトヘトなのに、なんてことを!」
でも父は、静かにニコニコ笑っていた。
生活は苦しかったが、家には笑顔があふれ、兄や姉たちも優しかった。
古賀が5歳のときに、父が亡くなる。
享年50歳。辞世の句は、古賀の弟のことを詠んだ。
「撫子(なでしこ)の花に変わりはなけれども おくれて咲くが 哀れなりけり」
大黒柱を失くした一家の運命は、か細い母の肩にのしかかる。
古賀政男が幼少期を過ごした田口村は、筑後川の下流にあった。
川から引いた水路、掘割は、子どもたちの格好の泳ぎ場だった。
夏になると、みんなは飛び込み、泳いだ。
でも、古賀は泳げない。
いつも堀の近くでしゃがんで、水面を眺めていた。
さみしい。水の中から笑われる。
ある日、母が、そんな古賀をいきなり掘割に突き落とした。
驚いた。水の中で、もがく。
着物が体にまとわりつき、沈みそうになる。
なんとか必死で、岸にたどり着いた。
母は、びしょぬれの古賀に言った。
「お前は、これから泳ぎを覚えんといかん」
そのときは、なんてひどいことをするのかと思ったけれど、後に、古賀は思う。
あれは、父なきあと、逆境を生きていく、母の決意、そして、この先、水の中に叩き落されても、自力ではいあがる強さを持ちなさい、という戒めだったのかもしれない。
あのときの母の表情は、逆光になってよくわからなかったが、きっと、厳しく、哀しく、そして慈愛に満ちていたに違いない。
掘割で泳ぐようになった幼い古賀政男が、水の中で発見したものがあった。
それは、音。
水にもぐっていると、外界の音が違って聴こえる。
一緒に遊ぶ子どもの声が不思議に響き、歌のように思えた。
水の中で、石をぶつけると、変った音色を奏でる。
もぐる。水面から顔を出す。またもぐる。
音の聴こえ方の変化が面白くて、何度も試す。
古賀の家に音楽的環境は皆無だったが、初めて音の魅力を知った。
もうひとつ、運命的な音楽との出会いがあった。
それは、村にやってきたサーカスと旅芸人。
森の向こうに、クラリネットの音が響く。
哀しい。涙が出る。
どうしてだろう…。
旅芸人がやってくると、今度は月琴の調べが聴こえる。
月琴とは、丸い共鳴胴に、細く短い首をつけた弦楽器。
この音も物悲しい。
胸が締め付けられるような思い。忘れられない旋律。
「これはいったいどういうことなんだろう…」
そんな疑問が、彼を音楽の道に駆り立てた。
中学3年生で、初めてマンドリンを手にしたとき、子どもの頃聴いた、月琴を思い出した。
あのとき感じた物悲しさこそ、古賀メロディの原点かもしれない。
そして、苦難の道につまずきそうになると、いつも 水路に自分を突き落とした母を思い出した。
どんな逆境にあっても、歌を信じ、歌に生涯を捧げた。
「一言も褒めることなく、また けなすことなくして、私の曲を口ずさんで下さる人々だけが私の心の支え」
古賀政男

【ON AIR LIST】
◆東京ラプソディ / 藤山一郎
◆影を慕いて / 藤山一郎
◆サーカスの唄 / 松平晃
◆丘を越えて / 藤山一郎
【参考文献】
『古賀政男 歌はわが友わが心』(日本図書センター)
★掲載写真は、「古賀政男音楽博物館」様にご協力いただきました。ありがとうございました。
アクセスなど、詳しくは公式HPにてご確認ください。
古賀政男音楽博物館 公式HP
古賀政男(こが・まさお)。
作曲した楽曲は、5000曲とも言われ、『酒は涙か溜息か』『丘を越えて』『影を慕いて』や『東京ラプソディ』など、独特の曲調、旋律はリスペクトを込めて、『古賀メロディ』と呼ばれています。
古賀は、昭和13年から東京、代々木上原に移り住み、その地を音楽村にしようという構想を持っていました。
現在、その遺志は「古賀政男音楽博物館」として結実。
大衆音楽の伝統を守り続けています。
この博物館にはホールもあり、古賀の自宅から一部移築した書斎や日本間が展示されている他、1000曲にも及ぶ彼の楽曲を視聴できるコーナーもあります。
作曲家として大成功を収めた古賀ですが、実は、その人生は苦難の連続でした。
幼い頃、父を亡くし、故郷を追われて朝鮮に渡ったこと。
貧しさや強い喪失感は、後に発表した楽曲に影響を与えています。
さらに、有名になってからも苦労は絶えませんでした。
特に古賀を苦しめたのは、誹謗中傷。
日本図書センター刊『古賀政男 歌はわが友わが心』には、そのときの思いが綴られています。
・・・心ない批評にたいして、血の気の多い頃の私は、ほんとうに腹がたった。
作品がヒットしても、「なに、あれはマスコミの力さ」と、こともなげに言い放つ人々もいた。
しかし、私は一言も反論や弁解をせずにじっと耐えてきた。・・・
古賀がイチバンに信じたのは、彼が作曲した曲を口ずさんでくれる一般大衆でした。
毎日、汗水たらして働き、嫌な思い、辛い思いをかみしめ、ささやかな幸せを大切にして生きているひとたちに、届く歌。
彼は、歌の力を信じていたのです。
常に聴くひとの心に寄り添い続けたレジェンド・古賀政男が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

戦前戦後、数多くの流行歌を世に送り出した作曲家、古賀政男は、1904年11月18日、福岡県三潴郡田口村、現在の大川市に生まれた。八人兄弟の六番目。
父は、瀬戸物を天秤棒にかついで売り歩く行商人。
幼い古賀は、父の帰りを待つ夕暮れ時が大好きだった。
山間の向こうに、陽が落ちていく。
カラスが鳴きながら空を横切る。
村に続く一本道を父が、えっちらおっちら帰ってくる。
古賀が、天秤棒の片方の畚にのせてもらう。
風景が、揺れる。
父の動きに合わせて、揺れる。
家に戻ると、母に叱られた。
「お父さんは疲れてヘトヘトなのに、なんてことを!」
でも父は、静かにニコニコ笑っていた。
生活は苦しかったが、家には笑顔があふれ、兄や姉たちも優しかった。
古賀が5歳のときに、父が亡くなる。
享年50歳。辞世の句は、古賀の弟のことを詠んだ。
「撫子(なでしこ)の花に変わりはなけれども おくれて咲くが 哀れなりけり」
大黒柱を失くした一家の運命は、か細い母の肩にのしかかる。
古賀政男が幼少期を過ごした田口村は、筑後川の下流にあった。
川から引いた水路、掘割は、子どもたちの格好の泳ぎ場だった。
夏になると、みんなは飛び込み、泳いだ。
でも、古賀は泳げない。
いつも堀の近くでしゃがんで、水面を眺めていた。
さみしい。水の中から笑われる。
ある日、母が、そんな古賀をいきなり掘割に突き落とした。
驚いた。水の中で、もがく。
着物が体にまとわりつき、沈みそうになる。
なんとか必死で、岸にたどり着いた。
母は、びしょぬれの古賀に言った。
「お前は、これから泳ぎを覚えんといかん」
そのときは、なんてひどいことをするのかと思ったけれど、後に、古賀は思う。
あれは、父なきあと、逆境を生きていく、母の決意、そして、この先、水の中に叩き落されても、自力ではいあがる強さを持ちなさい、という戒めだったのかもしれない。
あのときの母の表情は、逆光になってよくわからなかったが、きっと、厳しく、哀しく、そして慈愛に満ちていたに違いない。
掘割で泳ぐようになった幼い古賀政男が、水の中で発見したものがあった。
それは、音。
水にもぐっていると、外界の音が違って聴こえる。
一緒に遊ぶ子どもの声が不思議に響き、歌のように思えた。
水の中で、石をぶつけると、変った音色を奏でる。
もぐる。水面から顔を出す。またもぐる。
音の聴こえ方の変化が面白くて、何度も試す。
古賀の家に音楽的環境は皆無だったが、初めて音の魅力を知った。
もうひとつ、運命的な音楽との出会いがあった。
それは、村にやってきたサーカスと旅芸人。
森の向こうに、クラリネットの音が響く。
哀しい。涙が出る。
どうしてだろう…。
旅芸人がやってくると、今度は月琴の調べが聴こえる。
月琴とは、丸い共鳴胴に、細く短い首をつけた弦楽器。
この音も物悲しい。
胸が締め付けられるような思い。忘れられない旋律。
「これはいったいどういうことなんだろう…」
そんな疑問が、彼を音楽の道に駆り立てた。
中学3年生で、初めてマンドリンを手にしたとき、子どもの頃聴いた、月琴を思い出した。
あのとき感じた物悲しさこそ、古賀メロディの原点かもしれない。
そして、苦難の道につまずきそうになると、いつも 水路に自分を突き落とした母を思い出した。
どんな逆境にあっても、歌を信じ、歌に生涯を捧げた。
「一言も褒めることなく、また けなすことなくして、私の曲を口ずさんで下さる人々だけが私の心の支え」
古賀政男

【ON AIR LIST】
◆東京ラプソディ / 藤山一郎
◆影を慕いて / 藤山一郎
◆サーカスの唄 / 松平晃
◆丘を越えて / 藤山一郎
【参考文献】
『古賀政男 歌はわが友わが心』(日本図書センター)
★掲載写真は、「古賀政男音楽博物館」様にご協力いただきました。ありがとうございました。
アクセスなど、詳しくは公式HPにてご確認ください。
古賀政男音楽博物館 公式HP