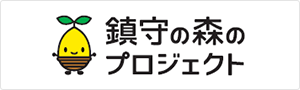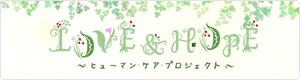әЈҪөӨПАиҪөӨЛ°ъӨӯВіӨӯЎўЈұЈұ·оЈөЖьЎҰДЕЗИЛЙәТӨОЖьӨЛ№ФӨпӨмӨҝҘ·ҘуҘЭҘёҘҰҘаӨОМПННӨтӨӘЖПӨұӨ·ӨЮӨ№ЎЈӨіӨмӨПҝ№ӨОД№ҫлҘЧҘнҘёҘ§ҘҜҘИӨКӨЙЎЦДЕЗИӨ«ӨйМҝӨтјйӨлҝ№ӨЕӨҜӨкЎЧӨтВзӨӯӨКҘЖЎјҘЮӨЛӨ·ӨҝӨвӨОӨЗЎўЛЙәТЎҰёәәТӨПӨёӨбЎўіЖАмМзІИӨЛӨиӨл№ЦұйӨ¬№ФӨпӨмӨЮӨ·ӨҝЎЈ
әЈІуӨПӨҪӨОӨКӨ«Ө«ӨйЎўҝ№ОУК¬»ТАёВЦіШӨИӨӨӨҰЎўҝўКӘӨтDNAҘмҘЩҘлӨЗёҰөжӨ№ӨлёҰөжјФЎўЕмЛМВзіШВзіШұЎ ҪЪ¶өјшӨОЖ«»іІВөЧӨөӨуӨО№ЦұйӨО°мЙфӨтӨӘЖПӨұӨ·ӨЮӨ№ЎЈ
ДЕЗИӨ«ӨйМҝӨтјйӨлЎЦҝ№әоӨкЎЧӨдЎЦҝўјщЎЧӨЛӨДӨӨӨЖЎўҝўКӘӨОАмМзІИЎҰЖ«»іӨөӨуӨПЎўӨЙӨҰ№НӨЁӨЖӨӨӨлӨОӨЗӨ·ӨзӨҰӨ«ЎЈ
ўЎАёКӘӨЛӨПГП°иАӯӨ¬ӨўӨл
ҝўјщӨИӨӨӨҰӨОӨПМӨНиӨЛВРӨ·ӨЖӨОАХЗӨӨ¬АёӨёӨл№Ф°ЩӨИӨӨӨЁӨЮӨ№ЎЈӨКӨјӨКӨйМӨНиӨОҙД¶ӯӨЛұЖ¶БӨтөЪӨЬӨ№Ө«ӨйӨЗӨ№ЎЈМЪӨПАёӨӯӨЖА®Д№Ө·ӨЖҫӯНиӨОҙД¶ӯӨтӨДӨҜӨкӨЮӨ№ЎЈІЦӨтәйӨ«Ө»ӨмӨРІЦКҙӨтИфӨРӨ·ЎўјпӨтәоӨкЎўјюӨкӨОј«БіҙД¶ӯӨЛӨвұЖ¶БӨтөЪӨЬӨ№ӨОӨЗӨ№ЎЈӨ·ӨҝӨ¬ӨГӨЖҝўјщӨИӨӨӨҰӨОӨПӨиӨкОЙӨӨМӨНиӨОҙД¶ӯӨтЖіӨҜӨИӨӨӨҰӨіӨИӨ¬ӨӨӨЁӨЮӨ№ЎЈ
ӨҪӨ·ӨЖЎўАёКӘӨЛӨПГП°иАӯӨ¬ӨўӨкӨЮӨ№ЎЈӨКӨјӨКӨйіЖГП°иӨЛӨПіЖГП°иӨҪӨмӨҫӨмӨООт»ЛЎҰҙД¶ӯӨ¬ӨўӨкЎўӨҪӨООт»ЛӨОҫеӨЗӨҪӨОҫмҪкӨЛӨӨӨлӨОӨ¬ҙрЛЬӨАӨ«ӨйӨЗӨ№ЎЈӨ·ӨҝӨ¬ӨГӨЖГП°иАӯӨтМө»лӨ·ӨҝҝўјщӨПј«БіЗЛІхӨЛӨвӨКӨкЖАӨЮӨ№ЎЈОгӨИӨ·ӨЖЎўҝ№ӨОЛЙД¬ДйӨЛ»ИӨпӨмӨЖӨӨӨлВеЙҪјпЎҰҘҝҘЦҘОҘӯЎЈӨіӨмӨПИуҫпӨЛВзӨӯӨҜА®Д№Ө№ӨлМЪӨЗЎўЕмЛМГПКэӨОіӨҙЯӨОВеЙҪЕӘӨК№ӯНХјщЎўЖьЛЬӨОВеЙҪЕӘӨКҫпОРӨО№ӯНХјщӨЗӨ№ЎЈВАКҝНОВҰӨПҙдјкё©Ө«ӨйЎўЖоВҰӨПВжПСӨдГж№сЛЬЕЪӨЛӨвӨўӨлЎЈӨіӨмӨ¬ҘҝҘЦҘОҘӯӨИӨӨӨҰМЪӨОК¬ЙЫ°иӨЗӨ№ЎЈӨіӨОӨиӨҰӨЛ№ӯӨӨИП°ПӨЛК¬ЙЫӨ№ӨлӨОӨЗЎўГП°иГП°иӨЛӨҪӨмӨҫӨм°гӨГӨҝҘҝҘЦӨОМЪӨ¬ВёәЯӨ№ӨлӨИӨӨӨҰӨпӨұӨЗӨ№ЎЈ
јВәЭЎўБҙ№сӨ«ӨйҘҝҘЦҘОҘӯӨтҪёӨбӨЖЈіЈіЈ·ёДВОӨОDNAӨтИжӨЩӨҝӨИӨіӨнЎўБҙВОӨИӨ·ӨЖЈіӨДӨОҘ°ҘлЎјҘЧӨЛК¬Ө«ӨмӨЖӨӨӨлӨіӨИӨ¬ӨпӨ«ӨкӨЮӨ·ӨҝЎЈАҫЎўҙШЕмЎўЕмЛМӨИӨӯӨГӨСӨкКМӨмӨлЎЈӨвӨБӨнӨуВҝҫҜӨОҘОҘӨҘәӨПӨўӨкӨЮӨ№Ө¬ЎўӨіӨОЈіӨДӨОҘ°ҘлЎјҘЧӨ¬ӨЙӨҰӨӨӨГӨҝ·Р°ЮӨЗЎўӨЙӨмӨҜӨйӨӨӨОЗҜВеӨЗК¬Ө«ӨмӨЖӨӯӨҝӨОӨ«ӨПІтАПӨ№ӨлӨіӨИӨ¬ӨЗӨӯӨЮӨ№ЎЈӨіӨмӨ¬К¬Ө«ӨмӨҝӨОӨПҫҜӨКӨҜӨИӨвҝфЛьЗҜБ°ӨЗӨ№ЎЈЙ№ІП»юВеӨОҙЁӨ«ӨГӨҝәўӨПЕмЛМГПКэӨЛӨПӨўӨкӨЮӨ»ӨуӨЗӨ·ӨҝЎЈЛјБнИҫЕзӨИӨ«өӘ°ЛИҫЕзӨОАиЎўјҜ»щЕзӨЛӨ·Ө«ВёәЯӨ·ӨКӨӨЎЈҙЁӨ«ӨГӨҝӨ«ӨйӨЗӨ№ЎЈ
ӨЯӨКӨөӨуӨПЎўҝ№ӨПӨәӨГӨИӨҪӨОҫмӨЛӨўӨлӨиӨҰӨКөӨӨЛӨКӨГӨЖӨӨӨлӨ«ӨвӨ·ӨмӨЮӨ»ӨуӨ¬ЎўӨҪӨуӨКӨіӨИӨПӨўӨкӨЮӨ»ӨуЎЈҫҜӨКӨҜӨИӨвЈұЛьЗҜ°КҫеӨ«ӨұӨЖәЈӨОК¬ЙЫ°иӨЮӨЗ№ӯӨ¬ӨГӨЖӨӨӨлЎЈЖ°ӨӨӨЖӨӨӨлӨОӨЗӨўӨмӨРәЈӨвЖ°Ө«Ө·ӨЖӨвӨӨӨӨӨёӨгӨКӨӨӨ«ӨИ»ЧӨпӨмӨлӨ«ӨвӨ·ӨмӨЮӨ»ӨуӨ¬ЎўӨҪӨуӨКӨіӨИӨПӨКӨӨӨуӨЗӨ№ЎЈК¬ЙЫ°иӨ¬Ж°ӨҜӨОӨЛӨПҝфЙҙАӨВе°КҫеӨ¬Ө«Ө«ӨГӨЖӨӨӨЮӨ№ЎЈЛиАӨВеЛиАӨВеЎўӨҝӨҜӨөӨуӨОјпӨтәоӨГӨЖӨҪӨОГжӨЗҙД¶ӯӨЛЕ¬Ө·ӨҝӨвӨОӨ¬АёӨӯ»ДӨГӨЖЎўӨҪӨмӨт·«ӨкКЦӨ·ЎўҘИҘйҘӨҘўҘуҘЙҘЁҘйЎјӨ¬·«ӨкКЦӨөӨмӨЖёҪәЯӨЛ»кӨГӨЖӨӨӨлӨпӨұӨЗӨ№ЎЈӨҪӨмӨҫӨмӨОГПӨЛАёӨӯ»ДӨГӨЖӨӨӨлАёКӘӨПЎўҙрЛЬЕӘӨЛЖұӨёӨиӨҰӨКОт»ЛӨт»эӨГӨЖӨӨӨЖЎўӨҪӨмӨ¬іЖГПӨЛә¬ЙХӨӨӨЖӨӨӨлӨуӨЗӨ№ӨНЎЈӨҪӨҰ№НӨЁӨлӨИЎўӨҪӨмӨҫӨмӨОГПӨЛӨҪӨмӨҫӨмӨОКхӨ¬ӨўӨлӨИёАӨГӨЖӨвӨӨӨӨӨИ»ЧӨӨӨЮӨ№ЎЈ
Ж«»іӨөӨуӨПӨіӨОЎЦҘҝҘЦҘОҘӯЎЧӨИӨӨӨҰјщМЪӨОDNAӨтБҙ№сЕӘӨЛДҙәәЎЈЖұӨёҘҝҘЦҘОҘӯӨЗӨвЎўЕмЛМӨИЎўӨҪӨм°Кі°ӨЗӨПКМӨОҘ°ҘлЎјҘЧӨЛК¬Ө«ӨмӨлӨіӨИӨтЖНӨӯ»ЯӨбӨЖӨӨӨлӨуӨЗӨ№Ө¬ЎўӨіӨОДҙәә·лІМӨПЎўҝўјщӨдҝ№ӨЕӨҜӨкӨтӨ№ӨлҫеӨЗВзӨӯӨК°ХМЈӨ¬ӨўӨлӨуӨЗӨ№ЎЈ
ўЎМӨНиӨЛӨиӨкОЙӨӨҙД¶ӯӨт»ДӨ№
ҘҝҘЦҘОҘӯӨПӨіӨОӨиӨҰӨЛ№ӯӨӨИП°ПӨЛК¬ЙЫӨ№ӨлӨОӨЗЎўГП°иГП°иӨЛӨҪӨмӨҫӨм°гӨГӨҝҘҝҘЦҘОҘӯӨ¬ВёәЯӨ№ӨлӨОӨЗӨ№Ө¬ЎўБҙВОӨИӨ·ӨЖАҫЎҰҙШЕмЎҰЕмЛМӨОЈіӨДӨОҘ°ҘлЎјҘЧӨЛК¬Ө«ӨмӨлӨіӨИӨ¬ӨпӨ«ӨкӨЮӨ·ӨҝЎЈ
ҝўјщӨОәЭӨЛӨПЎўОгӨЁӨРЙДМЪӨ¬ВӯӨкӨКӨӨӨИӨ«Ўў·РәСЕӘӨКМдВкӨЗӨдӨаӨтЖАӨә°гӨҰГП°иӨ«Өй°ЬҝўӨөӨмӨлӨіӨИӨ¬ӨўӨкӨЮӨ№ЎЈӨӨӨЮӨПӨіӨОҘЗЎјҘҝӨ¬ӨўӨлӨОӨЗЎЦӨҪӨмӨП°гӨҰГП°иӨОӨвӨОӨЗӨ№ӨиЎЧӨИёАӨҰӨіӨИӨ¬ӨЗӨӯӨлӨ¬ЎўӨіӨОҘЗЎјҘҝӨ¬МөӨұӨмӨРЎўЖұӨёҘҝҘЦҘОҘӯӨАӨ«ӨйӨӨӨӨӨЗӨ·ӨзӨИҝўӨЁӨйӨмӨЖӨ·ӨЮӨҰЎЈ°дЕБЕӘӨЛ°гӨҰӨіӨИӨ¬ӨКӨј°ӯӨӨӨОӨ«ӨтАвМАӨ№ӨлӨҝӨбӨЛјВәЭӨЛҝўӨЁӨЖИжіУӨтӨ·ӨЖӨЯӨҝЎЈАйЗҜҙхЛҫӨОөЦӨЗЎўЖұӨёҝфӨАӨұЖұӨёҫмҪкӨЛЕэ·ЧЕӘӨЛИжіУӨЗӨӯӨлӨиӨҰӨЛҘҝҘЦҘОҘӯӨтҝўӨЁӨЮӨ·ӨҝЎЈ°мЕЯұЫӨЁӨҝӨўӨИЎў°ҰГОё©»әЎҰ°сҫлё©»әӨОЙДМЪӨПёПӨмӨЖӨӨӨЮӨ·ӨҝЎЈ°мКэӨЗЎўБҙӨҜЖұӨёҫт·пӨЗӨвЎўөЬҫлё©»әӨОӨвӨОӨПёөөӨӨЛ°йӨГӨЖӨӨӨлӨвӨОӨ¬ӨўӨлЎЈЖо»°ОҰӨЗӨвИжіУӨ·ӨҝӨОӨЗӨ№Ө¬ЎўөЬҫлё©ӨОӨвӨОӨПӨдӨПӨкА®Д№Ө¬ОЙӨӨЎЈјщ№вӨ¬ӨпӨәӨ«ЈұЗҜӨЗВҫӨОГП°иӨОӨвӨОӨИӨҜӨйӨЩӨЖЎўЈұЈ°Ҙ»ҘуҘБӨҜӨйӨӨә№Ө¬ҪРӨБӨгӨҰЎЈА®Д№ӨАӨұӨЗӨКӨҜЎўЕЯӨтұЫӨЁӨҝ»юӨЛ°мИЦАиГјӨОІкЎЦДәІкЎЧӨ¬ӨҝӨҜӨөӨуёПӨмӨЖӨ·ӨЮӨҰӨИӨӨӨҰӨіӨИӨвӨпӨ«ӨкӨЮӨ·ӨҝЎЈөЬҫлё©»әӨЗӨвЈөЈ°ЎуӨҜӨйӨӨёПӨмӨЖӨ·ӨЮӨҰӨОӨЗӨ№Ө¬Ўў°ҰГОё©»әӨПӨпӨәӨ«ЈұЈөЎуӨ·Ө«АёӨӯ»ДӨкӨЮӨ»ӨуӨЗӨ·ӨҝЎЈөЬҫлё©»әӨПЕЯӨОҙЁӨӨҫх¶·ӨЛВРұюӨЗӨӯӨЖӨӨӨлӨ«ӨйӨіӨҰӨКӨлӨОӨЗӨ№Ө¬ЎўӨіӨмӨ¬ӨпӨ«ӨГӨЖӨӨӨҝӨйВҫӨОГП°иӨОМЪӨтҝўјщӨПӨ·ӨКӨӨӨЗӨ№ӨиӨНЎЈ
ӨЮӨәГП°иӨЛӨПЖИј«ӨО°дЕБЕӘӨК·ПЕэӨ¬ӨўӨлӨИӨӨӨҰӨіӨИӨтіРӨЁӨЖӨӘӨӨӨЖӨҜӨАӨөӨӨЎЈГП°иҙД¶ӯӨЛЕ¬ұюӨ·ӨҝёДВОӨЛӨиӨГӨЖЎўҫӯНиӨЛіОјВӨКіӨҙЯОУӨтА®О©Ө¬ҙьВФӨЗӨӯӨлӨ·Ўўҝ№ӨО·ГӨЯӨтөэјхӨ№ӨлӨіӨИӨ¬ӨЗӨӯӨлӨпӨұӨЗӨ№ЎЈӨДӨЮӨкГП°иАӯјпЙДЎҰГП°иӨОЙДМЪӨПОт»ЛӨИӨӨӨҰКЭёұӨ¬НшӨӨӨЖӨӨӨлӨИӨӨӨҰӨіӨИӨКӨуӨЗӨ№ЎЈ
ВҫГП°и»әӨОјпЙДӨЗӨўӨГӨЖӨвМдВкӨКӨҜА®Д№Ө№ӨлӨіӨИӨПӨвӨБӨнӨуӨўӨкӨЮӨ№ЎЈі°НијпӨЗӨвӨиӨҜА®Д№Ө·ИЛұЙӨ·ӨЖӨӨӨлӨвӨОӨвӨўӨкӨЮӨ№ЎЈӨЗӨвӨҪӨмӨП°дЕБ»ТЩшНрӨтөҜӨіӨ·ӨЖӨ·ӨЮӨҰӨОӨЗЎўА®Д№Ө·ӨиӨҰӨ¬Ө·ӨЮӨӨӨ¬ЎўВҫГП°и»әӨОӨвӨОӨт»эӨГӨЖӨҜӨлӨОӨПОЙӨӨ»цӨПӨўӨкӨЮӨ»ӨуЎЈМӨНиӨЛАХЗӨӨОМөӨӨ№Ф°ЩӨАӨИӨӨӨҰӨіӨИӨ¬ӨЗӨӯӨлӨИ»ЧӨӨӨЮӨ№ЎЈ
»дӨПёҰөжӨтӨ·ӨЖӨӨӨЖҝ§Ў№ІҝӨтӨдӨмӨРӨӨӨӨӨОӨ«ӨИ»ЧӨҰӨіӨИӨ¬ӨўӨлӨ¬ЎўәЈӨПӨПӨГӨӯӨкӨИӨіӨҰӨ·ӨҝӨӨӨИӨӨӨҰөӨ»эӨБӨ¬ӨўӨкӨЮӨ№ЎЈЛНӨОӨЗӨӯӨлӨіӨИӨП°дЕБ»ТӨтДҙӨЩӨлӨіӨИӨКӨОӨЗЎўГП°иӨО°дЕБ»сё»ӨтјЎВеӨЛ»ДӨ·ЎўМӨНиӨЛӨиӨкОЙӨӨҙД¶ӯӨт»ДӨ№ӨҝӨбЎўҝ№ӨОЛЙД¬ДйӨЛӨв№ЧёҘӨЗӨӯӨмӨРӨИ»ЧӨГӨЖӨӨӨЮӨ№ЎЈ
Ж«»іІВөЧӨөӨуӨОӨӘПГӨ·ӨӨӨ«Ө¬ӨАӨГӨҝӨЗӨ·ӨзӨҰӨ«ЎЈҘЭҘГҘЙҘӯҘгҘ№ҘИӨЗӨвҫЬӨ·ӨҜӨҙҫТІрӨ·ӨЖӨӨӨЮӨ№ӨОӨЗЎўӨіӨБӨйӨвӨјӨТӨӘК№ӨӯӨҜӨАӨөӨӨЎӘ
ЎЪәЈҪөӨОИЦБИЖвӨЗӨОҘӘҘуҘЁҘў¶КЎЫ
ЎҰBrighter Than The Sun / Colbie Caillat
ЎҰHappy Tomorrow / Nina
әЈІуӨПӨҪӨОӨКӨ«Ө«ӨйЎўҝ№ОУК¬»ТАёВЦіШӨИӨӨӨҰЎўҝўКӘӨтDNAҘмҘЩҘлӨЗёҰөжӨ№ӨлёҰөжјФЎўЕмЛМВзіШВзіШұЎ ҪЪ¶өјшӨОЖ«»іІВөЧӨөӨуӨО№ЦұйӨО°мЙфӨтӨӘЖПӨұӨ·ӨЮӨ№ЎЈ
ДЕЗИӨ«ӨйМҝӨтјйӨлЎЦҝ№әоӨкЎЧӨдЎЦҝўјщЎЧӨЛӨДӨӨӨЖЎўҝўКӘӨОАмМзІИЎҰЖ«»іӨөӨуӨПЎўӨЙӨҰ№НӨЁӨЖӨӨӨлӨОӨЗӨ·ӨзӨҰӨ«ЎЈ
ўЎАёКӘӨЛӨПГП°иАӯӨ¬ӨўӨл
ҝўјщӨИӨӨӨҰӨОӨПМӨНиӨЛВРӨ·ӨЖӨОАХЗӨӨ¬АёӨёӨл№Ф°ЩӨИӨӨӨЁӨЮӨ№ЎЈӨКӨјӨКӨйМӨНиӨОҙД¶ӯӨЛұЖ¶БӨтөЪӨЬӨ№Ө«ӨйӨЗӨ№ЎЈМЪӨПАёӨӯӨЖА®Д№Ө·ӨЖҫӯНиӨОҙД¶ӯӨтӨДӨҜӨкӨЮӨ№ЎЈІЦӨтәйӨ«Ө»ӨмӨРІЦКҙӨтИфӨРӨ·ЎўјпӨтәоӨкЎўјюӨкӨОј«БіҙД¶ӯӨЛӨвұЖ¶БӨтөЪӨЬӨ№ӨОӨЗӨ№ЎЈӨ·ӨҝӨ¬ӨГӨЖҝўјщӨИӨӨӨҰӨОӨПӨиӨкОЙӨӨМӨНиӨОҙД¶ӯӨтЖіӨҜӨИӨӨӨҰӨіӨИӨ¬ӨӨӨЁӨЮӨ№ЎЈ
ӨҪӨ·ӨЖЎўАёКӘӨЛӨПГП°иАӯӨ¬ӨўӨкӨЮӨ№ЎЈӨКӨјӨКӨйіЖГП°иӨЛӨПіЖГП°иӨҪӨмӨҫӨмӨООт»ЛЎҰҙД¶ӯӨ¬ӨўӨкЎўӨҪӨООт»ЛӨОҫеӨЗӨҪӨОҫмҪкӨЛӨӨӨлӨОӨ¬ҙрЛЬӨАӨ«ӨйӨЗӨ№ЎЈӨ·ӨҝӨ¬ӨГӨЖГП°иАӯӨтМө»лӨ·ӨҝҝўјщӨПј«БіЗЛІхӨЛӨвӨКӨкЖАӨЮӨ№ЎЈОгӨИӨ·ӨЖЎўҝ№ӨОЛЙД¬ДйӨЛ»ИӨпӨмӨЖӨӨӨлВеЙҪјпЎҰҘҝҘЦҘОҘӯЎЈӨіӨмӨПИуҫпӨЛВзӨӯӨҜА®Д№Ө№ӨлМЪӨЗЎўЕмЛМГПКэӨОіӨҙЯӨОВеЙҪЕӘӨК№ӯНХјщЎўЖьЛЬӨОВеЙҪЕӘӨКҫпОРӨО№ӯНХјщӨЗӨ№ЎЈВАКҝНОВҰӨПҙдјкё©Ө«ӨйЎўЖоВҰӨПВжПСӨдГж№сЛЬЕЪӨЛӨвӨўӨлЎЈӨіӨмӨ¬ҘҝҘЦҘОҘӯӨИӨӨӨҰМЪӨОК¬ЙЫ°иӨЗӨ№ЎЈӨіӨОӨиӨҰӨЛ№ӯӨӨИП°ПӨЛК¬ЙЫӨ№ӨлӨОӨЗЎўГП°иГП°иӨЛӨҪӨмӨҫӨм°гӨГӨҝҘҝҘЦӨОМЪӨ¬ВёәЯӨ№ӨлӨИӨӨӨҰӨпӨұӨЗӨ№ЎЈ
јВәЭЎўБҙ№сӨ«ӨйҘҝҘЦҘОҘӯӨтҪёӨбӨЖЈіЈіЈ·ёДВОӨОDNAӨтИжӨЩӨҝӨИӨіӨнЎўБҙВОӨИӨ·ӨЖЈіӨДӨОҘ°ҘлЎјҘЧӨЛК¬Ө«ӨмӨЖӨӨӨлӨіӨИӨ¬ӨпӨ«ӨкӨЮӨ·ӨҝЎЈАҫЎўҙШЕмЎўЕмЛМӨИӨӯӨГӨСӨкКМӨмӨлЎЈӨвӨБӨнӨуВҝҫҜӨОҘОҘӨҘәӨПӨўӨкӨЮӨ№Ө¬ЎўӨіӨОЈіӨДӨОҘ°ҘлЎјҘЧӨ¬ӨЙӨҰӨӨӨГӨҝ·Р°ЮӨЗЎўӨЙӨмӨҜӨйӨӨӨОЗҜВеӨЗК¬Ө«ӨмӨЖӨӯӨҝӨОӨ«ӨПІтАПӨ№ӨлӨіӨИӨ¬ӨЗӨӯӨЮӨ№ЎЈӨіӨмӨ¬К¬Ө«ӨмӨҝӨОӨПҫҜӨКӨҜӨИӨвҝфЛьЗҜБ°ӨЗӨ№ЎЈЙ№ІП»юВеӨОҙЁӨ«ӨГӨҝәўӨПЕмЛМГПКэӨЛӨПӨўӨкӨЮӨ»ӨуӨЗӨ·ӨҝЎЈЛјБнИҫЕзӨИӨ«өӘ°ЛИҫЕзӨОАиЎўјҜ»щЕзӨЛӨ·Ө«ВёәЯӨ·ӨКӨӨЎЈҙЁӨ«ӨГӨҝӨ«ӨйӨЗӨ№ЎЈ
ӨЯӨКӨөӨуӨПЎўҝ№ӨПӨәӨГӨИӨҪӨОҫмӨЛӨўӨлӨиӨҰӨКөӨӨЛӨКӨГӨЖӨӨӨлӨ«ӨвӨ·ӨмӨЮӨ»ӨуӨ¬ЎўӨҪӨуӨКӨіӨИӨПӨўӨкӨЮӨ»ӨуЎЈҫҜӨКӨҜӨИӨвЈұЛьЗҜ°КҫеӨ«ӨұӨЖәЈӨОК¬ЙЫ°иӨЮӨЗ№ӯӨ¬ӨГӨЖӨӨӨлЎЈЖ°ӨӨӨЖӨӨӨлӨОӨЗӨўӨмӨРәЈӨвЖ°Ө«Ө·ӨЖӨвӨӨӨӨӨёӨгӨКӨӨӨ«ӨИ»ЧӨпӨмӨлӨ«ӨвӨ·ӨмӨЮӨ»ӨуӨ¬ЎўӨҪӨуӨКӨіӨИӨПӨКӨӨӨуӨЗӨ№ЎЈК¬ЙЫ°иӨ¬Ж°ӨҜӨОӨЛӨПҝфЙҙАӨВе°КҫеӨ¬Ө«Ө«ӨГӨЖӨӨӨЮӨ№ЎЈЛиАӨВеЛиАӨВеЎўӨҝӨҜӨөӨуӨОјпӨтәоӨГӨЖӨҪӨОГжӨЗҙД¶ӯӨЛЕ¬Ө·ӨҝӨвӨОӨ¬АёӨӯ»ДӨГӨЖЎўӨҪӨмӨт·«ӨкКЦӨ·ЎўҘИҘйҘӨҘўҘуҘЙҘЁҘйЎјӨ¬·«ӨкКЦӨөӨмӨЖёҪәЯӨЛ»кӨГӨЖӨӨӨлӨпӨұӨЗӨ№ЎЈӨҪӨмӨҫӨмӨОГПӨЛАёӨӯ»ДӨГӨЖӨӨӨлАёКӘӨПЎўҙрЛЬЕӘӨЛЖұӨёӨиӨҰӨКОт»ЛӨт»эӨГӨЖӨӨӨЖЎўӨҪӨмӨ¬іЖГПӨЛә¬ЙХӨӨӨЖӨӨӨлӨуӨЗӨ№ӨНЎЈӨҪӨҰ№НӨЁӨлӨИЎўӨҪӨмӨҫӨмӨОГПӨЛӨҪӨмӨҫӨмӨОКхӨ¬ӨўӨлӨИёАӨГӨЖӨвӨӨӨӨӨИ»ЧӨӨӨЮӨ№ЎЈ
Ж«»іӨөӨуӨПӨіӨОЎЦҘҝҘЦҘОҘӯЎЧӨИӨӨӨҰјщМЪӨОDNAӨтБҙ№сЕӘӨЛДҙәәЎЈЖұӨёҘҝҘЦҘОҘӯӨЗӨвЎўЕмЛМӨИЎўӨҪӨм°Кі°ӨЗӨПКМӨОҘ°ҘлЎјҘЧӨЛК¬Ө«ӨмӨлӨіӨИӨтЖНӨӯ»ЯӨбӨЖӨӨӨлӨуӨЗӨ№Ө¬ЎўӨіӨОДҙәә·лІМӨПЎўҝўјщӨдҝ№ӨЕӨҜӨкӨтӨ№ӨлҫеӨЗВзӨӯӨК°ХМЈӨ¬ӨўӨлӨуӨЗӨ№ЎЈ
ўЎМӨНиӨЛӨиӨкОЙӨӨҙД¶ӯӨт»ДӨ№
ҘҝҘЦҘОҘӯӨПӨіӨОӨиӨҰӨЛ№ӯӨӨИП°ПӨЛК¬ЙЫӨ№ӨлӨОӨЗЎўГП°иГП°иӨЛӨҪӨмӨҫӨм°гӨГӨҝҘҝҘЦҘОҘӯӨ¬ВёәЯӨ№ӨлӨОӨЗӨ№Ө¬ЎўБҙВОӨИӨ·ӨЖАҫЎҰҙШЕмЎҰЕмЛМӨОЈіӨДӨОҘ°ҘлЎјҘЧӨЛК¬Ө«ӨмӨлӨіӨИӨ¬ӨпӨ«ӨкӨЮӨ·ӨҝЎЈ
ҝўјщӨОәЭӨЛӨПЎўОгӨЁӨРЙДМЪӨ¬ВӯӨкӨКӨӨӨИӨ«Ўў·РәСЕӘӨКМдВкӨЗӨдӨаӨтЖАӨә°гӨҰГП°иӨ«Өй°ЬҝўӨөӨмӨлӨіӨИӨ¬ӨўӨкӨЮӨ№ЎЈӨӨӨЮӨПӨіӨОҘЗЎјҘҝӨ¬ӨўӨлӨОӨЗЎЦӨҪӨмӨП°гӨҰГП°иӨОӨвӨОӨЗӨ№ӨиЎЧӨИёАӨҰӨіӨИӨ¬ӨЗӨӯӨлӨ¬ЎўӨіӨОҘЗЎјҘҝӨ¬МөӨұӨмӨРЎўЖұӨёҘҝҘЦҘОҘӯӨАӨ«ӨйӨӨӨӨӨЗӨ·ӨзӨИҝўӨЁӨйӨмӨЖӨ·ӨЮӨҰЎЈ°дЕБЕӘӨЛ°гӨҰӨіӨИӨ¬ӨКӨј°ӯӨӨӨОӨ«ӨтАвМАӨ№ӨлӨҝӨбӨЛјВәЭӨЛҝўӨЁӨЖИжіУӨтӨ·ӨЖӨЯӨҝЎЈАйЗҜҙхЛҫӨОөЦӨЗЎўЖұӨёҝфӨАӨұЖұӨёҫмҪкӨЛЕэ·ЧЕӘӨЛИжіУӨЗӨӯӨлӨиӨҰӨЛҘҝҘЦҘОҘӯӨтҝўӨЁӨЮӨ·ӨҝЎЈ°мЕЯұЫӨЁӨҝӨўӨИЎў°ҰГОё©»әЎҰ°сҫлё©»әӨОЙДМЪӨПёПӨмӨЖӨӨӨЮӨ·ӨҝЎЈ°мКэӨЗЎўБҙӨҜЖұӨёҫт·пӨЗӨвЎўөЬҫлё©»әӨОӨвӨОӨПёөөӨӨЛ°йӨГӨЖӨӨӨлӨвӨОӨ¬ӨўӨлЎЈЖо»°ОҰӨЗӨвИжіУӨ·ӨҝӨОӨЗӨ№Ө¬ЎўөЬҫлё©ӨОӨвӨОӨПӨдӨПӨкА®Д№Ө¬ОЙӨӨЎЈјщ№вӨ¬ӨпӨәӨ«ЈұЗҜӨЗВҫӨОГП°иӨОӨвӨОӨИӨҜӨйӨЩӨЖЎўЈұЈ°Ҙ»ҘуҘБӨҜӨйӨӨә№Ө¬ҪРӨБӨгӨҰЎЈА®Д№ӨАӨұӨЗӨКӨҜЎўЕЯӨтұЫӨЁӨҝ»юӨЛ°мИЦАиГјӨОІкЎЦДәІкЎЧӨ¬ӨҝӨҜӨөӨуёПӨмӨЖӨ·ӨЮӨҰӨИӨӨӨҰӨіӨИӨвӨпӨ«ӨкӨЮӨ·ӨҝЎЈөЬҫлё©»әӨЗӨвЈөЈ°ЎуӨҜӨйӨӨёПӨмӨЖӨ·ӨЮӨҰӨОӨЗӨ№Ө¬Ўў°ҰГОё©»әӨПӨпӨәӨ«ЈұЈөЎуӨ·Ө«АёӨӯ»ДӨкӨЮӨ»ӨуӨЗӨ·ӨҝЎЈөЬҫлё©»әӨПЕЯӨОҙЁӨӨҫх¶·ӨЛВРұюӨЗӨӯӨЖӨӨӨлӨ«ӨйӨіӨҰӨКӨлӨОӨЗӨ№Ө¬ЎўӨіӨмӨ¬ӨпӨ«ӨГӨЖӨӨӨҝӨйВҫӨОГП°иӨОМЪӨтҝўјщӨПӨ·ӨКӨӨӨЗӨ№ӨиӨНЎЈ
ӨЮӨәГП°иӨЛӨПЖИј«ӨО°дЕБЕӘӨК·ПЕэӨ¬ӨўӨлӨИӨӨӨҰӨіӨИӨтіРӨЁӨЖӨӘӨӨӨЖӨҜӨАӨөӨӨЎЈГП°иҙД¶ӯӨЛЕ¬ұюӨ·ӨҝёДВОӨЛӨиӨГӨЖЎўҫӯНиӨЛіОјВӨКіӨҙЯОУӨтА®О©Ө¬ҙьВФӨЗӨӯӨлӨ·Ўўҝ№ӨО·ГӨЯӨтөэјхӨ№ӨлӨіӨИӨ¬ӨЗӨӯӨлӨпӨұӨЗӨ№ЎЈӨДӨЮӨкГП°иАӯјпЙДЎҰГП°иӨОЙДМЪӨПОт»ЛӨИӨӨӨҰКЭёұӨ¬НшӨӨӨЖӨӨӨлӨИӨӨӨҰӨіӨИӨКӨуӨЗӨ№ЎЈ
ВҫГП°и»әӨОјпЙДӨЗӨўӨГӨЖӨвМдВкӨКӨҜА®Д№Ө№ӨлӨіӨИӨПӨвӨБӨнӨуӨўӨкӨЮӨ№ЎЈі°НијпӨЗӨвӨиӨҜА®Д№Ө·ИЛұЙӨ·ӨЖӨӨӨлӨвӨОӨвӨўӨкӨЮӨ№ЎЈӨЗӨвӨҪӨмӨП°дЕБ»ТЩшНрӨтөҜӨіӨ·ӨЖӨ·ӨЮӨҰӨОӨЗЎўА®Д№Ө·ӨиӨҰӨ¬Ө·ӨЮӨӨӨ¬ЎўВҫГП°и»әӨОӨвӨОӨт»эӨГӨЖӨҜӨлӨОӨПОЙӨӨ»цӨПӨўӨкӨЮӨ»ӨуЎЈМӨНиӨЛАХЗӨӨОМөӨӨ№Ф°ЩӨАӨИӨӨӨҰӨіӨИӨ¬ӨЗӨӯӨлӨИ»ЧӨӨӨЮӨ№ЎЈ
»дӨПёҰөжӨтӨ·ӨЖӨӨӨЖҝ§Ў№ІҝӨтӨдӨмӨРӨӨӨӨӨОӨ«ӨИ»ЧӨҰӨіӨИӨ¬ӨўӨлӨ¬ЎўәЈӨПӨПӨГӨӯӨкӨИӨіӨҰӨ·ӨҝӨӨӨИӨӨӨҰөӨ»эӨБӨ¬ӨўӨкӨЮӨ№ЎЈЛНӨОӨЗӨӯӨлӨіӨИӨП°дЕБ»ТӨтДҙӨЩӨлӨіӨИӨКӨОӨЗЎўГП°иӨО°дЕБ»сё»ӨтјЎВеӨЛ»ДӨ·ЎўМӨНиӨЛӨиӨкОЙӨӨҙД¶ӯӨт»ДӨ№ӨҝӨбЎўҝ№ӨОЛЙД¬ДйӨЛӨв№ЧёҘӨЗӨӯӨмӨРӨИ»ЧӨГӨЖӨӨӨЮӨ№ЎЈ
Ж«»іІВөЧӨөӨуӨОӨӘПГӨ·ӨӨӨ«Ө¬ӨАӨГӨҝӨЗӨ·ӨзӨҰӨ«ЎЈҘЭҘГҘЙҘӯҘгҘ№ҘИӨЗӨвҫЬӨ·ӨҜӨҙҫТІрӨ·ӨЖӨӨӨЮӨ№ӨОӨЗЎўӨіӨБӨйӨвӨјӨТӨӘК№ӨӯӨҜӨАӨөӨӨЎӘ
ЎЪәЈҪөӨОИЦБИЖвӨЗӨОҘӘҘуҘЁҘў¶КЎЫ
ЎҰBrighter Than The Sun / Colbie Caillat
ЎҰHappy Tomorrow / Nina