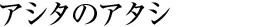 |  |
第2話
しばらくして、
あたしは、豆大福の粉で汚れた手と涙で濡れた子機とを持った自分が、
なんだか、酷く滑稽で笑えてきた。
だから声に出して再確認。
「明日、あたしは死ぬんやで」
そうして、あたしはリビングから自室に移動。
これから少し出掛けよう。
悔いなど残したくないのだ。
だって明日、あたしは死ぬのだから。
髪を整える。
リキッドファンデを塗る。
アイシャドーは軽く。
マスカラは下睫毛だけ。
あたしは、一般的な女の子の仮面を作り上げて、手鏡に映す。
化学物質に包まれた、あたしの顔。
ただ、真っ直ぐ見つめてみる。
なにか。
どこか。
間違ってしまった様な疑問の雲を胸に宿して、あたしは、鏡の中の彼女を見据える。
小さく動き、呼吸しているのが解る。
今、あたしは生きているんだな。
そんなことを想う。
鏡の中の彼女が言う。
「いま、あたし生きてるわ」と。
それは、すごく大切なこと。
なぜなら、あたしが母にあげられる唯一のものだから。
鏡の中の彼女が言う。
「だめよ。顔を歪めては。化粧が落ちるから」
あたしは、お気に入りのワンピを着て外に繰り出す。
気持ち悪い青空に、白い月が浮かんでる。
なんやねん。
神様、励まそうとしてんのか、喧嘩売ってんのか、どっちやねん。
まぁ、ええわ。
うん、もぉええて。
あたしは、時間を有効につかおと思う。
だって、あと1日もないんやで?
嗚呼、ほんま訳解らんわ。
せやけど、悩んでも仕方ないしな。
それに、あたしの命なんぞ、どないなってもええような代物や。
うむ。
人間ポジティブに生きなあかん。
おっしゃ、やったるでー。
そないなことを思う、あたしの足は自然とあの橋へと向かう。
ビーサンを履いとる、あたしの素足。
やけに力強くて、思わずわろてしまう。
こんな状況下でも、わろてる自分て、やっぱ吹っ飛んでんねんな。
とつくづく思うて、ある意味感心する。
そーして程なく商店街に差し掛かって、焼き鳥の匂いが鼻を掠める。
しかし生憎、肉は好きちゃう。
どっちかゆーたら嫌いや。
あんな油っぽくてグロいもんよくもまぁ食うわと、思うわけで。
あたしは、ちょっとひーてまう。
もちろん、そないなことゆーとる、変人なあたしのほーがひかれてまうけど。
こんな、肉大好き人間の心情すら察することのできひんあたしなんかには、
もっと複雑な、母が死ぬという理由や心境なんて全く想像もつかへんよ。
そして、ちょっとばかし憂鬱になって、結局あたしが理解し把握できんのなんて、
自分のたった今の感情くらいやんなと思う。
そんなん、今あたしが出した舌打ちの音くらいちっぽけなもんやん、なんて
軽く肩を落とす。
いや、ほんまに。
今のあたしは、何でもそっちの方向に結びつけてまう。
せやなぁ、状況が状況やからしゃぁないな。
橋に着く。
ここは、あたしの「始まりの場所」
母と父が出会い、別れた地。
あたしが唯一持ってる父の写っている写真もここ。
母の言う「あんたは、橋の下から拾ってきたのよ」って言う冗談の橋もここ。
母とあたしと、それから父と。
唯一、家族だった場所なんだ、ここは。
そして、あたしは記憶の片隅に残る、あの写真を思い出す。
中指を立てて笑う父の顔。
ちょうど、この橋の下の川原のあたり。
小さく向こう側にビルが見える。
もっとも今のように高くはなかったけど。
1年程前に見た、その写真は日に当たったのか、セピア色になっていたけど、
妙に鮮明に記憶に残っていた。
あたしは、小さな階段を下って、かつて父が立っていた場所に立ってみる。
川の水面がチラチラと白く輝いていて眩しい。
ほんのりとオレンジに染まった夕空が、なんだか懐かしい。
あたしは思った。
「死ぬならここで」なんて。
始まった場所で終わりたいなぁ、みたいな。
なぁんて、今のあたしは死ぬことにえらい前向きで、死に場所なんかも探しちゃってる。
そうして、あたしは中指を立てる。
父に母にあたしに、そして世界に。
「森田―!」
川原に響く、聞き覚えのある声。
担任佐藤や。
ジャージ姿で階段を駆け下りてくる佐藤は、体育教師そのもの。
つーか、なんでこんなとこにおんねん?
あたしは、ちょっとイラついて軽く舌打ちをした。
「森田、どーしたぁ?」
佐藤は未だに森田と勘違い。
なんやねんな。
てめーこそ、がっこは?部活はどーしたん?
「せんせこそ、なんでここにいんの?」
「そりゃお前、訳解んねぇこというからだろーがぁ」
あぁ、しまった。
こいつ何も解ってへんくせに、めっちゃお節介な奴やったんや。
あたしは、自分の発言に後悔の念を覚える。
せやけど、家までこーへんかったことに安堵する。
「死ぬっつったことですか?」
「学校は休みがちだし、意味不明なこというしー、何だ今死のうとしてたんかぁ?」
「下見です。あたし明日死ぬんです」
「俺の所為か?」
そうやって、噛み合わへん不毛な会話をあたしらは続ける。
「お前何したい?どうしたい?何なの?」
佐藤は、人の話なんか全く聞かないで、切羽詰ったように疑問符を並べた。
でも残念なことに、あたしがそれ聞きたいわ。
「まぁ、あたしが解ってんのは、明日死ぬことと、森田じゃないことですね」
「は?」
この惚け面が、癪に障んねんな。
「だからー・・・・・・」
「いい、いい。もういいわぁ」
佐藤、手を振り回して、あたしを制止させる。
「明日、文化祭だろ、来い。死ぬのはその後でいいだろぉが」
佐藤、な?と肩に手を置く。
暑い、暑苦しいねん。
しかも、やっぱりなんも解ってへんし。
「まっ、元気そうだしな。来いよ、明日ぁ」
そう言う背中は、階段を登って去って行く。
「うぜぇーよ!いかねーわ!ばぁーか!」
あたしは中指を突き立てた。
すんげぇ腹立つねん、あいつ。
でも、カッコつけて片手を挙げるあいつの手は、おっきかった。
つーか、あたし何でこないにムキになってん?
あいつくらい、アホらしなぁ。
うぜぇよ、ばーか、いかれへんわ。
明日、あたしは「お肉」やねん。
少し呼吸を整え、コンクリの階段に腰を下ろす。
いつの間にか空は暗さの混じった夕空へと変わっていた。
今日は綺麗な夜空で星が見えるかもしれない。
あたしは、夜空の輝きを思う。
けど、夕焼けの侘しさを胸に感じる。
レベッカの「フレンズ」。
あたしには、その歌をうたえる友達なんかいないけど、
今、こんときの夕暮れは、レベッカの「フレンズ」を連想させた。
特に2番なんかは、あたしの憧れでもあった。
もう隣に居ない君を想って唄う。
悲しい場面だけど、羨ましい。
あたしには「君」なんて最初からいなかったから。
あたしは、静かに口ずさむ。
随分前の歌なのに、どこか新鮮で、「歌ってすごいわ」と思った。
でも、あたしはもう歌えない。
命と一緒に失くしてしまうから。
あーあ、あたし16年間何やってたんだろ?
もったいないなぁ。
日常を怠惰と惰性と平穏で終えてしまうっちゅーわけか。
なんか、結局のところ元から「生きて」なんかいなかった気さえする。
なんつって。
あたしは、哀愁と悲しみの少女に成り下がろうとしてる自分に気がついた。
やーめた。
もう余計な、どーしょもないことなんて意味ないねん。
はっきし言って無駄やねんな。
だー。
ここにおると、駄目やなぁ。
帰ろ。
砂払って、あたし静かに帰宅。
うち着いた頃には、大分暗くなって飲み屋の灯りもつき始めていた。
母のとこにも、そろそろお客さん入ってきたかな。
まだ早いか。
まぁ、ええわ。
腹減ったし、飯でも食お。
あ、つーか、冷蔵庫あんま入ってへんかったよな。
もやしとキャベツと大根さんは、あったわ。
でも、白っ。
彩り野菜さんがないやん。
にんじんでも、こーておけばよかった。
失敗したなぁ。
あたしは、日常を想う。
「非」日常の隣り合わせに。
あたしは、生を想う。
死の隣り合わせに。
それでも、あたしの隣には誰も居ない。
|
【第1話に戻る】 【第3話に続く】
| 第2話 |  |
 Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved.
Copyright (c) TOKYO FM Broadcasting Co., Ltd. All rights reserved. |