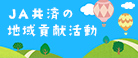第127回 高校生と自転車
2017/08/31
そろそろ始まる新学期。
自転車で通学する中学生 高校生は多いでしょう。
中学生も勿論ですが 特に高校生のみなさん
自転車に乗っている時の交通事故には気をつけましょう。
今週は公益財団法人 交通事故総合分析センター
研究部 主任研究員の山口朗 さんにお話を伺い
「高校生と自転車」を追跡しました。
去年2016年に交通事故で死傷した人は およそ 62万人 。
そのうち自転車に乗っていたのは およそ 9万人。
だいたい 7分の1 。
2016年の「乗用車 対 自転車の事故」による死傷者を年齢別に見てみると
被害者となった自転車の運転手には顕著な特徴があります。
15〜18歳が他の年齢に対して突出して多いのです。
16歳 ー 約3,500人
17歳 ー 約3,000人
15歳 ー 約2,500人
この年代は高校生にあたる年齢。
学齢別に見てみると、やはり高校1年〜3年生が
他の学齢に対して多くなっています。
さらに学齢別に分けた死傷者数を「登下校中」と「登下校中以外」で見ると
中学生と比較して増えた分は ほぼ「登下校中の事故」にあたります。
では 自転車がどこで乗用車との事故に遭遇しているのか? というと
これは自転車に乗った高校生に中学生も含めた2016年 データですが
76%が交差点で発生をしています。約3/4です。
交差点の規模で見てみると 比較的小さな交差点で多くの事故が発生していて
大きな交差点ほど 事故発生の割合は低くなっています。
さらに交差点の規模よって 発生する事故の形態にも大きな特徴があって
小さな交差点では自転車と乗用車の出合い頭の事故が多くを占めています。
交差点の規模が大きくなるにつれて出合い頭の事故が減り
乗用車が右左折中の事故の割合が増えています。
自転車と乗用車の交差点での事故の90%以上は
出合い頭か乗用車が右左折中です。
交差点以外の4分の1の場について。
歩道が3分の1 第一通行帯が3分の1 残りが3分の1。
歩道の場合はコンビニから乗用車が出てきて
歩道を走っていた自転車とぶつかる出合い頭の事故
車道から道路沿いの駐車場に入るため右左折をした時に歩道を走る自転車とぶつかる事故
などが歩道では発生をしています。
第一通行帯は複数車線なら一番左側の車線 往復2車線なら走行車線
自動車と自転車が同じ方向に走っている自転車を乗用車が追い越しや追い抜き
もしくはすれ違いの時に接触をするという事故。
非分離道路はセンターラインの無い道路。
乗用車と自転車が同じ方向に走るだけでなく対面走行するケースもあるので
出合い頭や右左折中・追い越し・追い抜き・正面衝突
ありとあらゆる事故が混在しています。
つまり 高校生の自転車通学は危険。
2年生・3年生も、もちろんですが
通学路の自転車運転に慣れない高校1年生
まだ、自転車で危険な目にあっていないので
スピードを出しすぎたり 友だちとふざけたりするのかもしれません。
充分 気をつけて下さい。
第126回 煽り運転の対処法
2017/08/24
円滑な交通を乱さない速度で走っているのに
後ろの車が車間を開けずピッタリとついてくる。
スピードを上げても追いかけてくる。
パッシングする クラクションを鳴らす 幅寄せする いわゆる「煽り運転」。
多くのドライバーが、遭遇したことがあるのではないでしょうか。
それに対して頭に血が上り こちらが事故を起こしてしまう、
あるいは巻き込まれてしまったらたまったものではありません。
煽り運転。
大きな事故も少なからず起こっています。
【平成22年 8月 静岡県 三島市】
後方の車が前のバイクを煽り
煽られたバイクはトラックに衝突
載っていた少年2人が死傷しました
【平成24年 9月 栃木県 矢板市】
後続車が前の車を煽り
前の車は交差点に出てしまい他の車と衝突
運転手が意識不明の重体になりました
「煽り運転」は法律違反。
東京麹町のみらい総合法律事務所の吉田太郎弁護士によると
煽り運転は「煽り運転をしてはいけない」という直接表現した規定はありません。
しかし 道路交通法の26条で車間距離を保持しなさいと定められています。
車両等は同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行する時は
その直前の車両等が急に停止した時においても
これに追突するのを避けることが出来るよう
必要な距離を保たなければいけません。
煽り運転は前の車と後ろの車の距離が詰まる事。
これは適切な距離とは言えません。
道路交通法26条の禁止事項に当てはまります。
8年前の2009年。
「煽り運転」の取り締まりを強化するため
車間距離を保持しないことに対する罰則は強化されました。
高速道路の死亡事故のうち衝突事故の割合が非常に多かったためです。
【2007年】
高速道路での死亡事故245件
そのうち車間距離の不保持・衝突事故による死亡事故 56件
およそ23%
【2008年】
高速道路での死亡事故196件
そのうち車間距離の不保持・衝突事故による死亡事故 45件
およそ23%
車間距離の不保持・衝突事故による死亡事故がすべて
ピッタリと車の鼻先をつけて煽ったり
スピードを上げて追い回したりということではないでしょうが
単純に必要な車間距離を保たなければ危険が増すとわかります。
吉田太郎弁護士によると
罰則が強化されて法律上 車間距離不保持はどうなったかというと
一般道路で車間距離を適切に保持しない場合は5万円以下の罰金。
高速道路では5万円以下の罰金。あるいは3か月以上の懲役です。
死亡事件や傷害事件などに至らなくても懲役という事もありうるという事になりました。
また 煽り運転が危険運転致死傷罪における危険運転とに判断された場合には
人をケガさせた場合は15年以下の懲役になる可能性があります。
仮に人を死亡させた場合には1年以上20年以下の有期懲役に処せられます。
罰則が強化されたといっても
かまわずに煽り運転をしてくるドライバーはいるでしょう。
そうされた場合 どう対応するのかも大切なことです。
意地を張って邪魔をしようという気持ちを持つのはやめましょう。
環境が許すなら道を譲って先に行かせること。
ただ狭い山道など なかなか後ろの車をやり過ごせない場合は
後ろの車は気にせず自分の運転に集中するようにしましょう。
走っている中で先に行かせるスペースが見つけられたら
停止したり スペースに車を寄せたりして 先に進ませます。
自分が事故の当事者にならないという事を心がける事が大切です。
煽り運転に遭遇した時は
事故を起こしたり、巻き込まれてしまわないよう冷静に対処しましょう。
そして 当たり前ですが決して「煽り運転」をしないことを肝に銘じて下さい。
第125回 君は’宮古島まもる君’を知っているか!?
2017/08/17
この夏休み。
みなさん帰省や旅行で日本の各地に出かけていることでしょう。
交通事故が1つでも減ることは全国に共通する思い。
地域それぞれに工夫を凝らして交通安全への取り組みを行っています。
中には功を奏して交通事故減少に繋がるばかりか地域活性化に一役買っている例もあります。
それは沖縄県の本島から南西におよそ290キロの宮古島。
取り組みは警察官型の人形「宮古島まもる君」の設置。

どうですか?
なかなかシュールでしょう(笑)
宮古島地区交通安全協会 砂川米子さんによると
まもる君の設置が始まった平成3年当時
宮古島では交通事故が多発していて死亡事故は2ケタ台。
これまで設置してきたありきたりの立て看板ではない
もっと交通安全の意識の啓発が期待出来るものは何かないか?
みんなで頭を凝らして考えて行き当たったのが警察官人形。
「宮古島まもる君」が誕生したのです。
現在、宮古島まもる君の人形は19体
女子の宮古島まるこちゃん1体が設置されています。

2人は仲良し ♡
なかなかいい雰囲気ですよね?
さらに今年2017年は宮古島地区交通安全協会 創立60周年。
3月に開かれた記念イベントではまもる君の石像がお披露目されました。

石像のまもる君は明るい雰囲気。
人形の時とはずいぶんと雰囲気が違いますね。
宮古島まもる君が設置されて四半世紀で島の状況は変わりました。
最近ではお菓子・ストラップ・ネックレスなど
まもる君お土産品がたくさん売られているのです。
そう まもる君はインターネット時代
観光にやってくる人たちの間で有名になり
島の地域活性化に繋がっているのです。
「交通安全の守り神という位置づけだったまもる君ですけど
今では宮古島の守り神みたいになっています」と
宮古島地区交通安全協会 砂川米子さん
まもるくんとまるこちゃんが設置されている
宮古島警察署の正面玄関にも観光客が訪ねて来るとか。
さすがInstagram時代。
「警察署が観光名所になっているところは他に無いんじゃない?」
砂川さんたちは そんな話をしているそうです。
そして 肝心の交通事故件数。
なんと 宮古島は今年の3月で交通事故死者ゼロ1年を達成。
8.17日現在 まだ継続しているそうです。