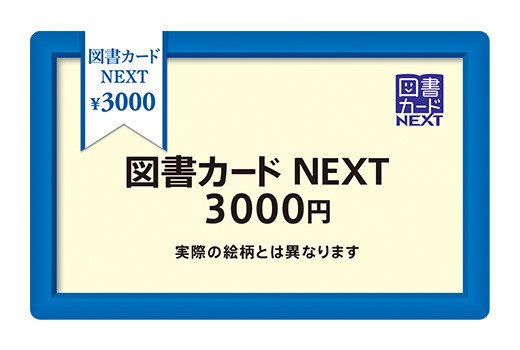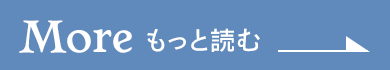2026.01.20
睡眠の悩みを解決する手助けを
ONE MORNING「 The Starters 」
火曜日のこの時間は社会に風穴を開けようと取り組む若き起業家をお迎えして
そのアイデアの根っこにあるものや未来へ向けたビジョンを伺います。
今週と来週のゲストは、株式会社太陽 代表取締役社長兼CEOの川嶋 伶さんです。
川嶋伶さんは大学院在学中の2019年に、株式会社太陽を設立。一人でも多くの人たちの日常を素敵なモノにしたい…という思いから、太陽で様々な製品の企画・販売を実施。そこから生まれた「ヒツジのいらない枕」は、累計販売数100万個を超える大ヒット製品です。
今週は主な事業内容をうかがいます。まず始めに、「太陽」という会社名について、スケールが大きいですよね!この社名の由来は何でしょうか?
「名前の通り、我々が「なくてはならない存在になりたい」という思いでこの会社名をつけました。」
今何名ぐらいの方が勤めてらっしゃるんですか?
「業務委託の方などをすべて含めると約50名ほどです。」
太陽には「ヒツジのいらない枕」というヒット商品がありますけれども、主にどんな製品を扱っているんですか?
「主に、人間のエネルギーの源になる「睡眠」を軸にブランドを展開しております。睡眠は生活の基盤になるものなので、心地よく快適な眠りにつけるような商品などを展開しております。」
では、枕以外にもいろいろな寝具を出しているんですね。
「そうですね。掛け布団やマットレスも展開しています。」
太陽って朝や起きる!みたいな印象がありますが、扱っているものは睡眠で真逆のイメージのものを会社名にするというのもインパクトがあっていいですよね。
例えばどんな製品があるのかぜひ教えてください。まず、「ヒツジのいらない枕」からお願いします。
「我々は、羊を数えなくても寝られるまくらというのを展開しています。TPE素材という独自の素材と三角格子構造を特徴としたまくらを展開しております。」
今その「ヒツジのいらない枕」が目の前にあるんですが、メッシュ構造になっていて、しかも立体的でプルンプルンしていますね。
枕って低い方がいいのかなと思っていたんですが意外と高さがあるんですよ。実際に頭を乗せると自分に合った高さになるということなんですね。
先ほどお話にあったTPE素材というのはどういった素材なんでしょうか?
「TPEは、Thermoplastic Elastomer(サーモプラスチックエラストマー)の略で、日本語でいうと熱可塑性エラストマーと言います。ゴムの弾力性とプラスチックの強靭性を兼ね備えているような素材で、 実際に医療機関であったり、キッチンで使われるゴムヘラに使われていたりと、意外と皆様の日常にも存在しているような素材になります。」
川嶋さんは実際にこの枕を使われているんですか?
「もちろん使っています。やっぱりめちゃくちゃ良いですね。」
三角格子構造っていうのがポイントなんですね。
「この構造が大きなポイントで、我々が考える構造の中で一番圧力を分散してくれる構造になっているんですね。そのため、無理のない寝返りが打てたり、実際に頭に嫌な違和感なく眠れるような枕になっています。」
実際に寝てみたんですが、柔らかくて包み込まれているような感じでした。程よい厚みのおかげで柔らかすぎず、反発しすぎずで頭にフィットして支えてくれました。これはすぐに寝ちゃいそうですね。
開発する上でこだわった部分っていうのはどういったところでしょうか?
「特にこだわったのは、「とにかく気持ちよく眠れる」という部分です。先程、ユージさんがおっしゃっていただいたように、枕に頭を預けるだけで眠れるっていうところはすごく大切にしております。」
結構耐久性もあるんですか?
「そうですね!TPE という素材の特性上、素材を伸ばしても形状記憶性に非常に優れているので、10年間の寝返りを想定した実験を行っているんですが、10年間使っても全く枕がへたらないくらいの耐久性を持っています。」
それはすごいですね!衛生面についてはどうでしょうか?
「これ実は丸洗いが可能なんです。洗濯機には入れないでほしいんですが、手洗いでシャワーをそのままかけてジャブジャブ洗うことができるんです。」
メッシュ構造になっているので乾くのも早そうですよね。
「そうです。全く水分を吸収しないので、ざっと洗った後は、はたいていただいて水気をタオルなどで取っていただくだけで簡単に乾きます。また完全な通気構造になっているので、乾きやすいだけでなく頭が蒸れる心配もないんです。」
さらに枕カバーも販売されているんですよね?
「そうです!我々もテンセルという素材を使った、「ヒツジのいらない枕」の特徴をさらに生かす気持ちよさを体験できるようなカバーを付属して販売しております。」
ぜひ使ってみたいですね!他にも気になるのがマットレスや毛布などもあるんですよね?
「そうですね。マットレスに関しては、この「ヒツジのいらない枕」と同じ素材を全面に使ったマットレスがあります。」
それはちょっと寝転がってみたいですね!毛布はどんな感じなんでしょうか?
「毛布は新商品なんですが、それもすごく肌触りがいい毛布になっていて、保温性もあります。冬で使えるものの通常の布団の他にも、夏用のお肌触りが非常に冷たく感じる掛け布団も販売しています。」
ここまで聞いている中で、寝具にまつわること全部やっているんですね!
枕の試作品を作っている時には、いろいろ試行錯誤はあったと思うんですが、実際にそれを持ち帰って家で寝て試したりしたんですか?
「そうですね。 一人一人自宅で使ってみて、我々もいわばお客さんなので、その意見も生かしながら、「世の中のお客様の悩みを解決できるポイントってどこなのかな」というところを洗いざらいやりました。」
ビジネス面について、いい商品ができましたといっても、売り出す上で工夫も必要だったは思うのですが、その辺りで苦労したことはありますか?
「我々が商品を打ち出す時に、どうしてもメーカー目線になってしまうことって多いと思うんです。「こういう機能があります、こういう機能があります」というふうに。しかし、お客様が求めている部分は、「悩みを解決したい」っていうところだと思うので、やはりそこを我々の力でどう伝えきるかっていうところはすごく悩んだというか、すごく大事にしている部分ではありますね。」
そうですよね。ビジネスをするにあたって、この枕に限らず、全ての商品でいい商品というのは、努力の末に生み出すことはできるんですが、それを人々に届けるまでの流通に乗せるまでが難しい部分なんですよね。
寝具の商品をたくさん紹介していただきましたが、川嶋さんご自身は睡眠に悩まれていたんですか?
「そうですね。 私自身も眠れる時と眠れない時の差が激しかったです。私はそういう悩みだったんですが、睡眠自体は色んな悩みが多分あるんですよね。そういった中で睡眠の中でいろいろな悩みを解決できるお助けができればいいかなというところで起業したというのがありますね。」
睡眠ってあらゆるパフォーマンスに影響しますし、かといってみんな頭の形も違えば、寝相も違うわけで、みんなに合う枕を作るって相当難しかったと思います。これは一回ちょっと試してみてほしいですね。
ということで、今週はそろそろお時間となりました。最後に、これまで乗り越えてきたハードルを教えてください。
「経営者にとっては売上や利益はもちろんなところではあるんですけれども、やっぱり正解がない中での意思決定みたいなところは常にハードルとしてあるのかなというふうには思っております。 日々のプレッシャーもしかりですけれども、日々お客様の声にどれだけ応えられるかというところは非常に大事にしてきましたし、これからも応えられ続けるように頑張りたいなというふうに思っております。」


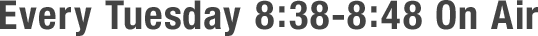




 20代~30代の若手起業家をゲストに迎え、
20代~30代の若手起業家をゲストに迎え、