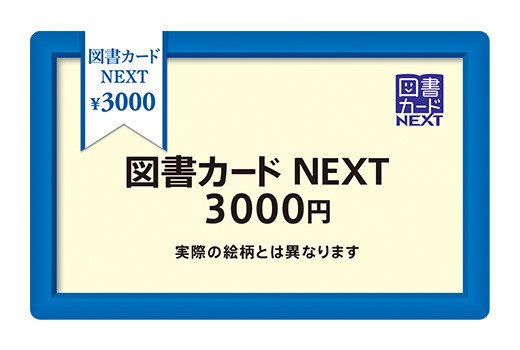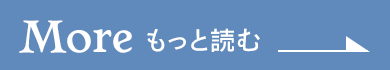2025.03.04
サステナビリティ活動で、企業も、社会も持続可能に
- ICHI COMMONS株式会社
CEO - 伏見 崇宏さん
社会課題解決の仲間と出会える共助共創プラットフォーム「サステナNET」、サステナ活動のさまざまなお悩みをワンストップで解決「サステナ推進」を展開
ONE MORNING「 The Starters 」
火曜日のこの時間は社会に風穴を開けようと取り組む若き起業家をお迎えして
そのアイデアの根っこにあるものや未来へ向けたビジョンを伺います。
今週と来週のゲストは、ICHI COMMONS株式会社 代表取締役の伏見 崇宏さんです。
シンガポール生まれ、アメリカ育ちの伏見 崇宏さんは学生時代に教育系NPOに携わり、2014年にGEに入社、その後投資分野の事業に携わり、2020年にICHI COMMONSを創業されています。
今週は主な事業内容について伺っていきます。ICHI COMMONSはどういうサービスを展開してるんでしょうか?
「ICHI COMMONSは大きく分けて二つのサービスを展開しています。一つはプラットフォーム事業で、サステナNETというプラットフォームを運営しています。もう一つはですね、どちらかというと社会課題解決に取り組む企業であったりだとか、そういう組織の取り組みの可視化であったり、サステナ推進の領域で取り組みをやってますね。」
それぞれ具体的にどんなサービスなのかも教えていただきたいんですが、まずはサステナNETについてお願いします。
「サステナNETはですね、主なユーザーさんたちは企業とNPOなんですけれども、何をやってるかっていうと、社会課題を実は54個公開してるんですね。で教育的な要素として、そもそもどんな社会課題があるのかというのを、子供の貧困であったりとか地域の過疎化であったりとか、そういう54個の社会課題について学べるページを全部作っていて、そこに紐づいて日本中のNPOさんとか企業さんが紐付けて登録・投稿できる仕組みにしています。なので、日本中のNPOさんが、誰が・どこでどんな社会課題解決に取り組んでるのかというのを可視化するプラットフォームですね。なので課題軸で、例えば従業員投票型の寄付みたいなサービスもプラットフォーム上でやっていて、例えば企業さんが子供の貧困で活動してるNPOさんに寄付がしたいですとなったときにもうNPOが500団体ぐらい登録してくださっていて、プラットフォームにインタビュー動画を載せてるんですね。そうすると従業員皆さんが課題について学んで、その課題に取り組んでいるNPOさんたちの動画を見てどこを応援したいのかというのを選べると。」
例えば、企業としてこんな社会課題に取り組みたいんだ、でもどこにどうやってコンタクトを取って、どうアクセスしていいかわかんないというところのこの課題をここは解決してくれるわけですね。
「そうです。なので寄付だけじゃなくて、それこそNPOと連携して事業がやりたいであったりだとか、我々すごい大事にしてるのが、セクターを超えた連携っていうのを民間・自治体・NPO、そういう方々が課題軸とか地域軸でちゃんと連携できるようなマッチングのプラットフォームですね。」
チャレンジマーケットというのは何ですか?
「チャレンジマーケットというのは、例えばNPOさんが連携したい企業を探してますということを募集できたりだとか、あとは企業さんも寄付だけじゃなくて寄付もお金の寄付だけじゃなくて物の寄付とかもあったりするんですけれども、余ってる在庫であったりというものを、寄付先のNPOを探してますというところを募集できるようになってます。なのでそういう募集をかけていただくとうちのプラットフォームに登録してくださってるNPOの皆さんにご案内が行って、そこで審査をして我々が企業さんと繋ぐというようなことをやっています。」
実際にサステナNETで実現した例があれば、いくつか教えてください。
「一つはそのわくわく寄付コンペというのを結構企業さんたちが従業員のエンゲージメントのために使ってくださっていて、結局社長がその社会課題について考えているだけじゃなくて、従業員がちゃんと学んで、NPOに対して寄付をするというプロセスをやりたいというところで、三木プーリさんというそれこそ85年ぐらいの中小企業さんなんですけれども、全国に300人ぐらい従業員がいるところが、工場がずっと山形県の米沢にあって、本社は神奈川県にあるんですけど、山形県の米沢って10万人の都市だったのが今5万人ぐらいに減っていて、その地域でのNPOを探して寄付したいんだけどどうやってアクセスすればいいかわからない。で我々のプラットフォームに乗っていただいて、その地域に特化して、お世話になっている地域に寄付をしたいというので、神奈川の従業員が米沢の課題を学んで、NPOさんたちの動画を見て、で寄付をするというようなプログラムやっていたりだとか、企業の中でのグループ間の連携というところにも使っていただいたりだとか。あとは企業側から他例えばプログラムをやりたいと、例えば東京のICT関係の人材派遣の会社・エンジニアの派遣とかをやってる会社さんが、これから日本で人口が減っていって、それで子供たちにもっとICTを学ぶ機会を提供したい。東京でやったらただのプログラミングスクールじゃないですか。そうじゃなくて我々がマッチングしたのは広島県のめっちゃ過疎地域で自然体験とかを子供たちに提供してるNPOさんと連携したらどうでしょう、というので、広島の本当にもう過疎がめちゃめちゃ進んでる地域で、子供たちが自然体験をしながらそこでプログラミングを学ぶというような、そういう機会を。企業としてもグループ会社がそこにあるので地域貢献にもなるし、次の人材育成にもなると。」
続いてサステナ推進、これはどんなサービスでしょうか?
「結局プラットフォームでそういうマッチングであったりというところは、まだまだあんまりない事業領域なので、ここは自分たちでどんどんどんどんリッチデータを集めて作っていってるんですけれども、サステナ推進はどちらかというとコンサル寄りであったり、可視化にフォーカスをしています。なので例えば企業としても、そもそも課題を選ぶ前に自分たちの事業がどんな社会課題解決をしているのか、これ社会貢献ではなくて、ビジネスとしてどんな社会課題解決をしてるのかというところを特定したい企業さんたちに対して、事業サイドの人たちのインタビューをして、でそもそもビジネスがどんな社会課題に関連していて、ビジネスとしての社会関連指標が何なのかというところを、我々の方で半分コンサルティングで準備させていただくようなサービスであったりだとか、あとはいわゆるインパクトレポートって最近よくどんな社会課題解決ができてるのかということをちゃんと世の中に知ってもらう、そういうレポーティングが必要になってきているんですけれども、そういうところを我々サービスとして、レポーティングのサービスを提供したりしてますね。」
こういったサービス提供することでイチ コモンズさんはどうやって利益を上げてるんですか?
「サステナNETのプラットフォームではまだ全然利益は出ていないんですけれども、やっぱりいろんな企業さんたちが自分たちの事業が、先ほどお伝えしたサステナサマリーの文脈で、事業がどんな社会課題解決をしてるのかというところの特定というところに大きな課題を感じている方が多いので、ここのサービスでどちらかというと利益を生み出しているというような状況ですね。」
やはりこういった活動で日本と海外との違いというのはまだ差は大きいですか?
「大きいですね。社会貢献であったりCSRの文脈だと、アメリカはどちらかというともう寄付文化がある程度醸成されているのと、そもそもの土台が結構違うんですよね。アメリカが何で寄付文化があるかっていうと、税優遇の仕組みがすごいしっかりしていて、寄付をすると税額控除される、要はそんなに損をしないというか、全額お金が出ていかないという、そういう対象の組織が100万組織ぐらいあるんですよ。日本はNPOだけで見ると実は1500団体ぐらいしかないんですよね。なので精神は日本もアメリカも両方あるんですけれども、まだまだインフラが整っていないなというところです。実際日本も市場があるんですよね。企業の寄付、個人の寄付両方合わせると年間1兆円超えるんですよ。これ実は誰がどこにどんな思いで寄付をしてるかとか、なんで企業はそういう取り組みをしているのかというところが全く可視化されていないので、そこってめちゃめちゃもったいないよねと。アメリカの方が寄付文化があって日本にはないってよく言われるんですけどそんなことないと僕は思っていて、実は日本は江戸時代から例えば三方よしであったりだとか、社会とどう共生していくかっていうところが大前提としてあるのにもかかわらず、資本主義的にどう評価されるかというところだけにやっぱり引っ張られてしまっているところがあるなと思っていて、元々あるそういう日本の良さっていうところを僕はすごい引っ張り出していきたいなって思っていますね。」
SDGsはこれからどういう取り組みが求められるんでしょうか?
「SDGs自体は共通言語としてすごくいいと思うんですよね。日本も教育がすごく進んで、そもそも誰1人取り残さないという世界全体の共通言語という形で17個の項目が生まれてってあるんですけれども、でも必ずしもSDGsって別に全部が全部日本が該当しない部分もあるわけですよね。なので私がこれから重要になってくるなと思うのは、各企業・各団体・各個人いろんな価値観があると思うんですけれども、そこの先にある社会課題が何なのかということをしっかりとそれぞれがコミュニケートできるようになっていく必要があると。それぞれの価値が何なのかということ、そこって本当にビジネスをどういうふうに回していくかという観点もあれば、社会性の観点もあれば、様々な複合的なものがあるので、何が正しいというよりかは、なぜそれをやっているのかということをちゃんとみんながコミュニケーションできるようになるのが大事かなと思います。」
最後にこれまで乗り越えてきたハードルを教えてください。
「この領域ってあんまり市場原理がまだないんですよね。マーケットがないので、本当にこの領域でちゃんとエコシステムを作っていくために、本当に多くのお仲間を募らせていただいて、そういう方々と出会えてきたというところが一番大きな乗り越えてきたことかなと。で乗り越えていき、その方々と一緒に巻き込んでいきながら、社会課題の解決をみんなでやっていければなというふうに思っています。」
ICHI COMMONS株式会社の伏見 崇宏さんにお話を伺いました。ありがとうございました。


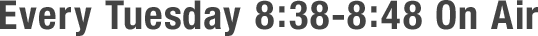




 20代~30代の若手起業家をゲストに迎え、
20代~30代の若手起業家をゲストに迎え、