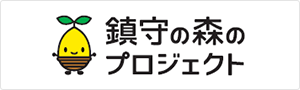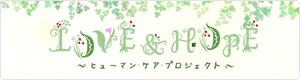¤µ¤Ć¤¤ç¤¦¤Ďˇ˘żą¤Î¤Ę¤«¤Ë¤¤¤ëŔ¸¤Ęޤż¤Á¤Ë¤ß¤é¤ě¤ëˇÖ¤˘¤ëĆĂħˇ×¤Ë¤Ä¤¤¤ĆÄ´şş¤ňÂł¤±¤Ć¤¤¤ëˇ˘¸¦µćĽÔ¤ÎĘý¤ň¤Şľ·¤¤·¤Ţ¤ąˇŁ
¤˝¤ÎĆĂħ¤Č¤Ď¤Ę¤Ë¤«¤Č¤¤¤¤¤Ţ¤ą¤Čˇ¦ˇ¦ˇ¦Î㤨¤ĐĄ«ĄżĄÄĄŕĄęˇŁĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤ÎłĚ¤ÎÉôʬ¤ňÁŰÁü¤·¤Ć¤ß¤Ć¤Ż¤Ŕ¤µ¤¤ˇŁ¤µ¤Ćˇ˘Ą«ĄżĄÄĄŕĄę¤ÎłĚ¤Ďˇ¦ˇ¦ˇ¦±¦´¬¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«ˇŁş¸´¬¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«ˇŁĽÂ¤Ď¤ł¤ěˇ˘¤Č¤Ă¤Ć¤â¶˝ĚŁżĽ¤¤ÍýÍł¤Çˇ˘¤É¤Á¤é¤«¤Ë´¬¤¤¤Ć¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤ąˇŞ
ĹěµţÂçłŘ¤ÎĆĂǤ˝ő¶µˇ˘şŮľµ®¤µ¤ó¤Ë¤ŞĎäň»Ç¤¤¤Ţ¤·¤żˇŁ

ˇˇ¸µˇąŔ¸¤ĘŞ¤Ď˛ż¤Ç¤âąĄ¤¤Çˇ˘Ćä˱¦ş¸¤Ç¶˝ĚŁ¤ň»ý¤Ă¤ż¤ď¤±¤Ç¤Ď¤Ę¤¤¤Î¤Ç¤ą¤¬ˇ˘ÂçłŘŔ¸¤Î»ţ¤Ë¤ż¤Ţ¤ż¤ŢĽő¤±¤żĽř¶Č¤ÎĂć¤Çˇ˘Ŕ¸¤Ęޤ˱¦ş¸¤¬¤˘¤ë¤ČˇŁ¤˝¤ě¤¬¤Č¤Ć¤âÂç»ö¤ĘĚňłä¤ň˛Ě¤ż¤·¤Ć¤¤¤ë¤Č¤¤¤¦¤ŞĎäňĘą¤¤¤ż¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁĄ˘ĄŐĄęĄ«¤ÎĄżĄóĄ¬ĄËˇĽĄ«¤Č¤¤¤¦¸Đ¤Ë˝»¤ó¤Ç¤¤¤ëµű¤Î¤Ę¤«¤Ë¤¦¤í¤ł¤Đ¤«¤ęż©¤Ů¤ëµű¤¬¤¤¤Ćˇ˘¤˝¤Î¤¦¤í¤ł¤ňż©¤Ů¤ëµű¤Ď¸ý¤¬¤Ň¤ó¶Ę¤¬¤Ă¤Ć¤¤¤Ćˇ˘¸ÄÂΤˤč¤Ă¤ĆÁęĽę¤Î±¦Â¦¤Đ¤«¤ę˝±¤¦¤â¤Î¤Čˇ˘ş¸Â¦¤Đ¤«¤ę˝±¤¦¤â¤Î¤Č¤¤¤¦2ĄżĄ¤Ą×¤¤¤ëˇŁ¤Çˇ˘¸ý¤¬±¦¤Ë¶Ę¤¬¤Ă¤Ć¤¤¤ë¤â¤Î¤Čˇ˘ş¸¤Ë¶Ę¤¬¤Ă¤Ć¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Čľˇą¤¤¤Ćˇ˘¤Á¤ç¤¦¤ÉČľˇą¤Ë¶ŃąŐ¤¬Ęݤż¤ě¤Ć¤¤¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤ňČŻ¸«¤µ¤ě¤ż¤Č¤¤¤¦Ď䬤ą¤´¤Ż°őľÝżĽ¤«¤Ă¤ż¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁ¤Çˇ˘Ľ«Ę¬¤â¤˝¤ó¤Ę¤«¤Ă¤ł¤¤¤¤¸¦µć¤ň¤·¤ż¤¤¤Ę¤Č»×¤Ă¤ĆĄĆˇĽĄŢ¤ňõ¤·¤Ć¤¤¤Ćˇ˘şŁ¤Î¸¦µć¤ËąÔ¤¤Ä¤¤Ţ¤·¤żˇŁ
ˇÁ¤¸¤ă¤˘Ć±¤¸Ŕ¸¤ĘŞ¤Ç¤âˇ˘´Ęñ¤ËĄ¤ĄáˇĽĄ¸¤ą¤ë¤Č±¦Íř¤¤Čş¸Íř¤¤¬¤¤¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ç¤ą¤ÍˇŁ
ˇˇ¤˝¤¦¤Ç¤ą¤ÍˇŁÍř¤Ľę¤Č¤¤¤¦¤Î¤ĎżÍ¤Ŕ¤±¤Ç¤Ď¤Ę¤Żˇ˘ĄÁĄóĄŃĄóĄ¸ˇĽ¤Ë¤â¤˘¤ę¤Ţ¤ą¤·ˇ˘Ę¸¸Ą¤ňÄ´¤Ů¤ë¤Čˇ˘ĄŇĄĄ¬Ą¨Ąë¤Ë¤â¤˘¤ë¤Č¤«ˇ˘Ä»¤¬¤Č¤Ţ¤ë¤Č¤¤Ë¤ň»Č¤¦Â¦¤¬¤É¤Ă¤Á¤Ŕ¤Č¤«ˇ˘¤¤¤í¤ó¤Ę¸¦µć¤¬¤˘¤ë¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁ
ˇÁ¤ą¤´¤ŻÉԻ׵Ĥʤó¤Ç¤ą¤±¤Éˇ˘¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ďˇ˘ş¸Íř¤¤ÎŔ¸¤Ęޤ¬»Ä¤ëÍýÍł¤Č¤¤¤¦¤Î¤¬¤˘¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ç¤ą¤č¤ÍˇŁ
ˇˇ¤˝¤¦¤Ç¤ą¤ÍˇŁĄŢĄ¤ĄÎĄęĄĆĄŁ¤Ë¤Ę¤ë¤Č¤Ę¤Ë¤«ĆŔ¤Ę¤ł¤Č¤¬¤˘¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤ňąÍ¤¨¤ë¤Čˇ˘ÎľĘý¤¬¤Ň¤Č¤Ä¤ÎĄ°ĄëˇĽĄ×¤Ë¤¤¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤ňŔâĚŔ¤·¤ä¤ą¤¤¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁŔč¤Ű¤É¤Î¤¦¤í¤ł¤ňż©¤Ů¤ëµű¤Îľěąç¤Ďˇ˘ş¸¤Ë¶Ę¤¬¤Ă¤Ć¤¤¤ë¤Ű¤¦¤Îµű¤¬ˇ˘ÁęĽę¤Ë·Ů˛ü¤µ¤ě¤Ćż©¤Ů¤ë¤Î¤¬Ćń¤·¤Ż¤Ę¤Ă¤Ć¤Ż¤ë¤Č±¦¤¬Áý¤¨¤Ć¤¤¤Ż¤ČˇŁ¤Çˇ˘Áý¤¨¤ą¤®¤ë¤Č¤Ţ¤ż·Ů˛ü¤µ¤ě¤Ćˇ˘ĄŢĄ¤ĄÎĄęĄĆĄŁ¤Î¤Ű¤¦¤¬ĆŔ¤ň¤ą¤ë¤Č¤¤¤¦ľő¶·¤Ë¤Ę¤ëˇŁ¤˝¤¦¤¤¤¦»ĹÁȤߤdzäąç¤¬Čľˇą¤Ë¶á¤Ĺ¤¤¤Ć¤¤¤ë¤Č¤¤¤¦ąÍ¤¨¤¬¤Ç¤¤Ţ¤ą¤ÍˇŁ
ˇÁşŮ¤µ¤ó¤¬Ćä˽ĹĹŔĹŞ¤Ë¸¦µć¤ňżĘ¤á¤Ć¤¤¤é¤Ă¤·¤ă¤ë¤Î¤¬ˇ˘ŔľÉ˝Ĺç¤äŔĐłŔĹç¤Ë¤¤¤ë¤˘¤ëŔ¸¤ĘŞ¤Č»Ç¤Ă¤ż¤Î¤Ç¤ą¤¬ˇŁ
ˇˇ¤Ď¤¤ˇ˘Ą«ĄżĄÄĄŕĄę¤Đ¤«¤ę¤ňż©¤Ů¤ëĘѤď¤Ă¤żĄŘĄÓ¤Ç¤ą¤ÍˇŁĄ»ĄŔĄ«ĄŘĄÓ¤Č¤¤¤¦Ăç´Ö¤ÎĄŘĄÓ¤Ç¤ąˇŁ

Ą¤ĄďĄµĄĄ»ĄŔĄ«ĄŘĄÓ
¤Ş¤â¤·¤í¤¤¤ł¤Č¤ËĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤Čˇ˘¤Ţ¤˘Íż¤¨¤ě¤ĐĄĘĄáĄŻĄ¸¤âż©¤Ů¤Ţ¤ą¤ÍˇŁż©¤Ů¤ë¤â¤Î¤¬·č¤Ţ¤Ă¤Ć¤¤¤ë¤ó¤Ç¤ąˇŁ˝é¤á¤Ë¸¦µć¤·¤č¤¦¤Č»×¤Ă¤ż¤Î¤Ďˇ˘ĄŘĄÓ¤Î¤Ű¤¦¤Ç¤Ď¤Ę¤Żˇ˘ż©¤Ů¤é¤ě¤Ć¤¤¤ëĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤Î¸¦µć¤Č¤·¤Ć¤Ç¤·¤żˇŁ´¬ł¤ÎĂç´Ö¤Ë¤Ď±¦´¬¤¤Î¤â¤Î¤Čş¸´¬¤¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤Ćˇ˘ĄµĄ¶Ą¨¤Č¤«ĄżĄËĄ·¤Č¤«ˇ˘˛ćˇą¤¬¤č¤Ż¸«¤ë´¬ł¤Ď¤ß¤ó¤Ę±¦´¬¤¤Ę¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁ

¤Ŕ¤±¤Éˇ˘¤ż¤Ţ¤Ëş¸´¬¤¤ÎĽďÎŕ¤â¤¤¤ëˇŁ¤ł¤ě¤ĎÉԻ׵Ĥʤł¤Č¤Çˇ˘±¦´¬¤¤Î¤â¤Î¤â¤¤¤Ćş¸´¬¤¤Î¤â¤Î¤â¤¤¤ë¤Č¤Ę¤ë¤Čˇ˘¤´ŔčÁÄÍͤϤɤ¦¤Ŕ¤Ă¤ż¤ó¤Ŕ¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ç¤ą¤±¤ě¤É¤âˇ˘¤ż¤¤¤Ć¤¤¤Îľěąç±¦´¬¤¤«¤éş¸´¬¤¤ÎĂç´Ö¤¬˝Đ¤Ć¤Ż¤ë¤Č¤¤¤¦ˇ˘¤˝¤¦¤¤¤¦Ą¤ĄŮĄóĄČ¤¬¤˘¤Ă¤Ćˇ˘żĘ˛˝¤·¤Ć¤¤Ćˇ˘ş¸´¬¤¤Ë¤Ę¤Ă¤Ć¤¤¤Ż¤Č¤¤¤¦Ą¤ĄŮĄóĄČ¤¬¤˘¤Ă¤ż¤ČąÍ¤¨¤é¤ě¤ë¤ó¤Ç¤ąˇŁ¤ł¤ł¤¬¤ą¤´¤ŻÉԻ׵Ĥʤł¤Č¤Çˇ˘±¦´¬¤¤ÎĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤Čş¸´¬¤¤ÎĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤Ď¸ňČř¤·¤ş¤é¤¤¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁČŕ¤é¤Ď»óͺƱÂΤʤΤǡ˘¤É¤Á¤é¤¬ĄŞĄą¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ď¤Ę¤¤¤ó¤Ç¤ą¤¬ˇ˘¤Č¤ę¤˘¤¨¤ş˝Đ˛ń¤Ă¤Ćˇ˘ÁęĽę¤ËŔş»Ň¤ňĹϤ·¤ĆÍń¤ň»ş¤ŕ¤Č¤¤¤¦˛áÄř¤ň·Đ¤ĆČËżŁ¤·¤Ţ¤ąˇŁ¤˝¤Î¤Č¤¤Ë¸ňČř¤¬Ć±¤¸´¬¤¤Î¤â¤ÎƱ»Î¤Ŕ¤Ă¤ż¤é¤¦¤Ţ¤Ż»ŃŔޤňŔ°¤¨¤ë¤ł¤Č¤ł¤Č¤¬¤Ç¤¤Ć»Ň¤É¤â¤ňşî¤ë¤ł¤Č¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ą¤¬ˇ˘´¬¤¤¬ĘѤď¤Ă¤Á¤ă¤¦¤Č¤˝¤ł¤¬¤¦¤Ţ¤Żąç¤ď¤Ę¤Ż¤Ę¤Ă¤Ćˇ˘»Ň¤É¤â¤ňşî¤ě¤Ę¤¤¤Ď¤ş¤Ę¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁ¤Ę¤Î¤Çˇ˘±¦´¬¤¤ÎĽďÎफ¤éş¸´¬¤¤ÎĽďÎब˝Đ¤Ć¤Ż¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ďˇ˘±¦´¬¤¤Đ¤«¤ę¤Î˝¸ĂĤÎĂć¤Ëş¸´¬¤¤¬ĄÝĄó¤Ă¤Č˝Đ¤Ć¤¤Ćˇ˘¤˝¤ě¤¬żô¤ňÁý¤ä¤·¤Ć¤¤¤Ă¤Ćş¸´¬¤¤ÎĄ°ĄëˇĽĄ×¤Ë¤Ę¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ç¤ą¤±¤ě¤É¤âˇ˘żô¤ňÁý¤ä¤»¤Ę¤¤¤Ď¤ş¤Ę¤ó¤Ç¤ąˇŁ¤Ç¤âş¸´¬¤¤ÎĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤ĎĽÂşÝ¤Ë¤¤¤ëˇŁ¤ł¤ě¤ĎÉԻ׵Ĥʤł¤Č¤Çˇ˘˛ň¤«¤ě¤Ć¤¤¤Ę¤¤Ćć¤Ŕ¤Ă¤ż¤Î¤Çˇ˘¤ł¤ě¤ň˛ň¤ł¤¦¤ČąÍ¤¨¤Ţ¤·¤żˇŁ¤ł¤ě¤ňŔâĚŔ¤ą¤ë¤Î¤Ëˇ˘ĄŢĄ¤ĄÎĄęĄĆĄŁ¤Ę¤é¤Ç¤Ď¤ÎÍÍř¤µ¤¬¤˘¤Ă¤ż¤éżĘ˛˝¤·¤ä¤ą¤¤¤Î¤Ç¤Ď¤Ę¤¤¤«¤ČąÍ¤¨¤ż¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁ¤˝¤ě¤ÇĄŢĄ¤ĄÎĄęĄĆĄŁ¤Ę¤é¤Ç¤Ď¤ÎÍÍř¤µ¤Č¤·¤Ćˇ˘ż©¤Ů¤é¤ě¤Ë¤Ż¤¤¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤¬¤˘¤ë¤ó¤¸¤ă¤Ę¤¤¤«¤ČąÍ¤¨¤ż¤ó¤Ç¤ąˇŁ¤˝¤¦¤·¤Ć¤ß¤Ć¤¤¤Ż¤Čˇ˘´¬ł¤ňż©¤Ů¤ëŔ¸¤ĘŞ¤Çˇ˘±¦´¬¤¤Î´¬ł¤ňż©¤Ů¤ë¤Î¤ËĆü첽¤·¤żŔ¸¤Ęޤ¬ż§ˇą¤¤¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤¬¤ď¤«¤Ă¤ż¤ó¤Ç¤ąˇŁł¤¤Îł¤Ă¤Ć¤Ű¤Č¤ó¤É¤¬±¦´¬¤¤Ę¤Î¤Ç¤ą¤¬ˇ˘Ą«ĄË¤ÎĂç´Ö¤Ç¤˝¤ě¤ňż©¤Ů¤ë¤Î¤Ë¤Č¤Ć¤â¶ńąç¤¬¤¤¤¤¤Ď¤µ¤ß¤Î·Á¤ň¤·¤ż¤â¤Î¤¬¤¤¤ë¤ł¤Č¤ĎŔΤ«¤éĂΤé¤ě¤Ć¤¤¤Ţ¤ąˇŁ¤˝¤¦¤¤¤¦Ŕ¸¤Ęޤ¬¤¤¤ż¤éˇ˘ş¸´¬¤¤ÎĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤âżĘ˛˝¤·¤ä¤ą¤Ż¤Ę¤ë¤ó¤¸¤ă¤Ę¤¤¤«¤Č»×¤¤¤Ţ¤·¤żˇŁ¤˝¤ě¤Çş¸´¬¤¤ÎĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤¬¤¤¤ë¤Č¤ł¤í¤Ë¤¤Ă¤Č¤˝¤¦¤¤¤¦Ĺ·Ĺ¨¤¬¤¤¤ë¤Ď¤ş¤Ŕ¤Č»×¤Ă¤ĆĚÜŔ±¤ň¤Ä¤±¤ż¤Î¤¬Ą»ĄŔĄ«ĄŘĄÓ¤Č¤¤¤¦ĄŘĄÓ¤Ç¤ąˇŁłÍĘŞ¤Î¤Ű¤Č¤ó¤É¤¬±¦´¬¤¤Ę¤Î¤Çˇ˘¤˝¤ě¤ňż©¤Ů¤ë¤Î¤ËĆü첽¤·¤Ć¤¤¤Ć¤â¤Ş¤«¤·¤Ż¤Ę¤¤¤ó¤¸¤ă¤Ę¤¤¤«¤Č»×¤Ă¤Ć¸¦µć¤ň»Ď¤á¤ż¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁ¤˝¤·¤Ćˇ˘Ą»ĄŔĄ«ĄŘĄÓ¤Ďş¸´¬¤¤ÎĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤Ď¤¦¤Ţ¤Żż©¤Ů¤é¤ě¤Ę¤¤¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤¬ĽÂ¸ł¤Ç¤ď¤«¤Ă¤Ć¤¤Ţ¤·¤żˇŁ
şŮľµ®ŔčŔ¸¤Î¤ŞĎᢤ¤¤«¤¬¤Ŕ¤Ă¤ż¤Ç¤·¤ç¤¦¤«ˇŁÂł¤¤Ď¤Ţ¤żÍ轵¤ŞĆϤ±¤·¤Ţ¤ąˇŞ
ˇÚşŁ˝µ¤ÎČÖÁČĆâ¤Ç¤ÎĄŞĄóĄ¨Ą˘¶ĘˇŰ
ˇ¦Look At What The Light Did Now / Flo Morrissey and Matthew E. White
ˇ¦Don't Be Denied / Norah Jones
¤˝¤ÎĆĂħ¤Č¤Ď¤Ę¤Ë¤«¤Č¤¤¤¤¤Ţ¤ą¤Čˇ¦ˇ¦ˇ¦Î㤨¤ĐĄ«ĄżĄÄĄŕĄęˇŁĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤ÎłĚ¤ÎÉôʬ¤ňÁŰÁü¤·¤Ć¤ß¤Ć¤Ż¤Ŕ¤µ¤¤ˇŁ¤µ¤Ćˇ˘Ą«ĄżĄÄĄŕĄę¤ÎłĚ¤Ďˇ¦ˇ¦ˇ¦±¦´¬¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«ˇŁş¸´¬¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«ˇŁĽÂ¤Ď¤ł¤ěˇ˘¤Č¤Ă¤Ć¤â¶˝ĚŁżĽ¤¤ÍýÍł¤Çˇ˘¤É¤Á¤é¤«¤Ë´¬¤¤¤Ć¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤ąˇŞ
ĹěµţÂçłŘ¤ÎĆĂǤ˝ő¶µˇ˘şŮľµ®¤µ¤ó¤Ë¤ŞĎäň»Ç¤¤¤Ţ¤·¤żˇŁ

ˇˇ¸µˇąŔ¸¤ĘŞ¤Ď˛ż¤Ç¤âąĄ¤¤Çˇ˘Ćä˱¦ş¸¤Ç¶˝ĚŁ¤ň»ý¤Ă¤ż¤ď¤±¤Ç¤Ď¤Ę¤¤¤Î¤Ç¤ą¤¬ˇ˘ÂçłŘŔ¸¤Î»ţ¤Ë¤ż¤Ţ¤ż¤ŢĽő¤±¤żĽř¶Č¤ÎĂć¤Çˇ˘Ŕ¸¤Ęޤ˱¦ş¸¤¬¤˘¤ë¤ČˇŁ¤˝¤ě¤¬¤Č¤Ć¤âÂç»ö¤ĘĚňłä¤ň˛Ě¤ż¤·¤Ć¤¤¤ë¤Č¤¤¤¦¤ŞĎäňĘą¤¤¤ż¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁĄ˘ĄŐĄęĄ«¤ÎĄżĄóĄ¬ĄËˇĽĄ«¤Č¤¤¤¦¸Đ¤Ë˝»¤ó¤Ç¤¤¤ëµű¤Î¤Ę¤«¤Ë¤¦¤í¤ł¤Đ¤«¤ęż©¤Ů¤ëµű¤¬¤¤¤Ćˇ˘¤˝¤Î¤¦¤í¤ł¤ňż©¤Ů¤ëµű¤Ď¸ý¤¬¤Ň¤ó¶Ę¤¬¤Ă¤Ć¤¤¤Ćˇ˘¸ÄÂΤˤč¤Ă¤ĆÁęĽę¤Î±¦Â¦¤Đ¤«¤ę˝±¤¦¤â¤Î¤Čˇ˘ş¸Â¦¤Đ¤«¤ę˝±¤¦¤â¤Î¤Č¤¤¤¦2ĄżĄ¤Ą×¤¤¤ëˇŁ¤Çˇ˘¸ý¤¬±¦¤Ë¶Ę¤¬¤Ă¤Ć¤¤¤ë¤â¤Î¤Čˇ˘ş¸¤Ë¶Ę¤¬¤Ă¤Ć¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Čľˇą¤¤¤Ćˇ˘¤Á¤ç¤¦¤ÉČľˇą¤Ë¶ŃąŐ¤¬Ęݤż¤ě¤Ć¤¤¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤ňČŻ¸«¤µ¤ě¤ż¤Č¤¤¤¦Ď䬤ą¤´¤Ż°őľÝżĽ¤«¤Ă¤ż¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁ¤Çˇ˘Ľ«Ę¬¤â¤˝¤ó¤Ę¤«¤Ă¤ł¤¤¤¤¸¦µć¤ň¤·¤ż¤¤¤Ę¤Č»×¤Ă¤ĆĄĆˇĽĄŢ¤ňõ¤·¤Ć¤¤¤Ćˇ˘şŁ¤Î¸¦µć¤ËąÔ¤¤Ä¤¤Ţ¤·¤żˇŁ
ˇÁ¤¸¤ă¤˘Ć±¤¸Ŕ¸¤ĘŞ¤Ç¤âˇ˘´Ęñ¤ËĄ¤ĄáˇĽĄ¸¤ą¤ë¤Č±¦Íř¤¤Čş¸Íř¤¤¬¤¤¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ç¤ą¤ÍˇŁ
ˇˇ¤˝¤¦¤Ç¤ą¤ÍˇŁÍř¤Ľę¤Č¤¤¤¦¤Î¤ĎżÍ¤Ŕ¤±¤Ç¤Ď¤Ę¤Żˇ˘ĄÁĄóĄŃĄóĄ¸ˇĽ¤Ë¤â¤˘¤ę¤Ţ¤ą¤·ˇ˘Ę¸¸Ą¤ňÄ´¤Ů¤ë¤Čˇ˘ĄŇĄĄ¬Ą¨Ąë¤Ë¤â¤˘¤ë¤Č¤«ˇ˘Ä»¤¬¤Č¤Ţ¤ë¤Č¤¤Ë¤ň»Č¤¦Â¦¤¬¤É¤Ă¤Á¤Ŕ¤Č¤«ˇ˘¤¤¤í¤ó¤Ę¸¦µć¤¬¤˘¤ë¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁ
ˇÁ¤ą¤´¤ŻÉԻ׵Ĥʤó¤Ç¤ą¤±¤Éˇ˘¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ďˇ˘ş¸Íř¤¤ÎŔ¸¤Ęޤ¬»Ä¤ëÍýÍł¤Č¤¤¤¦¤Î¤¬¤˘¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ç¤ą¤č¤ÍˇŁ
ˇˇ¤˝¤¦¤Ç¤ą¤ÍˇŁĄŢĄ¤ĄÎĄęĄĆĄŁ¤Ë¤Ę¤ë¤Č¤Ę¤Ë¤«ĆŔ¤Ę¤ł¤Č¤¬¤˘¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤ňąÍ¤¨¤ë¤Čˇ˘ÎľĘý¤¬¤Ň¤Č¤Ä¤ÎĄ°ĄëˇĽĄ×¤Ë¤¤¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤ňŔâĚŔ¤·¤ä¤ą¤¤¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁŔč¤Ű¤É¤Î¤¦¤í¤ł¤ňż©¤Ů¤ëµű¤Îľěąç¤Ďˇ˘ş¸¤Ë¶Ę¤¬¤Ă¤Ć¤¤¤ë¤Ű¤¦¤Îµű¤¬ˇ˘ÁęĽę¤Ë·Ů˛ü¤µ¤ě¤Ćż©¤Ů¤ë¤Î¤¬Ćń¤·¤Ż¤Ę¤Ă¤Ć¤Ż¤ë¤Č±¦¤¬Áý¤¨¤Ć¤¤¤Ż¤ČˇŁ¤Çˇ˘Áý¤¨¤ą¤®¤ë¤Č¤Ţ¤ż·Ů˛ü¤µ¤ě¤Ćˇ˘ĄŢĄ¤ĄÎĄęĄĆĄŁ¤Î¤Ű¤¦¤¬ĆŔ¤ň¤ą¤ë¤Č¤¤¤¦ľő¶·¤Ë¤Ę¤ëˇŁ¤˝¤¦¤¤¤¦»ĹÁȤߤdzäąç¤¬Čľˇą¤Ë¶á¤Ĺ¤¤¤Ć¤¤¤ë¤Č¤¤¤¦ąÍ¤¨¤¬¤Ç¤¤Ţ¤ą¤ÍˇŁ
ˇÁşŮ¤µ¤ó¤¬Ćä˽ĹĹŔĹŞ¤Ë¸¦µć¤ňżĘ¤á¤Ć¤¤¤é¤Ă¤·¤ă¤ë¤Î¤¬ˇ˘ŔľÉ˝Ĺç¤äŔĐłŔĹç¤Ë¤¤¤ë¤˘¤ëŔ¸¤ĘŞ¤Č»Ç¤Ă¤ż¤Î¤Ç¤ą¤¬ˇŁ
ˇˇ¤Ď¤¤ˇ˘Ą«ĄżĄÄĄŕĄę¤Đ¤«¤ę¤ňż©¤Ů¤ëĘѤď¤Ă¤żĄŘĄÓ¤Ç¤ą¤ÍˇŁĄ»ĄŔĄ«ĄŘĄÓ¤Č¤¤¤¦Ăç´Ö¤ÎĄŘĄÓ¤Ç¤ąˇŁ

Ą¤ĄďĄµĄĄ»ĄŔĄ«ĄŘĄÓ
¤Ş¤â¤·¤í¤¤¤ł¤Č¤ËĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤Čˇ˘¤Ţ¤˘Íż¤¨¤ě¤ĐĄĘĄáĄŻĄ¸¤âż©¤Ů¤Ţ¤ą¤ÍˇŁż©¤Ů¤ë¤â¤Î¤¬·č¤Ţ¤Ă¤Ć¤¤¤ë¤ó¤Ç¤ąˇŁ˝é¤á¤Ë¸¦µć¤·¤č¤¦¤Č»×¤Ă¤ż¤Î¤Ďˇ˘ĄŘĄÓ¤Î¤Ű¤¦¤Ç¤Ď¤Ę¤Żˇ˘ż©¤Ů¤é¤ě¤Ć¤¤¤ëĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤Î¸¦µć¤Č¤·¤Ć¤Ç¤·¤żˇŁ´¬ł¤ÎĂç´Ö¤Ë¤Ď±¦´¬¤¤Î¤â¤Î¤Čş¸´¬¤¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤Ćˇ˘ĄµĄ¶Ą¨¤Č¤«ĄżĄËĄ·¤Č¤«ˇ˘˛ćˇą¤¬¤č¤Ż¸«¤ë´¬ł¤Ď¤ß¤ó¤Ę±¦´¬¤¤Ę¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁ

¤Ŕ¤±¤Éˇ˘¤ż¤Ţ¤Ëş¸´¬¤¤ÎĽďÎŕ¤â¤¤¤ëˇŁ¤ł¤ě¤ĎÉԻ׵Ĥʤł¤Č¤Çˇ˘±¦´¬¤¤Î¤â¤Î¤â¤¤¤Ćş¸´¬¤¤Î¤â¤Î¤â¤¤¤ë¤Č¤Ę¤ë¤Čˇ˘¤´ŔčÁÄÍͤϤɤ¦¤Ŕ¤Ă¤ż¤ó¤Ŕ¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ç¤ą¤±¤ě¤É¤âˇ˘¤ż¤¤¤Ć¤¤¤Îľěąç±¦´¬¤¤«¤éş¸´¬¤¤ÎĂç´Ö¤¬˝Đ¤Ć¤Ż¤ë¤Č¤¤¤¦ˇ˘¤˝¤¦¤¤¤¦Ą¤ĄŮĄóĄČ¤¬¤˘¤Ă¤Ćˇ˘żĘ˛˝¤·¤Ć¤¤Ćˇ˘ş¸´¬¤¤Ë¤Ę¤Ă¤Ć¤¤¤Ż¤Č¤¤¤¦Ą¤ĄŮĄóĄČ¤¬¤˘¤Ă¤ż¤ČąÍ¤¨¤é¤ě¤ë¤ó¤Ç¤ąˇŁ¤ł¤ł¤¬¤ą¤´¤ŻÉԻ׵Ĥʤł¤Č¤Çˇ˘±¦´¬¤¤ÎĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤Čş¸´¬¤¤ÎĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤Ď¸ňČř¤·¤ş¤é¤¤¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁČŕ¤é¤Ď»óͺƱÂΤʤΤǡ˘¤É¤Á¤é¤¬ĄŞĄą¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ď¤Ę¤¤¤ó¤Ç¤ą¤¬ˇ˘¤Č¤ę¤˘¤¨¤ş˝Đ˛ń¤Ă¤Ćˇ˘ÁęĽę¤ËŔş»Ň¤ňĹϤ·¤ĆÍń¤ň»ş¤ŕ¤Č¤¤¤¦˛áÄř¤ň·Đ¤ĆČËżŁ¤·¤Ţ¤ąˇŁ¤˝¤Î¤Č¤¤Ë¸ňČř¤¬Ć±¤¸´¬¤¤Î¤â¤ÎƱ»Î¤Ŕ¤Ă¤ż¤é¤¦¤Ţ¤Ż»ŃŔޤňŔ°¤¨¤ë¤ł¤Č¤ł¤Č¤¬¤Ç¤¤Ć»Ň¤É¤â¤ňşî¤ë¤ł¤Č¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ą¤¬ˇ˘´¬¤¤¬ĘѤď¤Ă¤Á¤ă¤¦¤Č¤˝¤ł¤¬¤¦¤Ţ¤Żąç¤ď¤Ę¤Ż¤Ę¤Ă¤Ćˇ˘»Ň¤É¤â¤ňşî¤ě¤Ę¤¤¤Ď¤ş¤Ę¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁ¤Ę¤Î¤Çˇ˘±¦´¬¤¤ÎĽďÎफ¤éş¸´¬¤¤ÎĽďÎब˝Đ¤Ć¤Ż¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ďˇ˘±¦´¬¤¤Đ¤«¤ę¤Î˝¸ĂĤÎĂć¤Ëş¸´¬¤¤¬ĄÝĄó¤Ă¤Č˝Đ¤Ć¤¤Ćˇ˘¤˝¤ě¤¬żô¤ňÁý¤ä¤·¤Ć¤¤¤Ă¤Ćş¸´¬¤¤ÎĄ°ĄëˇĽĄ×¤Ë¤Ę¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤Ç¤ą¤±¤ě¤É¤âˇ˘żô¤ňÁý¤ä¤»¤Ę¤¤¤Ď¤ş¤Ę¤ó¤Ç¤ąˇŁ¤Ç¤âş¸´¬¤¤ÎĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤ĎĽÂşÝ¤Ë¤¤¤ëˇŁ¤ł¤ě¤ĎÉԻ׵Ĥʤł¤Č¤Çˇ˘˛ň¤«¤ě¤Ć¤¤¤Ę¤¤Ćć¤Ŕ¤Ă¤ż¤Î¤Çˇ˘¤ł¤ě¤ň˛ň¤ł¤¦¤ČąÍ¤¨¤Ţ¤·¤żˇŁ¤ł¤ě¤ňŔâĚŔ¤ą¤ë¤Î¤Ëˇ˘ĄŢĄ¤ĄÎĄęĄĆĄŁ¤Ę¤é¤Ç¤Ď¤ÎÍÍř¤µ¤¬¤˘¤Ă¤ż¤éżĘ˛˝¤·¤ä¤ą¤¤¤Î¤Ç¤Ď¤Ę¤¤¤«¤ČąÍ¤¨¤ż¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁ¤˝¤ě¤ÇĄŢĄ¤ĄÎĄęĄĆĄŁ¤Ę¤é¤Ç¤Ď¤ÎÍÍř¤µ¤Č¤·¤Ćˇ˘ż©¤Ů¤é¤ě¤Ë¤Ż¤¤¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤¬¤˘¤ë¤ó¤¸¤ă¤Ę¤¤¤«¤ČąÍ¤¨¤ż¤ó¤Ç¤ąˇŁ¤˝¤¦¤·¤Ć¤ß¤Ć¤¤¤Ż¤Čˇ˘´¬ł¤ňż©¤Ů¤ëŔ¸¤ĘŞ¤Çˇ˘±¦´¬¤¤Î´¬ł¤ňż©¤Ů¤ë¤Î¤ËĆü첽¤·¤żŔ¸¤Ęޤ¬ż§ˇą¤¤¤ë¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤¬¤ď¤«¤Ă¤ż¤ó¤Ç¤ąˇŁł¤¤Îł¤Ă¤Ć¤Ű¤Č¤ó¤É¤¬±¦´¬¤¤Ę¤Î¤Ç¤ą¤¬ˇ˘Ą«ĄË¤ÎĂç´Ö¤Ç¤˝¤ě¤ňż©¤Ů¤ë¤Î¤Ë¤Č¤Ć¤â¶ńąç¤¬¤¤¤¤¤Ď¤µ¤ß¤Î·Á¤ň¤·¤ż¤â¤Î¤¬¤¤¤ë¤ł¤Č¤ĎŔΤ«¤éĂΤé¤ě¤Ć¤¤¤Ţ¤ąˇŁ¤˝¤¦¤¤¤¦Ŕ¸¤Ęޤ¬¤¤¤ż¤éˇ˘ş¸´¬¤¤ÎĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤âżĘ˛˝¤·¤ä¤ą¤Ż¤Ę¤ë¤ó¤¸¤ă¤Ę¤¤¤«¤Č»×¤¤¤Ţ¤·¤żˇŁ¤˝¤ě¤Çş¸´¬¤¤ÎĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤¬¤¤¤ë¤Č¤ł¤í¤Ë¤¤Ă¤Č¤˝¤¦¤¤¤¦Ĺ·Ĺ¨¤¬¤¤¤ë¤Ď¤ş¤Ŕ¤Č»×¤Ă¤ĆĚÜŔ±¤ň¤Ä¤±¤ż¤Î¤¬Ą»ĄŔĄ«ĄŘĄÓ¤Č¤¤¤¦ĄŘĄÓ¤Ç¤ąˇŁłÍĘŞ¤Î¤Ű¤Č¤ó¤É¤¬±¦´¬¤¤Ę¤Î¤Çˇ˘¤˝¤ě¤ňż©¤Ů¤ë¤Î¤ËĆü첽¤·¤Ć¤¤¤Ć¤â¤Ş¤«¤·¤Ż¤Ę¤¤¤ó¤¸¤ă¤Ę¤¤¤«¤Č»×¤Ă¤Ć¸¦µć¤ň»Ď¤á¤ż¤ó¤Ç¤ą¤ÍˇŁ¤˝¤·¤Ćˇ˘Ą»ĄŔĄ«ĄŘĄÓ¤Ďş¸´¬¤¤ÎĄ«ĄżĄÄĄŕĄę¤Ď¤¦¤Ţ¤Żż©¤Ů¤é¤ě¤Ę¤¤¤Č¤¤¤¦¤ł¤Č¤¬ĽÂ¸ł¤Ç¤ď¤«¤Ă¤Ć¤¤Ţ¤·¤żˇŁ
şŮľµ®ŔčŔ¸¤Î¤ŞĎᢤ¤¤«¤¬¤Ŕ¤Ă¤ż¤Ç¤·¤ç¤¦¤«ˇŁÂł¤¤Ď¤Ţ¤żÍ轵¤ŞĆϤ±¤·¤Ţ¤ąˇŞ
ˇÚşŁ˝µ¤ÎČÖÁČĆâ¤Ç¤ÎĄŞĄóĄ¨Ą˘¶ĘˇŰ
ˇ¦Look At What The Light Did Now / Flo Morrissey and Matthew E. White
ˇ¦Don't Be Denied / Norah Jones