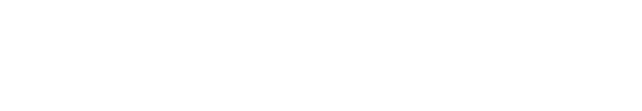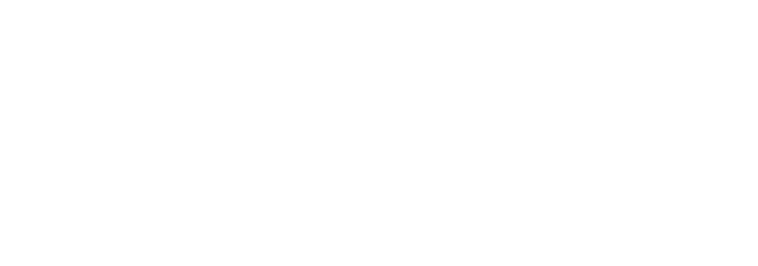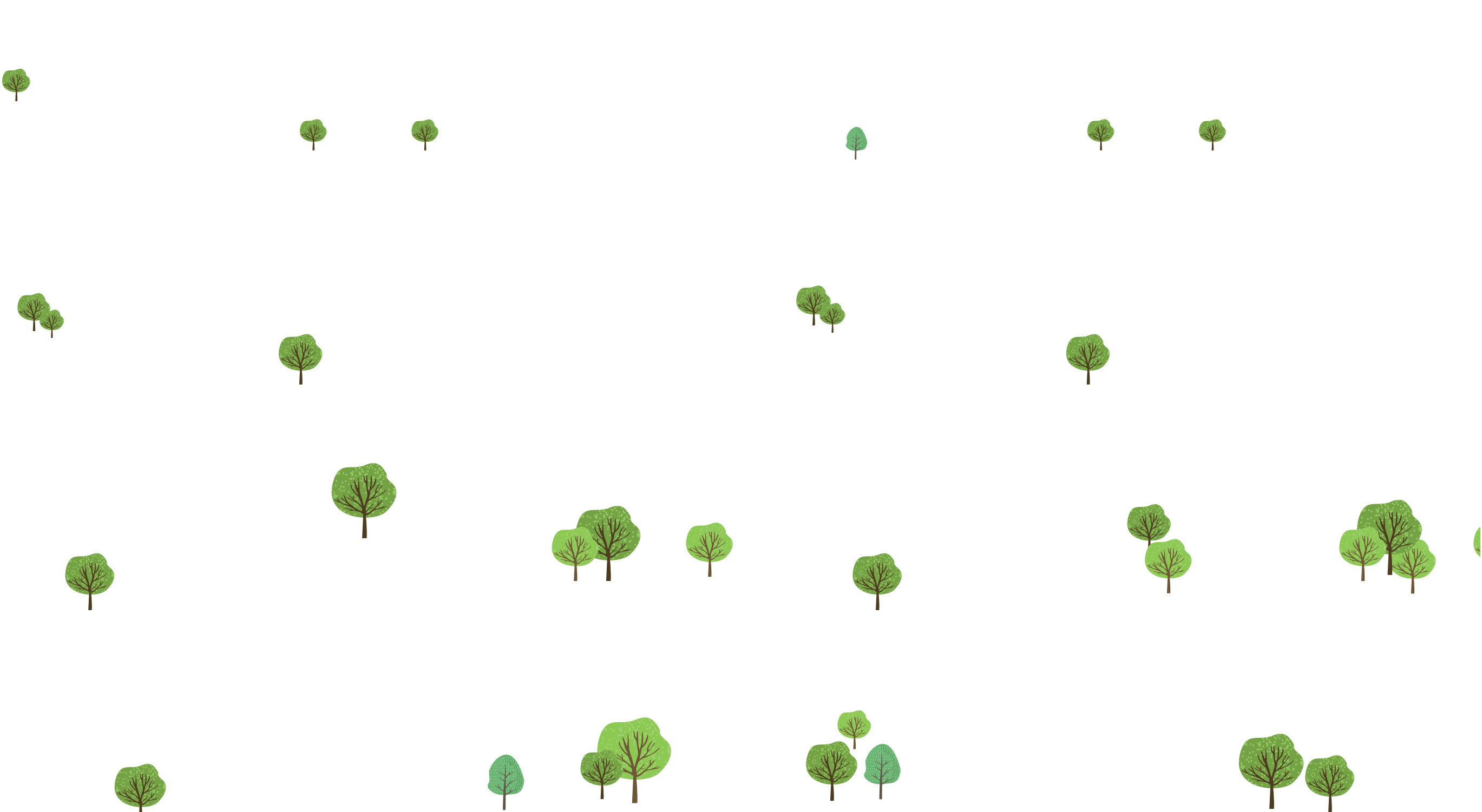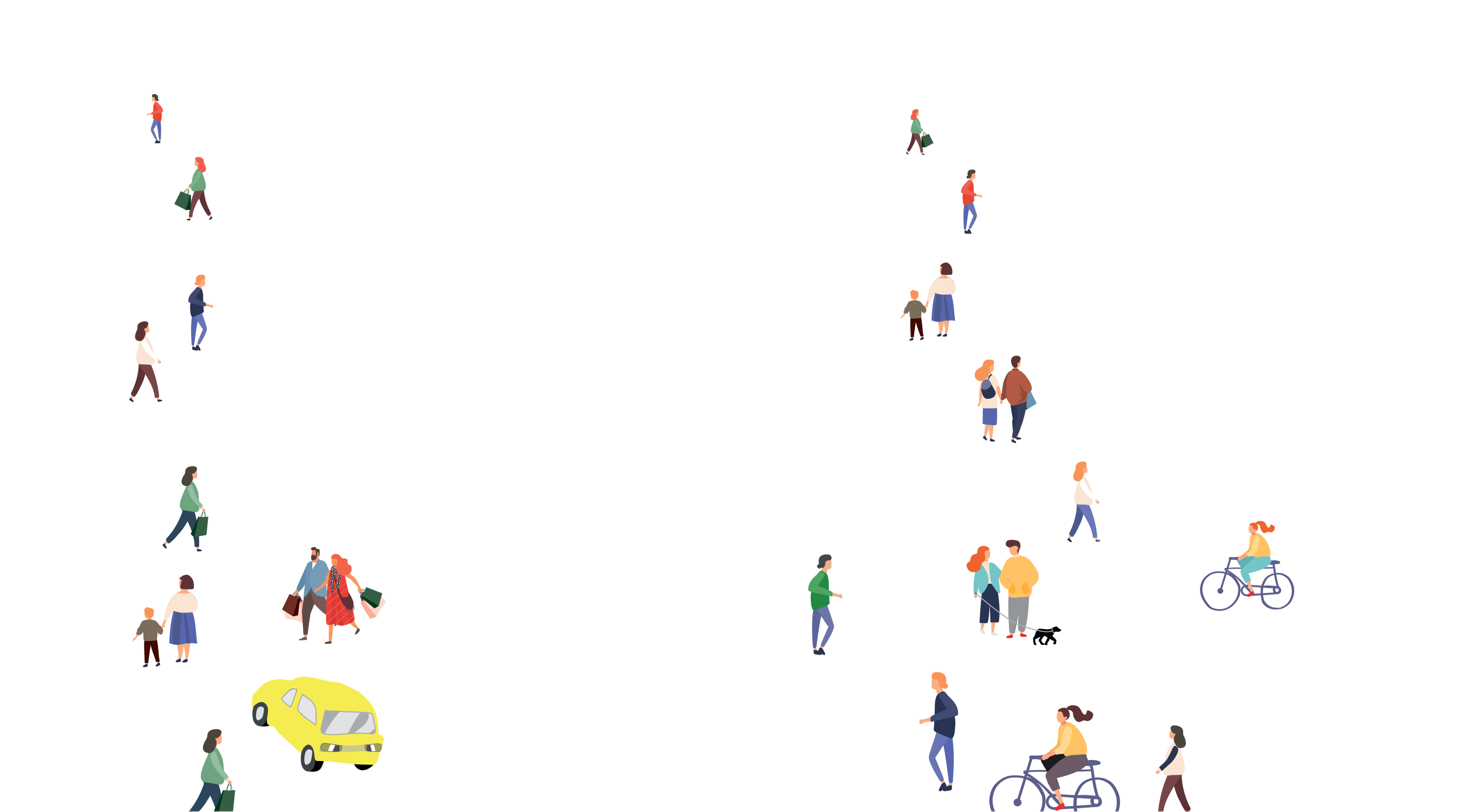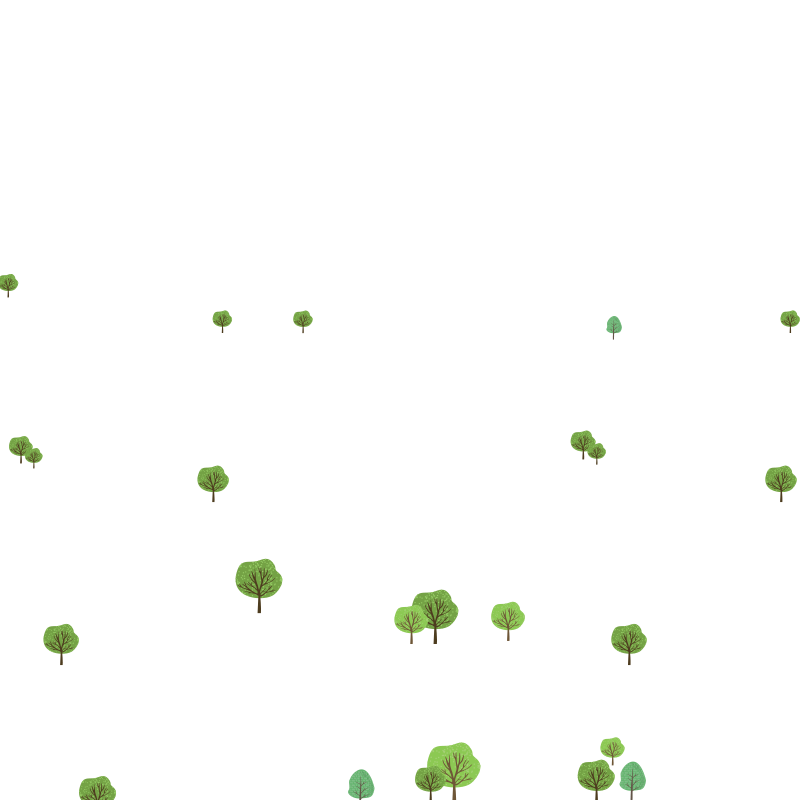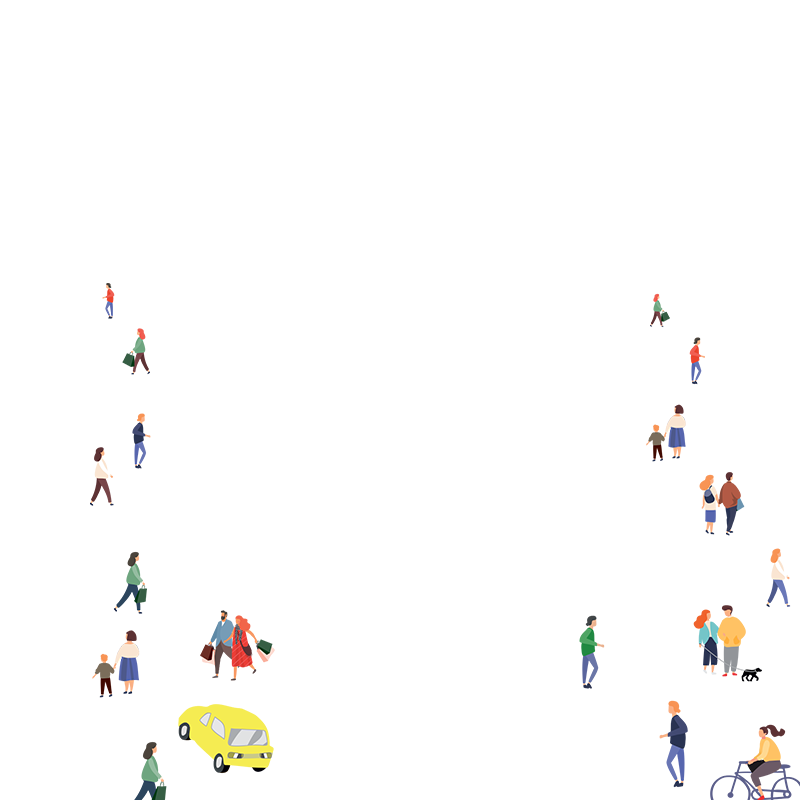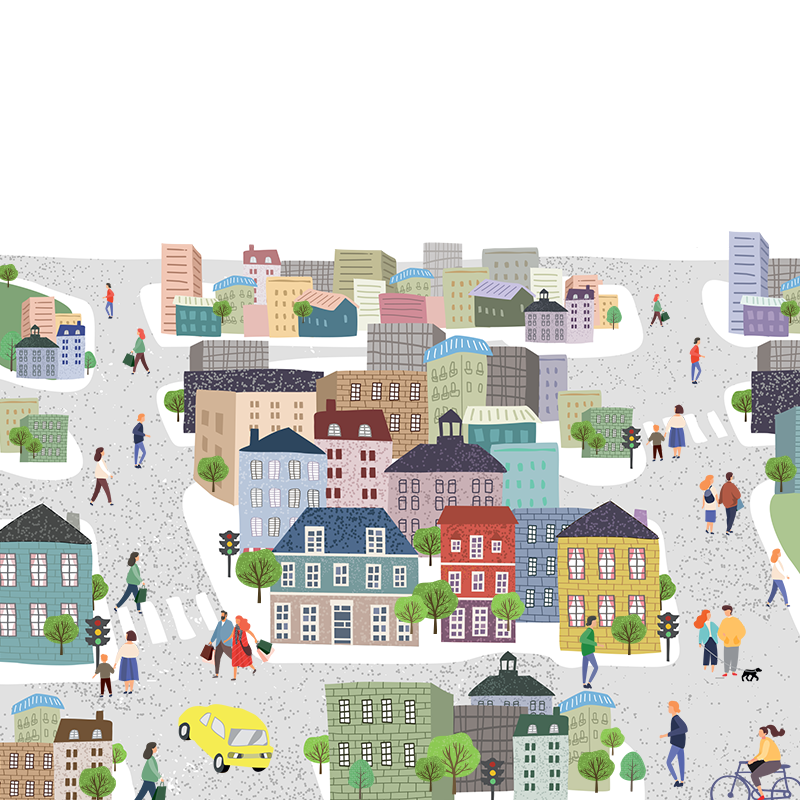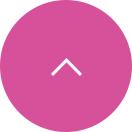第67回 1月26日「ビスケット」後編
2025.01.26
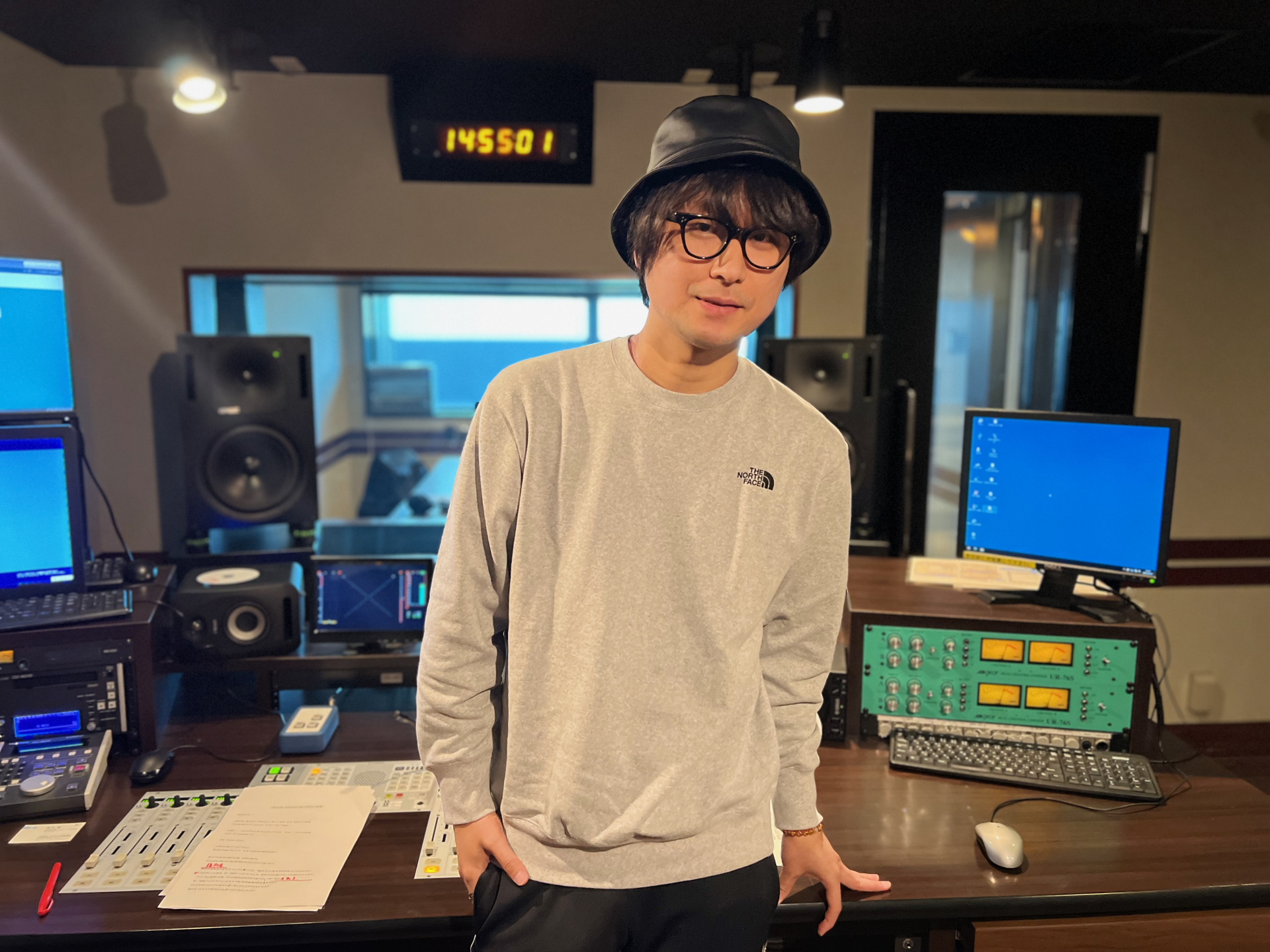
1543年に種子島にやってきたポルトガル人が日本にもたらしたビスケット。
残念ながら当時の日本人の好みには合わず、江戸時代には外国への窓口があった
出島近郊の長崎でのみ、外国人に向けて作られていたようです。
そのビスケットが、幕末になって保存のきく兵糧として注目されます。
水戸藩の蘭医 柴田方庵という人物が、長崎でオランダ人から学んだビスケットの作り方を藩に送った手紙が残っています。また、薩摩藩も兵糧として準備していました。
そんな時代を経て明治・大正時代になると菓子店でビスケットの製造・販売が始まります。
日本で最初にビスケットを研究して製造、販売したとされるのは米津松蔵という人物。
1875年(明治8年)のことでした。
この方は、その2年後の第1回内国勧業博覧会にビスケットを出品。
最高賞を授与されています。イギリスからビスケット製造機を購入した記録もあります。
ビスケットの美味しさが飛躍的に向上するのは戦後。
材料の供給が回復し、製造方法の機械化が進み、大量生産も可能となりました。
1971年(昭和46年)にはビスケットの輸入も自由化されています。
そんなビスケット。
今では美味しいものがたくさんありティータイムを至福のひと時に演出してくれています。
あなたはどんなビスケットが好きですか?
残念ながら当時の日本人の好みには合わず、江戸時代には外国への窓口があった
出島近郊の長崎でのみ、外国人に向けて作られていたようです。
そのビスケットが、幕末になって保存のきく兵糧として注目されます。
水戸藩の蘭医 柴田方庵という人物が、長崎でオランダ人から学んだビスケットの作り方を藩に送った手紙が残っています。また、薩摩藩も兵糧として準備していました。
そんな時代を経て明治・大正時代になると菓子店でビスケットの製造・販売が始まります。
日本で最初にビスケットを研究して製造、販売したとされるのは米津松蔵という人物。
1875年(明治8年)のことでした。
この方は、その2年後の第1回内国勧業博覧会にビスケットを出品。
最高賞を授与されています。イギリスからビスケット製造機を購入した記録もあります。
ビスケットの美味しさが飛躍的に向上するのは戦後。
材料の供給が回復し、製造方法の機械化が進み、大量生産も可能となりました。
1971年(昭和46年)にはビスケットの輸入も自由化されています。
そんなビスケット。
今では美味しいものがたくさんありティータイムを至福のひと時に演出してくれています。
あなたはどんなビスケットが好きですか?