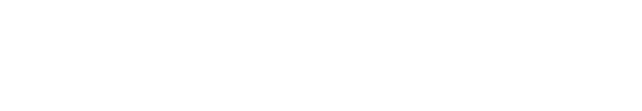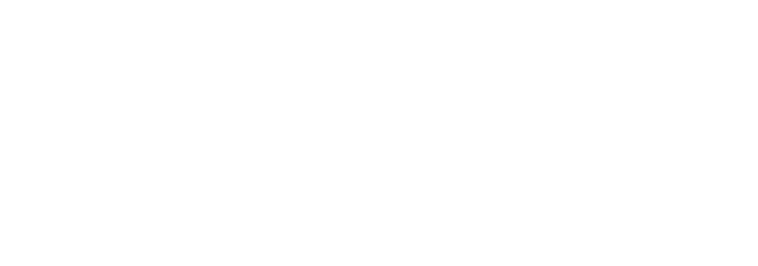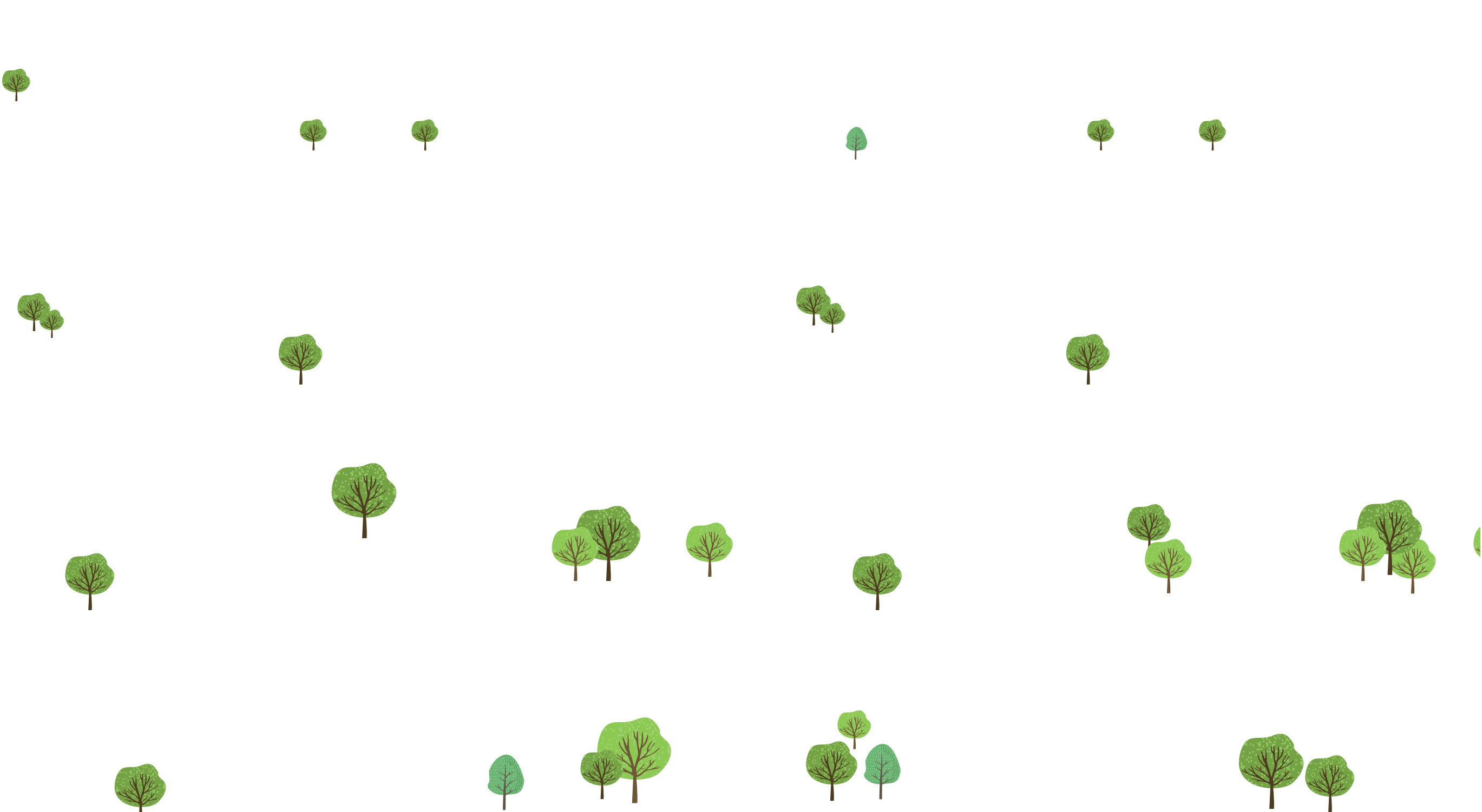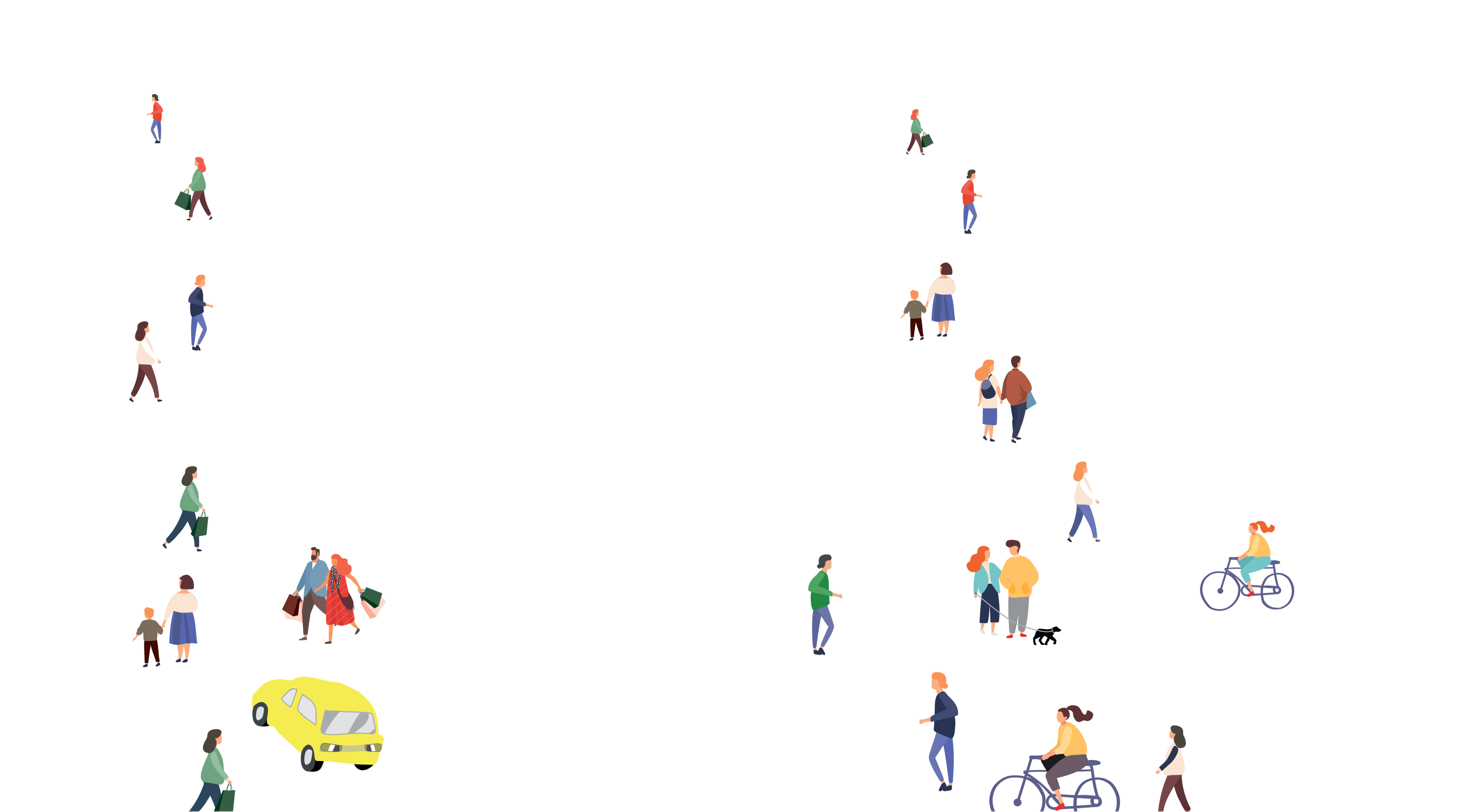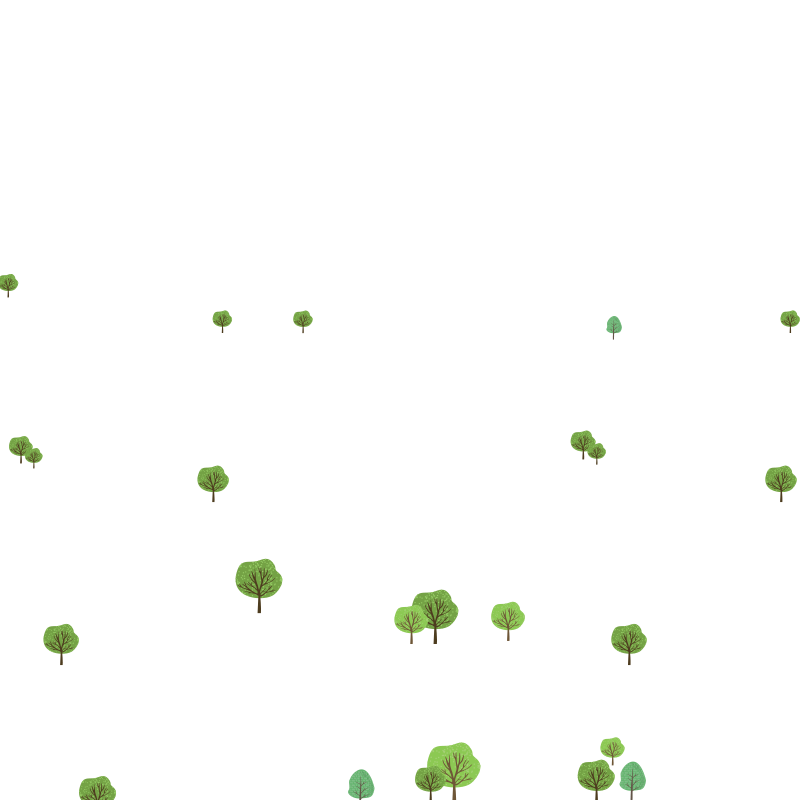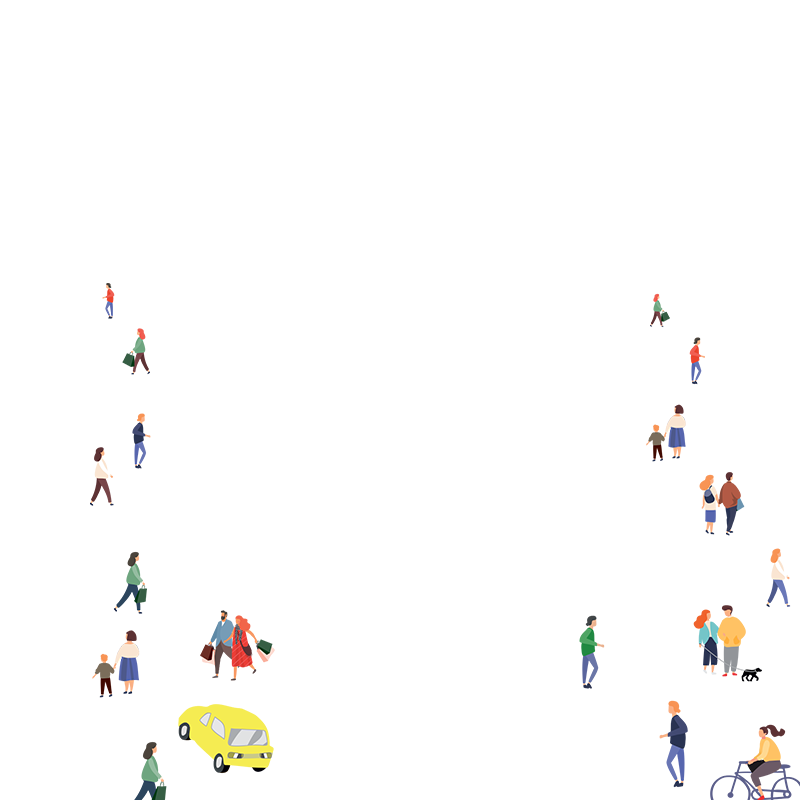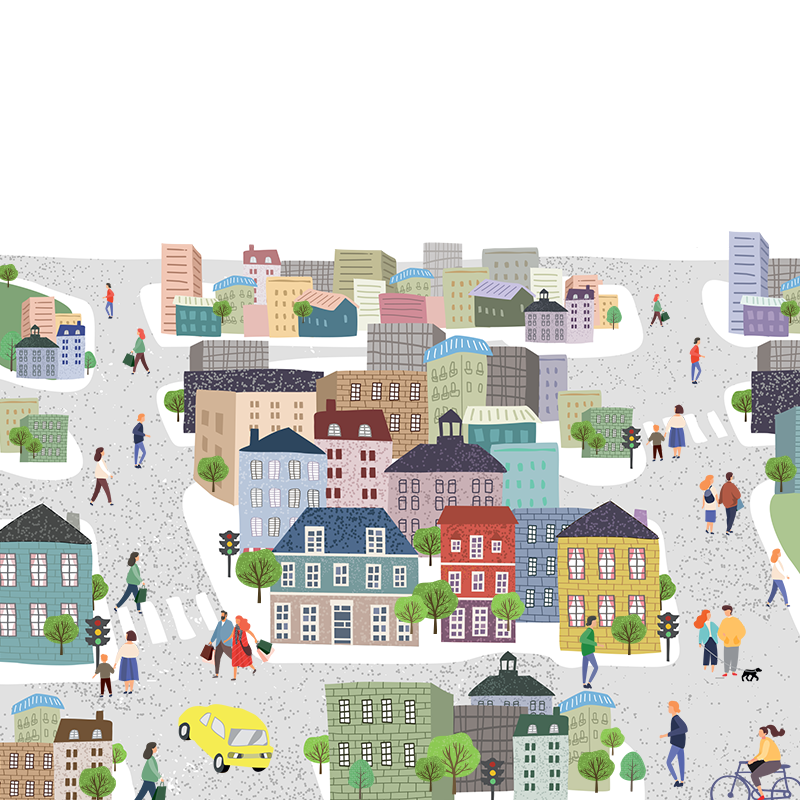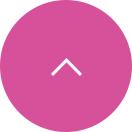第68回 2月2日「仕事着(ユニフォーム)」前編
2025.02.02

現代社会では多くの人が仕事着を着ています。
医師 / 電車の運転士 / 裁判官 / 工場で働く方 / 物流の現場で働く方など。
それらの仕事着の源流を1つにまとめるのは難しいですが・・・
歴史を振り返ると仕事着は身分を表したり、権威を知らしめるものでした。
日本では飛鳥時代に聖徳太子が冠位十二階を制定。
朝廷で働く人を12の位階に分けて異なる冠の色にしています。
その後の平安時代には、貴族は身分で衣服に使える色が決められていました。
時が経つと職業集団が、同じユニフォームを身につけるようにもなります。
わかりやすい例が、江戸時代の消防士である火消し。
ここには社会への身分提示という意味の他に仲間との連帯意識の構築の意図が伺えます。
現在のスポーツにおけるユニフォームが、チーム結束に一役買っているのと同じでしょう。
火消しは明暦の大火の後、丈夫な生地と織り方の火事羽織を着るようになります。
危険を考慮し、より機能性を考えてのことでした。
ほどなく、イギリスで産業革命が起こり
その技術革新で大きな恩恵を受けたのが繊維産業です。
紡績機や織機が機械化されて、性能が飛躍的に向上。
高品質の生地が安価で手に入るようになって
仕事着(ユニフォーム)の供給と需要は拡大しました。
産業革命は市民に富とゆとりを生み、また王政から市民社会へと移行していく中で
人々は礼節のため、自身の評価のため、服装への関心を高めます。
その中で自分の仕事に向いた実用的な仕事着を身につけるようになりました。
近代ヨーロッパでは、人は身なりで職業がわかったといいます。
医師 / 電車の運転士 / 裁判官 / 工場で働く方 / 物流の現場で働く方など。
それらの仕事着の源流を1つにまとめるのは難しいですが・・・
歴史を振り返ると仕事着は身分を表したり、権威を知らしめるものでした。
日本では飛鳥時代に聖徳太子が冠位十二階を制定。
朝廷で働く人を12の位階に分けて異なる冠の色にしています。
その後の平安時代には、貴族は身分で衣服に使える色が決められていました。
時が経つと職業集団が、同じユニフォームを身につけるようにもなります。
わかりやすい例が、江戸時代の消防士である火消し。
ここには社会への身分提示という意味の他に仲間との連帯意識の構築の意図が伺えます。
現在のスポーツにおけるユニフォームが、チーム結束に一役買っているのと同じでしょう。
火消しは明暦の大火の後、丈夫な生地と織り方の火事羽織を着るようになります。
危険を考慮し、より機能性を考えてのことでした。
ほどなく、イギリスで産業革命が起こり
その技術革新で大きな恩恵を受けたのが繊維産業です。
紡績機や織機が機械化されて、性能が飛躍的に向上。
高品質の生地が安価で手に入るようになって
仕事着(ユニフォーム)の供給と需要は拡大しました。
産業革命は市民に富とゆとりを生み、また王政から市民社会へと移行していく中で
人々は礼節のため、自身の評価のため、服装への関心を高めます。
その中で自分の仕事に向いた実用的な仕事着を身につけるようになりました。
近代ヨーロッパでは、人は身なりで職業がわかったといいます。