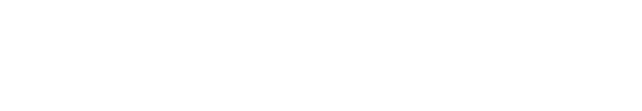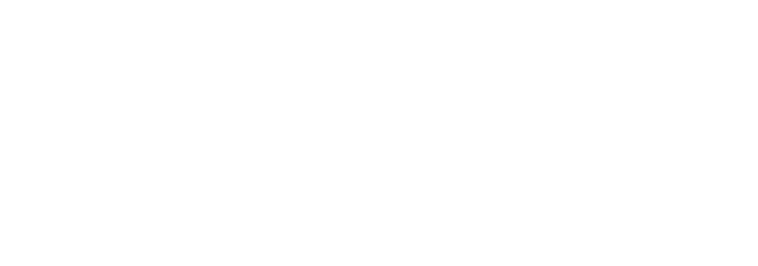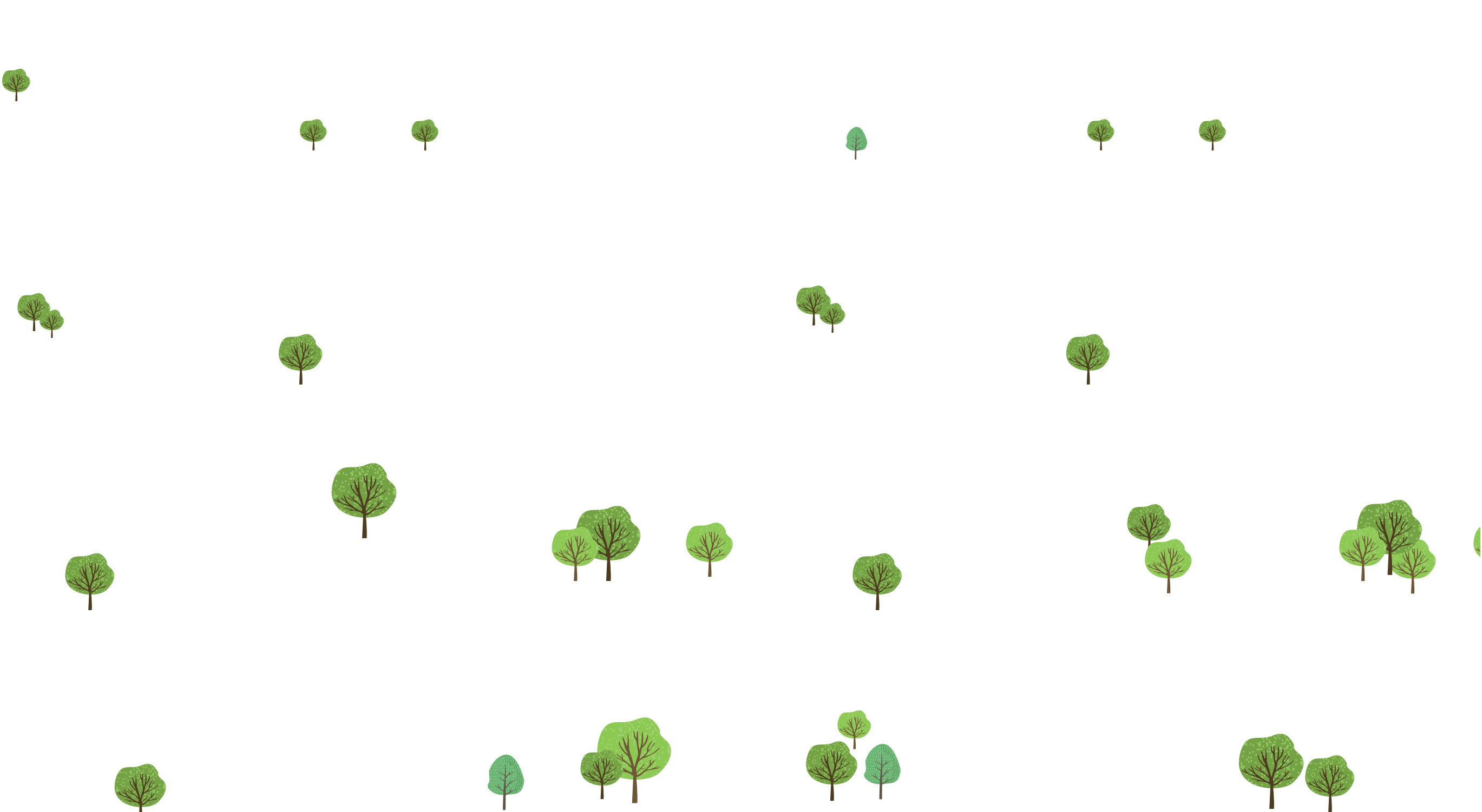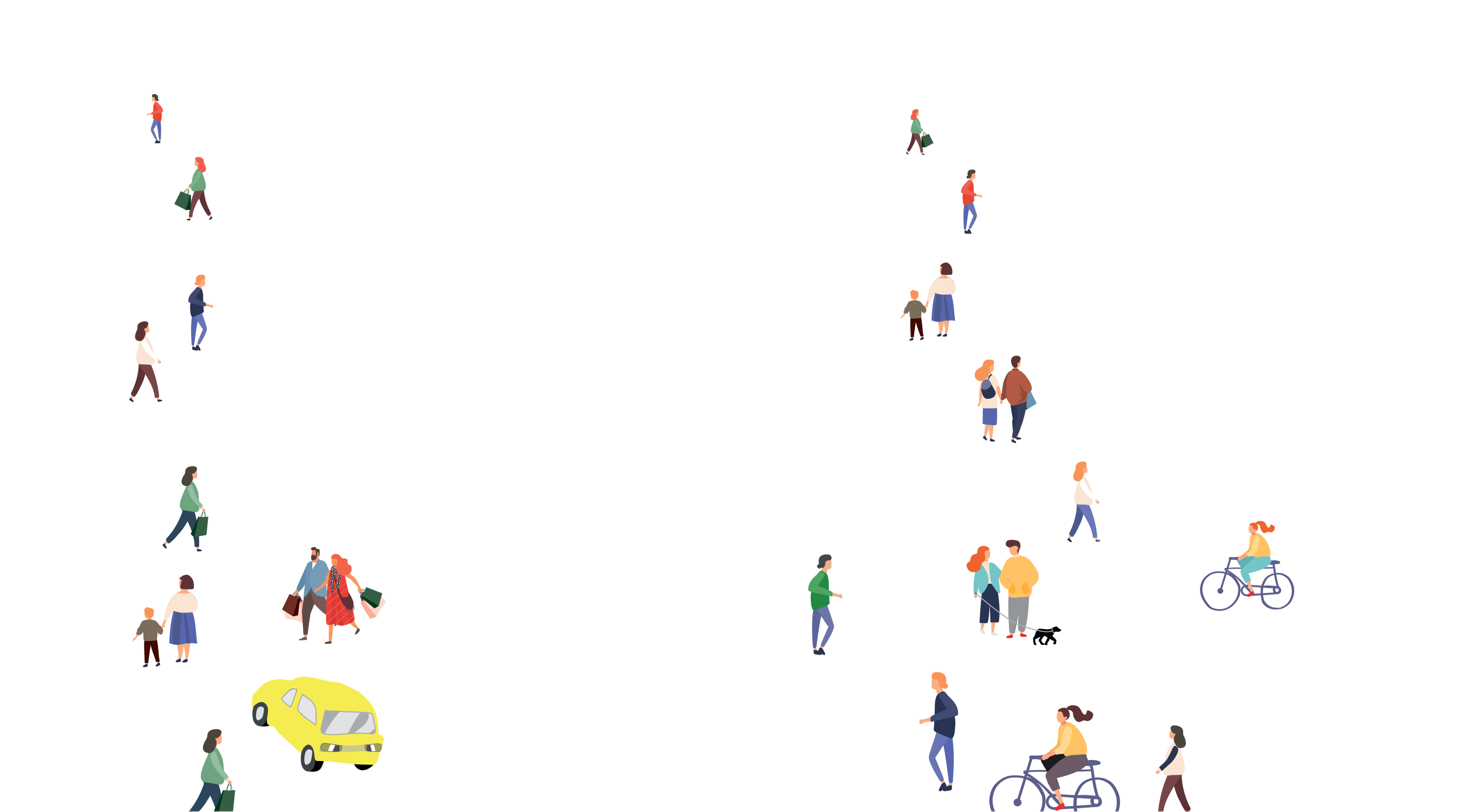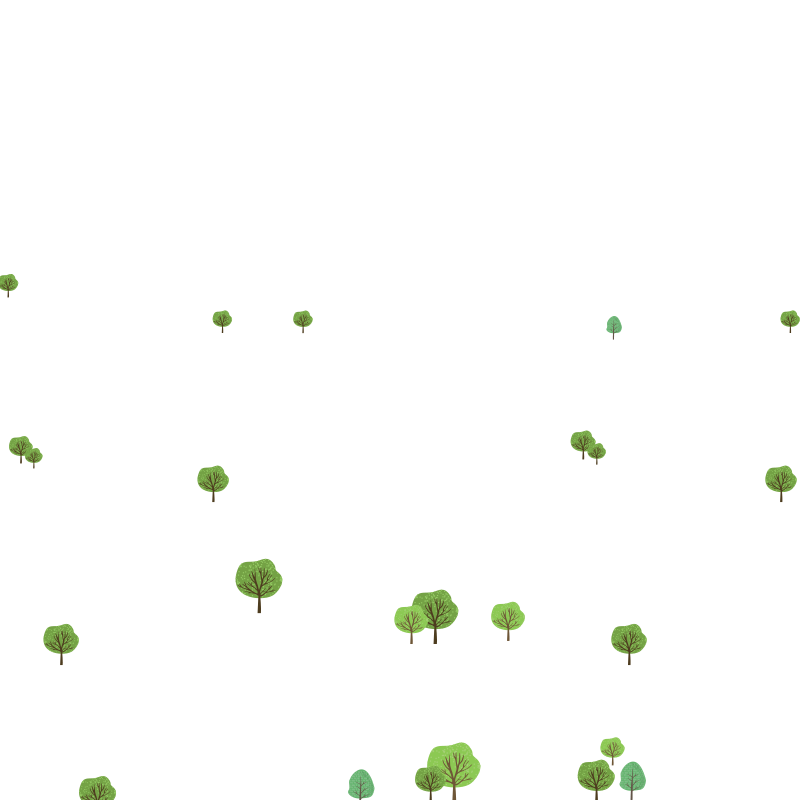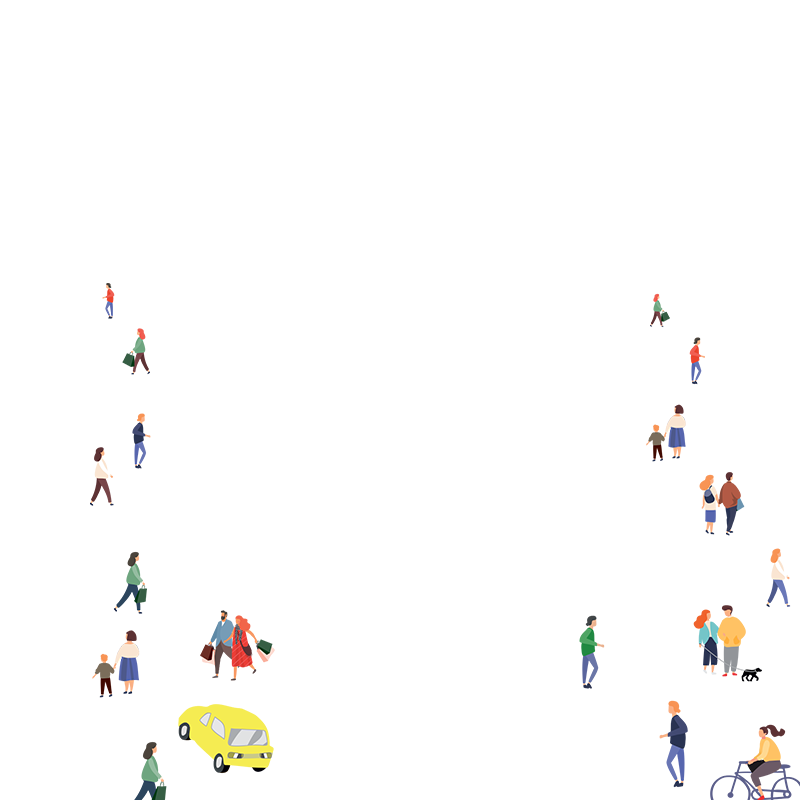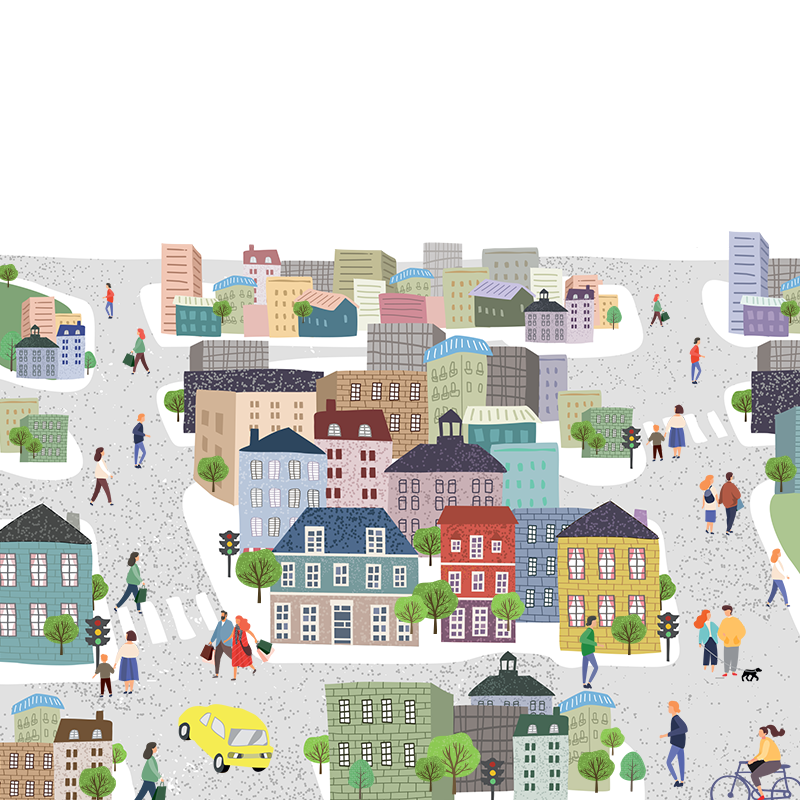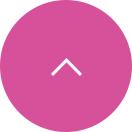第84回 5月25日「自動改札機」後編
2025.05.25

鉄道の駅や空港に普及している磁気式自動改札機の登場は1967年(昭和42年)。
大阪府吹田市で開業した阪急千里線 北千里駅。
その頃、電気製品による自動改札機の開発が世界で進められていました。
人件費の節減や不正乗車の防止が期待できて労働者不足を補えるからです。
その中で、乗車券の裏に情報を記録し、読みとる磁気式自動改札機が開発されたのは日本。
北千里駅は世界初の実用化として、2007年に電気・電子分野における世界最大の専門家組織
IEEEのマイルストーン賞を受賞。現在、改札内には認定プレートが設置されています。
当初は課題が山積みでした。
求められたのは、増える通勤客の改札通過を早く、効率的にすること。
しかし、大きさが違う定期券と切符を共に処理する技術がなく、2つの改札機が必要でした。
また、他の鉄道会社との連絡切符は、自動化に未対応。
駅係員がいる改札もなければならず、つまり3タイプの改札があったのです。
それでも、最先端の実験と受け入れた地元住民の協力の元で改良が重ねられました。
やがて、定期券用ときっぷ用改札機は1つになり、磁気式自動改札の共通規格が確立。
他の鉄道会社にも導入され、1990年代に入ると首都圏にも普及します。
21世紀になるとICカードがスタートして、今ではスマートフォンのタッチでも改札通過が可能。
私たちのスムーズな行動を陰で支えてくれています。
自動改札機の進化は止まっていません。
きっぷの主流は磁気式からQRコード式に切り替わる流れがあり
クレジットカードをかざす方式も普及し始めています。
未来の自動改札機は、どうなっているのでしょう。
大阪府吹田市で開業した阪急千里線 北千里駅。
その頃、電気製品による自動改札機の開発が世界で進められていました。
人件費の節減や不正乗車の防止が期待できて労働者不足を補えるからです。
その中で、乗車券の裏に情報を記録し、読みとる磁気式自動改札機が開発されたのは日本。
北千里駅は世界初の実用化として、2007年に電気・電子分野における世界最大の専門家組織
IEEEのマイルストーン賞を受賞。現在、改札内には認定プレートが設置されています。
当初は課題が山積みでした。
求められたのは、増える通勤客の改札通過を早く、効率的にすること。
しかし、大きさが違う定期券と切符を共に処理する技術がなく、2つの改札機が必要でした。
また、他の鉄道会社との連絡切符は、自動化に未対応。
駅係員がいる改札もなければならず、つまり3タイプの改札があったのです。
それでも、最先端の実験と受け入れた地元住民の協力の元で改良が重ねられました。
やがて、定期券用ときっぷ用改札機は1つになり、磁気式自動改札の共通規格が確立。
他の鉄道会社にも導入され、1990年代に入ると首都圏にも普及します。
21世紀になるとICカードがスタートして、今ではスマートフォンのタッチでも改札通過が可能。
私たちのスムーズな行動を陰で支えてくれています。
自動改札機の進化は止まっていません。
きっぷの主流は磁気式からQRコード式に切り替わる流れがあり
クレジットカードをかざす方式も普及し始めています。
未来の自動改札機は、どうなっているのでしょう。