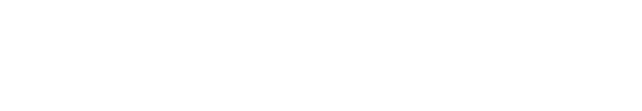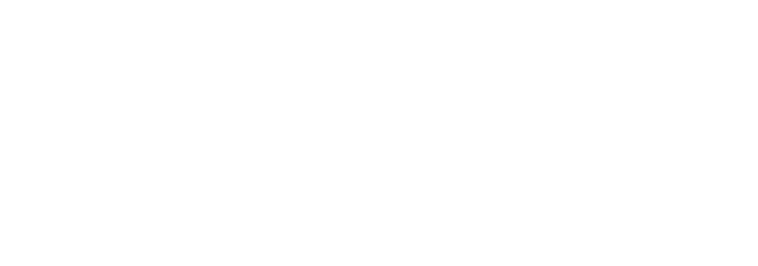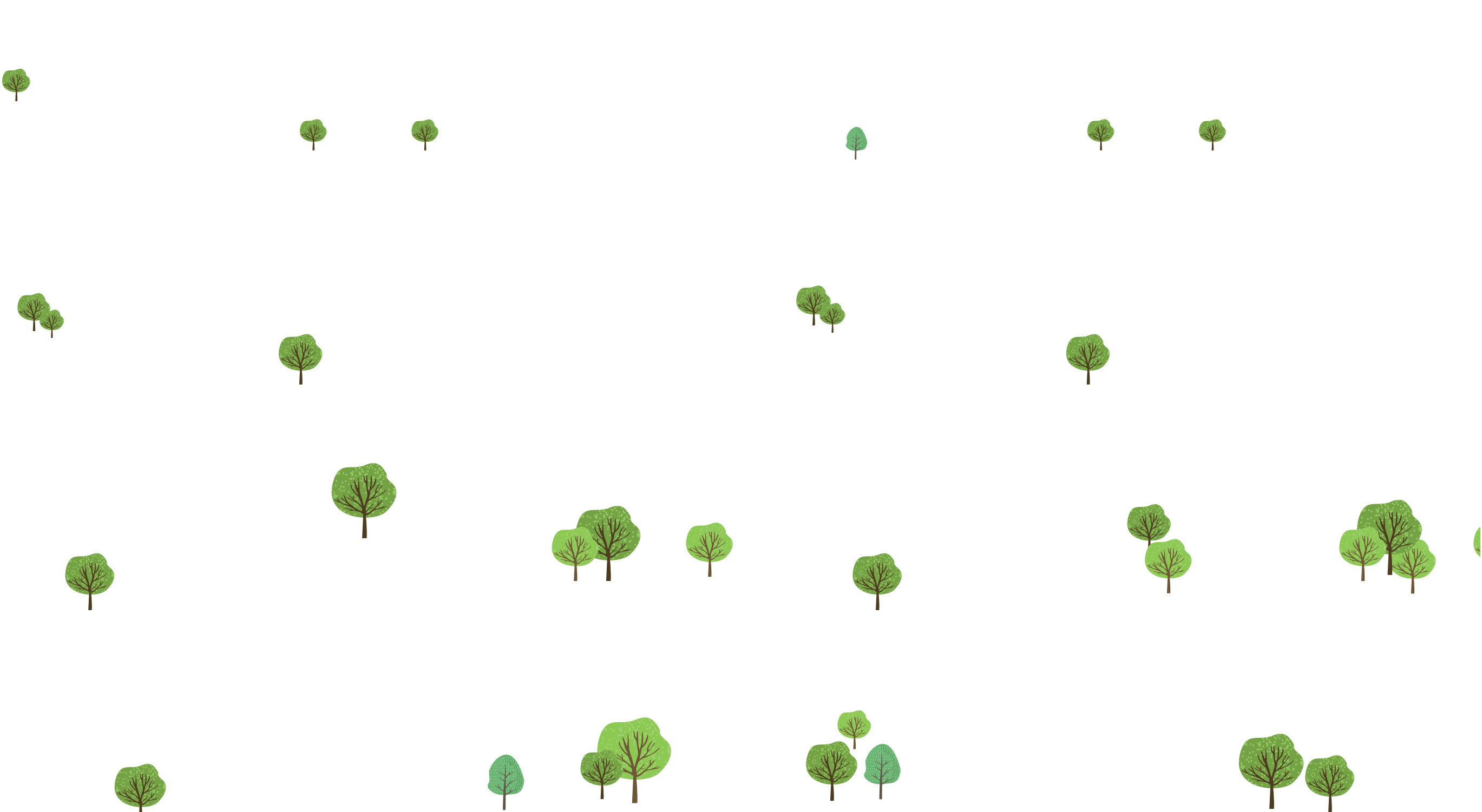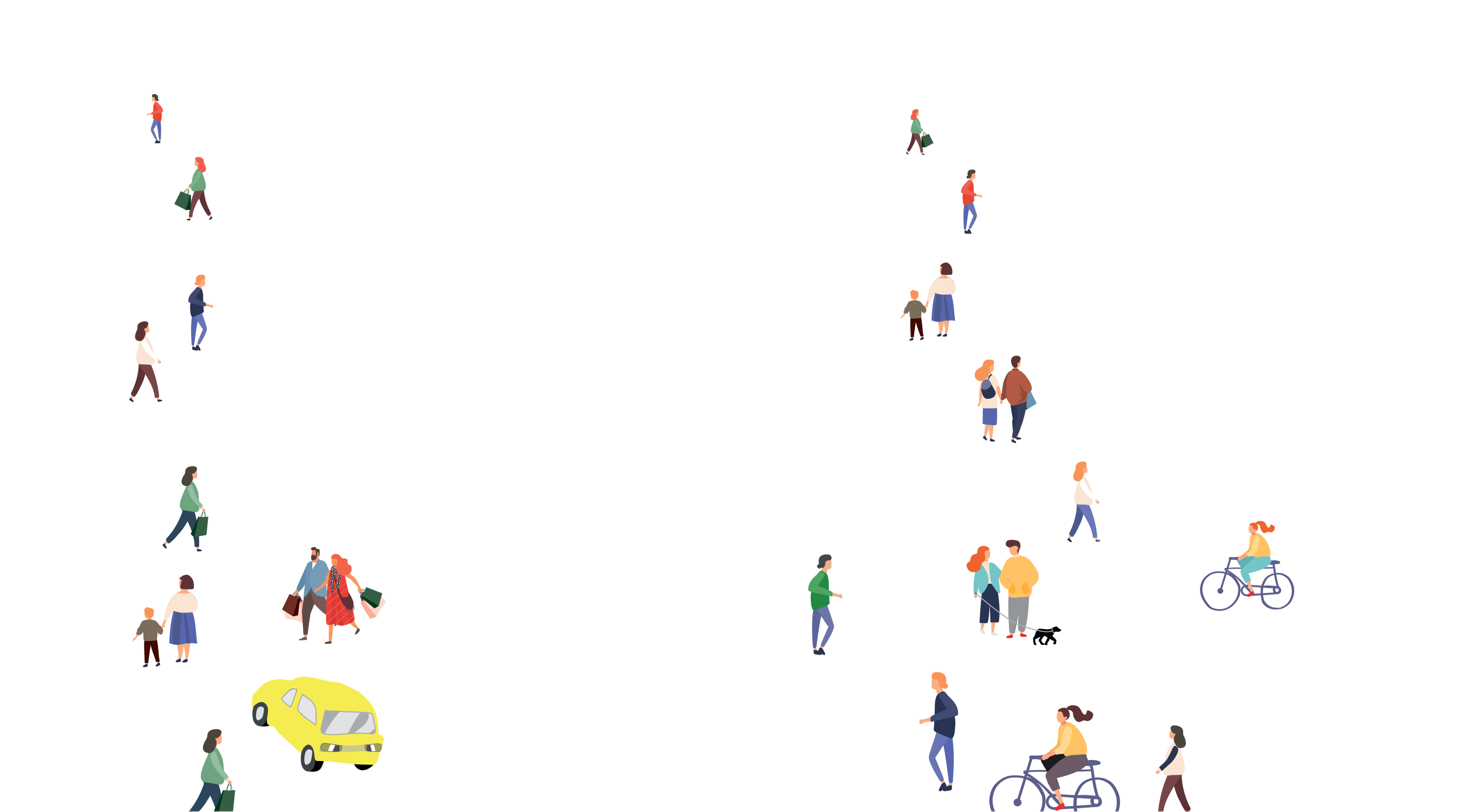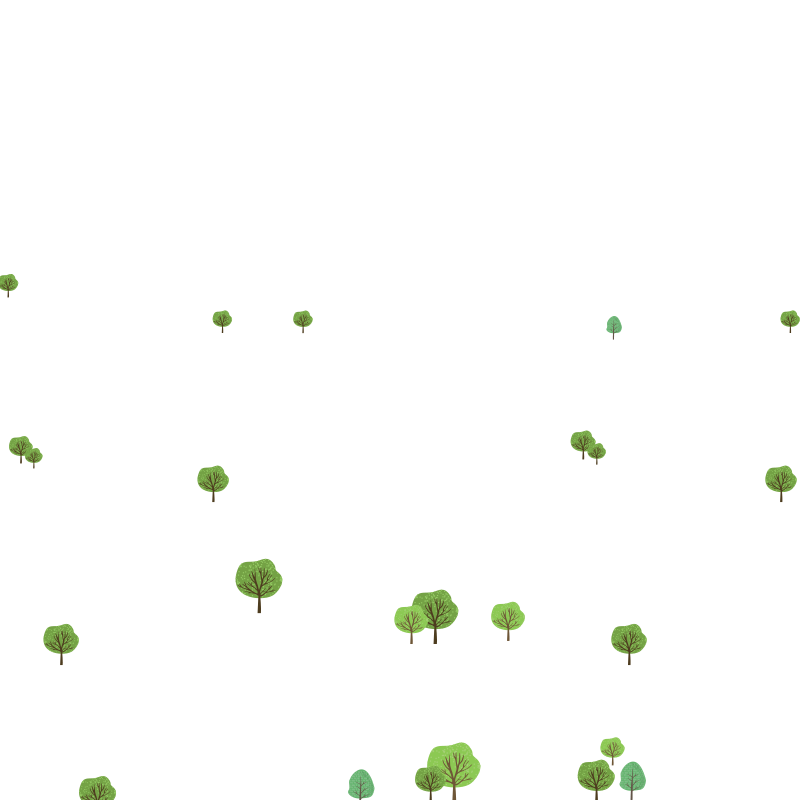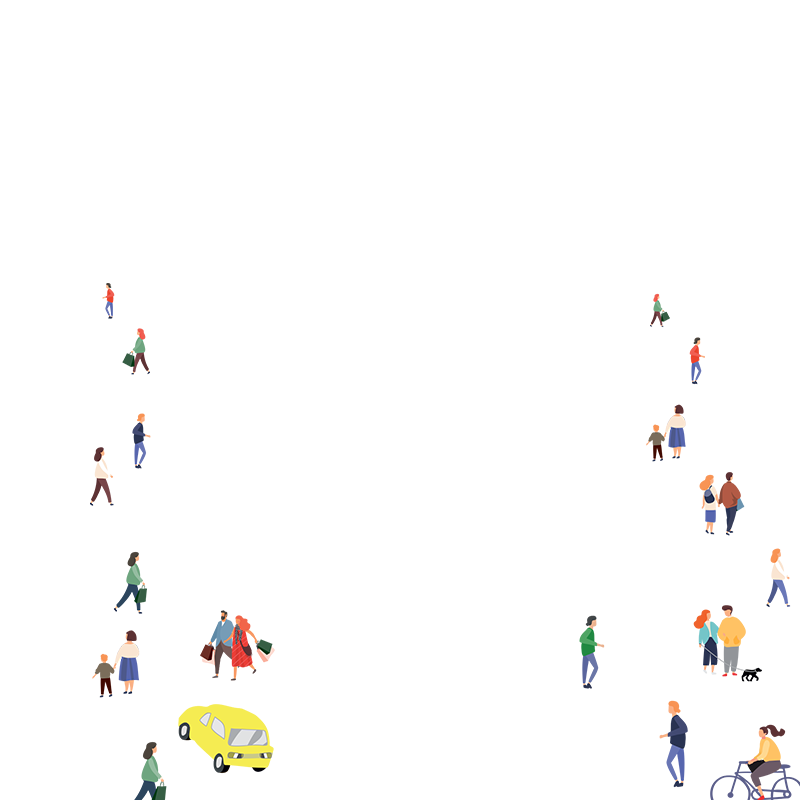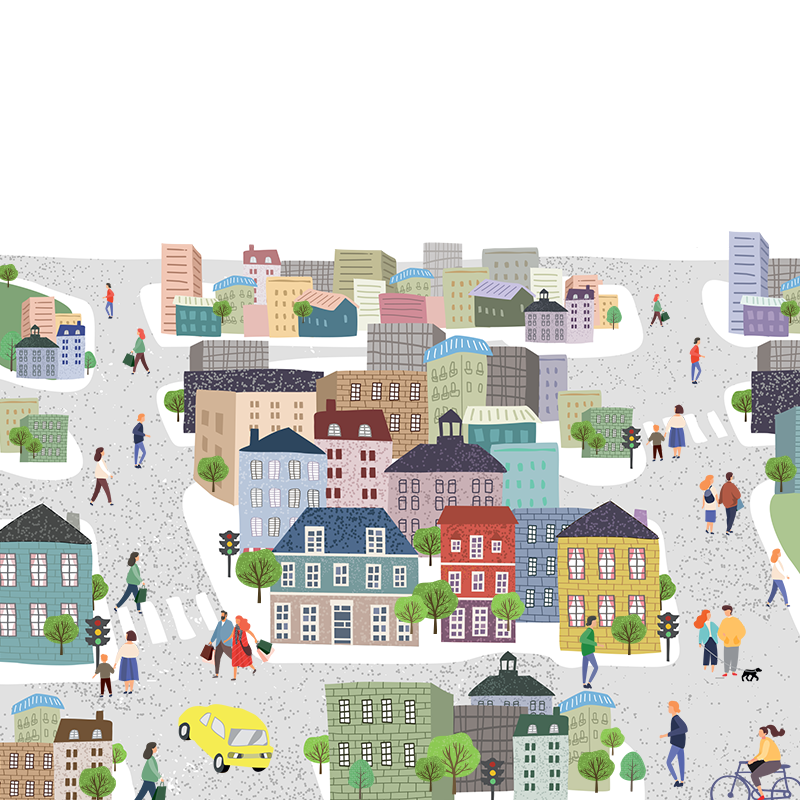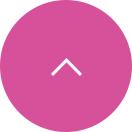第85回 6月1日「水筒」前編
2025.06.01

古の生活には、今のような飲料用の缶やペットボトルはありません。
人類は何千年もの昔から飲み物を持ち運ぶ容器を見出して「水筒」として使ってきました。
素材にしたのは、それぞれの地域の暮らしや特性に合ったもの。
例えば、以前「チーズの物語」でふれたように、
古代アラビア商人が、ミルクを携帯していたのはヤギの胃袋の「水筒」。
また、紀元前3千年頃には既に皮をなめす技術が確立していたと言われていて
ヨーロッパや中国で使われていたのは、動物の皮を縫い合わせた「水筒」。
天然素材としては、北アフリカ原産とされる瓢箪が世界で栽培され「水筒」が作られます。
東アジアでは、竹を「水筒」として利用しました。
長らく日本で使われてきたのは、縄文時代に伝わったとされる瓢箪と主には竹の「水筒」。
竹は軽くて持ち運びやすいことと、おにぎりを包むのも竹の皮だったように
その抗菌作用や腐敗防止効果に気づいていたからだと考えられます。
そんな水筒は、時代とともに装飾品としての要素を持つものも作られるようになりました。
日本では幕府が安定期に入り、産業が発達して町民文化が花開いた江戸時代中期、
庶民も家紋を身につけるようになると、行楽や芝居見物に持っていくための
漆塗りで家紋が入った木製の水筒も登場しています。
そして、明治時代に入った頃には、軽くて丈夫なアルミニウム製の水筒が誕生。
そこからプラスチック製、ステンレス製と水筒の素材は増えるともに機能性も上がっていきます。
戦後の高度経済成長期の頃には、保温タイプの水筒も登場しますが・・・
この続きは後編で。
人類は何千年もの昔から飲み物を持ち運ぶ容器を見出して「水筒」として使ってきました。
素材にしたのは、それぞれの地域の暮らしや特性に合ったもの。
例えば、以前「チーズの物語」でふれたように、
古代アラビア商人が、ミルクを携帯していたのはヤギの胃袋の「水筒」。
また、紀元前3千年頃には既に皮をなめす技術が確立していたと言われていて
ヨーロッパや中国で使われていたのは、動物の皮を縫い合わせた「水筒」。
天然素材としては、北アフリカ原産とされる瓢箪が世界で栽培され「水筒」が作られます。
東アジアでは、竹を「水筒」として利用しました。
長らく日本で使われてきたのは、縄文時代に伝わったとされる瓢箪と主には竹の「水筒」。
竹は軽くて持ち運びやすいことと、おにぎりを包むのも竹の皮だったように
その抗菌作用や腐敗防止効果に気づいていたからだと考えられます。
そんな水筒は、時代とともに装飾品としての要素を持つものも作られるようになりました。
日本では幕府が安定期に入り、産業が発達して町民文化が花開いた江戸時代中期、
庶民も家紋を身につけるようになると、行楽や芝居見物に持っていくための
漆塗りで家紋が入った木製の水筒も登場しています。
そして、明治時代に入った頃には、軽くて丈夫なアルミニウム製の水筒が誕生。
そこからプラスチック製、ステンレス製と水筒の素材は増えるともに機能性も上がっていきます。
戦後の高度経済成長期の頃には、保温タイプの水筒も登場しますが・・・
この続きは後編で。