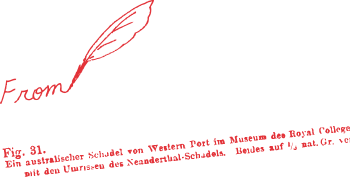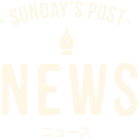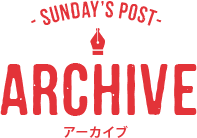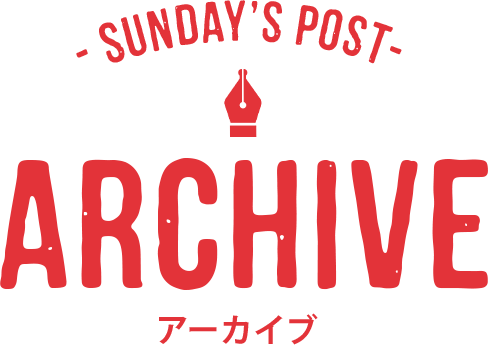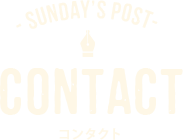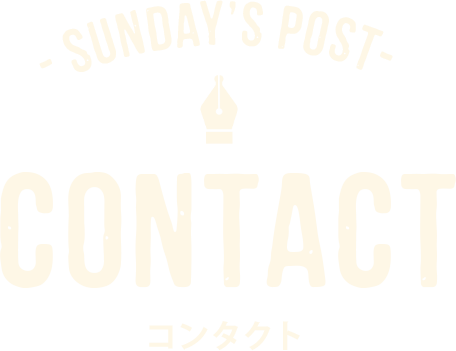齋藤孝さんと『はがきの名文コンクール』のお話
-

- 2020/09/06
教育学者 齋藤孝さんをお迎えして
 以前、番組でもご紹介した、“一言の願い”をテーマにした「はがきの名文コンクール」。今年の締め切りが、9月10日(木曜日)に迫ってきた中、今回は「はがきの名文コンクール」の選考委員でもある、教育学者で明治大学教授の齋藤孝さんにビデオ会議システムを使いお話をうかがいます。
以前、番組でもご紹介した、“一言の願い”をテーマにした「はがきの名文コンクール」。今年の締め切りが、9月10日(木曜日)に迫ってきた中、今回は「はがきの名文コンクール」の選考委員でもある、教育学者で明治大学教授の齋藤孝さんにビデオ会議システムを使いお話をうかがいます。 宇賀「改めて、今年で6回目を迎える『はがきの名文コンクール』をご紹介しますと……はがきに20字以上200字以内で願い事を書いて、応募していただくコンクールです。大賞は1名、賞金100万円が贈られ、佳作には選ばれた10名の方には10万円。そして、日本郵便大賞として10名の方に、1年間、毎月1回『ふるさと小包』が贈呈されます」
宇賀「改めて、今年で6回目を迎える『はがきの名文コンクール』をご紹介しますと……はがきに20字以上200字以内で願い事を書いて、応募していただくコンクールです。大賞は1名、賞金100万円が贈られ、佳作には選ばれた10名の方には10万円。そして、日本郵便大賞として10名の方に、1年間、毎月1回『ふるさと小包』が贈呈されます」小山「“願い”を書いて送るわけですよね。200文字以内だから、非常に書きやすい手紙ではありますよね」
宇賀「齋藤さんは1年目から選考委員をされているんですか?」
齋藤「そうですね」
宇賀「以前、番組にも来ていただいた作家の五木寛之さん、作家の村山由佳さんと選考委員をされていて、どうやって選んでいくんですか?」
齋藤「それぞれが下読みをして、これを大賞に推したいとか候補を持ち寄るんですね。それをホワイトボードにザーッと番号を書いて、重なったものを優先するのですが、重なるものが少ないのが特徴的ですね」
宇賀「それぞれ好みが違うということなんですね」
齋藤「感性というんでしょうかね、心の琴線にそれぞれ触れるところが違うんだと思います。僕なんかは割と戦争の時の話ですとか、障害を持つお子さんを育てられた話とかについ反応しがちなのですが、他の先生方、たとえばこれを始められた堺屋太一さんは“子どもの声”をすごく大切にされていましたね」
 小山「毎年、何通くらいの応募があるんですか?」
小山「毎年、何通くらいの応募があるんですか?」齋藤「多い時には4万通くらいの応募があります。前回は2万7千通くらいですね」
小山「大賞を決めるのは大変じゃないですか?」
齋藤「最後、議論にはなりますね。どれもいいんですよね、短いんですけどグッとくる。グッとくるものが多い中で、この1通を決めるのはなかなか難しいですね。でも何回も読んでいると、『やっぱりこれがいい』と味が出てくるものがあるんですよね。“願いごと”というテーマがありますので、願うという観点から見直した時に『これがいいだろう』、となります」
宇賀「特に印象に残っている作品では、どういうものがありますか?」
齋藤「第1回の大賞は印象に残っています。もうどうやればいいのか、というのがはっきりしない時だったんですね。第1回は山口さんという方がとられました」
↓第1回の大賞作品はこちらのリンクからご覧いただけます。
第1回 大賞作品
齋藤「これは90歳の男性の作品で。亡くなられた方に声を届けたい、というはがきは多いですね」
小山「亡くなられた奥様へ、と聞くとグッと来ますもんね。こんちくしょう、という言葉を使いながら」
齋藤「手書きで書かれる方も多くて、書き方とか字を見ると、風情があるなあと思います」
 小山「去年の齋藤孝賞に選ばれた後藤さんの作品も素晴らしいですね」
小山「去年の齋藤孝賞に選ばれた後藤さんの作品も素晴らしいですね」↓第5回 齋藤孝賞の作品はこちらのリンクからご覧ください。
第5回 齋藤孝賞
小山「素敵なはがきですね」
宇賀「願いごと、というテーマだから、皆さん誰かのことを想った文章なんですね。自分の欲望じゃなくて」
小山「短いのに物語になっていますよね。ショートフィルムを見せられたような気分になります」
齋藤「小山さんにシナリオにしていただきたいですね。これをきっかけにバスの風景から始まる物語をね、『おくりびと』のように(笑)。これのいいところは、長女に向かってはがきを書いているんじゃないんですよね。バスの乗客の皆さんに書かれているところに魅力があるのかなと思います」
他にも、相撲を題材にした第4回 齋藤孝賞の作品が印象に残っているそうです。
↓こちらのリンクからご覧ください。
第4回 齋藤孝賞
齋藤「77歳の方がお父さんを思い出している作品なんですね。僕も父親と相撲を取るのはずっとやっていたので、心惹かれましたね」
小山「77歳になってもそういう想いがあるというのが素敵ですね」
齋藤「じんわりくるんですよね。選ぶ時に、僕は声に出してみることが多いんですね。声に出すとじんわりイメージが湧いてくる、言葉の響きがいいなとか、分かりやすいですね。
さらに、第3回 齋藤孝賞の作品も印象深いそうです。
↓こちらのリンクからご覧ください。
第3回 齋藤孝賞
小山「これは同じ教育者としてどうですか?」
齋藤「素晴らしいですよね。ポケットに煙草の屑が入っていて、それを『お前の兄貴のズボンだろう』と。わかっているんですけどね、先生は。でも『お前はこんなことやらないだろう』というメッセージなんですよね。私は明治大学で教員養成をしているのですが、こんな先生になってくれたら本当に嬉しいです」
小山「今までの応募作品を読み返してみると“願い”というテーマではありますけど、願い=自分はこうしたいというより、誰かのことを強く想っているものが多いですね」
齋藤「そうですね。自分が、というよりも『こうあってほしい』というものが多いですね。相手にこういう風に幸せになってもらいたいという想いがはがきに詰まっていて、読んでいると心がじわっと温まってくる感じなんです」
「第6回 はがきの名文コンクール」、興味のある方はぜひ、ご応募ください。
宛先は、【〒639-2321奈良県 御所市名柄326-1 「はがきの名文コンクール」】。9月10日(木曜日)消印有効です。
詳細はウェブサイトでもご確認いただけます。
はがきの名文コンクール
 宇賀「齋藤さんはたくさん本を出版されていますが、その中に『これなら読める龍馬からの手紙』という本がありまして」
宇賀「齋藤さんはたくさん本を出版されていますが、その中に『これなら読める龍馬からの手紙』という本がありまして」小山「これはタイトルを聞いただけで面白そうですね」
齋藤「龍馬の手紙はすごく数がたくさんありまして。1つひとつ、肉声のように聞こえてくるんですよ。たとえば勝海舟の弟子になった時に、お姉さんに手紙を書くんですね。その時に『エヘンエヘン』という風に書いてあるんですよ」
小山「咳払いから書いてあるんですか?」
齋藤「どんなもんだい、と話す声が聞こえてくるような手紙なんですね。すごい言葉の力だと思いますね。この人が目の前で話したらどれだけ心を持っていかれるんだろう、と」
小山「読んでみたいですね」
齋藤「昔の人はすごく手紙を書いたんですよね。西郷隆盛についての本を書いた時に書簡集を読んだのですが、ものすごい量で。西郷隆盛の人生がほぼわかるくらいでした」
小山「本のタイトルが『これなら読める龍馬からの手紙』じゃないですか。これなら、ということは、普通なら読めないくらいに達筆だったということですか?」
 齋藤「達筆ですし、言葉遣いが古いものですからパッと読んだ時に意味が分かりづらいので、私が口語訳をつけていて。昔の人の手紙を読むのは楽しいですね。その人の生活がグッと出てくるので。著書だとちょっと構えて書きますけど、手紙は構えずに、日常の言葉で書いているので」
齋藤「達筆ですし、言葉遣いが古いものですからパッと読んだ時に意味が分かりづらいので、私が口語訳をつけていて。昔の人の手紙を読むのは楽しいですね。その人の生活がグッと出てくるので。著書だとちょっと構えて書きますけど、手紙は構えずに、日常の言葉で書いているので」宇賀「声が聞こえるように手紙を書くって、参考にしたいですよね」
齋藤「SNSの時代で、新しい日本語の時代が来たと思うんですよね。話すように書くということがいよいよ進んで、声が聞こえるような文体がどんどん進化している。その中で先駆けとして龍馬の手紙がある」
宇賀「世界初のつぶやきだったかもしれないですね」
齋藤「普通、手紙で『エヘンエヘン』って書かないですよね。その中で『今一度日本を洗濯したい』という有名な言葉もあって。文は人なり、と言いますけど、やっぱり人柄は文体にちょっと出るような気がしますね」
そして最後、齋藤さんからはこんな言葉もいただきました。
 齋藤「こういうコロナの状況で、できるだけ皆さんに本をたくさん読んでいただきたいなと思っています。せっかくですから長編ものがいいんじゃないかなと思います。普段、手をつけないような長いものですね。小山さんが出されたもので『お厚いのがお好き?』ってありますよね、大変面白い本で(笑)。厚い本を読んでいただきたいなと」
齋藤「こういうコロナの状況で、できるだけ皆さんに本をたくさん読んでいただきたいなと思っています。せっかくですから長編ものがいいんじゃないかなと思います。普段、手をつけないような長いものですね。小山さんが出されたもので『お厚いのがお好き?』ってありますよね、大変面白い本で(笑)。厚い本を読んでいただきたいなと」小山「ちなみに、先生がいちばんオススメする厚い本はなんですか?」
齋藤「長い物語では『ドン・キホーテ』。すごく長いんですけど、偉大な馬鹿馬鹿しさがあるんです。今の時代、皆さん人の目に敏感ですよね。心が疲れていると思うんです。ドン・キホーテという人は、人の目が気にならない人なんですね。近代小説の祖と言われている作品です」
齋藤孝さん、ありがとうございました!
レターソングプロジェクト with YOASOBI
 YOASOBIと番組がコラボした企画「レターソングプロジェクト with YOASOBI」がスタートしました!
YOASOBIと番組がコラボした企画「レターソングプロジェクト with YOASOBI」がスタートしました!あなたの手紙を、音楽ユニットYOASOBIが歌にするプロジェクト。テーマは〈「ありがとう」を伝える手紙〉。家族に、友だちに、恋人に、それ以外でも。面と向かっては少し気恥ずかしい「ありがとう」を手紙で伝えてみませんか?
ご応募は【郵便番号102-8080 TOKYO FM 「SUNDAY’S POST」レターソングプロジェクト】までお願いします。氏名、住所、電話番号の明記を忘れずにお願いします。締め切りは10月31日です。
詳しい情報は、こちらのページからご確認ください。
レターソングプロジェクト with YOASOBI
今週の後クレ
 今回のメッセージは、埼玉県<吉川郵便局>関根将太さんでした!
今回のメッセージは、埼玉県<吉川郵便局>関根将太さんでした!「配達中に、よく声をかけていただき、ジュースやお菓子をくださるお客さまがいらして、最初は気づかなかったのですが、実は私の中学校時代の担任の先生でした。それ以降、その先生と手紙の交換をするようになり、先生が体調を崩された時に、『教え子と、まさかこうして再会できるとは思わなかった。本当に嬉しい。』という手紙をくださったり、今年、私が子供を授かった時に、その報告を手紙ですることができ、郵便局で働いていて良かったなと思いました。」
MORE

楠田枝里子さんとチョコレートのお話を!
-

- 2026/02/08

小説家 グレゴリー・ケズナジャットさんが登場
-

- 2026/02/01

SUNDAY’S POSTオリジナル! お年玉付き年賀状 抽選発表会
-

- 2026/01/25

この番組ではみなさんからの手紙を募集しています。
全国の皆さんからのお便りや番組で取り上げてほしい場所
を教えてください。
〒102-8080 東京都千代田区麹町1−7
SUNDAY'S POST宛