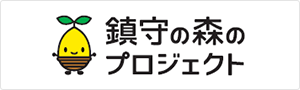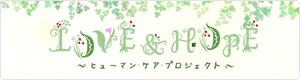- 2013.05.19
”Ö„¢„Ž„¾„ó¤Ī湤ņ¹Ō¤Æ”דŲĢīµČĄ²¤µ¤ó¤ĪĪ¹”Į?
JFN£³£ø¶É·ė¤ó¤Ē¤ŖĮ÷¤ź¤¹¤ė”Ų¤¤¤Ī¤Į¤Īæ¹ voice of forest”Ł”£
¤³¤ĪČÖĮȤĻ”¢”Ö湤ĪĹ¾ė„ׄķ„ø„§„Æ„Č”×¤ņ¤Ļ¤ø¤į”¢
Į“¹ń¤Ė¹¤¬¤ėæ¢ĪÓ³čĘ°¤ä”¢¼«Į³ŹŻøī¤Ī¼č¤źĮȤߤĖ„¹„Ż„ƄȤņÅö¤Ę¤ė
„ׄķ„°„é„ą¤Ē¤¹”£³ĘŹ¬Ģī¤Ī”Ö湤ĪøæĶ”פæ¤Į¤ĪĄ¼¤Ė¼Ŗ¤ņ·¹¤±”¢
æ¹¤Č¶¦Āø¤¹¤ėĄø¤Źż¤ņ¹Ķ¤Ø¤Ę¤¤¤¤Ž¤¹”£
ŗ£½µ¤Ļ”¢³¤³°”Ä¤Č¤Æ¤Ė„¢„Ž„¾„ó¤Ī湤ņĪɤÆĆĪ¤ėŹż¤Ī„¤„ó„æ„ӄ唼¤ņ¤ŖĘĻ¤±¤·¤Ž¤¹”£
¤ŖĻƤņ»Ē¤Ć¤æ¤Ī¤Ļ”¢Ćµø”²Č¤ĒÉšĀ¢ĢīČž½ŃĀē³Ų¤Ī¶µ¼ų”¢“ŲĢīµČĄ²(¤»¤¤Ī”¦¤č¤·¤Ļ¤ė)¤µ¤ó”£
„¢„Õ„ź„«¤ĒĄø¤Ž¤ģ¤ææĶĪą¤¬”¢„ę”¼„é„·„¢ĀēĪ¦¤ņ·Š¤Ę”¢Ęī„¢„į„ź„«¤Ų¤æ¤É¤źĆ夤¤æ
ĶŖµ×¤ĪĪ¹”Ų„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼”Ł”£“ŲĢī¤µ¤ó¤Ļ”¢¤½¤Ī5Ėü„„ķ¤ĪĘ»¤Ī¤ź¤ņ
¤µ¤«¤Ī¤Ü¤ėĪ¹¤ņĄ®¤·æė¤²¤æŹż¤Č¤·¤ĘĆĪ¤é¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£
¼Ā¤Ļ³ŲĄø»žĀ夫¤éĘīŹĘ¤ņĪ¹¤·¤Ę¤¤æ¤Č¤¤¤¦“ŲĢī¤µ¤ó¤¬”¢¤½¤ĪĢܤĒø«¤Ę¤¤æ
„¢„Ž„¾„ó¤Īæ¹ĪÓ¤¬»ż¤ÄĪĻ”¢¼«Į³¤Ī¤·¤Æ¤ß¤Ė¤Ä¤¤¤Ę”¢æ§”¹¶µ¤Ø¤ĘÄŗ¤¤Ž¤·¤æ”£

6ĖüĒÆĮ°¤Ė„¢„Õ„ź„«¤ĒĄø¤Ž¤ģ¤ææĶĪą¤¬”¢5Ėü„„ķ¤ņ·Š¤Ę
ĘīŹĘ¤ĪŗĒĘīĆ¼¤Ė¹Ō¤Ć夤¤æ„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼”£
“ŲĢī¤µ¤ó¤¬”¢¤³¤Ī„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤ņ¤µ¤«¤Ī¤Ü¤ėĪ¹¤ņ¹Ķ¤Ø¤æ¤Ī¤Ļ”¢
ĘīŹĘ”¦„¢„Ž„¾„ó¤Ē½Š²ń¤Ć¤æ”¢ø½ĆĻ¤ĪæĶ”¹¤Ī”Ö“é”פĒ¤·¤æ”£„ā„ó„“„ķ„¤„ɤČ
øʤŠ¤ģ¤ėČą¤é¤Ī“é¤Ļ”¢»ä¤æ¤ĮĘüĖÜæĶ¤Č¶¦ÄĢÅĄ¤¬Ā椤¤ó¤Ą¤½¤¦¤Ē¤¹”£

”Ö„¢„Ž„¾„ó¤Ė¹Ō¤Æ¤Č”¢»÷¤Ę¤¤¤ė¤ļ¤±¤Ē¤¹¤č¤Ķ”¢ĘüĖÜæĶ¤Č“餬”£
“餥¤±¤ø¤ć¤Ź¤ÆĒŲ³Ź¹„¤ä»ÅĮš”¢Ą³Ź¤ā„·„愤¤Ź¤ó¤Ē¤¹”£
„é„Ę„ó„¢„į„ź„«¤Ė½»¤ó¤Ē¤¤¤ė¤Ī¤Ė„é„Ę„ó·Ļ¤Ē¤Ļ¤Ź¤Æ„¢„ø„¢·Ļ¤ĪæĶ¤æ¤Į”£
¤½¤ģ¤Ļ¹Ō¤ÆĮ°¤«¤é¤ļ¤«¤Ć¤Ę¤¤¤æ¤ó¤Ē¤¹¤¬”¢¤ä¤Ć¤Ń¤ź»÷¤Ę¤¤¤Ę¶Ć¤¤¤æ”£
„¢„Ž„¾„ó¤Ėµļ¤ėæĶ¤æ¤Į¤Ī„ė”¼„ĤĻ”¢
„·„Ł„ź„¢¤«¤é„Ł”¼„ź„ó„°³¤¶®¤¬Ī¦Ā³¤¤Ą¤Ć¤æŗ¢¤Ė„Ž„ó„ā„¹¤ä„Č„Ź„«„¤¤ņÄɤ¤¤«¤±¤Ę„¢„į„ź„«ĀēĪ¦¤ŲÅĻ¤Ć¤Ę¤·¤Ž¤Ć¤ææĶ¤ø¤ć¤Ź¤¤¤«¤Č”£
»Ä¤Ć¤ææĶ¤ā¤¤¤ė¤ļ¤±¤Ą¤¬Ęī²¼¤·¤ææĶ¤ā¤¤¤ė¤«¤é”¢
¤½¤¦¤¤¤¦æĶ¤æ¤Į¤Ą¤«¤é»÷¤Ę¤¤¤ė¤Ī¤ĻÅö¤æ¤źĮ°¤Ē¤¹¤Ķ”£”×
¤É¤¦¤·¤Ę„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤Č¤¤¤¦Ī¹¤ņ»Ļ¤į¤æ¤Ī¤«”¢“ŲĢī¤µ¤ó¤Ė¤Ŗ»Ē¤¤¤·¤Ž¤·¤æ”£
”Ö20ĒÆ“Ö¤Ė¤ļ¤æ¤Ć¤Ę„¢„Ž„¾„ó¤ä„¢„ó„Ē„¹”¢„Ń„æ„“„Ė„¢¤ĪĄč½»Ģ±¤ČÉÕ¤¹ē¤Ć¤Ę¤¤¤ė¤¦¤Į¤Ė”¢
¤³¤ĪæĶ¤æ¤Į¤¬¤¤¤Ä¤É¤Ī¤č¤¦¤Ė¤·¤Ę”¢¤Ź¤¼¤ä¤Ć¤Ę¤¤æ¤Ī¤«¤ņĆĪ¤ėĪ¹¤ņ¤·¤æ¤¤¤Č»×¤Ć¤Ę»Ļ¤į¤æ¤Ī¤¬„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤Ź¤ó¤Ē¤¹”£
„“”¼„ė¤Ļ„¢„Õ„ź„«”£
„¢„Õ„ź„«¤ĒĄø¤Ž¤ģ¤Ę„č”¼„ķ„Ć„Ń”¢„Ŗ„»„¢„Ė„¢”¢ĘüĖÜĪóÅē¤ĖĶč¤ææĶ¤ā¤¤¤ė¤±¤ģ¤É”¢
°ģČÖ±ó¤Æ¤Ž¤Ē¹Ō¤Ć¤æ¤Ī¤¬„¢„Õ„ź„«ČÆ”¢„·„Ł„ź„¢”¢„¢„鄹„«·ŠĶ³”¢ĘīŹĘŗĒĘīĆ¼”£
¤½¤ĪĪ¹Ļ©¤ņ„¤„®„ź„¹æĶ¹ĶøųŲ¼Ō¤¬„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤ČĢ¾ÉÕ¤±¤æ¤ó¤Ē¤¹”£
ĘīŹĘ¤ĪĄč½»Ģ±¤æ¤Į¤¬¤¤¤Ä¤É¤Ī¤č¤¦¤Ė¤·¤Ę¤ä¤Ć¤Ę¤¤æ¤Ī¤«¤ČøĄ¤¦ČÆĮŪ¤Ē¤ä¤Ć¤Ę¤¤æ¤«¤éµÕ„ė”¼„ȤĖ¤Ź¤Ć¤æ¤Ī¤Ē¤¹”£
„ė”¼„ė¤ņ·č¤į¤Ę”¢½ŠĶč¤ė¤Ą¤±ĀĄøŤĪæĶ¤ĖĮŪ¤¤¤ņĆŚ¤»¤Ź¤¬¤é”¢ĀĄøŤĪæĶ¤æ¤Į¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ĮŪ¤¤¤ĒĪ¹¤ņ¤·¤æ¤Ī¤«”£
É÷¤ä½ė¤µ“ؤµ”¢½¤¤¤äŌ¼¤ņĀĄøŤĪæĶ¤æ¤Į¤Čʱ¤ø¤č¤¦¤ĖøŽ“¶¤Ē“¶¤ø¤Ź¤¬¤éĪ¹¤¬¤·¤æ¤«¤Ć¤æ¤«¤é”¢
¼«Ź¬¤ĪĻÓĪĻ¤äµÓĪĻ¤Ē¤ä¤Ć¤æ”£
¤æ¤Ą”¢„Č„Ź„«„¤¤äø¤¤ä„é„Æ„Ą”¢„¦„Ž¤ĻĄĪ¤ĪæĶ¤ā»Č¤Ć¤Ę¤¤¤æ¤Ą¤ķ¤¦¤«¤é”¢¤½¤ģ¤ņ¼«Ź¬¤Ē¤Æ¤Æ¤ģ¤ģ¤Š¤¤¤¤¤Č¤¤¤¦„ė”¼„ė¤Ė¤·¤æ”£
ĄĪ¤ĪæĶ¤¬¤ä¤Ć¤æĪ¹¤¬„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤Ź¤Ī¤Ē”¢ĖĶ¤¬¤ä¤Ć¤æ¤Ī¤Ļ„ׄ鄤„Ł”¼„Č„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼”¢„Ž„¤„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤ČøĄ¤Ć¤æŹż¤¬Īɤ¤¤«¤ā¤·¤ģ¤Ž¤»¤ó”£”×
“ŲĢī¤µ¤ó¤Ļ”¢¤³¤Ī„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤ĪĪ¹¤Ė½Š¤ėĮ°¤«¤é”¢
²æÅŁ¤ā„¢„Ž„¾„ó¤ņĖ¬¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£
„¢„Ž„¾„óĄīĪ®°č¤Ė¹¤¬¤ėĒ®ĀÓ±«ĪÓ¤ĪµšĀē¤Źæ¹ĪӤȔ¢
¤½¤³¤ĒĄø¤¤ėĄč½»Ģ±¤æ¤Į¤ČĄÜ¤¹¤ėĆę”¢“ŲĢī¤µ¤ó¤¬“¶¤ø¤æ¤³¤Č¤ņ»Ē¤¤¤Ž¤·¤æ”£

”ÖŗĒ½é¤Ė“¶¤ø¤æ¤Ī¤Ļ”¢æ¹¤ĪĆę¤Ē¼ž¤ź¤ņø«¤ė¤Čʱ¤øĢŚ¤ņø«¤ė¤Ī¤Ė¶ģĻ«¤¹¤ė¤Č¤¤¤¦¤³¤Č”£
槤ó¤ŹĢŚ¤¬Ąø¤Ø¤Ę¤¤¤ė”£
¤Ź¤¼¤«¤Č¤¤¤¦¤Č”¢Ę±¤øĢŚ¤¬Ąø¤Ø¤Ę¤¤¤æ¤éŗ¬¤ĪÄ„¤źŹż¤āʱ¤ø¤Ēʱ¤ø±ÉĶܤņ¼č¤ė¤æ¤į”֤Ĥ֤·¤¢¤¦”פ«¤é”£
°ć¤¦ĢŚ¤¬Ąø¤Ø¤ė¤³¤Č¤Ē”¢ŗ¬¤ĪÄ„¤źŹż¤ā±ÉĶܤā°ć¤¦¤æ¤į¤Ŗøߤ¤¤Ė¾ł¤ź¹ē¤Ć¤Ę”¢¤³¤ó¤ā¤ź¤·¤æ湤¬ĪŠ¤Ī¤ø¤å¤¦¤æ¤ó¤Ī¾å¤Ė¤Ē¤¤ė¤ó¤Ē¤¹”£
¼Ā¤Ļ„¢„Ž„¾„ó¤ĪÅŚ¤ĻÉåĶÕÅŚ¤¬Ēö¤ÆÉĻ¤·¤¤¤¬”¢æ¢ŹŖ¤¬ĀæĶĶ¤Ē¤¢¤ė¤³¤Č¤Ē¤Ź¤ó¤Č¤«¤Ź¤Ć¤Ę¤¤¤ė”£
¤½¤ģ¤¬Ēķ¤¬¤µ¤ģ¤Ę¤·¤Ž¤¦”ÄĀēµ¬ĢĻ¤ŹĒĄ±ą¤ņŗī¤Ć¤æ¤źµķ¤ņ»ō¤¦¤æ¤į¤ĖĢŚ¤ņĮ“¤ĘĄŚ¤Ć¤Ę¤·¤Ž¤¦¤Č”¢Ä¾¼ĶĘüø÷¤¬¤¢¤æ¤ź±«µÓ¤Ī¶Æ¤µ¤ĒĶÜŹ¬¤¬¾Ć²½¤µ¤ģ¤æ¤źĪ®¤µ¤ģ¤Ę¤·¤Ž¤¦¤³¤Č¤Ēŗ½Ēł²½¤·¤Ę¤·¤Ž¤¦”£
¤½¤ģ¤ņ„¢„Ž„¾„ó¤ĪæĶ¤æ¤Į¤Ļ¾å¼ź¤Æææ»÷¤·¤Ę¤¤¤ė¤Ē¤¹¤č”£
ĢŚ¤ņĮ“ÉōĄŚ¤é¤Ź¤¤¤Ē”¢„Ń„¤„Ź„Ƅׄė¤ä„Č„¦„ā„ķ„³„·”¢„Š„Ź„Ź¤ä„¤„ā¤Ź¤Éæ§¤ó¤Ź¤ā¤Ī¤ņ梤ؤė¤Č¤¤¤¦¤Ī¤Ļ”¢æ¹¤Īææ»÷¤ņ¤·¤Ę¤¤¤ė¤Č¤¤¤¦¤³¤Č”£
¾Ę¤ČŖ¤¬°¤¤¤³¤Č¤Ą¤ČøĄ¤ļ¤ģ¤ė¤¬”¢æ¹¤ņææ»÷¤·¤æ¤ä¤źŹż”£¤³¤ĪæĶ¤æ¤Į¤ĻĄøĀÖ³Ų¼Ō¤Ź¤Ī¤«¤ČøĄ¤¦¤Æ¤é¤¤»żĀ³²ÄĒ½¤ŹĒĄĖ”¤ņ¤ä¤Ć¤Ę¤¤¤ė¤ó¤Ē¤¹¤Ķ”£”×
¤Ź¤ó¤«”¢”Ö湤ĪĹ¾ė„ׄķ„ø„§„Æ„Č”×¤Ī»ŲĘīĢņ”¢
µÜĻĘĄčĄø¤¬¾§¤Ø¤Ę¤¤¤ė”ÖĄųŗß¼«Į³æ¢ĄøĶżĻĄ”פĖ»÷¤Ę¤ė¤č¤¦¤Ź„„„”£
„¢„Ž„¾„ó¤ĪæĶ¤æ¤Į¤Ļ”¢
”Ö湤Čʱ¤ø¤č¤¦¤Ė”¢æ§¤ó¤Ź¤ā¤Ī¤ņ梤ؤæ¤Ū¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤ø¤ć¤Ź¤¤¤«”פȔ¢
¤ŗ¤Ć¤ČĄĪ¤Ėµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Ę¤¤¤æ¤ó¤Ē¤¹¤Ķ”£
¤½¤Ī°ģŹż”¢“ŲĢī¤µ¤ó¤Ļ”¢
湤ĪĆę¤ĒĘ°ŹŖ¤ņ¼ķ¤ź”¢ĢŚ¤Ī¼Ā¤ņ¼č¤Ć¤ĘŹė¤é¤¹Ąč½»Ģ±¤ĪĄø³č¤āø«¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£
¤½¤³¤Ē“¶¤ø¤æ¤Ī¤Ļ”¢Čą¤é¤ČĘüĖÜæĶ¤ĪĄø¤Źż”¦¹Ķ¤ØŹż¤ĪĀē¤¤Ź°ć¤¤¤Ē¤¹”£
”ÖČą¤é¤Ī¤¹¤“¤¤¤Ī¤Ļ”¢ĀĄ×¤ņø«¤Ę¤¤¤Ä¤Ī¤ā¤Ī¤«Ź¬¤«¤ė¤Č¤¤¤¦¤³¤Č”£
¤Į¤ē¤Ć¤Č¤Ų¤³¤ß¤¬¤¢¤ė¤Č¤É¤ó¤ŹĘ°ŹŖ¤Ź¤Ī¤«¤ā¤ļ¤«¤ė¤ó¤Ē¤¹”£
„Š„Ƥņø«¤Ä¤±¤ė¤Č”¢„Š„ƤĻĀēĀĪʱ¤ø„³”¼„¹¤ņÄĢ¤¦¤Ī¤Ē”¢¤½¤ģ¤ņÄɤ¤¤«¤±¤ė”£
Ę°ŹŖ¤Ė¤č¤Ć¤Ę¤Ļ°ć¤¦Źā¤Źż¤ņ¤¹¤ė”£µŻĢš¤ĒµŽ½ź¤Ė¤¢¤æ¤Ć¤Ę¤ā¤¹¤°¤Ė¤Ļ»ą¤Ź¤Ź¤¤”£·ģ¤ņ½Š¤·¤ĘŹā¤¤¤Ę¤¤¤Æ”£
ĀĄ×¤Č·ģŗƤņø«¤Ź¤¬¤éÄɤ¤¤«¤±¤Ę”¢½Š·ģ»ą¤¹¤ė¤Ī¤ņÄɤ¤¤«¤±¤Ę¤Č¤É¤į¤ņ»É¤·¤ĘŹį¤Ž¤Ø¤ė”£
¤Ą¤«¤é湤äĘ°ŹŖ¤ņ¤Į¤ć¤ó¤ČĆĪ¤é¤Ź¤¤¤Č¤Č¼ķ¤ź¤Ļ½ŠĶ褏¤¤¤Ī¤Ē¤¹”£
¤¤¤Ä¤āʱ¤ø¤ø¤ć¤Ź¤¤¤«¤éĮĻ°Õ¹©É×”¢ĆĪ·Ć”¢ĮŪĮüĪĻ¤¬É¬ĶפĒ¤¹”£
„¢„Ž„¾„ó¤ĪĢ±¤Ļ”¢ĖÜÅö¤Ė¼ķ¤ź¤ņ¹„¤¤Ē¤ä¤Ć¤Ę¤¤¤ė”£“ī”¹¤Č¤·¤Ę„ļ„Æ„ļ„Ƥä¤Ć¤Ę¤¤¤ė”£
¤½¤ģ¤Ļ”¢ĒĄ¹ĢĢ±¤Č¤Ļ°ć¤¦¤ó¤Ē¤¹”£
ĒĄ¹ĢĢ±¤ĻĢĢĒņ¤Æ¤Ź¤¤”£
¼ļ¤ņ¤Ž¤¤¤ĘÉĤņæ¢¤Ø¤Ę»ØĮš¤ņ¼č¤Ć¤Ę¤Č¤¤¤¦¤Ī¤Ļ³Ś¤·¤Æ¤Ź¤¤”£
²æ¤«·īøå1ĒÆøå¤Ī¼ż³Ļ¤Ī¤æ¤į¤Ėŗ£¤Īŗī¶Č¤ņ¤·¤Ę¤¤¤ė”£
¤½¤ģ¤¬æ¹¤Ī¾ģ¹ē¤Ļ¤½¤ĪĘü¤Ī¤¦¤Į¤ĖĢŚ¤Ī¼Ā¤Ļ¼č¤ģ¤ė¤·”¢Ę°ŹŖ¤āµū¤ā³Ķ¤ģ¤ė”£
Ąø¤Źż¤¬°ć¤¦¤ó¤Ē¤¹”£
湤ĖĄø¤¤ėæĶ¤Ļŗ£¤ņĀēĄŚ¤Ė¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£
ŗ£¤ņĄø¤Ąø¤¤ČĢ£¤ļ¤Ć¤ĘĄø¤¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£
¤æ¤Ą¤·¾Ķč¤ĪĢ“¤ß¤æ¤¤¤Ź¤ā¤Ī¤ņ¤ā¤æ¤Ź¤¤¤Č¤¤¤¦·¹øž¤Ļ¤¢¤ź¤Ž¤¹”£
²ę”¹¤Ī¾šŹó¼Ņ²ń¤Ī¤ā¤Č¤ĻĒĄ¶Č¤¬“šČ×”£
¤½¤Ī±Ę¶Į¤¬Ķč¤Ę¤¤¤Ę”¢¾Ķč¤Ī¤æ¤į¤ĖĄø¤¤Ę¤¤¤ė”£
¶ĖĆ¼¤ŹĻƤņ¤¹¤ė¤Č¾®³Ų¹»¤ĖĘž¤ėĮ°¤Ė¤¤¤¤¾®³Ų¹»”¢Ćę³Ų¹»”¢Āē³Ų”¢Īɤ¤½¢æ¦Ąč”¢Īɤ¤„Ż„¹„Ȥņ“ź¤¤¤Ž¤¹¤č¤Ķ”£
µ¤¤¬¤Ä¤¤¤æ¤é”Ö²¶¤Ļ¤Ź¤ó¤Ī¤æ¤į¤ĖĄø¤¤Ę¤¤¤æ¤ó¤Ą”פȤ¤¤¦¤³¤Č¤Ė¤Ź¤ź¤«¤Ķ¤Ź¤¤”£
Ģ“¤Ļ»ż¤Ę¤ė¤¬²¼¼ź¤¹¤ė¤ČĢ¤Ķ褊¤«¤źø«¤ĘĄø¤¤Ęŗ£¤ņĀēĄŚ¤Ė¤·¤Ę¤¤¤Ź¤¤¤Č¤¤¤¦¤Č¤³¤ķ¤¬¤¢¤ė”£
湤ĪæĶ“Ö¤Ļ”¢Ąø¤¤¬¤¤¤¬¤Ź¤¤¤ļ¤±¤ø¤ć¤Ź¤¤”£
»Ņ¤É¤ā¤æ¤Į¤ņ°é¤Ę”¢¤ß¤ó¤Ź¤ČĆēĪɤƤä¤Ć¤Ę²Ī¤ņ²Ī¤¤ĶŁ¤ė”£Ąø¤¤¬¤¤¤Ļ¤¢¤ė”£
¤æ¤Ą”¢¤½¤ģ¤Ļ±ó¤¤Ģ¤Ķč¤Ē¤Ļ¤Ź¤¤”£
ŗ£¤ņĀēĄŚ¤Ė¤¹¤ė¤Č¤¤¤¦°ÕĢ£¤Ē¤Ļ湤ĪæĶ¤æ¤Į¤Ė¤ĻÅؤļ¤Ź¤¤”£
ĖĶ¤æ¤Į¤Ė¤ĻĢ“¤ņ»ż¤Ä”¢Ąø¤¤¬¤¤¤ņ»ż¤Ä¤Č¤¤¤¦°ć¤¦ÅžĆ£ÅĄ¤¬¤¢¤ė”£
¤æ¤Ą”¢¤ā¤¦¤Į¤ē¤Ć¤Čŗ£¤ņĀēĄŚ¤Ė¤·¤æŹż¤¬¤¤¤¤¤ó¤ø¤ć¤Ź¤¤¤«¤Č¤ā»×¤¦”£”×
¤Ź¤ė¤Ū¤É”Į”Į”Ŗ
”Öŗ£¤ņĄø¤¤ė„¢„Ž„¾„ó¤ĪĢ±”פȔÖĢ¤Ķč¤Ī°Ł¤Ėŗ£¤ņ²į¤“¤¹»ä¤æ¤Į”×”£
漤¤¤Ē¤¹”Ŗ”Ŗ
Ķč½µ¤ā”¢¤³¤ĪĀ³¤¤ņ¤ŖĮ÷¤ź¤·¤Ž¤¹¤Ķ”Ŗ
“ŲĢī¤µ¤ó¤ĪĶ„¤·¤¤øģ¤źøż¤ņŹ¹¤¤æ¤¤æĶ¤Ļ”¢„Ż„Ć„Č„„ć„¹„ȤĒ¤Ŗ³Ś¤·¤ß²¼¤µ¤¤”£
¤³¤ĪČÖĮȤĻ”¢”Ö湤ĪĹ¾ė„ׄķ„ø„§„Æ„Č”×¤ņ¤Ļ¤ø¤į”¢
Į“¹ń¤Ė¹¤¬¤ėæ¢ĪÓ³čĘ°¤ä”¢¼«Į³ŹŻøī¤Ī¼č¤źĮȤߤĖ„¹„Ż„ƄȤņÅö¤Ę¤ė
„ׄķ„°„é„ą¤Ē¤¹”£³ĘŹ¬Ģī¤Ī”Ö湤ĪøæĶ”פæ¤Į¤ĪĄ¼¤Ė¼Ŗ¤ņ·¹¤±”¢
æ¹¤Č¶¦Āø¤¹¤ėĄø¤Źż¤ņ¹Ķ¤Ø¤Ę¤¤¤¤Ž¤¹”£
ŗ£½µ¤Ļ”¢³¤³°”Ä¤Č¤Æ¤Ė„¢„Ž„¾„ó¤Ī湤ņĪɤÆĆĪ¤ėŹż¤Ī„¤„ó„æ„ӄ唼¤ņ¤ŖĘĻ¤±¤·¤Ž¤¹”£
¤ŖĻƤņ»Ē¤Ć¤æ¤Ī¤Ļ”¢Ćµø”²Č¤ĒÉšĀ¢ĢīČž½ŃĀē³Ų¤Ī¶µ¼ų”¢“ŲĢīµČĄ²(¤»¤¤Ī”¦¤č¤·¤Ļ¤ė)¤µ¤ó”£
„¢„Õ„ź„«¤ĒĄø¤Ž¤ģ¤ææĶĪą¤¬”¢„ę”¼„é„·„¢ĀēĪ¦¤ņ·Š¤Ę”¢Ęī„¢„į„ź„«¤Ų¤æ¤É¤źĆ夤¤æ
ĶŖµ×¤ĪĪ¹”Ų„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼”Ł”£“ŲĢī¤µ¤ó¤Ļ”¢¤½¤Ī5Ėü„„ķ¤ĪĘ»¤Ī¤ź¤ņ
¤µ¤«¤Ī¤Ü¤ėĪ¹¤ņĄ®¤·æė¤²¤æŹż¤Č¤·¤ĘĆĪ¤é¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£
¼Ā¤Ļ³ŲĄø»žĀ夫¤éĘīŹĘ¤ņĪ¹¤·¤Ę¤¤æ¤Č¤¤¤¦“ŲĢī¤µ¤ó¤¬”¢¤½¤ĪĢܤĒø«¤Ę¤¤æ
„¢„Ž„¾„ó¤Īæ¹ĪÓ¤¬»ż¤ÄĪĻ”¢¼«Į³¤Ī¤·¤Æ¤ß¤Ė¤Ä¤¤¤Ę”¢æ§”¹¶µ¤Ø¤ĘÄŗ¤¤Ž¤·¤æ”£

6ĖüĒÆĮ°¤Ė„¢„Õ„ź„«¤ĒĄø¤Ž¤ģ¤ææĶĪą¤¬”¢5Ėü„„ķ¤ņ·Š¤Ę
ĘīŹĘ¤ĪŗĒĘīĆ¼¤Ė¹Ō¤Ć夤¤æ„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼”£
“ŲĢī¤µ¤ó¤¬”¢¤³¤Ī„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤ņ¤µ¤«¤Ī¤Ü¤ėĪ¹¤ņ¹Ķ¤Ø¤æ¤Ī¤Ļ”¢
ĘīŹĘ”¦„¢„Ž„¾„ó¤Ē½Š²ń¤Ć¤æ”¢ø½ĆĻ¤ĪæĶ”¹¤Ī”Ö“é”פĒ¤·¤æ”£„ā„ó„“„ķ„¤„ɤČ
øʤŠ¤ģ¤ėČą¤é¤Ī“é¤Ļ”¢»ä¤æ¤ĮĘüĖÜæĶ¤Č¶¦ÄĢÅĄ¤¬Ā椤¤ó¤Ą¤½¤¦¤Ē¤¹”£

”Ö„¢„Ž„¾„ó¤Ė¹Ō¤Æ¤Č”¢»÷¤Ę¤¤¤ė¤ļ¤±¤Ē¤¹¤č¤Ķ”¢ĘüĖÜæĶ¤Č“餬”£
“餥¤±¤ø¤ć¤Ź¤ÆĒŲ³Ź¹„¤ä»ÅĮš”¢Ą³Ź¤ā„·„愤¤Ź¤ó¤Ē¤¹”£
„é„Ę„ó„¢„į„ź„«¤Ė½»¤ó¤Ē¤¤¤ė¤Ī¤Ė„é„Ę„ó·Ļ¤Ē¤Ļ¤Ź¤Æ„¢„ø„¢·Ļ¤ĪæĶ¤æ¤Į”£
¤½¤ģ¤Ļ¹Ō¤ÆĮ°¤«¤é¤ļ¤«¤Ć¤Ę¤¤¤æ¤ó¤Ē¤¹¤¬”¢¤ä¤Ć¤Ń¤ź»÷¤Ę¤¤¤Ę¶Ć¤¤¤æ”£
„¢„Ž„¾„ó¤Ėµļ¤ėæĶ¤æ¤Į¤Ī„ė”¼„ĤĻ”¢
„·„Ł„ź„¢¤«¤é„Ł”¼„ź„ó„°³¤¶®¤¬Ī¦Ā³¤¤Ą¤Ć¤æŗ¢¤Ė„Ž„ó„ā„¹¤ä„Č„Ź„«„¤¤ņÄɤ¤¤«¤±¤Ę„¢„į„ź„«ĀēĪ¦¤ŲÅĻ¤Ć¤Ę¤·¤Ž¤Ć¤ææĶ¤ø¤ć¤Ź¤¤¤«¤Č”£
»Ä¤Ć¤ææĶ¤ā¤¤¤ė¤ļ¤±¤Ą¤¬Ęī²¼¤·¤ææĶ¤ā¤¤¤ė¤«¤é”¢
¤½¤¦¤¤¤¦æĶ¤æ¤Į¤Ą¤«¤é»÷¤Ę¤¤¤ė¤Ī¤ĻÅö¤æ¤źĮ°¤Ē¤¹¤Ķ”£”×
¤É¤¦¤·¤Ę„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤Č¤¤¤¦Ī¹¤ņ»Ļ¤į¤æ¤Ī¤«”¢“ŲĢī¤µ¤ó¤Ė¤Ŗ»Ē¤¤¤·¤Ž¤·¤æ”£
”Ö20ĒÆ“Ö¤Ė¤ļ¤æ¤Ć¤Ę„¢„Ž„¾„ó¤ä„¢„ó„Ē„¹”¢„Ń„æ„“„Ė„¢¤ĪĄč½»Ģ±¤ČÉÕ¤¹ē¤Ć¤Ę¤¤¤ė¤¦¤Į¤Ė”¢
¤³¤ĪæĶ¤æ¤Į¤¬¤¤¤Ä¤É¤Ī¤č¤¦¤Ė¤·¤Ę”¢¤Ź¤¼¤ä¤Ć¤Ę¤¤æ¤Ī¤«¤ņĆĪ¤ėĪ¹¤ņ¤·¤æ¤¤¤Č»×¤Ć¤Ę»Ļ¤į¤æ¤Ī¤¬„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤Ź¤ó¤Ē¤¹”£
„“”¼„ė¤Ļ„¢„Õ„ź„«”£
„¢„Õ„ź„«¤ĒĄø¤Ž¤ģ¤Ę„č”¼„ķ„Ć„Ń”¢„Ŗ„»„¢„Ė„¢”¢ĘüĖÜĪóÅē¤ĖĶč¤ææĶ¤ā¤¤¤ė¤±¤ģ¤É”¢
°ģČÖ±ó¤Æ¤Ž¤Ē¹Ō¤Ć¤æ¤Ī¤¬„¢„Õ„ź„«ČÆ”¢„·„Ł„ź„¢”¢„¢„鄹„«·ŠĶ³”¢ĘīŹĘŗĒĘīĆ¼”£
¤½¤ĪĪ¹Ļ©¤ņ„¤„®„ź„¹æĶ¹ĶøųŲ¼Ō¤¬„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤ČĢ¾ÉÕ¤±¤æ¤ó¤Ē¤¹”£
ĘīŹĘ¤ĪĄč½»Ģ±¤æ¤Į¤¬¤¤¤Ä¤É¤Ī¤č¤¦¤Ė¤·¤Ę¤ä¤Ć¤Ę¤¤æ¤Ī¤«¤ČøĄ¤¦ČÆĮŪ¤Ē¤ä¤Ć¤Ę¤¤æ¤«¤éµÕ„ė”¼„ȤĖ¤Ź¤Ć¤æ¤Ī¤Ē¤¹”£
„ė”¼„ė¤ņ·č¤į¤Ę”¢½ŠĶč¤ė¤Ą¤±ĀĄøŤĪæĶ¤ĖĮŪ¤¤¤ņĆŚ¤»¤Ź¤¬¤é”¢ĀĄøŤĪæĶ¤æ¤Į¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ĮŪ¤¤¤ĒĪ¹¤ņ¤·¤æ¤Ī¤«”£
É÷¤ä½ė¤µ“ؤµ”¢½¤¤¤äŌ¼¤ņĀĄøŤĪæĶ¤æ¤Į¤Čʱ¤ø¤č¤¦¤ĖøŽ“¶¤Ē“¶¤ø¤Ź¤¬¤éĪ¹¤¬¤·¤æ¤«¤Ć¤æ¤«¤é”¢
¼«Ź¬¤ĪĻÓĪĻ¤äµÓĪĻ¤Ē¤ä¤Ć¤æ”£
¤æ¤Ą”¢„Č„Ź„«„¤¤äø¤¤ä„é„Æ„Ą”¢„¦„Ž¤ĻĄĪ¤ĪæĶ¤ā»Č¤Ć¤Ę¤¤¤æ¤Ą¤ķ¤¦¤«¤é”¢¤½¤ģ¤ņ¼«Ź¬¤Ē¤Æ¤Æ¤ģ¤ģ¤Š¤¤¤¤¤Č¤¤¤¦„ė”¼„ė¤Ė¤·¤æ”£
ĄĪ¤ĪæĶ¤¬¤ä¤Ć¤æĪ¹¤¬„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤Ź¤Ī¤Ē”¢ĖĶ¤¬¤ä¤Ć¤æ¤Ī¤Ļ„ׄ鄤„Ł”¼„Č„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼”¢„Ž„¤„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤ČøĄ¤Ć¤æŹż¤¬Īɤ¤¤«¤ā¤·¤ģ¤Ž¤»¤ó”£”×
“ŲĢī¤µ¤ó¤Ļ”¢¤³¤Ī„°„ģ”¼„Č„ø„ć”¼„Ė”¼¤ĪĪ¹¤Ė½Š¤ėĮ°¤«¤é”¢
²æÅŁ¤ā„¢„Ž„¾„ó¤ņĖ¬¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£
„¢„Ž„¾„óĄīĪ®°č¤Ė¹¤¬¤ėĒ®ĀÓ±«ĪÓ¤ĪµšĀē¤Źæ¹ĪӤȔ¢
¤½¤³¤ĒĄø¤¤ėĄč½»Ģ±¤æ¤Į¤ČĄÜ¤¹¤ėĆę”¢“ŲĢī¤µ¤ó¤¬“¶¤ø¤æ¤³¤Č¤ņ»Ē¤¤¤Ž¤·¤æ”£

”ÖŗĒ½é¤Ė“¶¤ø¤æ¤Ī¤Ļ”¢æ¹¤ĪĆę¤Ē¼ž¤ź¤ņø«¤ė¤Čʱ¤øĢŚ¤ņø«¤ė¤Ī¤Ė¶ģĻ«¤¹¤ė¤Č¤¤¤¦¤³¤Č”£
槤ó¤ŹĢŚ¤¬Ąø¤Ø¤Ę¤¤¤ė”£
¤Ź¤¼¤«¤Č¤¤¤¦¤Č”¢Ę±¤øĢŚ¤¬Ąø¤Ø¤Ę¤¤¤æ¤éŗ¬¤ĪÄ„¤źŹż¤āʱ¤ø¤Ēʱ¤ø±ÉĶܤņ¼č¤ė¤æ¤į”֤Ĥ֤·¤¢¤¦”פ«¤é”£
°ć¤¦ĢŚ¤¬Ąø¤Ø¤ė¤³¤Č¤Ē”¢ŗ¬¤ĪÄ„¤źŹż¤ā±ÉĶܤā°ć¤¦¤æ¤į¤Ŗøߤ¤¤Ė¾ł¤ź¹ē¤Ć¤Ę”¢¤³¤ó¤ā¤ź¤·¤æ湤¬ĪŠ¤Ī¤ø¤å¤¦¤æ¤ó¤Ī¾å¤Ė¤Ē¤¤ė¤ó¤Ē¤¹”£
¼Ā¤Ļ„¢„Ž„¾„ó¤ĪÅŚ¤ĻÉåĶÕÅŚ¤¬Ēö¤ÆÉĻ¤·¤¤¤¬”¢æ¢ŹŖ¤¬ĀæĶĶ¤Ē¤¢¤ė¤³¤Č¤Ē¤Ź¤ó¤Č¤«¤Ź¤Ć¤Ę¤¤¤ė”£
¤½¤ģ¤¬Ēķ¤¬¤µ¤ģ¤Ę¤·¤Ž¤¦”ÄĀēµ¬ĢĻ¤ŹĒĄ±ą¤ņŗī¤Ć¤æ¤źµķ¤ņ»ō¤¦¤æ¤į¤ĖĢŚ¤ņĮ“¤ĘĄŚ¤Ć¤Ę¤·¤Ž¤¦¤Č”¢Ä¾¼ĶĘüø÷¤¬¤¢¤æ¤ź±«µÓ¤Ī¶Æ¤µ¤ĒĶÜŹ¬¤¬¾Ć²½¤µ¤ģ¤æ¤źĪ®¤µ¤ģ¤Ę¤·¤Ž¤¦¤³¤Č¤Ēŗ½Ēł²½¤·¤Ę¤·¤Ž¤¦”£
¤½¤ģ¤ņ„¢„Ž„¾„ó¤ĪæĶ¤æ¤Į¤Ļ¾å¼ź¤Æææ»÷¤·¤Ę¤¤¤ė¤Ē¤¹¤č”£
ĢŚ¤ņĮ“ÉōĄŚ¤é¤Ź¤¤¤Ē”¢„Ń„¤„Ź„Ƅׄė¤ä„Č„¦„ā„ķ„³„·”¢„Š„Ź„Ź¤ä„¤„ā¤Ź¤Éæ§¤ó¤Ź¤ā¤Ī¤ņ梤ؤė¤Č¤¤¤¦¤Ī¤Ļ”¢æ¹¤Īææ»÷¤ņ¤·¤Ę¤¤¤ė¤Č¤¤¤¦¤³¤Č”£
¾Ę¤ČŖ¤¬°¤¤¤³¤Č¤Ą¤ČøĄ¤ļ¤ģ¤ė¤¬”¢æ¹¤ņææ»÷¤·¤æ¤ä¤źŹż”£¤³¤ĪæĶ¤æ¤Į¤ĻĄøĀÖ³Ų¼Ō¤Ź¤Ī¤«¤ČøĄ¤¦¤Æ¤é¤¤»żĀ³²ÄĒ½¤ŹĒĄĖ”¤ņ¤ä¤Ć¤Ę¤¤¤ė¤ó¤Ē¤¹¤Ķ”£”×
¤Ź¤ó¤«”¢”Ö湤ĪĹ¾ė„ׄķ„ø„§„Æ„Č”×¤Ī»ŲĘīĢņ”¢
µÜĻĘĄčĄø¤¬¾§¤Ø¤Ę¤¤¤ė”ÖĄųŗß¼«Į³æ¢ĄøĶżĻĄ”פĖ»÷¤Ę¤ė¤č¤¦¤Ź„„„”£
„¢„Ž„¾„ó¤ĪæĶ¤æ¤Į¤Ļ”¢
”Ö湤Čʱ¤ø¤č¤¦¤Ė”¢æ§¤ó¤Ź¤ā¤Ī¤ņ梤ؤæ¤Ū¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤ø¤ć¤Ź¤¤¤«”פȔ¢
¤ŗ¤Ć¤ČĄĪ¤Ėµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Ę¤¤¤æ¤ó¤Ē¤¹¤Ķ”£
¤½¤Ī°ģŹż”¢“ŲĢī¤µ¤ó¤Ļ”¢
湤ĪĆę¤ĒĘ°ŹŖ¤ņ¼ķ¤ź”¢ĢŚ¤Ī¼Ā¤ņ¼č¤Ć¤ĘŹė¤é¤¹Ąč½»Ģ±¤ĪĄø³č¤āø«¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£
¤½¤³¤Ē“¶¤ø¤æ¤Ī¤Ļ”¢Čą¤é¤ČĘüĖÜæĶ¤ĪĄø¤Źż”¦¹Ķ¤ØŹż¤ĪĀē¤¤Ź°ć¤¤¤Ē¤¹”£
”ÖČą¤é¤Ī¤¹¤“¤¤¤Ī¤Ļ”¢ĀĄ×¤ņø«¤Ę¤¤¤Ä¤Ī¤ā¤Ī¤«Ź¬¤«¤ė¤Č¤¤¤¦¤³¤Č”£
¤Į¤ē¤Ć¤Č¤Ų¤³¤ß¤¬¤¢¤ė¤Č¤É¤ó¤ŹĘ°ŹŖ¤Ź¤Ī¤«¤ā¤ļ¤«¤ė¤ó¤Ē¤¹”£
„Š„Ƥņø«¤Ä¤±¤ė¤Č”¢„Š„ƤĻĀēĀĪʱ¤ø„³”¼„¹¤ņÄĢ¤¦¤Ī¤Ē”¢¤½¤ģ¤ņÄɤ¤¤«¤±¤ė”£
Ę°ŹŖ¤Ė¤č¤Ć¤Ę¤Ļ°ć¤¦Źā¤Źż¤ņ¤¹¤ė”£µŻĢš¤ĒµŽ½ź¤Ė¤¢¤æ¤Ć¤Ę¤ā¤¹¤°¤Ė¤Ļ»ą¤Ź¤Ź¤¤”£·ģ¤ņ½Š¤·¤ĘŹā¤¤¤Ę¤¤¤Æ”£
ĀĄ×¤Č·ģŗƤņø«¤Ź¤¬¤éÄɤ¤¤«¤±¤Ę”¢½Š·ģ»ą¤¹¤ė¤Ī¤ņÄɤ¤¤«¤±¤Ę¤Č¤É¤į¤ņ»É¤·¤ĘŹį¤Ž¤Ø¤ė”£
¤Ą¤«¤é湤äĘ°ŹŖ¤ņ¤Į¤ć¤ó¤ČĆĪ¤é¤Ź¤¤¤Č¤Č¼ķ¤ź¤Ļ½ŠĶ褏¤¤¤Ī¤Ē¤¹”£
¤¤¤Ä¤āʱ¤ø¤ø¤ć¤Ź¤¤¤«¤éĮĻ°Õ¹©É×”¢ĆĪ·Ć”¢ĮŪĮüĪĻ¤¬É¬ĶפĒ¤¹”£
„¢„Ž„¾„ó¤ĪĢ±¤Ļ”¢ĖÜÅö¤Ė¼ķ¤ź¤ņ¹„¤¤Ē¤ä¤Ć¤Ę¤¤¤ė”£“ī”¹¤Č¤·¤Ę„ļ„Æ„ļ„Ƥä¤Ć¤Ę¤¤¤ė”£
¤½¤ģ¤Ļ”¢ĒĄ¹ĢĢ±¤Č¤Ļ°ć¤¦¤ó¤Ē¤¹”£
ĒĄ¹ĢĢ±¤ĻĢĢĒņ¤Æ¤Ź¤¤”£
¼ļ¤ņ¤Ž¤¤¤ĘÉĤņæ¢¤Ø¤Ę»ØĮš¤ņ¼č¤Ć¤Ę¤Č¤¤¤¦¤Ī¤Ļ³Ś¤·¤Æ¤Ź¤¤”£
²æ¤«·īøå1ĒÆøå¤Ī¼ż³Ļ¤Ī¤æ¤į¤Ėŗ£¤Īŗī¶Č¤ņ¤·¤Ę¤¤¤ė”£
¤½¤ģ¤¬æ¹¤Ī¾ģ¹ē¤Ļ¤½¤ĪĘü¤Ī¤¦¤Į¤ĖĢŚ¤Ī¼Ā¤Ļ¼č¤ģ¤ė¤·”¢Ę°ŹŖ¤āµū¤ā³Ķ¤ģ¤ė”£
Ąø¤Źż¤¬°ć¤¦¤ó¤Ē¤¹”£
湤ĖĄø¤¤ėæĶ¤Ļŗ£¤ņĀēĄŚ¤Ė¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£
ŗ£¤ņĄø¤Ąø¤¤ČĢ£¤ļ¤Ć¤ĘĄø¤¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£
¤æ¤Ą¤·¾Ķč¤ĪĢ“¤ß¤æ¤¤¤Ź¤ā¤Ī¤ņ¤ā¤æ¤Ź¤¤¤Č¤¤¤¦·¹øž¤Ļ¤¢¤ź¤Ž¤¹”£
²ę”¹¤Ī¾šŹó¼Ņ²ń¤Ī¤ā¤Č¤ĻĒĄ¶Č¤¬“šČ×”£
¤½¤Ī±Ę¶Į¤¬Ķč¤Ę¤¤¤Ę”¢¾Ķč¤Ī¤æ¤į¤ĖĄø¤¤Ę¤¤¤ė”£
¶ĖĆ¼¤ŹĻƤņ¤¹¤ė¤Č¾®³Ų¹»¤ĖĘž¤ėĮ°¤Ė¤¤¤¤¾®³Ų¹»”¢Ćę³Ų¹»”¢Āē³Ų”¢Īɤ¤½¢æ¦Ąč”¢Īɤ¤„Ż„¹„Ȥņ“ź¤¤¤Ž¤¹¤č¤Ķ”£
µ¤¤¬¤Ä¤¤¤æ¤é”Ö²¶¤Ļ¤Ź¤ó¤Ī¤æ¤į¤ĖĄø¤¤Ę¤¤¤æ¤ó¤Ą”פȤ¤¤¦¤³¤Č¤Ė¤Ź¤ź¤«¤Ķ¤Ź¤¤”£
Ģ“¤Ļ»ż¤Ę¤ė¤¬²¼¼ź¤¹¤ė¤ČĢ¤Ķ褊¤«¤źø«¤ĘĄø¤¤Ęŗ£¤ņĀēĄŚ¤Ė¤·¤Ę¤¤¤Ź¤¤¤Č¤¤¤¦¤Č¤³¤ķ¤¬¤¢¤ė”£
湤ĪæĶ“Ö¤Ļ”¢Ąø¤¤¬¤¤¤¬¤Ź¤¤¤ļ¤±¤ø¤ć¤Ź¤¤”£
»Ņ¤É¤ā¤æ¤Į¤ņ°é¤Ę”¢¤ß¤ó¤Ź¤ČĆēĪɤƤä¤Ć¤Ę²Ī¤ņ²Ī¤¤ĶŁ¤ė”£Ąø¤¤¬¤¤¤Ļ¤¢¤ė”£
¤æ¤Ą”¢¤½¤ģ¤Ļ±ó¤¤Ģ¤Ķč¤Ē¤Ļ¤Ź¤¤”£
ŗ£¤ņĀēĄŚ¤Ė¤¹¤ė¤Č¤¤¤¦°ÕĢ£¤Ē¤Ļ湤ĪæĶ¤æ¤Į¤Ė¤ĻÅؤļ¤Ź¤¤”£
ĖĶ¤æ¤Į¤Ė¤ĻĢ“¤ņ»ż¤Ä”¢Ąø¤¤¬¤¤¤ņ»ż¤Ä¤Č¤¤¤¦°ć¤¦ÅžĆ£ÅĄ¤¬¤¢¤ė”£
¤æ¤Ą”¢¤ā¤¦¤Į¤ē¤Ć¤Čŗ£¤ņĀēĄŚ¤Ė¤·¤æŹż¤¬¤¤¤¤¤ó¤ø¤ć¤Ź¤¤¤«¤Č¤ā»×¤¦”£”×
¤Ź¤ė¤Ū¤É”Į”Į”Ŗ
”Öŗ£¤ņĄø¤¤ė„¢„Ž„¾„ó¤ĪĢ±”פȔÖĢ¤Ķč¤Ī°Ł¤Ėŗ£¤ņ²į¤“¤¹»ä¤æ¤Į”×”£
漤¤¤Ē¤¹”Ŗ”Ŗ
Ķč½µ¤ā”¢¤³¤ĪĀ³¤¤ņ¤ŖĮ÷¤ź¤·¤Ž¤¹¤Ķ”Ŗ
“ŲĢī¤µ¤ó¤ĪĶ„¤·¤¤øģ¤źøż¤ņŹ¹¤¤æ¤¤æĶ¤Ļ”¢„Ż„Ć„Č„„ć„¹„ȤĒ¤Ŗ³Ś¤·¤ß²¼¤µ¤¤”£