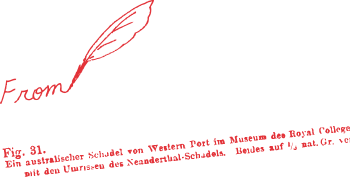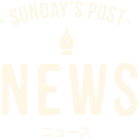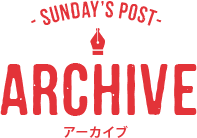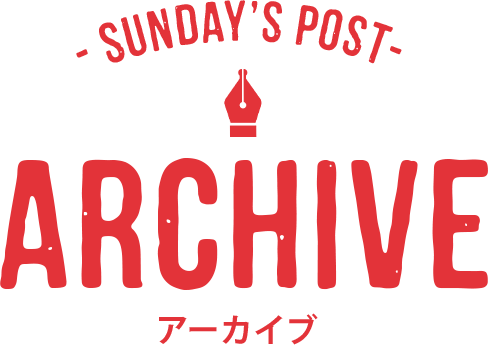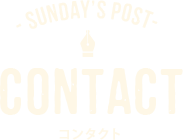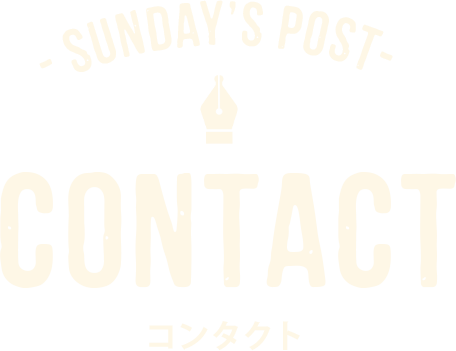スタジオで茶会も! 茶人の松村宗亮さんが登場
-

- 2025/04/27
茶人の松村宗亮さんをお迎えして
 今回はスタジオに、裏千家の茶人の松村宗亮さんをお迎えしました。
今回はスタジオに、裏千家の茶人の松村宗亮さんをお迎えしました。
宇賀「松村さんは裏千家茶道準教授であり、2009年には横浜・関内で茶道教室『SHUHALLY』を開始。“茶の湯をもっと自由に、楽しく”をコンセプトに活動をされています」
小山「 “さどう”“ちゃどう”と言い方が違いますけど、裏千家では“ちゃどう”なんですよね。これはなぜですか?」
 松村「一説によりますと、かつてお殿様にお茶を教える職業の方として“茶頭(さどう)”というポジションがあったということがありまして、それと混乱しないように呼び方を変えているというふうに聞いております」
松村「一説によりますと、かつてお殿様にお茶を教える職業の方として“茶頭(さどう)”というポジションがあったということがありまして、それと混乱しないように呼び方を変えているというふうに聞いております」
小山「なるほど! 松村さんは自らの茶道教室を守破離ではなく『SHUHALLY(シュハリ)』と表記されていて。これを見るだけでもいろんな新しい茶道の世界を開拓されているのかなという印象があります。今までいろんな場所でお茶を点てていらっしゃったと聞きましたが……」
松村「海外は今まで15カ国行って茶会を開催したり、日本の中でも川沿いやサウナ、ホストクラブのど真ん中であったり、サンリオピューロランドのキティちゃんがDJをしている横でお茶会をしたりですとか。もともとお茶というのが、日常から非日常に離れるというのがコンセプトにあると聞いておりましたので、現代における非日常の空間でお茶をするというのも、もしかたら茶の湯に適うかなと思いまして。いわゆる変な場所でやったりもしています」
 宇賀「ちょっと変わったところでやるとなると、いいのかな、大丈夫なのかな? とつい思っちゃうんですけど」
宇賀「ちょっと変わったところでやるとなると、いいのかな、大丈夫なのかな? とつい思っちゃうんですけど」
松村「お茶会というと敷居が高いとか、二の足を踏んでしまうみたいなところがあるんですけども。非日常の空間の中で、お菓子を食べて一服のお茶を楽しんでいただいて、いい時間を過ごしていただけるというのもお茶の一つの楽しみ方、過ごし方なんじゃないかと思っています。どうかリラックスして楽しんでいただきたいですね」
宇賀「茶道を始めたきっかけは何だったんですか?」
 松村「横浜生まれ横浜育ちで、アメリカとかヨーロッパとかいろいろな文化が入り混じっている地域で育って、むしろ外国にあこがれがあって日本の文化を全然知らずに育ってしまいまして。大学の時に休学をしてヨーロッパを中心に一人で放浪をしているタイミングがあり、あちらの方は日本に関心を持ってくださる方がすごく多くて、昔の文学のことであったり、映画のことであったり禅のことであったりを聞かれるんですけども、全然自分が答えられなくて。語るべき内容を持っていないことにすごく恥ずかしい思いをしまして。これは日本文化を知っている方が国際交流ができるな、と思い直して、日本に帰ってきてから始めたのが、お習字とかお花、お茶だった、というのがきっかけです。それが20歳を過ぎてからでした」
松村「横浜生まれ横浜育ちで、アメリカとかヨーロッパとかいろいろな文化が入り混じっている地域で育って、むしろ外国にあこがれがあって日本の文化を全然知らずに育ってしまいまして。大学の時に休学をしてヨーロッパを中心に一人で放浪をしているタイミングがあり、あちらの方は日本に関心を持ってくださる方がすごく多くて、昔の文学のことであったり、映画のことであったり禅のことであったりを聞かれるんですけども、全然自分が答えられなくて。語るべき内容を持っていないことにすごく恥ずかしい思いをしまして。これは日本文化を知っている方が国際交流ができるな、と思い直して、日本に帰ってきてから始めたのが、お習字とかお花、お茶だった、というのがきっかけです。それが20歳を過ぎてからでした」
小山「それで裏千家学園に入学されて?」
松村「入っちゃいましたね」
小山「いきなりホストクラブの真ん中で茶会をやるような……」
 松村「(笑)。徐々に徐々にそういう方向に行ったんですけども一般的にお茶というと、私の学校もそうでしたけど、代々お茶の先生をやっている家ですとか、そういう方のご子息や娘さんが多いんです。私はまったくの初代であったので、ある先生に言われたのが『三代やっていないとなかなかお茶教室として成立しないよ』と。稽古場があって地元ではある程度名前が知れていて、長年やっているから道具が集まっている。『じゃあ私はどうしたらいいんだ?』と思いまして、いろいろ考えたところ、若手の作家さんに新しい道具を作ってもらって、そういう道具をお披露目するなら違いが出るんじゃないかなということで、違うタイプのお茶会をやり始めたら転がっていった感じですね」
松村「(笑)。徐々に徐々にそういう方向に行ったんですけども一般的にお茶というと、私の学校もそうでしたけど、代々お茶の先生をやっている家ですとか、そういう方のご子息や娘さんが多いんです。私はまったくの初代であったので、ある先生に言われたのが『三代やっていないとなかなかお茶教室として成立しないよ』と。稽古場があって地元ではある程度名前が知れていて、長年やっているから道具が集まっている。『じゃあ私はどうしたらいいんだ?』と思いまして、いろいろ考えたところ、若手の作家さんに新しい道具を作ってもらって、そういう道具をお披露目するなら違いが出るんじゃないかなということで、違うタイプのお茶会をやり始めたら転がっていった感じですね」
小山「今は何名くらいいらっしゃるんですか?」
松村「生徒さんは100名前後ですね。比較的、お茶教室としては集まってくださるようになりました」
宇賀「どういう方が多いですか?」
松村「男の先生自体が少ない世界でして、うちの教室は比較的若い方が他の教室よりも多いのと、男性比率が高いのが特徴かもしれませんね」
小山「横浜の方が多いんですか?」
松村「東京からも通っていただいたりですとか、横浜の関内と代官山の2箇所でやっていますので、東京の方もお越しいただいていますね」
 小山「やはり宗亮さんが尊敬する人物といえば、千利休とか村田珠光とかになるんですか?」
小山「やはり宗亮さんが尊敬する人物といえば、千利休とか村田珠光とかになるんですか?」
松村「裏千家茶道なので、千家のルーツがあるので利休さんってどうしても言っちゃうんですけど、すごい方ですよね。400年早いパンクな人ですよね」
小山「パンク?」
松村「パンクですよね、あの方がやっているのは。いわゆるパンクミュージック、70年代とかに反体制で革ジャンを着てスタッズつけて、ネックレスをつけて、既存の音楽とは全然違う3コードで弾ける音楽みたいな。全然違う価値観を打ち出したんですけど、利休さんは当時の唐物とか中国からやってきた舶来品の道具が主流の中で、カウンターカルチャーとして日本製のもの、名も知れない陶工が作っているものを茶会に出して、それを新しい価値観として認めていく。金を持っていなくてもお茶会ができるぞというのを示したと思います」
 小山「それが今や長次郎の器みたいになって」
小山「それが今や長次郎の器みたいになって」
松村「400年経って、その価値観にいまだに日本は影響を受けていると思いますし、もしかしたら利休さんが思っていた世界とは違う世界かもしれないですが、その影響力はすごいな、素晴らしいなと思ってしまいますね」
小山「じゃあ宗亮さんも破壊してやろうみたいな思いもあるんですか?」
松村「15年前はありました。今はやっぱり自分の価値観も変わってきますので、お茶がもともと持っている爆発力、革新性みたいなところ、精神性は引き継ぎたいと思いますけど、決して過去を否定することなく、自分の新しい形を見せていけたらとは考えています」
 松村さんにスタジオでお茶を点てていただきました。
松村さんにスタジオでお茶を点てていただきました。
小山「それはお茶碗ですか?」
宇賀「見たことないです! 現代アート風というか」

 松村「九谷の作家さんの作品でして。九谷焼は大体分業制なんですよね、焼き物を作る方と絵付けをする方が別々なんですけど、こちらの作品は形を作ってそれに絵付けをしているので、すごく連動性が高いというか」
松村「九谷の作家さんの作品でして。九谷焼は大体分業制なんですよね、焼き物を作る方と絵付けをする方が別々なんですけど、こちらの作品は形を作ってそれに絵付けをしているので、すごく連動性が高いというか」



 小山「これ、飲み口は……」
小山「これ、飲み口は……」
松村「お好きなところから」

 小山「初めてです、こんなお茶碗。よく見ると、たくさんの目が自分の方を見ているようで。ちょっとドキッとしますね……(いただいて)結構なお点前でございます。なんか落ち着きますよね」
小山「初めてです、こんなお茶碗。よく見ると、たくさんの目が自分の方を見ているようで。ちょっとドキッとしますね……(いただいて)結構なお点前でございます。なんか落ち着きますよね」

 松村「お茶ってそういうパワーがありますよね。ほっこりできる」
松村「お茶ってそういうパワーがありますよね。ほっこりできる」
小山「あと、健康にいいですよね」
松村「もともと薬として入ってきていますしね。鎌倉時代には歴史書に、『抹茶が二日酔いに効く』って書いてありますね」

 宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、今日は松村さんに『いま、想いを伝えたい方』に宛てたお手紙を書いてきていただきました。どなたに宛てたお手紙ですか?」
宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、今日は松村さんに『いま、想いを伝えたい方』に宛てたお手紙を書いてきていただきました。どなたに宛てたお手紙ですか?」
松村「もしよかったら、最後にでも(明かしても)いいですか?」
 松村さんは誰に宛ててお手紙を書いたのか、朗読はぜひradikoでお聞きください(5月4日まで聴取可能)。
松村さんは誰に宛ててお手紙を書いたのか、朗読はぜひradikoでお聞きください(5月4日まで聴取可能)。
宇賀「今日の放送を聞いて、松村さんにお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。責任をもってご本人にお渡しします。
【〒102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST 松村宗亮さん宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」
松村宗亮さん、ありがとうございました!
SHUHALLY

小山「 “さどう”“ちゃどう”と言い方が違いますけど、裏千家では“ちゃどう”なんですよね。これはなぜですか?」
 松村「一説によりますと、かつてお殿様にお茶を教える職業の方として“茶頭(さどう)”というポジションがあったということがありまして、それと混乱しないように呼び方を変えているというふうに聞いております」
松村「一説によりますと、かつてお殿様にお茶を教える職業の方として“茶頭(さどう)”というポジションがあったということがありまして、それと混乱しないように呼び方を変えているというふうに聞いております」小山「なるほど! 松村さんは自らの茶道教室を守破離ではなく『SHUHALLY(シュハリ)』と表記されていて。これを見るだけでもいろんな新しい茶道の世界を開拓されているのかなという印象があります。今までいろんな場所でお茶を点てていらっしゃったと聞きましたが……」
松村「海外は今まで15カ国行って茶会を開催したり、日本の中でも川沿いやサウナ、ホストクラブのど真ん中であったり、サンリオピューロランドのキティちゃんがDJをしている横でお茶会をしたりですとか。もともとお茶というのが、日常から非日常に離れるというのがコンセプトにあると聞いておりましたので、現代における非日常の空間でお茶をするというのも、もしかたら茶の湯に適うかなと思いまして。いわゆる変な場所でやったりもしています」
 宇賀「ちょっと変わったところでやるとなると、いいのかな、大丈夫なのかな? とつい思っちゃうんですけど」
宇賀「ちょっと変わったところでやるとなると、いいのかな、大丈夫なのかな? とつい思っちゃうんですけど」松村「お茶会というと敷居が高いとか、二の足を踏んでしまうみたいなところがあるんですけども。非日常の空間の中で、お菓子を食べて一服のお茶を楽しんでいただいて、いい時間を過ごしていただけるというのもお茶の一つの楽しみ方、過ごし方なんじゃないかと思っています。どうかリラックスして楽しんでいただきたいですね」
宇賀「茶道を始めたきっかけは何だったんですか?」
 松村「横浜生まれ横浜育ちで、アメリカとかヨーロッパとかいろいろな文化が入り混じっている地域で育って、むしろ外国にあこがれがあって日本の文化を全然知らずに育ってしまいまして。大学の時に休学をしてヨーロッパを中心に一人で放浪をしているタイミングがあり、あちらの方は日本に関心を持ってくださる方がすごく多くて、昔の文学のことであったり、映画のことであったり禅のことであったりを聞かれるんですけども、全然自分が答えられなくて。語るべき内容を持っていないことにすごく恥ずかしい思いをしまして。これは日本文化を知っている方が国際交流ができるな、と思い直して、日本に帰ってきてから始めたのが、お習字とかお花、お茶だった、というのがきっかけです。それが20歳を過ぎてからでした」
松村「横浜生まれ横浜育ちで、アメリカとかヨーロッパとかいろいろな文化が入り混じっている地域で育って、むしろ外国にあこがれがあって日本の文化を全然知らずに育ってしまいまして。大学の時に休学をしてヨーロッパを中心に一人で放浪をしているタイミングがあり、あちらの方は日本に関心を持ってくださる方がすごく多くて、昔の文学のことであったり、映画のことであったり禅のことであったりを聞かれるんですけども、全然自分が答えられなくて。語るべき内容を持っていないことにすごく恥ずかしい思いをしまして。これは日本文化を知っている方が国際交流ができるな、と思い直して、日本に帰ってきてから始めたのが、お習字とかお花、お茶だった、というのがきっかけです。それが20歳を過ぎてからでした」小山「それで裏千家学園に入学されて?」
松村「入っちゃいましたね」
小山「いきなりホストクラブの真ん中で茶会をやるような……」
 松村「(笑)。徐々に徐々にそういう方向に行ったんですけども一般的にお茶というと、私の学校もそうでしたけど、代々お茶の先生をやっている家ですとか、そういう方のご子息や娘さんが多いんです。私はまったくの初代であったので、ある先生に言われたのが『三代やっていないとなかなかお茶教室として成立しないよ』と。稽古場があって地元ではある程度名前が知れていて、長年やっているから道具が集まっている。『じゃあ私はどうしたらいいんだ?』と思いまして、いろいろ考えたところ、若手の作家さんに新しい道具を作ってもらって、そういう道具をお披露目するなら違いが出るんじゃないかなということで、違うタイプのお茶会をやり始めたら転がっていった感じですね」
松村「(笑)。徐々に徐々にそういう方向に行ったんですけども一般的にお茶というと、私の学校もそうでしたけど、代々お茶の先生をやっている家ですとか、そういう方のご子息や娘さんが多いんです。私はまったくの初代であったので、ある先生に言われたのが『三代やっていないとなかなかお茶教室として成立しないよ』と。稽古場があって地元ではある程度名前が知れていて、長年やっているから道具が集まっている。『じゃあ私はどうしたらいいんだ?』と思いまして、いろいろ考えたところ、若手の作家さんに新しい道具を作ってもらって、そういう道具をお披露目するなら違いが出るんじゃないかなということで、違うタイプのお茶会をやり始めたら転がっていった感じですね」小山「今は何名くらいいらっしゃるんですか?」
松村「生徒さんは100名前後ですね。比較的、お茶教室としては集まってくださるようになりました」
宇賀「どういう方が多いですか?」
松村「男の先生自体が少ない世界でして、うちの教室は比較的若い方が他の教室よりも多いのと、男性比率が高いのが特徴かもしれませんね」
小山「横浜の方が多いんですか?」
松村「東京からも通っていただいたりですとか、横浜の関内と代官山の2箇所でやっていますので、東京の方もお越しいただいていますね」
 小山「やはり宗亮さんが尊敬する人物といえば、千利休とか村田珠光とかになるんですか?」
小山「やはり宗亮さんが尊敬する人物といえば、千利休とか村田珠光とかになるんですか?」松村「裏千家茶道なので、千家のルーツがあるので利休さんってどうしても言っちゃうんですけど、すごい方ですよね。400年早いパンクな人ですよね」
小山「パンク?」
松村「パンクですよね、あの方がやっているのは。いわゆるパンクミュージック、70年代とかに反体制で革ジャンを着てスタッズつけて、ネックレスをつけて、既存の音楽とは全然違う3コードで弾ける音楽みたいな。全然違う価値観を打ち出したんですけど、利休さんは当時の唐物とか中国からやってきた舶来品の道具が主流の中で、カウンターカルチャーとして日本製のもの、名も知れない陶工が作っているものを茶会に出して、それを新しい価値観として認めていく。金を持っていなくてもお茶会ができるぞというのを示したと思います」
 小山「それが今や長次郎の器みたいになって」
小山「それが今や長次郎の器みたいになって」松村「400年経って、その価値観にいまだに日本は影響を受けていると思いますし、もしかしたら利休さんが思っていた世界とは違う世界かもしれないですが、その影響力はすごいな、素晴らしいなと思ってしまいますね」
小山「じゃあ宗亮さんも破壊してやろうみたいな思いもあるんですか?」
松村「15年前はありました。今はやっぱり自分の価値観も変わってきますので、お茶がもともと持っている爆発力、革新性みたいなところ、精神性は引き継ぎたいと思いますけど、決して過去を否定することなく、自分の新しい形を見せていけたらとは考えています」
 松村さんにスタジオでお茶を点てていただきました。
松村さんにスタジオでお茶を点てていただきました。小山「それはお茶碗ですか?」
宇賀「見たことないです! 現代アート風というか」

 松村「九谷の作家さんの作品でして。九谷焼は大体分業制なんですよね、焼き物を作る方と絵付けをする方が別々なんですけど、こちらの作品は形を作ってそれに絵付けをしているので、すごく連動性が高いというか」
松村「九谷の作家さんの作品でして。九谷焼は大体分業制なんですよね、焼き物を作る方と絵付けをする方が別々なんですけど、こちらの作品は形を作ってそれに絵付けをしているので、すごく連動性が高いというか」


 小山「これ、飲み口は……」
小山「これ、飲み口は……」松村「お好きなところから」

 小山「初めてです、こんなお茶碗。よく見ると、たくさんの目が自分の方を見ているようで。ちょっとドキッとしますね……(いただいて)結構なお点前でございます。なんか落ち着きますよね」
小山「初めてです、こんなお茶碗。よく見ると、たくさんの目が自分の方を見ているようで。ちょっとドキッとしますね……(いただいて)結構なお点前でございます。なんか落ち着きますよね」
 松村「お茶ってそういうパワーがありますよね。ほっこりできる」
松村「お茶ってそういうパワーがありますよね。ほっこりできる」小山「あと、健康にいいですよね」
松村「もともと薬として入ってきていますしね。鎌倉時代には歴史書に、『抹茶が二日酔いに効く』って書いてありますね」

 宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、今日は松村さんに『いま、想いを伝えたい方』に宛てたお手紙を書いてきていただきました。どなたに宛てたお手紙ですか?」
宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、今日は松村さんに『いま、想いを伝えたい方』に宛てたお手紙を書いてきていただきました。どなたに宛てたお手紙ですか?」松村「もしよかったら、最後にでも(明かしても)いいですか?」
 松村さんは誰に宛ててお手紙を書いたのか、朗読はぜひradikoでお聞きください(5月4日まで聴取可能)。
松村さんは誰に宛ててお手紙を書いたのか、朗読はぜひradikoでお聞きください(5月4日まで聴取可能)。宇賀「今日の放送を聞いて、松村さんにお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。責任をもってご本人にお渡しします。
【〒102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST 松村宗亮さん宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」
松村宗亮さん、ありがとうございました!
SHUHALLY

皆さんからのお手紙、お待ちしています
 毎週、お手紙をご紹介した方の中から抽選で1名様に、大分県豊後高田市の「ワンチャー」が制作してくださったSUNDAY’S POSTオリジナル万年筆をプレゼントします。
毎週、お手紙をご紹介した方の中から抽選で1名様に、大分県豊後高田市の「ワンチャー」が制作してくださったSUNDAY’S POSTオリジナル万年筆をプレゼントします。引き続き、皆さんからのお手紙、お待ちしています。日常のささやかな出来事、薫堂さんと宇賀さんに伝えたいこと、大切にしたい人や場所のことなど、何でもOKです。宛先は、【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST】までお願いします。
今週の後クレ
 今回のメッセージは、北海道〈岩見沢郵便局〉瓶子剛司さんでした!
今回のメッセージは、北海道〈岩見沢郵便局〉瓶子剛司さんでした!「私には9歳の娘がいます。娘は、幼稚園に通っていた時に大好きだった担任の先生や、外国にいる友達へ手紙を書きます。なかなか会うことのできない先生や友達ですが、その人を思い出しながら、とても楽しそうに手紙を書いています。その先生や友達に会うときには、久しぶりに会うとは思えないほど、自然に接しています。相手のことを思って手紙を書くことで、遠くにいても近くにいるような、そんな気持ちになっているようです。いつもとても悩んで手紙を書いているのですが、一生懸命その人のことを思いながら、考えながら書いているんだなと感じます。それを見ると、私もとても嬉しくなります。手紙は、気持ちをつなぐ力や、心に響かせる力を持っている、素晴らしいものだと思います。」
MORE

この番組ではみなさんからの手紙を募集しています。
全国の皆さんからのお便りや番組で取り上げてほしい場所
を教えてください。
〒102-8080 東京都千代田区麹町1−7
SUNDAY'S POST宛