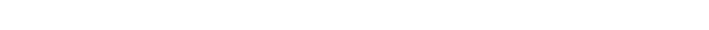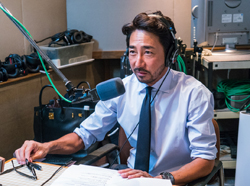ΚΘΖνΛ¥ΨηΝΞΛΛΛΩΛάΛΛΛΤΛΛΛκΛΈΛœΓΔΓ÷ΦΪΆ≥Λ«ΛΔΛξ¬≥Λ±ΛκΛΩΛαΛΥ: 20¬εΛ«ΦΈΛΤΛκΛΌΛ≠50ΛΈΛ≥Λ»ΓΉΛΈΟχΦ‘ΓΔΞΔΓΦΞΤΞΘΞΙΞ»ΞΛΞσΞ≠ΞεΞΌΓΦΞΩΓΦΛΈΜΆ≥―¬γ εΛΒΛσΛ«ΛΙΓΘ
ΞΥΞεΓΦΞΗΓΦΞιΞσΞ…ΛΈΗΕάΗΈ”ΛΥΑœΛόΛλΛΩΗ–ΛρΒρ≈άΛΥΓΔάΛ≥ΠΟφΛρΑήΤΑΛΖΛ Λ§ΛιάΗ≥ηΛΙΛκΞ·ΞξΞ®ΓΦΞΩΓΦΛ«ΓΔΦΙ…°≤»ΛΈΜΆ≥―ΛΒΛσΓΘ
ΚΘΫΒΛΈΈΙάηΛœΓΔΓ÷Ξ«ΞσΞόΓΦΞ·ΓΉΛΥΛΡΛΛΛΤΜ«ΛΛΛόΛΖΛΩΓΘ

ΜΆ≥―Γ÷Λ≥ΛλΛβΒν«·Ι‘Λ≠ΛόΛΖΛΩΛΆΓΉ
¥≥ΨλΓ÷1«·Λ«Υή≈ωΛΥΛΛΛμΛσΛ ΨλΫξΛρΈΙΛΒΛλΛΤΛΛΛκΛσΛ«ΛΙΛΆΓΘΛ ΛΦΓΔΞ«ΞσΞόΓΦΞ·ΛΥΙ‘Λ≥ΛΠΛ»ΜΉΛοΛλΛΩΛσΛ«ΛΙΛΪéù
ΜΆ≥―Γ÷ΞμΞιΞσ≈γΛ»ΛΛΛΠ≈γΛ§ΛΔΛξΛόΛΖΛΤΓΔΛ≥Λ≥Λ§≈≈ΈœΦΪΒκΈ®Λ§Ωτ100%Λ ΛσΛ«ΛΙΓΘ…ςΈœΛ§ΞαΞΛΞσΛ ΛσΛ«ΛΙΛ±Λ…ΓΔ≈γΛΈ≈≈ΈœΛœΚΤάΗ≤Ρ«Ϋή΢ΞκΞ°ΓΦΛ«œ≈ΛΟΛΤΛΛΛκΨεΛΥΓΔΆΨΛΟΛΩή΢ΞκΞ°ΓΦΛρΕαΈΌΛΥ«δΛΟΛΤΛΛΛκΛ»ΛΛΛΠ≈γΛ ΛσΛ«ΛΙΓΘΓΉ
¥≥ΨλΓ÷ΧΧ«ρΛΛ≈γΛ«ΛΙΛΆΓΣΓΉ
ΜΆ≥―Γ÷ΛΔΛ»ΛœΓΔΞ≥ΞΎΞσΞœΓΦΞ≤ΞσΛ«ΛΙΛΆΓΘΛ≥Λ≥ΛρΛΗΛΟΛ·ΛξΗΪΛΩΛΛΛ Λ»ΛΛΛΠΛΈΛ§ΛΔΛξΛόΛΖΛΤΓΔΛ≥ΛΈ2ΞΪΫξΛρΙ‘Λ≠ΛόΛΖΛΩΓΉ
¥≥ΨλΓ÷Ι‘ΛΟΛΤΛΏΛΤΛ…ΛΠΛ«ΛΖΛΩéù
ΜΆ≥―Γ÷ΞμΞιΞσ≈γΛœΓΔΞλΞΙΞ»ΞιΞσΛβΞΪΞ’ΞßΛβΞΣΓΦΞ§ΞΥΞΟΞ·ΞΌΓΦΞΙΛΈΛβΛΈΛ§¬ΩΛΛΛσΛ«ΛΙΛ±Λ…ΓΔ≥Ι ¬ΛΏΛ»ΛΪΛβΙΕΛαΛΤΛόΛΖΛΩΛΆΓΘΚΘΓΔΞμΞιΞσ≈γΛœ«άΕ»ΛδΕΒΑιΛΈΧΧΛ«ΛβάΛ≥Π≈ΣΛΥΛβΟμΧήΛΒΛλΛΤΛΛΛΤΓΔΩßΛσΛ ΩΆΛ§ΜκΜΓΛΥΛ·ΛκΨλΫξΛΥΛβΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΛσΛ«ΛΙΓΘ
Λ«ΛβΓΔΗΒΓΙΛœ≤ΩΛβΛ ΛΪΛΟΛΩΨλΫξΛ ΛσΛ«ΛΙΛηΛΆΓΘΛάΛΪΛιΛ≥ΛΫΓΔ≈γΧ±ΛΈΩΆΛΩΛΝΛ§ΦΪ §ΛΩΛΝΛιΛΖΛ·ΓΔΛ≥Λ≥Λ«Ϋ–ΆηΛκΓΔΟ·ΛβΛδΛΟΛΤΛΛΛ ΛΛΛ≥Λ»ΛρΛδΛΟΛΤΛΏΛηΛΠΛ»ΓΔΜ¬ΩΖΛ Λ≥Λ»ΛρΛδΛΟΛΤΛΛΛΩΛιΒΛΛ≈Λ±Λ–άΛ≥ΠΟφΛΪΛιΟμΧήΛ§ΫΗΛόΛΟΛΤΆηΛΤΛΛΛκΨλΫξΛ ΛσΛ«ΛΙΓΉ

ΜΆ≥―Γ÷ΛΙΛ¥Λ·Έ…ΛΪΛΟΛΩΛ«ΛΙΓΘΦΘΑ¬ΛœΈ…ΛΛΛΖΓΔΩΆΛœΛΏΛσΛ ΆΞΛΖΛΛΛΖΓΔΩ©ΛΌ ΣΛœ»ΰΧΘΛΖΛΛΛΖΓΔάΕΖιΛάΛΖΓΡΓΡΓΘΛΩΛάΓΔ Σ≤ΝΛœΙβΛΪΛΟΛΩΛ«ΛΙΓ Ψ–ΓΥΓΉ
¥≥ΨλΓ÷ Σ≤ΝΛ§ΙβΛΛΛσΛ«ΛΙΛΪΓΣΓΉ
ΜΆ≥―Γ÷ΡΕ ΓΜψΙώ≤»Λ ΛΈΛ«ΓΔΑεΈ≈Λ»ΛΪœΖΗεΛ»ΛΪΛΫΛΠΛΛΛΟΛΩ…‘Α¬Λ§Λ ΛΛ §ΓΔΙβΛΛά«ΕβΛρ ßΛΟΛΤΛΛΛιΛΟΛΖΛψΛΟΛΤΓΔΨΟ»ώά«ΛβΛΙΛ¥Λ·ΙβΛΛΛσΛ«ΛΙΓΘ
ΈΙΙ‘Φ‘ΛΥΛ»ΛΟΛΤΓΔΡΙ¥ϋ¬ΎΚΏΛΙΛκΛΥΛœΛΣΕβΛ§ΛΪΛΪΛκΨλΫξΛ«ΛœΛΔΛκΛσΛ«ΛΙΛηΛΆΓΉ
¥≥ΨλΓ÷ΞΣΓΦΞ§ΞΥΞΟΞ·ΛΥΛ≥ΛάΛοΛκΛ»ΙβΛΛΛΟΛΤΛΛΛΠΞΛΞαΓΦΞΗΛβΛΔΛκΛ»ΜΉΛΠΛσΛ«ΛΙΛ±Λ…ΓΔΛΫΛΈ ’ΛξΛΛΛΪΛ§Λ«ΛΖΛγΛΠéù
ΜΆ≥―Γ÷Ξ≥ΞΎΞσΞœΓΦΞ≤ΞσΛœΓΔΑϊΩ©≈ΙΛΈΞΣΓΦΞ§ΞΥΞΟΞ·Έ®Λ§ΛΙΛ¥Λ·ΙβΛ·ΛΤΓΔ…αΡΧΛΈΞΙΓΦΞ―ΓΦΛΥΙ‘ΛΟΛΤΛβΛΙΛ¥ΛΛ≥δΙγΛ«ΞΣΓΦΞ§ΞΥΞΟΞ·Λ ΛβΛΈΛ§ ¬ΛσΛ«ΛΛΛόΛΙΓΘ
Κ«ΕαΓΔ≈λΒΰ≈‘ΤβΛ«ΛβΞΣΓΦΞ§ΞΥΞΟΞ·Ξ÷ΓΦΞύΛ«ΓΔΞΪΞ’ΞßΛδΞλΞΙΞ»ΞιΞσΛ«ΛβΞΣΓΦΞ§ΞΥΞΟΞ·ΛρΛΠΛΩΛΟΛΤΛΛΛκΛΣ≈ΙΛ§¬ΩΛΛΛσΛ«ΛΙΛ±Λ…ΓΔΥΆΓΔΖκΙΫΞΖΞ”ΞΔΛ ΩΆΛ ΛΈΛ«ΓΊΚΘΤϋΛΈΩ©ΚύΓΔ≤Ω%ΞΣΓΦΞ§ΞΥΞΟΞ·Λ«ΛΙΛΪéüΛΟΛΤ ΙΛ·ΛσΛ«ΛΙΓΘΛΙΛκΛ»ΓΔΖκΙΫΡψΛΛΛσΛ«ΛΙΛηΓΘ
ΥΆΓΔΞλΞΙΞ»ΞιΞσΛΥΤΰΛκΛ»…§ΛΚΓΊΞ”ΞΣΞοΞΛΞσΓ ΞΣΓΦΞ§ΞΥΞΟΞ·ΞοΞΛΞσΓΥΛΔΛξΛόΛΙΛΪéüΛΟΛΤ ΙΛ·ΛσΛ«ΛΙΛ±Λ…ΓΔΓΊΛΠΛΝΛœΝ¥…τΞΣΓΦΞ§ΞΥΞΟΞ·ΞοΞΛΞσΛάΛηΓΌΛΟΛΤΗάΛοΛλΛΤΓΘΩ©ΚύΛœΓ©ΛΟΛΤ ΙΛΛΛΩΛιΓΔΩ©ΚύΛβΛάΛηΛΟΛΤΓΡΓΡΓΘΛΫΛσΛ ΛΣ≈ΙΛ§Ξ≥ΞΎΞσΞœΓΦΞ≤ΞσΛΥΛœΛΛΛΟΛ―ΛΛΛΔΛκΛσΛ«ΛΙΓΘΓΉ
¥≥ΨλΓ÷ΛΊΛß〜ΓΣΛΫΛΠΛ ΛσΛ«ΛΙΛΆΓΣΓΉ
ΜΆ≥―Γ÷…αΡΧΛœΛΫΛΠΛΛΛΠΛΈΛρΞΔΞ‘ΓΦΞκΛΙΛκΛσΛάΛ±Λ…ΓΔΗΰΛ≥ΛΠΛ«Λœ≈ωΛΩΛξΝΑΛΈΛ≥Λ»Λ ΛσΛ«ΛΙΓΘΜ‘Χ±ΛΈΑ’Φ±Λ»ΛΖΛΤΓΔΛΫΛΠΛΛΛΠΛΈΛ§ΞΙΞΩΞσΞάΓΦΞ…Λ«ΛΔΛκΛΟΛΤΛΛΛΠΛΈΛ§Κ§…’ΛΛΛΤΛΛΛκ¥ΕΛΗΛ§Ω¥ΟœΛηΛΪΛΟΛΩΛσΛ«ΛΙΛηΛΆΓΉ
¥≥ΨλΓ÷ΙώΦΪ¬ΈΛ§ΛΫΛΠΛ ΛσΛ«ΛΙΛΆΓΘΜΆ≥―ΛΒΛσΛΥΛ»ΛΟΛΤΓΔΈΙΛ»ΛœΛ…ΛσΛ ΞΛΞσΞΙΞ‘ΞλΓΦΞΖΞγΞσΛρΆΩΛ®ΛΤΛ·ΛλΛκΛβΛΈΛ«ΛΖΛγΛΠΛΪéù
ΜΆ≥―Γ÷ΥΆΛ§άΗΛ≠ΛΤΛΛΛκΨεΛ«Αλ»÷¬γΜωΛΥΛΖΛΤΛΛΛκΗάΆ’ΛœΓΊ ―≤ΫΛρΛΖ¬≥Λ±ΛκΓΌΛ ΛσΛ«ΛΙΓΘ ―≤ΫΛρΛΖ¬≥Λ±ΛκΛΟΛΤΦ¬ΛœΛΙΛ¥Λ·ΤώΛΖΛ·ΛΤΓΔΩΆ¥÷ΛΟΛΤ ―≤ΫΛρΒώΛύάΗΛ≠ ΣΛ ΛσΛ«ΛΙΛηΓΘ
ΧΐΟ«ΛΖΛΤΛκΛ» ―≤ΫΛρΛδΛαΛΤΗ«ΛόΛΟΛΤΛΖΛόΛΠΛΈΛ§ΩΆ¥÷ΛΈΥήΦΝΛ ΛσΛ«ΛΙΛ±Λ…ΓΔ ―≤ΫΛΖΛ ΛΛΛηΛΠΛΥ¥ηΡΞΛμΛΠΛ»ΜΉΛΟΛΤΥήΛρΤ…ΛσΛάΛξΓΔΙ÷±ι≤ώΛρΙ‘ΛΟΛΩΛξΛ»ΓΔΩßΛσΛ Λ≥Λ»Λ§Ϋ–ΆηΛκΛ»ΜΉΛΠΛσΛ«ΛΙΛ±Λ…ΓΔΈΙΛ§Αλ»÷ΦξΛΟΦηΛξΝαΛ·ΈΙΛœ ―≤ΫΛρΛΖ¬≥Λ±ΛκΛΟΛΤΛ≥Λ»ΛρΗε≤ΓΛΖΛΖΛΤΛ·ΛλΛκΞΡΓΦΞκΛάΛ»ΜΉΛΟΛΤΛΛΛκΛσΛ«ΛΙΓΉ
¥≥ΨλΓ÷Λ≥ΛλΛœάΈΛΪΛι¥ΕΛΗΛΤΛΛΛκΛσΛ«ΛΙΛΪéù
ΜΆ≥―Γ÷Ψ°ΛΒΛΛΜΰΛΪΛιΟœΛΥ¬≠Λ§ΛΡΛΪΛ ΛΛΛ»ΛΛΛΠΛΪΓΔΛΜΛοΛΖΛ ΛΛ≈έΛάΛΟΛΤΛΚΛΟΛ»ΗάΛοΛλΛΤΛΛΛΤΓΔΛΫΛλΛœΞάΞαΛ Λ≥Λ»ΛάΛ»ΜΉΛΛΙΰΛσΛ«ΛΛΛΩΛσΛ«ΛΙΓΘ
Λ«ΛβΓΔΟœΛΥ¬≠Λ§ΛΡΛΪΛ ΛΛΛΟΛΤΛΛΛΠΛΈΛœΛΔΛκΑ’ΧΘΗ«Ρξ≤ΫΛΖΛ ΛΛΛΟΛΤΛ≥Λ»ΛάΛΪΛιΓΔΒ’ΛΥΈ…ΛΛΛ≥Λ»ΛάΛ»ΛΛΛΠΛΈΛΥΒΛ…’ΛΛΛΤΓΔΛΫΛ≥ΛΪΛιΑ’Φ±≈ΣΛΥΈΙΛρΛΙΛκΛηΛΠΛΥΛ ΛξΛόΛΖΛΩΓΉ
¥≥ΨλΓ÷ΩΆάΗΛœΈΙΛΫΛΈΛβΛΈΓΘΜΆ≥―ΛΒΛσΛœΛ≥ΛλΛρΟœΛ«ΛδΛΟΛΤΛΛΛόΛΙΛΆΓΣΓΉ

ίΧΎΓ÷Κ«ΕαΓΔ≥ΑΙώΛΈΝΞΛ§ΤϋΥήΛΥΛδΛΟΛΤΆηΛΤΛΛΛκΛσΛ«ΛΙΛ±Λ…ΓΔά≈≤§Η©ΛΈάΕΩεΙΝΛ»ΛΪΒν«·ΛΥ»φΛΌΛΩΛι≥ΑΙώΛΈΝΞΛ§ΑλΒΛΛΥ«ήΝΐΛΖΛΤΛΛΛκΛσΛ«ΛΙΓΘ
ΛΫΛΠΛΙΛκΛ»ΓΔΙΝΛ«ΛœΚΘΛόΛ«30ΩΆΡχ≈ΌΛΈ ΐΛ§ΛΣΖόΛ®ΛΖΛΤΛΣΛβΛΤΛ ΛΖΛρΞήΞιΞσΞΤΞΘΞΔΛ«ΛΒΛλΛΤΛΛΛΩΛσΛ«ΛΙΛ±Λ…ΓΔΛ≥ΛλΛΪΛιΞΣΞξΞσΞ‘ΞΟΞ·ΛΥΗΰΛ±ΛΤΛβΛΟΛ»ΝΞΛ§ΛδΛΟΛΤΛ·ΛκΛΈΛ«ΓΔάΕΩεΙΝΛ«ΛœΩΖΛΖΛΛΦηΛξΝ»ΛΏΛ»ΛΖΛΤΜ‘Χ±ΛΈ ΐΓΙΛΥΞήΞιΞσΞΤΞΘΞΔΛ«ΡΧΧθΛΈΞ»ΞλΓΦΞΥΞσΞΑΛρΛΖΛΤΛΛΛκΛσΛ«ΛΙΓΘ
ΟœΗΒΛΈΤΟΜΚ… ΛΈΈ…ΛΒΛρ±―ΗλΛ«…ΫΗΫΛ«Λ≠ΛκΛηΛΠΛΥΈΐΫ§ΛΥΦηΛξΝ»ΛσΛ«ΛΛΛΤΓΔΈψΛ®Λ–ΓΔάΕΩεΛΟΛΤΙθΛœΛσΛΎΛσΛ»ΛΪΆ≠ΧΨΛ«ΛΙΛηΛΆΓΘ
Λ«ΛβΓΔΛœΛσΛΎΛσΛρ±―ΗλΛ«άβΧάΛΙΛκΛ»Λ ΛκΛ»Γ…FishcakeΓ…Λ ΛσΛ«ΛΙΓΘΛΫΛλΛΗΛψ §ΛΪΛιΛ ΛΛΛΪΛιΓΔΛΙΛξΩ»ΛΥΛΖΛΤΓΡΓΡΛ»ΛΛΛΠΙ©ΡχΛΈάβΧάΛβΛΖΛΤΛΔΛ≤Λ ΛΛΛ»ΛΛΛ±Λ ΛΛΛσΛ«ΛΙΓΘ
≈λ≥Λ¬γΛΈ±―ΗλΛΈάηάΗΛœΞλΞΟΞΙΞσΛρΛΒΛλΛΤΛΛΛκΛΫΛΠΛ«ΓΔΗΠΫΛ≤ώΛΥΛœ80ΩΆΛ·ΛιΛΛΜ≤≤ΟΛΖΛΤΛιΛΟΛΖΛψΛκΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»Λ ΛΈΛ«ΓΔΛ≥ΛλΛΪΛιΛ≥ΛΠΛΛΛΠΛ≥Λ»Λœ≤Θ…ΆΛΈ¬γΜΖΕΕΓΔά≤≥ΛΛΈΒ“ΝΞΞΩΓΦΞΏΞ ΞκΛ ΛσΛΪΛ«ΛβΝΐΛ®ΛΤΛ·ΛκΛσΛΗΛψΛ ΛΛΛΪΛ»ΜΉΛΛΛόΛΙΓΘ
Λ≥ΛΠΛδΛΟΛΤ≥ΑΙώΛΈ ΐΛ§ΝΐΛ®ΛκΛ»ΙΝΛβΛ»ΛΟΛΤΛβΤχΛδΛΪΛΥΛ ΛκΛΖΓΔ≥ηά≠≤ΫΛΥΛβΛ ΛκΛΈΛ«ΛΙΛ¥Λ·ΛΛΛΛΦηΛξΝ»ΛΏΛάΛ»ΜΉΛΛΛόΛΙΛΆΓΉ