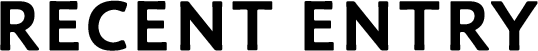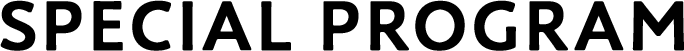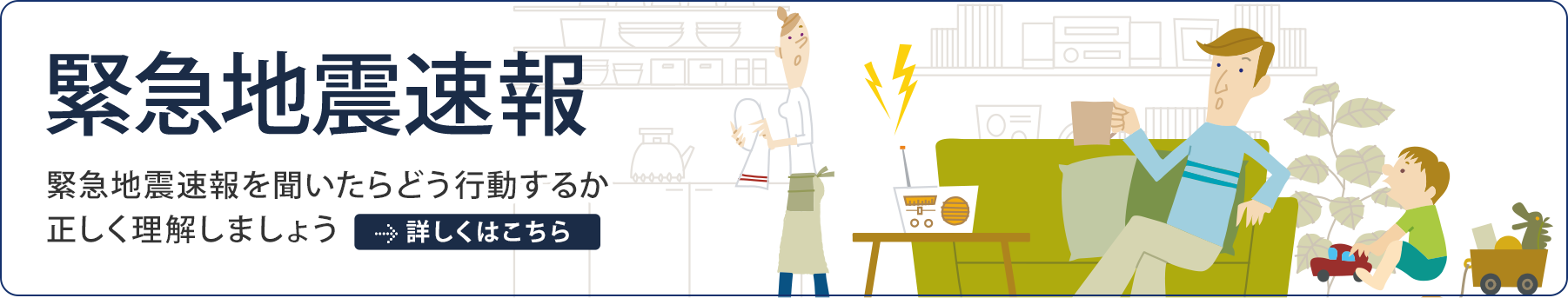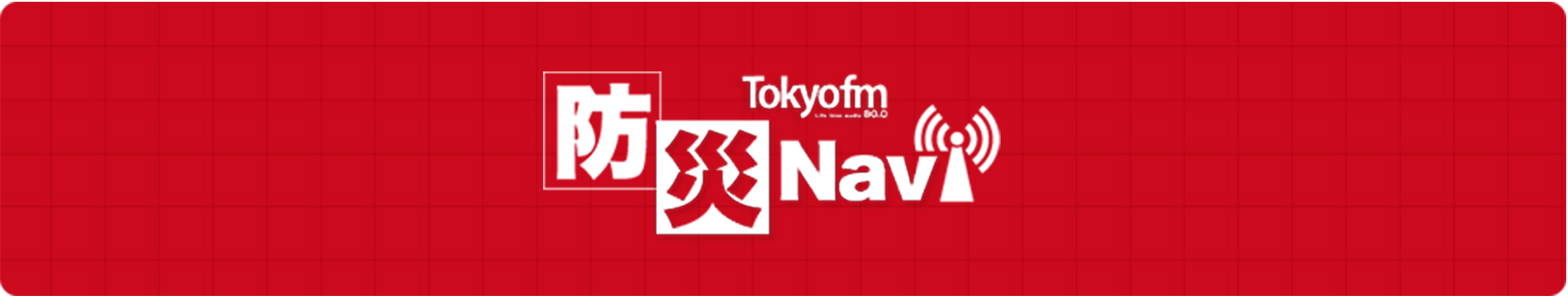2025年最後の放送は、地震などが起きた時の安否確認などの連絡方法
「災害用伝言ダイヤル」についてお伝えします。
お正月「三が日」に体験利用ができる災害用伝言ダイヤル
この災害伝言ダイヤルは、
NTT東日本、NTT西日本が提供しているサービスで、
無料で利用できる声の伝言板です。
災害が起きた時に、固定電話や公衆電話、携帯電話などから
171にかけることで利用できます。
例えば自分自身がいる地域が被災して、
被災していない地域に住む両親に安否を伝えたいとします。
その場合、被災しているあなたは171に電話をかけて自分自身の電話番号に安否情報を登録します。
安否を気にする両親などは171に電話をかけて、
被災地に住む子供の電話番号に登録された音声を再生することで、安否を確認できるという仕組みです。
災害用伝言ダイヤルを利用して音声を登録できる電話番号は、
災害によって電話が繋がりにくくなっている地域の電話番号のみですが、
例えば日中、仕事や学校などで同じ地域に住む家族と離れている時に
災害が発生した場合、自分自身の電話番号だけではなく、
安否を伝えたい相手の電話番号に伝言を登録する事もできます。
ここで重要なのは録音の起点となる電話番号を事前に家族で決めておくことです。
自分自身が被災したら、もしくは自分を含めて家族みんなが被災したら、
誰の電話番号に録音するか事前に話し合っておく事が大切です。
1つの電話番号には最大20件まで伝言を残す事ができます。
21件目の伝言を登録する時には、古い順に削除されていきます。
被災をした時に録音する内容についても事前に確認しておきましょう。
録音時間は30秒と限られています。
名前、今いる場所、誰といるのか、
安否の情報。これからの行動や次はいつ連絡するのか。
ここで気をつけたいのは、名前です。
録音を聴くときは相手の顔が見えないので
しっかりとフルネームで名乗るようにしましょう。
また今いる場所も具体的な地名を伝えるようにしましょう。
171に電話をかけると、録音をする場合は、①を押します。
再生する場合は②を押す事で、操作が進んでいきます。
音声ガイダンスがやりかたを説明してくれるので、それに従っていくと簡単に伝言の録音や再生をする事ができます。
災害用伝言ダイヤルは、災害が発生していない状況でも、体験利用する事ができます。
毎月1日と15日、1月1日~3日の三が日、
1月15日~1月21日の防災とボランティア週間
8月30日~9月5日の防災週間です。
災害が起きていない時に、家族みんなで利用方法を確かめたり、
録音・再生する電話番号、伝える内容を話あってみてはいかがでしょうか?