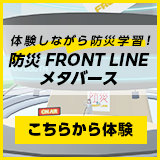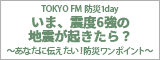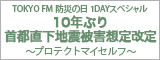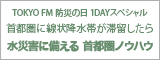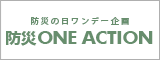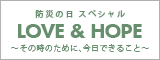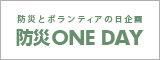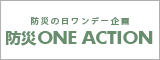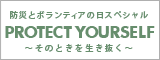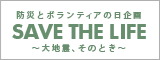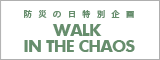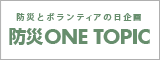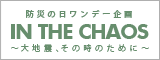2024年05月11日
08:25 災害が起きた時の水の備え
『災害が起きた時の水の確保』について考えます。
東京都が発表している
首都直下地震の被害想定では、
上水道の断水率は、都心で34.1%
復旧までおよそ17日かかると想定されていますが、
浄水施設に被害があれば、
さらに復旧までに時間がかかる可能性があります。
また、住宅内に設置された受水槽や給水管などの設備が
被害を受けた場合も断水被害は拡大する可能性があります。
特に高架水槽を設置しているマンションは、停電によって
ポンプで水を揚げられなくなってしまいます。
私たちは、1日におよそ250リットルの水道水を使用しています。
飲み水、食事の準備や後片付け、お風呂にシャワー、洗濯やトイレなど。
17日間、蛇口から水が出てこないという事は、想像以上不便さがあります。
また、能登半島地震の様に、何か月の断水が続く事も考えられます。
水の確保として、
『水の備蓄』はもちろん『災害時給水ステーション』や
給水車から水を貰うという事が考えられますが、
その他にどういう可能性が考えられるのでしょうか?
水ジャーナリストの橋本淳司さんに聞きました。
能登半島地震の事例を元にこう解説します。
『自前の井戸を活用する人たちが現れましたね。
元々、酒造とか醸造所が多い地域であったという事も
あるんですけれども、その人達が普段使っている井戸を、
この周囲の人に開放している。こういう事がありました。
防災用の井戸が残っている公園もありますから、
公園等にいった時に、いざという時に確認しておくと良い。
あと、雨水ですね。雨水は、汚いイメージを持っている人も
多いかもしれませんが、実際に降り始めて30分くらい経った雨は
綺麗、雨をどうやって貯めるかも重要ですね』
例えば、練馬区には、『防災井戸』以外に、
各学校に学校防災井戸が置かれている他、
ミニ防災井戸という、
深さおよそ8メートルの手動ポンプ付きの
浅井戸が区内のおよそ500か所に設置されています。
各自治体のHPには防災井戸の情報が載っています。
さて先ほどのお話の中にあった『雨水』を貯めるポイントについて
橋本さんはこう話します。
『雨水を貯めるっていう事でいうと、屋根の雨水を貯めるのが一番いいんですよ。
雨を貯める場合、面積を広い所で貯めた方が、沢山の雨水が貯められる。
バケツを直接置いておくと、バケツの入り口の面積分の雨水がたまるわけです。
雨どいに切り込みを入れて、プラスチックのようなもので雨水を引き寄せる装置を入れる、
例えばポリ袋のようなものを入れておくだけで雨水はたまります』
一度、梅雨の時期に実践してみるのも良いかもしれません。
災害に備えて1人、9リットル、
生活用水として使用するお水を、
水道水の汲み置きやお風呂の残り湯なので備えましょう。
今日お伝えした、「防災井戸」や「雨水」についても覚えておいてくださいね。
音声ファイルはこちら
東京都が発表している
首都直下地震の被害想定では、
上水道の断水率は、都心で34.1%
復旧までおよそ17日かかると想定されていますが、
浄水施設に被害があれば、
さらに復旧までに時間がかかる可能性があります。
また、住宅内に設置された受水槽や給水管などの設備が
被害を受けた場合も断水被害は拡大する可能性があります。
特に高架水槽を設置しているマンションは、停電によって
ポンプで水を揚げられなくなってしまいます。
私たちは、1日におよそ250リットルの水道水を使用しています。
飲み水、食事の準備や後片付け、お風呂にシャワー、洗濯やトイレなど。
17日間、蛇口から水が出てこないという事は、想像以上不便さがあります。
また、能登半島地震の様に、何か月の断水が続く事も考えられます。
水の確保として、
『水の備蓄』はもちろん『災害時給水ステーション』や
給水車から水を貰うという事が考えられますが、
その他にどういう可能性が考えられるのでしょうか?
水ジャーナリストの橋本淳司さんに聞きました。
能登半島地震の事例を元にこう解説します。
『自前の井戸を活用する人たちが現れましたね。
元々、酒造とか醸造所が多い地域であったという事も
あるんですけれども、その人達が普段使っている井戸を、
この周囲の人に開放している。こういう事がありました。
防災用の井戸が残っている公園もありますから、
公園等にいった時に、いざという時に確認しておくと良い。
あと、雨水ですね。雨水は、汚いイメージを持っている人も
多いかもしれませんが、実際に降り始めて30分くらい経った雨は
綺麗、雨をどうやって貯めるかも重要ですね』
例えば、練馬区には、『防災井戸』以外に、
各学校に学校防災井戸が置かれている他、
ミニ防災井戸という、
深さおよそ8メートルの手動ポンプ付きの
浅井戸が区内のおよそ500か所に設置されています。
各自治体のHPには防災井戸の情報が載っています。
さて先ほどのお話の中にあった『雨水』を貯めるポイントについて
橋本さんはこう話します。
『雨水を貯めるっていう事でいうと、屋根の雨水を貯めるのが一番いいんですよ。
雨を貯める場合、面積を広い所で貯めた方が、沢山の雨水が貯められる。
バケツを直接置いておくと、バケツの入り口の面積分の雨水がたまるわけです。
雨どいに切り込みを入れて、プラスチックのようなもので雨水を引き寄せる装置を入れる、
例えばポリ袋のようなものを入れておくだけで雨水はたまります』
一度、梅雨の時期に実践してみるのも良いかもしれません。
災害に備えて1人、9リットル、
生活用水として使用するお水を、
水道水の汲み置きやお風呂の残り湯なので備えましょう。
今日お伝えした、「防災井戸」や「雨水」についても覚えておいてくださいね。
音声ファイルはこちら