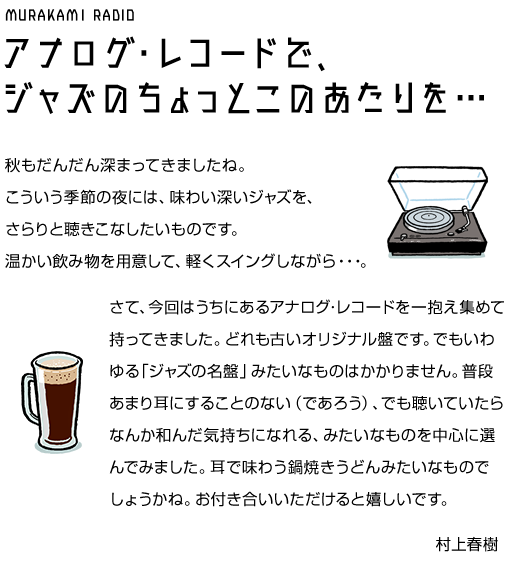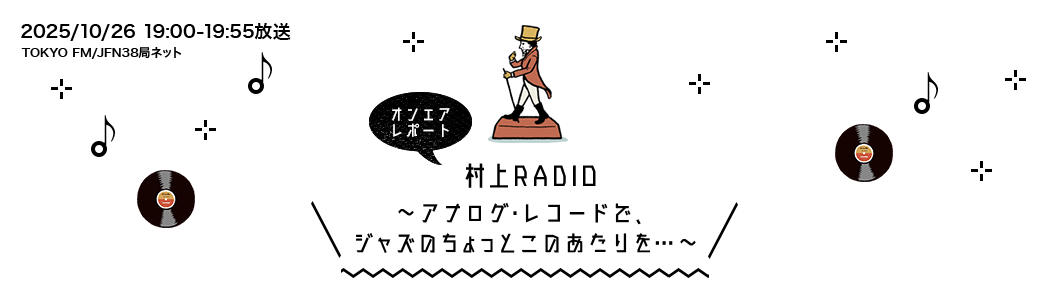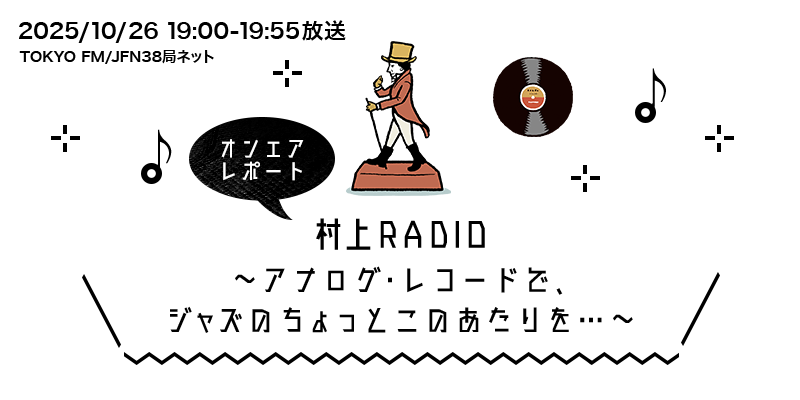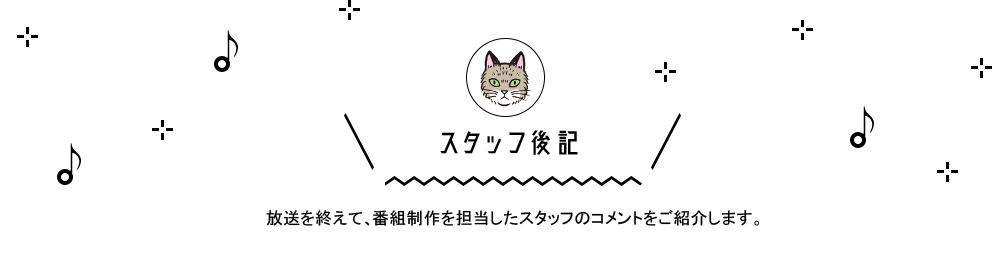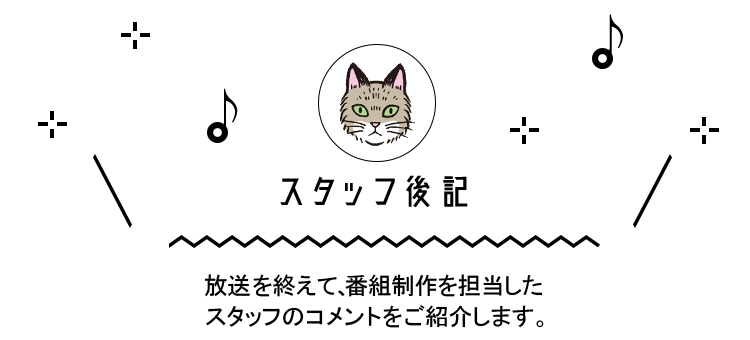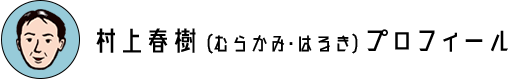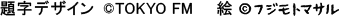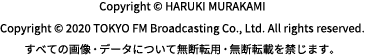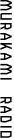


-
こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、今夜は「アナログ・レコードで、ジャズのちょっとこのあたりを…」というタイトルでお送りします。「ちょっとこのあたりって、どのあたりなんだ?」と疑問を抱かれる方も多いのではないかと思います。当然ですね。急に「このあたり」と言われても、何のことだかよくわかりませんものね。僕が意味しているのは、馴染みの料理屋さんで「普通のお客さんにはお出ししてないんですが、実はこのあたりが意外にいけるんです。お好みはあるかとは思いますが、おひとついかがでしょう?」みたいなことを言われたと想像してみてください。そうです、そのあたりです。
<オープニング曲>Donald Fagen「Madison Time」今日はうちからアナログ・レコードを一抱えまとめて持ってきました。ほとんどが古いオリジナル盤で、僕が長年聴き込んできたものばかりですが、今日おかけするものの中に誰もが認めるいわゆる「歴史的名演」みたいなものはほとんどありません。一般的にはとくに高く評価されてはいないというか、わりにすっと見過ごされている、みたいなものが多いです。そういう「でもなんか気に入っていて、ついターンテーブルに載っけちゃうんだよね」といった僕の個人的フェイバリット・トラックを揃えてみました。聴いてみてください。このあたり、シェフの密かなお勧めジャズです。
-
村上RADIO、今夜は「アナログ・レコードで、ジャズのちょっとこのあたりを…」というタイトルでお送りしています。まずジェリー・マリガンを聴いてください。マリガンは西海岸在住の白人ジャズマンで、バリトン・サックス奏者です。1950年代にチェト・ベイカーと組んだピアノレス・カルテットが高い評価を受けました。でかいバリトン・サックスを抱えた長身のジェリー・マリガン、かっこよかったです。
そのマリガンが、ここではなんとクラリネットを吹いています。僕の知る限り、マリガンがクラリネットを吹いたのは、ライムライトから出ているこの盤だけだと思うんだけど、まあとにかく珍しいです。曲は「The Lonely Night」っていうんですが、マリガンはこの自作曲をその2年前に『Night Lights』というタイトルで、フィリップス・レコードに吹き込んでいます。どうしてわざわざタイトルを変更したのか、そのへんは不明ですが、でもとにかく美しい素敵な曲です。マリガンの自作曲なんですが、フィリップス盤でもマリガンはやはりバリトンを吹いておらず、最初から最後までピアノを弾いています。よほどバリトン・サックスでこの曲を吹きたくなかったんでしょうかね。
でも、とにかくマリガンの吹くクラリネット、とてもロマンティックで心にしみます。聴いてみてください。ピアノのピート・ジョリー、ドラムズのハル・ブレイン、ベースのジミー・ボンド、ギターのジョニー・グレイに加えて、テン・ピースのストリング・セクションが伴奏をつとめます。1965年の録音です。


-
Killer Joe
Gene Harris
Gene Harris Of The Three Sounds
Blue Note
-
ジーン・ハリスはスリー・サウンズという黒人ピアノ・トリオで長い間活動していましたが、1973年に独立して、フリーランスのピアニストとして活躍するようになります。この『Gene Harris of the Three Sounds』というタイトルのブルーノート盤は、彼のソロ名義第1作にあたります。演奏メンバーはコーネル・デュプリーとサム・ブラウンのギター、ロン・カーターのベース、フレディ・ウェイツのドラムズと、スリー・サウンズ時代とはがらっと変わった面子(めんつ)ですが、新しいフィールドに踏み出したばかりのハリスの演奏はいかにも溌剌(はつらつ)としています。ベニー・ゴルソンの名曲「キラー・ジョー」を聴いてください。バシッとかっこいいです。
-
次はアール・ハインズを聴いてください。曲は「Fantastic, That's You(君はファンタスティック)」、ジミー・ハミルトンのクラリネット、アーロン・ベルのベース、エルヴィン・ジョーンズのドラムズです。エルヴィンがトラディショナル・ジャズっぽいドラミングを聴かせて、微笑ましい演奏になっています。
アール・ハインズはジャズ・ピアノの草分けと言われる人で、彼がいなかったらジャズ・ピアノの歴史は今あるものとはかなり違うものになっていただろうと言われています。1926年に吹き込まれたルイ・アームストロングの「ホット・ファイヴ」におけるハインズの演奏は歴史に残る貴重な演奏になっています。この人は1903年の生まれですが、活躍した期間は長くて、演奏スタイルも時代に合わせて微妙に変化し、1970年代まで現役としてしっかり活躍していました。
この『Once Upon A Time』というインパルスから出したレコードでは、エルヴィン・ジョーンズみたいな新世代のミュージシャンとも共演して、年齢を感じさせない闊達(かったつ)なプレイを聴かせてくれます。1966年の録音です。
-
ドン・ランディはキーボード奏者ですが、どちらかといえば西海岸の腕利きのスタジオ・ミュージシャンとして名を知られていて、ハル・ブレインを中心とするミュージシャン集団「レッキング・クルー」の中心メンバーの1人でした。数多くのレコーディング・セッションに参加していますが、有名なところではビーチボーイズの「グッド・ヴァイブレーション」と「ゴッド・オンリー・ノウズ」でキーボードを弾いています。
リーダーとしてジャズのレコードも何枚か出していますが、どちらかといえば軽量級のハッピーなジャズですね。でも中にはセンスの良さを感じさせる快演・好演もあります。この「スペース・オデッセイ・メドレー」は、映画「2001年宇宙の旅」に使われた音楽「ツァラトゥストラはかく語りき」と「美しく青きドナウ」をミックスしているんだけど、これがなかなか楽しい出来になっています。軽量級で何が悪いっていうかね。
ランディさんはロサンジェルスに「ベイクト・ポテト」というライブハウスを所有していて、そこでよく自分のバンドを率いて演奏をしていました。これはその「ベイクト・ポテト」での1972年のライブ録音です。お店のカジュアルで親密な雰囲気がひしひしと感じられます。
-
ペパー・アダムズはジェリー・マリガンと並んでバリトン・サックスの代表的なプレイヤーでした。マリガンが知的な都会風の雰囲気を漂わせているのに比べて、ペパー・アダムズは野性的な、ばりばり鋭いサウンドが売りでした。またマリガンが終始自分のバンドで演奏していたのに対して、アダムズはいろんなセッションに顔を出して、いわば他流試合で顔を売る、みたいな活動をしていました。いろんな面で2人は対照的だったんですね。
しかし、もしこの2人がいなかったら、ジャズの歴史の中でバリトン・サックスは、ただでかいだけの不器用な楽器、みたいなことで終わっていたかもしれません。ペパー・アダムズ・クインテットの演奏する「スター・クロスド・ラヴァーズ」を聴いてください。デューク・エリントンの作曲した美しいバラードです。
テナーサックスはズート・シムズ、ピアノはトミー・フラナガン、ベースはロン・カーター、ドラムズはエルヴィン・ジョーンズ。当時の最高のメンバーですね。1968年の録音です。前にも1回かけたことがあるんですけど、好きなんでもう一度かけます。しつこく。


-
A Whiter Shade Of Pale
Freddie McCoy
Beans & Greens
Prestige
-
フレディ・マッコイは1960年代半ばに、いわゆる「ソウル・ジャズ」で売り出したヴァイブラフォン奏者でした。1970年頃まではコンスタントにレコードを出していたんですけど、それ以降はぱったりと消息を絶っています。どうしたんでしょうね? 僕は意外にというか、この人がけっこう好きで、プレスティッジ・レコードから出ているレコードは全部オリジナル盤で揃えています。そんなこと、あまり自慢にもならないんですけどね……。その中から今日はプロコル・ハルムがヒットさせた「青い影(A Whiter Shade Of Pale)」を聴いてください。
このトラックの演奏メンバーには、名前を聞いたこともないトランペットが2人入っているんですが、この人たちがかなり下手というか、素人っぽいというか、どこでこんな人たちを見つけてきたんだろうと首をひねっちゃうんだけど、でも逆にその稚拙(ちせつ)さが、いかにもこの当時の即席のソウル・ジャズという雰囲気を出していて、不思議に好感が持てます。ピアノはジョーン・ブラッキーンという本格的な女性ジャズ・ピアニストなんですが。
-
久しぶりにチェト・ベイカーを聴いてください。「Funk In Deep Freeze」ばっちり冷凍されたファンク。いったいどういうファンクなんでしょうね。よくわかりません。テナーサックス奏者ハンク・モブレーが1957年に作曲して吹き込んだクールでファンキーなジャズ・チューンですが、これをチェト・ベイカーが1974年に取り上げて演奏しています。このレコードが出たときには、「え、チェト・ベイカーがこの曲やるの?」と、選曲の意外性に驚かされたものです。プロデュースはクリード・テイラー、さすがに目配りのきいたアルバム作りをしています。チェト・ベイカーも麻薬びたりのいっときの低迷期から持ち直して、しっかりしたジャズを聴かせてくれます。
メンバーはチェト・ベイカーのトランペットに加えて、ヒューバート・ロウズのフルート、ボブ・ジェームズのエレクトリック・ピアノ、ロン・カーターのベース、スティーヴ・ガッドのドラムズ。初めて聴いたとき、このエッジのきいたドラム、ジャック・ディジョネットかなあと思ったら、実はスティーヴ・ガッドでした。


-
Try A Litte Tenderness
Sonny Stitt
The Sensual Sound Of Sonny Stitt
Verve Records
-
ソニー・スティット、楽器を手に持って生まれてきたんじゃないかと思えるくらい、サキソフォンという楽器に精通した人です。本当にもう身体の一部になっているみたいに。ただあまりに天才的に上手すぎて、どんな難しそうなことでも、すらすらあっけなくこなしてしまうので、ときおり「ちょっと深みに欠けるかもな。もう少しくらい苦労があってもいいんじゃないか」と感じさせられることもありました。本来はとても優れた音楽家なんですけどね。音楽ってなかなか難しいものです。
ずいぶん昔に日本に来たことがあって、日米合同のジャム・セッションみたいなことをやったんですけど、なかなか豪華なメンバーで、ベニー・ゴルソンなんかも入っていました。僕もそのジャムを聴きに行ったんだけど、そのときとてもくたくたに疲れていまして、ほとんどうとうとしていて音楽もろくに聴いていませんでした。でもソニー・スティットがソロを取ると、はっと目が覚めちゃうんです。なにしろ素晴らしい音色だから。で、スティットのソロが終わるとまたすやすや寝ちゃう。それからまたスティットのソロではっと目が覚めるという繰り返しでした。
そのソニー・スティットの演奏を聴いてください。「Try A Litte Tenderness(優しさをちょっと試してみれば……)」。ラルフ・バーンズがストリング・セクションの伴奏をつけます。
-
今日のクロージング音楽はアルトサックス奏者、ジーン・クイルさんの演奏する「Smoke Gets In Your Eyes(煙が目にしみる)」です。伴奏はハンク・ジョーンズ・カルテット、1956年の録音です。ジーン・クイル、実力の割に過小評価されているジャズマンの1人ですね。これという代表作がないのがこの人の弱みなんですけど。

-
さて、今日の言葉は、そのジーン・クイルさんの言葉です。クイルさんは1950年代から60年代にかけて活躍し、チャーリー・パーカー派の逸材として名を知られていました。この時代のアルトサックス奏者って、だいたいみんなチャーリー・パーカーの影響を色濃く受けていました。受けないわけにはいかなかったんです。パーカーの音楽はあまりに偉大で強烈だったから。でもみんな誰かの真似をしながら、そのうちにだんだん自分自身のスタイルを発見していくものなんですね。ジーン・クイルもそんな1人でした。
あるとき彼がジャズクラブでの演奏を終えて引き上げてくると、批評家風のいかにも小生意気な若い男が寄ってきて言いました。「なあ、あんたの演奏って、チャーリー・パーカーがやってることとまるで同じじゃないか」と。クイルさんは手にしていた楽器を相手に向かって差し出し、こう言いました。「ほれ、おまえやってみろ。チャーリー・パーカーと同じことをやってみろや」
批評家ってほんとに好き勝手なことを言いますよね。でもアーティストはあれこれ勝手なことを言われながら、それぞれ勝手に成長していくものなんです。
それではまた来月。
今回かかるレコードは、村上さんが自宅から抱えてきた愛聴盤の数々です。特集タイトルは、「アナログ・レコードで、ジャズのちょっとこのあたりを…」。村上さんは、「“ちょっとこのあたり”って、どのあたりなんだ?」と言っていますが、「この辺(あた)りの者でござる」という古典芸能の狂言のセリフを思い出しますね。誰が聴いても心にしみる「このあたりのジャズ」、ぜひお楽しみください。(「村上RADIO」スタジオ・チーム)(「村上RADIO」スタジオ・チーム)
1949(昭和24)年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。’79年『風の歌を聴け』(群像新人文学賞)でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』(野間文芸新人賞)、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞)、『ノルウェイの森』、『国境の南、太陽の西』、『ねじまき鳥クロニクル』(読売文学賞)、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』(毎日出版文化賞)、最新長編小説に『街とその不確かな壁』がある。『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』、『パン屋再襲撃』などの短編小説集、『ポートレイト・イン・ジャズ』(絵・和田誠)など音楽に関わる著書、『村上ラヂオ』等のエッセイ集、紀行文、翻訳書など著訳書多数。多くの小説作品に魅力的な音楽が登場することでも知られる。海外での文学賞受賞も多く、2006(平成18)年フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、’09年エルサレム賞、’11年カタルーニャ国際賞、’16年アンデルセン文学賞を受賞。